
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年05月23日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
45 |
17/05 |
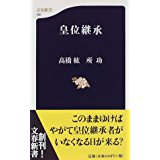 |
皇位継承 |
高橋 紘 所 功 |
文春新書 |
◎ |
第一章 「万世一系」はいかに保たれたか 兄弟継承と父子相承 ・歴代系譜をみると、五世紀から兄弟継承の例が少なくない。 ・三四代舒明天皇と三五代皇極(=斉明)女帝との間に生まれた ・しかしながら、天智天皇の本心は、大化四年(六四八)身分の低い伊賀 ・そこで、即位の翌年(六六九)、大化の改新から苦楽を共にしてきた藤原鎌足(五十六歳)が死去すると、その二年後(六七一)、天智天皇(四十六歳)は、皇太弟の大海人皇子(四十一歳か)をさしおいて大友皇子(二十四歳)を太政大臣に抜擢し、左右大臣ら五人に対して、皇子への直系継承を含みとする「詔」を守り、わが皇子に忠誠を尽くすよう誓わせている。 ・ところが、その矢先、天皇は重病に陥ったので、やむなく皇太弟に後事を託そうとした。しかし、兄帝の意中を察した大海人皇子は、それを断って一たん吉野へ退き、その年末に兄帝が崩御して大友皇子=三九代弘文天皇が近江の調停を受け継ぐと、翌壬申年(六七二)の六月に兵を挙げ、一ヵ月余の戦闘に勝利をおさめた(壬申の乱)。 ・そして翌春、飛鳥の ・このような内乱は、皇位継承の原則を兄弟相続から父子(直系)相続へと変えようとした際、引き起こされた骨肉の争いにほかならない。 ・これ以降、天智天皇の掲げた父子相承の方針を受け継いでいこうとする流れができた。ちなみに、一般の相続法も、大宝・養老の『令』( 両統 ・皇統(男系)の流れが二つに分かれて交互に即位した典型は、鎌倉時代の八八代 ・後嵯峨天皇は、在位四年で譲位してから二十六年間、皇子の八九代 ・しかし、文永九年(一二七二)崩御の際、次の院政と皇嗣について明言せず、その処置を幕府に委任すると遺詔している。 ・そこで、後深草上皇(三十歳)の側( ・持明院統と大覚寺統の両流から交互に天皇を立てることを “両統迭立” の原則という。 ただ、これは両統の関係者による激しい攻防の末、妥協策として作られた原則にすぎず、事態は常に流動的であった。 ・元弘元年(一三三一)討幕の計画が発覚したので、後醍醐天皇は神器を奉じて南都(奈良)へ逃れ、さらに隠岐まで流された。 ・元弘三年=正慶二年(一三三三)、後醍醐天皇は隠岐を脱出して京都に向かい、光厳天皇も正慶年号も廃した。のみならず翌年早々、皇子の ・しかし、その二年後(一三三六)、叛旗を翻した足利尊氏が、光厳上皇を "治天の君" に推し、その院宣により弟の ・そのため、後醍醐天皇は京都を逃れて吉野へ遷り、ここに吉野の南朝と京都の北朝とで「一天両 ・この対立は、以後五十数年も続く。幕府政治を再開した足利氏の擁する北朝は、軍事的経済的に南朝より圧倒的に強かったはずである。しかし南朝方は、三種の神器を奉ずる正統な天皇としての信念が強く、京都奪回のために苦しい戦を続けている。 織田・豊臣・徳川氏と天皇 ・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三雄は、かつての源頼朝や足利義満を凌ぐほどの権力をもち、 "天下人" などと称された。しかし、彼等でさえ、皇室を滅ぼしたり自分が天皇になろうとしたことはなく、むしろ天皇・朝廷の権威を借りながら天下統一を成しとげている。 君徳を養う帝王教育 ・大和王家以来の同一家系が少なくとも千数百年以上続いていることは、なんぴとも否定しえないであろう。 ・このような「万世一系」はどうして可能になったのか。 ・それにはいろいろな理由があげられるが、大きな要因のひとつは、多くの天皇が幼少の頃から "君徳" の修養に熱心であったからだと思われる。 ・そのような君徳を養う "帝王教育" は、様々な形で行われてきたが、本人に最も強い影響を与えたのは、身近な前帝(大半が父帝)の日常的な言動と治績そのものであろう。 ・しかも、その一端を皇嗣への教訓として書き遺したものが若干あり、それらが後々まで帝王学の教科書に使われている例も少なくない。 ・昭和天皇は、宮内記者の質問に対して「国体というものは、日本の皇室は、昔から国民の信頼によって 第二章 「女帝」出現の意味 明治民権家の女帝論議 ・飛鳥・奈良時代に六人(八代)および江戸時代に二人、あわせて八人(十代)の女帝は、すべて皇族の出身で、前帝の皇后(ないし皇太子妃)か未婚の皇女(ないし ・しかし、皇位の継承者は皇統(皇室の家系)に属する皇男子系(男系の男子)が優先するという不文律は、すでに大和時代の早い段階から形成されていたとみられる。 ・その上、天智天皇のころから直系(父子相承)を重視する傾向が強くなり、それが(実際には貫徹困難であれ)本来の望ましい在り方だ、と長らく考えられてきたことも確かである。 第三章 『皇室典範』の成り立ち 「祖宗の神器」承継の ・三種の神器( ・すでに縄文時代からある石製の ・それが、やがて全国を統一した大和朝廷の専有物となった。 ・そして、おそらく一九代 第四章 御側女官の役割 ・皇位継承はいつも “綱渡り” 的だった。むしろ皇后に男子が生まれ、そのまま継承された例の方が珍しいといってよい。皇統断絶の危機は常にあったが、多くの場合、側室の存在がその危機を救ったのである。 ・近世の例をみても一一五代桜町天皇以降、桃園・後桜町・後桃園・光格・仁孝・孝明・明治・大正と九代続いて天皇の生母は、すべて皇后でなく側室であった。 ・しかも、側室によって何人もの皇子が生まれてもなお、医学が未発達だった時代には、若くして亡くなる皇子皇女が多かった。 ・明治時代までは、何人もの側室との間に多くの皇子をもうけたが、成人したのは二割程度というありさまだった。 ・それだけに側室制度は、皇位継承にとって計り知れないほど大きな役割をはたしてきたのである。 ・古代から天皇の日常に奉仕していたのは、女官である。 ・彼女たちの中には天皇の寵愛を受けて寝所に侍するものがあり、「御側女官」と称された。 |