
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年02月22日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
5 |
17/01 |
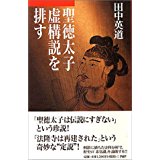 |
聖徳太子虚構説を排す |
田中英道 |
PHP研究所 |
◎ |
第一章 法隆寺は本当に「再建」なのか? 1 「法隆寺」そのものが語りはじめた 五重塔心柱の伐採年代は五九四年だった ・聖徳太子が建てた法隆寺五重塔の心柱の伐採年代が五九四年であることが年輪年代法によってはっきりした。 ・厩戸皇子(聖徳太子)の在世中に、この世界で最も古い木造建築、法隆寺が建てられたことが明確になれば、「聖徳太子」という人物の存在が改めてクローズアップされるのである。 ・つまり大きな力を持ち、仏教信徒として情念を持った一人の政治家がおり、その人物が大規模な美しい建築を計画し、それを実現させたのだ。そのために多くの仏像が制作されたのである。 イデオロギーが捻じ曲げた「聖徳太子」像 ・津田 ・一方でその不信論は、歴史を階級闘争と見るマルクス主義の立場であったり、権力者は国民の自由と権利を抑圧するものだ、というリベラリストの立場であったり、あるいは太子が仏教徒で、神道とか儒教とは相容れないとするセクショナリズムからきているものであった。 ・階級闘争論者からいわせれば、人民と権力者が、聖徳太子のいうように「和」をもって共同して社会をつくるという考え方はとれないし、リベラリストからいわせれば、聖徳太子のような天皇家の皇太子が、国民の権利を守るという立場をとることはできないだろう。 ・貴族政治家が国民から尊敬されているのも気に食わなかった。 ・また天皇のみを奉る神道家からいえば、聖徳太子は ・儒教的な立場からいっても、親族を殺すことを許した恥ずべき仏教信者である。 ・彼らにすれば、それぞれに融和して、思考し実践している聖徳太子は、「聖・徳」を併せ持つ人物ではありえなかったのである。彼らのイデオロギーからすれば、異口同音に聖徳太子などいなかった、と考えたくなるのも無理からぬことである。 「形象学」としての歴史 ・歴史はより「形象学」でなければならない。 ・たとえば日本には「前方後円墳」といわれる遺跡が数多くあるが、それは「形象学」しか成り立たない。一切文献がないからである。 ・聖徳太子に関する確実な史料は存在しない、という歴史家は、文献史料しか読んでいない。太子に関しては、法隆寺をはじめとする多くの形象史料が残っている。それを観察分析しなければ何も考察していないのと同じである。 第二章 天寿国繍帳と法華義疏は本物である 2 日本で最も古い書物が聖徳太子の『法華義疏』である 聖徳太子の真筆と考えざるをえない『法華義疏』 ・聖徳太子は岡本宮(現在の法起寺)で『法華経』を講じているのである。本書はこの講義のための草稿である、と考えることが出来る。 ・とすれば、これが聖徳太子の自筆であることは、ほぼ断言できるのである。 ・この『法華義疏』が法隆寺に八世紀から存在したことは確認されている。 ・それが今日まで伝えられていること自体、聖徳太子がここにいる、ということの証でるといってよい。 聖徳太子の『三経義疏』の思想とは何か ・『法華義疏』に説かれるのは、中国の法雲の『法華経』の注釈書『法華義記』を下敷きにした聖徳太子自らの考え方である。 『維摩経義疏』の思想 ・太子によれば、人間には本来聖人もなければ下愚もなく、すべて本来同一の仏子である。«汝は「仏はわが師である」と考えているけれども、仏は空であり、異教徒(外道)も空であるから、ともに一相であって、二つの別のものではない。ゆえに異教徒もまた汝の師である。もしも異教徒が汝の師ではないのならば、すべて空であって二つのものの対立がないということわりのゆえに、仏もまた汝の師ではないということになるのである»。 ・この考え方は、まさに日本の仏教の基本となったもので、聖徳太子の思想が日本人に受け入れられる理由である。 ・中村元氏も«現実(世俗)に対する積極的な働きかけという日本仏教の特徴的性格は、すでに仏教受容の初期段階で胚胎していたのである»と述べている。 ・津田左右吉氏はこの聖徳太子の三義疏について、摂政という政治的に重要で多忙な地位にありながら、このような専門的な述作ができたことに疑問を感じているが、しかし太子の解釈は、まさにその摂政という実践的な活動を通して得られた思想に基づくものであり、まさに十七条憲法の精神と一貫したものであったのである。 第三章 なぜ聖徳太子か? 1 聖徳太子思想の必要性――神・仏・儒教の融合 日本の「国家思想」の芽生え ・日本は四世紀後半に百済との交渉が始まり、三九一年から五世紀にかけて朝鮮半島に出兵し、百済、新羅を征服した。 ・四世紀の終わりには ・このような朝鮮との交渉のなかで五世紀から百済から日本へやって来る渡来人が多くなった。漢族も多く、その代表的なものは養蚕や絹に携わった ・こうした大陸からの移民とともに、大陸の文化、とくにこの頃においては儒教が漢字とともに伝わって来た。五世紀初め、百済から ・六世紀初めの継体天皇の頃に百済から五経博士(儒学者)が来朝し、中頃には医博士、易博士、暦博士などが招かれて医書、易書、暦本などが日本に知られるようになった。 ・儒教は紀元前五世紀の孔子の教えで、根本に天命を置き、 ・「修身 ・忠孝を中心に君臣、父子などのあるべき道を説く教えは、仏教の伝来前の日本人に道徳性を喚起し、その受け入れを可能にしたのである。それは聖徳太子の「十七条憲法」にも反映されている。 ・興味深いのは、日本が三世紀から五世紀にかけての前方後円墳の時代にほぼ、国内的な体制ができ上がり、中国、朝鮮からの仏教、儒教などの思想の流入によって、対外的な意識が喚起され「国家思想」が芽生えていったことである。 ・神道が、諸氏族が分立する多様性に依拠しているのに対し、仏教・儒教が抽象的な人間思想によって、国家としてまとまりのある思想を与えることになったのである。 現実と抽象化――聖徳太子と初期キリスト教 ・聖徳太子の十七条憲法にいう「和」を貴ぶ協調精神は、すでに日本の民族にあったものであり、それまでの口承として存在していた日本語から強く影響されたものであったのだ。 ・主語を欠く場合が多い日本語の言語構造は、個人よりも集団や状況を重視した心理に基づくものであり、述語の動詞が構文の最後に来るというのも、個人の判断を最後に置くという同じ心理によるものだと推測されている。 ・漢字の導入はその日本人の言語に文語的な表現力を与え、そのような日本語の特徴を明らかにさせた。 「仏像」の神々しさから始まった仏教 ・「 景教(ネストリウス派)の影響力 ・四天王寺に日本における社会救済事業の最初のものといわれる「 ・これは約百数十年経って、聖武天皇の妃、光明皇后がやはり療病院、施薬院、悲田院を造ったことと同じ精神である。 ・七三六年(天平八年)に、ペルシャ人の景教徒(キリスト教の一派でネストリウス派)の宣教師 ・光明皇后とは死後に贈られた「 第四章 谷沢永一『聖武天皇はいなかった』批判 1 史実と俗説 聖武天皇の存在を許さぬ風潮 ・養老四年(七二〇年)に完成した『日本書紀』の太子に関する部分の史料が、フィクションであることは、すでに江戸時代からいわれているが、それがいつのまにか「いなかった」まで極端に走ると、「とんでもないことだ」といわざるをえない。 ・戦後とくに過去のすぐれた日本人の存在やその行為を疑うことが、あたかも進歩的であるかのようなつまらぬ風潮になっている。 ・人々は西欧人や中国人は尊敬しても、日本人自身を尊敬しなくなっているおかしな自信喪失の時代が続いている。聖徳太子のような存在を許さぬ風潮ほど、そのことをよく示している例はない。 2 聖徳太子を高く評価していた谷沢氏 『新しい歴史教科書』における聖徳太子の記述 ・わが国は、中国から謙虚に文明を学びはするが、決して服属はしない――これが、その後もずっと変わらない、古代日本の基本姿勢となった。 ・仏教が入ってきた六世紀前半に、豪族たちは、これを外国の宗教であるとして排斥する勢力と、むしろ積極的に受け入れようとする勢力との二派に分かれ、政治抗争を引きおこした。排斥派の物部氏が討たれ、受け入れ派の蘇我氏が勝って、政治の主導権を握った。 第五章 大山誠一『‹聖徳太子›の誕生』を批判する 1 聖徳太子が日本の歴史から消えようとしている 「実証主義」という名の蒙昧 ・偉大な人間は生前よりも、死後に高く評価される。その評価もひとつの歴史資料である。 ・歴史というのは、人間史であるかぎり、不明な点があり、その書かれた記録にはすべて文学性がある。それを想像力で補うのが歴史である。 ・日本の学者の多くは人間を科学で割り切ろうとしている。歴史学の原則さえ知らない者が多い。 ・この事態の根底を見ると、日本の大多数の歴史家に、日本に起こった価値ある出来事をすべて否定する、という戦後の日本不信感が未だに蔓延していることがわかる。 ・端的に言えば実証主義を自称する戦後日本の歴史学は、権力を常に否定するマルクス主義史観に支えられている。 ・それが義務教育の歴史教科書にまで反映している。 津田左右吉氏と大山誠一氏 ・明治以降、実証主義とマルクス主義が移入されてから、この人物が天皇に近い権力者の一人であるというので、疑う史家が多くなった。典型は津田左右吉氏である。 ・氏は文献実証主義者として現在の聖徳太子否定論者の元祖になっている。 ・彼の考え方の基本には、『古事記』『日本書紀』に書かれた「神代」は、すべて天皇による支配を正当化するために書かれた政治的意図から生まれたものだ、という考え方がある。 ・聖徳太子の場合でいえば、「十七条憲法」は、その言葉の使用が、その時代にされておらず、大化改新以後の偽作である、と断定している。 ・この論を丸呑みしているのが、大山誠一氏である。 十七条憲法と教育勅語が似ている !? ・大山氏がいかなる考えに立脚しているのか。 ・聖徳太子像はまず七二〇年の『日本書紀』によって偽造されたもので、その後の彼に関する史料はすべて虚偽である、とする。 ・それは藤原不比等、長屋王が、唐から帰国した道慈に「厩戸王」という人物に、すべて理想像を仮託させて書かせたというものである。 ・「教育勅語」は、明治期の藩閥政府という権力者が、天皇を絶対君主に仕立て上げるイデオロギーによりつくられたと、大山氏はいう。そして、これは聖徳太子の十七条憲法がやはり、律令国家の成立以後、天皇の「至上の権威と権力が何に基づくか」という問いに答えるために、『日本書紀』で捏造されたのと等しいと述べている。 「最初に結論ありき」の歴史観 ・しかし誤りは指摘できる。 ・まず天皇は、江戸時代まで無力であった、という説であるが、戦国末期に天皇の権威が強化され、徳川幕府時代にも征夷大将軍の任命から武家の官位の授与、東照大権現といった幕府の祖神の形成に至るまで、武家政治の正統性に関わる重要な箇所に、すべて朝廷が関与していたのである。 ・この事実からわかることは、天皇の権威は徳川時代を通じて不可欠なものとして存続していたということだ。 ・日本の歴史を見ていくと、さまざまな治政者が登場するが、天皇と無関係に形成された権力は正統ならざるものである、という共通了解がずっと存在していた。 ・明治期に急に天皇を絶対君主に仕立てて、ときの藩閥政権がその安泰をはかったというわけではない。すでに幕末の尊皇攘夷の動きに表れているように、それは古来からの日本政治の原則であった。 ・明治期に及んで「近代国家」の体裁を整えるための憲法をつくるときに、 “天皇制立憲民主主義” としてそれを成文化したにすぎない。 ・そして天皇の「教育勅語」が国家への忠と親への孝を語っているのも、国際化した実情に合わせ、日本の道徳観を再認識させたものといってよい。 ・これを封建時代の家父長制と等しいものと考え、日本を半封建的で前近代的な絶対君主国家である、というテーゼに持っていったのが、ソ連共産党・コミンテルンの「三二年テーゼ」であり、共産党の「講座派」系の学者はその方針にすっかり従ったのである。 ・大山氏の聖徳太子捏造論は、実証の積み重ねというよりも、権力者の存在を否定したがる見解の上に引き出された一理論でしかない。 ・イデオロギーが先行している。 ・「聖徳太子が存在しなかった」という異説の前提に「天皇の権威」を否定したいという意図があるのだとすれば、実証的な歴史家としては失格といってよい。 2 法隆寺美術作品関係の史料の重要性 『釈迦三尊』像は捏造品だという主張 ・大山氏は、実際の「厩戸王」は聖徳太子としての行為とは関係ない、すべて『日本書紀』の捏造だともいう。十七条憲法もそうだし、冠位十二階の制定も、遣隋使も、この厩戸王の事績とは関係がない、という。 ・聖徳太子の居所である斑鳩宮も皇極天皇二年(六四三年)に蘇我入鹿によって焼かれ、氏寺の法隆寺も全焼しているはずなので、現存する法隆寺に残されている遺品も、すべて後代の偽造であるとする。 ・大山氏は、飛鳥時代の美術史は、主に聖徳太子の遺品を中心に組み立てられているので、聖徳太子の実在が問題になるならば存立しえないと述べる。したがって彼は、聖徳太子関係の仏像については、すべて仏像に書かれた銘文だけを問題にしているのである。 ・だが、たとえ銘文が後代に彫られたにせよ、その本体の仏像が様式的に飛鳥時代につくられているとしか考えられない事実が重要なのである。そのことを大山氏はまったく無視している。 ・明らかに聖徳太子と同じ時代の仏像、飛鳥様式であるものは『釈迦三尊』像である。 ・大山氏はさらに重要な事実を無視している。『釈迦三尊』像の台座の墨書銘に «辛巳八月九月作・・・・・・» という年記が見出され、これは書風からみても、この年代のものであることは確かであるとされた。この台座が聖徳太子の薨去の前の年(推古天皇二十九年)に準備されていたものであることが確かになったのである。 『天寿国繍帳』と天皇号 ・中宮寺の『天寿国繍帳』についても、大山氏はその銘文に天皇号が書かれているので、当時のものではなく持統朝以後のものと決めてかかっている。 ・大山氏が問題にしている「天皇号」の使用についても、異論がある。 ・天皇という名は北極星信仰に由来するもので、すでに中国でも一世紀前の六世紀中頃からある。 ・また、『隋書』倭国伝の開皇二十年(推古天皇八年、六〇〇年)の条で、「天皇」という考え方は知られていた。 ・事実、『隋書』倭国伝では «日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無きや» と小野妹子の持参した手紙に書かれており、この「天子」という言葉は、中国「皇帝」と対等の言葉であり、「天皇」の名が知られていたことがわかる。 ・『日本書紀』に聖徳太子の書簡として «東天皇敬白西皇帝» と書かれており、この天皇が天子に対応することが明らかにされている。 ・『薬師如来』像の銘文にも「天皇」の名だけでは使われていないにしても、「天下天皇」とか「大王天皇」と書かれている。もしそれが後代の「天皇」号が使われていた時代のものだとすれば、逆に「天下」とか「大王」とかを入れる必要はないのである。 3 語られない真実 五重塔心柱の年代にどう答えるのか ・法隆寺の建築は、高麗尺(飛鳥尺)といわれる単位で測って造られ、薬師寺東塔などで使われている天智天皇の時代の唐尺(奈良尺、天平尺)と異なっている。 ・法隆寺が再建されたというのならば、この時代にわざわざそこまで似せて造ったと主張していることになる。 ・また五重塔の造り方さえ時代によって異なる。 ・建築でさえ形の様式は時代によるのだ。 ・法隆寺の建物も仏像も、聖徳太子と同じ時代(死後三十年ほどを含めて)であることは動かないのである。 ・平成十三年(二〇〇一年)二月、法隆寺五重塔心柱が五九四年に伐採されたことが判明した。 ・『日本書紀』が「法隆寺に災けり」とした六七〇年以前の伐採年代をどう解釈するのか。 ・さらに、六七〇年以降に伐採された部材があったとしても、当然心柱の年代と尺度の問題は残る。心柱と違って、他の部材は後年修理された際のものだとも考えられるのだ。 ・いずれにしても、心柱が五九四年に伐採されたと発表された事実はゆるがない。 人間神の先駆 ・大山氏が比較しているが、「教育勅語」は天皇の ・日本では原則として天皇の存在は、それ自体「すめらみこと」であり、 ・しかし聖徳太子は天皇ではない。彼は現実の人間である。その存在を高く評価することは、彼自身がもともと人物として評価を受けるべき人格者であり、すぐれた能力の持ち主であったからである。夢殿の『救世観音』像が聖徳太子の姿である、といわれてきたのは、彼が人間であったからである。 ・日本の神道には、天照大神をはじめとする神々の姿と、その子孫である天皇は原則として「偶像崇拝禁止」であるという、貫かれた不文律がある。 ・一方で、聖徳太子像はそれ以後、数多くつくられている。それは神道の人間神の先駆であったからである。 ・聖徳太子が仏教の先駆者であり、法隆寺の創立者であるということは、彼が神道上の人間神となったことを見えづらくさせてきたのである。 中国では抹殺された聖徳太子 ・中国の他国に関する記述は蔑視を基本としている。日本人学者がそのとおりだととる慣習は、戦後できたものであろう。 ・『隋書』倭国伝には六〇〇年の条で、倭国王が «姓は ・六〇八年(推古天皇十六年)に隋からやって来た使節の ・北京の中国歴史博物館には中国と日本の外交関係の立て役者である聖徳太子のことが一切展示されていない。 ・「太子が皇室の出身であるからだ」という。皇室は日中戦争で侵略者日本の象徴であるからというのだ。 ・中国でも、すでに政治的な意図から、聖徳太子は抹殺されている。 ・それと同じ意図が大山氏の所論にも感じられる。その意図は日本の歴史学界にもひそかに生まれ、新たに聖徳太子否定論、軽視論が横行しはじめているようである。 ・それもあたかも文献考証の上に立った学問的な手つきで行なわれているので始末が悪い。 第六章 梅原猛・法隆寺怨恨説の終焉 3 法隆寺建立の年代の新説 ・もともと今の法隆寺は斑鳩寺と呼ばれていた。若草伽藍が法隆寺であり、その焼亡後は斑鳩寺が法隆寺になったと考えられるのである。その斑鳩寺はすでに、五九八年に建てられていたことになる。すると五重塔の心柱の五九四年という年代が必ずしも、早すぎる年代ではなくなるのである。 |