
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年02月01日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
6 |
17/01 |
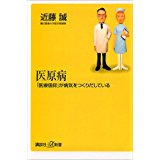 |
医原病 |
近藤 誠 |
講談社+α新書 |
◎ |
第二章 ワクチンと抗菌薬の功罪 有効なのはポリオ、天然痘 ・米国における、はしか( ・経済力が上がって栄養状態がよくなれば、人間の自然治癒力が強化され、衛生状態がよくなれば、感染の機会自体が減るのでしょう。 ・ただ感染症に対し、医療がまったく意味がないと考えるのも行きすぎです。 ・自然治癒力がおよびそうもないほど重篤であれば、抗菌薬が必要な場合といえます。 ・ワクチンのなかにも、確実に有効なものがあります。 ・その筆頭は天然痘のワクチン(種痘)で、ポリオ(小児麻痺)もワクチンが有効です。 抗菌薬から身を守るには ・下痢は、腸内にある病原菌や毒素を体外に排泄するための作用ですから、他の原因による中毒の場合にも止めてはいけません。 ・腹痛というのも、病原菌や毒素を体外に排泄したくても水分が無くてできず、腸管がのたうちまわっているために生じるのだと思います。ですから、腹痛があるからと水分を口にしないのは、逆効果なのです。 ・食中毒かな、と思ったら、まず水を飲む。そして水を飲んでもなおらなかったら、医者のところへ行く。そして点滴をもらい(検便も)、しかし抗菌薬は断る。それが抗菌薬が蔓延する日本で生きていくうえでの一般の方々の自衛策、ということになるでしょう。 第三章 期待と信頼が引き起こす「医原病」 アトピーも医原病 ・アトピー性皮膚炎、気管支喘息、花粉症、 ①合成化学物質など以前にはなかった物質が先進国に出回り、それがアトピーを引き起こしている ②人びとの身体がそなえる免疫の機構ないし機能(免疫状態)が以前とは違ってきた などが考えられます。 ・アトピーの原因調査研究結果 ◉子どもが一歳以内の時期に、家のなかで犬や猫を飼っている場合には、後年アレルギー性鼻炎や気管支喘息にかかる頻度が低かった。 ◉子ども時代に同居している人の数が多いほど、後年、アトピーにかかりにくかった。 ◉生後六ヵ月から一一ヵ月までに保育所に通いだした子どものほうが、それ以降に通い始めた子どもよりアトピーにかかりにくかった。 ・なぜペットや保育所が影響するのか。おそらく子どものときにどういう細菌やウイルスなどに感染したかが、その後の免疫状態にを左右するのでしょう。 ・アトピーに関しては、環境汚染よりも清潔度のほうが影響が大きいらしい。先進国でアトピーが増えたのは、清潔度が上がって子どもたちの免疫状態が従来とは違ったかたちになったため、というかの姓が高いわけです。 ・アトピーが増えたのは、青洟をたらす子がいなくなったことと関係がある。 災いとなる清潔好き ・目の下にある骨を上顎骨といい、なかは空洞になっていて、 ・慢性の副鼻腔炎が減ったことが、おそらく上顎洞がんが激減した理由で、それは好ましい変化です。しかし青洟をたらす子がいなくなったという環境ないし免疫状態の変化が、アトピーを増やしたのだとすれば、そう喜んでもいられません。 ・「清潔仮説」 新生児の免疫状態は大人と異なっている(特にヘルパーT細胞の反応性に違いがある)。免疫状態が順調に成熟するには種々の感染を経験しなければならない。生後すぐに清潔な環境におかれると、免疫状態が成熟することができず、アトピーが増加する、という仮説。 ・アトピーが増えたのは、寄生虫の感染率が低下したからだという説も、実質的に同じことをいっています。 ・先進国では清潔好きは災いをもたらすわけで、いわゆる「抗菌グッズ」の製造・販売や使用はやめなければなりません。 ・自分の子が将来アトピーにかかる可能性をできるだけ減らしたいと思うなら、乳児のときからある程度不潔ともみえる生活をさせ、抗菌薬をなるべく使わず、ワクチン接種をぎりぎり必要なものだけに絞ることが肝要です。 ・その意味で、保育所や公園の砂場の砂を(犬猫の糞が混じっているからと)消毒するのは逆効果でしょう。 「病院には来なさんな」 ・抗菌薬がからんだ医原病には、ほかに多剤耐性菌による感染症があります。 ・有名なものはMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)で、メチシリンというペニシリン製剤をはじめ、ほとんどの抗菌薬が効きません。 ・多剤耐性菌が生じる理由ははっきりしています。医者が抗菌薬を濫用するからです。 ・わたしは、抗がん剤治療を受けて白血球が下がった患者さんに「MRSAなどがウヨウヨしているから、なるべく病院には来なさんな」と伝えています。 第六章 医者の心理と患者の心理 うどん粉で痛みがとれることも ・毒にも薬にもならないはずの物質が発揮する効果を「プラセボ効果」「偽薬効果」などと呼びます。 ・人の心理がさまざまな身体的症状を強めたり弱めたりすることがあります。 ・副作用がなく、望む効果だけを得ることが出来るプラセボは、たとえ効果発揮率が低くても、臨床上有用なことがあるわけです。 いつわっているという後ろめたさ ・しかしプラセボが有用であることと、使用が許可されるか否かは別問題です。 ①患者を喜ばせるためなら嘘をついてもよいのか ②万一プラセボであることが患者さんに知れたとき、患者さんを傷つけないか ③担当医に対する不信感が芽生えないか などの難問がつきまといます。 ・仮に「プラセボはけしからん」といってみても、薬を飲む場合にはプラセボ効果と無縁でなくなります。多くの薬では、本来の作用による効果のうえに、プラセボ効果が上乗せされているからです。つまり、ある薬の有効率がAパーセントであれば、そのうち何割かはプラセボ効果によるのです。 ・プラセボ効果は、どの程度あるのでしょうか。この点、うどん粉のような純粋なプラセボでも「三割程度の人に効果がある」などと、一般論として三割という人もいます。 ・プラセボ効果の面からは、患者にとって陰気な医者より、快活な医者のほうが好ましいといえます。 臨床試験とプラセボ ・そもそも薬の説明をインフォームド・コンセント(患者さんが医療者から説明を聞いて、自分で治療法を決めること)の問題と考えた場合、患者さんの判断材料とするため、医者や薬剤師は正直に語る義務があるとされます。それなのにプラセボ効果については語らなくてよいとするなら、その理由づけが必要です。 臨床試験で得をするのはだれ ・新法にすれば生存期間がのびるという因果関係を承認した場合、最も利益をうけるのはだれかという問題がある。 ・この点、患者のほうからみると、かりにこれらの新しい抗がん剤で生存期間がのびるとしても、数ヵ月程度のことで、最終的になおる率は変わらず、副作用はしっかりこうむるので、治療を受ける意味や利益があるかというと疑わしいことになります。 ・これに対し医者のほうはというと、因果関係が認められれば、抗がん剤治療をうける患者は増えこそすれ減りません。そして患者が増えれば収入も増加し、抗がん剤治療によって生じた副作用を治療することによる収入増も見こめるわけです。 ・このような客観情勢があるなかで、くじ引き試験の担当者となって論文を発表するのは、因果関係が認定されれば仕事や収入が増えることが確実な「腫瘍内科医」たちです。 ・数百人を被験者として実施したくじ引き試験が、同種のがんに対し未来永劫にわたって、数十万人、数百万人に対し、抗がん剤治療を行う根拠となりえます。その場合、腫瘍内科医たちが無意識にしろどのような行動を取る可能性があるか、想像に難くありません。 ・どのような領域のくじ引き試験でも、それを実施するのは試験結果によっては利益を得ることになる専門家たちですから、くじ引き試験や結論を鵜呑みにせず、試験結果を報じる論文をしっかり吟味する必要があります。 医者や製薬会社の思惑 ・一般には、心理状態ががん患者の寿命を左右すると考えられています。そして明るく前向きに生きることが大切である、ストレスをうけない生活をすべきである、家庭・友人や医療者などの心理的サポートが大事である、などといわれている。 第七章 健康診断は安心をもたらすか 八割以上が「異常」の判定 ・日本病院会の一九九九年の全国集計によれば、人間ドックの健康診断で「異常なし」と判定された人は、じつに一六パーセントという少なさでした。八割以上が、なんらかの異常や問題点を指摘されていることになります。 なぜ「異常なし」が少ないか ・日本動脈硬化学会が決めたガイドラインの基準にしたがうと、日本には高脂血症の人が二〇〇〇万人以上いることになってしまうのです。 ・糖尿病や高血圧にも同じ問題があります。糖尿病は血糖値で、高血圧症は血圧で診断するのですが、それぞれの専門学会が決めた基準範囲の上限がかなり低いため、日本には、糖尿病患者が六九〇万人、高血圧症の患者が二〇〇〇万人以上いるのだそうです。 ・その数の成人病患者がいるというのは、日本人がよほど不健康なのか、専門学会が決めた基準が不当なのか、どちらかでしょう。 学界のさじ加減で決まる患者数 ・高脂血症、糖尿病、高血圧症はそれぞれ血中コレステロール値、血糖値、血圧という、検査によってしかわからない測定値が基準範囲を超えていれば診断されるという仕組みです。 ・それら診断名をつけるに際しては、症状の有無は関係ないのです。 ・数ある病気のなかで、このように測定器のみにたよって診断名をつけるものは他にあまり例をみません。 ・その結果どういうことになるかというと、専門学会が基準範囲となる数値を少しいじれば、受診者自身の体調になんの変わりがなくても、今日から糖尿病といわれたり、高血圧症と診断されたりするわけです。 ・基準範囲をわずかに動かすだけで、患者の数を数百万人単位で増減させることができるわけで、ある意味で各学会は打ち出の小槌をにぎった格好です。 思いつきで始まった人間ドック ・じつは人間ドックは、日本で生まれたシステムです。 第八章 いつわりだらけのがん検診 都合の悪い事実を隠蔽 ・大腸がん検診にしても、検診の専門家が寿命はのびないというのですから、皆さんが受ける意味がない。 「検診をうけてよかった」の短絡 ・がんもどき理論によれば、検診で発見されたがんは、「本物のがん」か「がんもどき」のどちらかになります。本物のがんであればね治療しても治らず、がんもどきならば、治療しないでそのままにしても命取りにはならないので、どちらにしても検診で発見する意味はありません。 ・がんもどき理論によれば、がん検診の精度を上げると、より多くのがんもどきが発見されて、より多くが不要な治療をうけることになるのですから、被害が拡大することとほぼイコールです。 「要精検」の確率 ・一人を発見するために、一〇〇〇人を検査して、その一〇〇〇人に結果がでるまでの数日から数週間、なにがしかの不安を与えます。そして二〇〇人ほどが「要精検」といわれて飛び上がるほどびっくりし、内視鏡検査をうけるまで不安な日々を送る。ようやく苦しい内視鏡検査がすんでも、正式に結果を聞くまでびくびくし、そして一九九人が「がんではない」という結果を聞くわけですが、それでもずっと心は晴れません。 第一〇章 医者が増えれば病気も増える 厚生省は何をしているのか ・厚生省は医者や製薬企業の味方です。他の官庁もそうですが、指導し規制する対象としての医療産業があってこその厚生省です。医療産業が衰退すれば天下り先も細くなるなど、役人にとって種々の不都合が生じます。 ・そのためでしょう、厚生省は人びとの病気への恐怖や不安をかきたてる尖兵の役割をになっています。 権威を批判できないジャーナリズム ・ジャーナリズムが批判勢力となって警鐘を鳴らし、医療の価値の本当のところを人びとに知らしめてくれればよいのですが、それもほとんど期待できないのが現状です。 ・というのも、一部にすぐれた人はいるものの、独自のデータ収集力と分析力がないため、権威たちを取材してその言葉を右から左へ流すだけの仕事しかしていない記者やライターが多いからです。 ・取材の途中で問題点に気づいても、少しでも批判的なことを書けば次から取材に応じてもらえなくなるであろうことを恐れてか、特定の医療行為や医者たちを持ち上げる記事内容になるケースが大半です。 ・記者クラブ制度も問題です。省庁内に新聞やテレビ局の記者が常駐してニュースを追うというのが建て前ですが、実際には取材力の関係で、役所が発表したことをそのままニュースとして流してしまうことが多い。 ・厚生省にしてみれば、記者たちをあやつるのは赤子の手をひねるようなものです。記者たちに、これこれが危険だという情報を流しさえすれば、ストレートに報道してもらえ、人びとの病気に対する恐怖や不安を増大させ、医療産業への助成が正当であるかのように思わせることに成功する。こんな便利な機関はそう存在しません。 |