
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年07月18日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
53 |
17/06 |
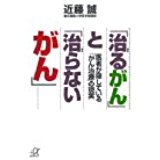 |
「治るがん」と「治らないがん」 |
近藤 誠 |
講談社+α文庫 |
◎ |
第一章 医者はなぜ、その治療法を選ぶのか 放射線治療の「こわさ」の正体 医者のウソから生まれた誤解 ・放射線は日光の仲間であるから、放射線治療によって、皮膚の赤らみや水泡といった日焼けと同じ症状がでる。 ・放射線はがん細胞の遺伝子を傷つけ、細胞分裂がうまくいかないようにする。正常細胞の遺伝子も傷つけられるが、がん細胞のほうが弱いので、がん細胞だけが死ぬといわれている。しかし、一定線量を超えれば正常細胞も死んでしまい、障害が永久に残ることになる。 ・放射線で発がんする、という話もある。これは事実である。放射線はたしかに発がん作用があるのだ。 ・診断のための検査にも発がんの危険があって、たとえばバリウムを飲む胃のレントゲン検査(このとき照射するX線は放射線である)だけでも、年間数百人が白血病その他のがんにかかると推計されている。 ・放射線治療は原則として一回かぎりの治療だ、ということもあまり知られていない。 放射線の影響が残っている。照射をされたという記憶は、細胞や組織や臓器に永久に残るのである。 第三章 「非科学的」な日本の医学 無意味な検診をやめられない「業界」事情 欧米にはない「肺がん検診」 ・胃、肺、子宮、乳房などのがん検診が有効という証明は、じつはされていない。 ・肺、大腸、乳房の検診には、「クジ引き割り付け試験」のデータがある。 ・これは一種の人体実験で、数千人ないし数万人を二つのグループに分け、片方のグループは放置し、他方は検診を繰り返して、がん死亡が減るか否かを調べる研究法である。 ・肺がん検診については、欧米でいくつかのクジ引き試験がおこなわれ、いずれも有効性が否定された。 ・それで欧米では「肺がん検診を公衆衛生上の施策にはできない」との結論になり、現に肺がん検診は実施されていない。 問題は、「いつ打ち切るか」だけ ・胃と子宮がんについては、世界のどこにもクジ引き割り付け試験のデータがないが、わが国では古くから検診が実施されている。 ・そもそも胃がんや子宮がんは、自然に減り始め、しかも減少の一途をたどっている。 ・今日、全子宮がんの4分の1までが検診で発見されるというが、検診開始以前から死亡率の減少傾向はほぼ一定で、検診が影響した気配はない。 検診で見つかる早期がんは「がんもどき」 ・人を殺さない「がん」の存在が実証されている。 ・他の病気で死んだ人を解剖したときに偶然見つかる「がん」がそれで、その人を死なせた原因ではない。 ・このようながんを「潜伏がん」とか「潜在がん」とか呼ぶ。 ・潜在がんが最も多いのは、おそらく前立腺がんで、五〇代では二〇パーセント、七〇代では四〇パーセントという報告もある。 ・しかし、これらのがんで死ぬ人はごくわずかで、日本の統計では甲状腺がんは全死亡原因の〇・一パーセント、前立腺がんは男性死因の〇・八パーセントでしかないから、潜在がんのほとんどが「致死性」ではないようだ。 ・胃では、六〇歳以上の人を解剖してみると、潜在がんと考えられる早期胃がんの頻度は五パーセントという報告がある。なんと、がん検診での胃がん発見率の五〇倍以上にも相当する。 「のんびりがん」という考え方 ・がんの中には、のんびりがんとスピードがんとの二種類がある。 ・スピードがんは増殖速度が速いから、早期がんのうちに発見されるチャンスは少なく、ほとんどは進行がんの状態で発見されることになる。 ・こう考えれば、早期がんとして発見されるものは倍増期間が長く、進行がんとして発見されるものはそれが短いという、臨床でよく観察される事実をきれいに説明できる。 ・潜在がんがきわめて多い事実や、放置・観察データからは、早期がんの大部分をのんびりがんが占めていると考えられる。 放置すれば、本当に転移するのか ・乳がんでは、死因の九九パーセントは転移による。早期がんの治癒率・生存率が高いのは、転移していない時期に見つかるものが多いからである。 ・乳がんの原発部位での再発と転移の関係について共通しているのは、「原発部位での再発がふえても転移は増加しない」という事実である。 ・治療・再発という増殖形式の場合に転移がふえないならば、放置・増大という増殖形式の場合にも、転移はふえないと類推できる。 ・そうすると、現在転移のない患者さんは、放置しても転移は生じないと考えてよいのではないか。 ①がんが早期発見できる大きさになるまで転移しなかった患者さんでは、そのまま放置しても転移は生じない。 ②転移するがんでは、がん細胞が分裂を初めてまもなく転移が起きてしまっており、早期発見でもとても間に合わない。 ・ゆっくり発育するのんびりがんは転移しにくく、勢いよく分裂・増殖するスピードがんは転移率が高い。 顕微鏡では「がん」に見える「がんもどき」 ・のんびりがんや転移しないがんは、顕微鏡では「がん」に見えて、性質上は「がん」ではないという意味で、「がんもどき」と呼ぶことができる。 ・アメリカでの統計をみると、単位人口あたりの乳がんの死亡数は一定なのに、乳がん発生率は一貫して増加している。 ・この期間、治療法にとくに前進があったわけではないのに死亡数がふえなかった事実は、致死性の乳がん発生数が一定であったことをうかがわせる。 ・つまり、住民の啓発や早期発見の努力によって、顕微鏡的には「がん」だが、じつは致死性ではない「がんもどき」の発見数がふえた、と考えられるのだ。 ・大阪府の子宮がんデータでは、死亡数は一貫して減っているのに、発生数の減少傾向が頭打ちなのだ。 ・このことは、子宮がん検診の導入をはじめとする早期発見努力が功を奏したからとも、検診で発見される「がんもどき」がふえたからとも解釈できる。 ・しかし、検診関係者は前者だけを特筆大書し、後者の化膿性には触れない。がんもどきの存在を認めると、がんでないのに臓器を切除していることになってしまうからだろう。 ・今後、「がん」と「がんもどき」とを区別できるようになる可能性はわずかである。 ・なぜなら、「がん」と診断すれば道義上、放置・観察はできず治療することになるので、それが致死性だったか否かは知ることはできないからだ。 ・ある病理医が「がん」といい、他の病理医が「良性」と診断するような病変は、いずれにしても致死性ではないのだろう。 医者に行くのは、症状がでてからにする ・がんもどきなのに臓器切除をされてしまうことを避けるコツは、症状がでてから医者へ行くことである。 ・検査に頼るよりも、自信で身体の調子の変化に気をつけていたほうが生産的なのではないか。 ・近代医学は、がんを早期発見しようとして、がんもどきをも発見するようになった。 ・がんもどきが全病変中に占める割合がふえれば、治癒率・生存率はおのずと向上するだろう。 ・しかしそれは治療法の進歩ではなく、むしろ臓器を失う被害者の増大を意味している。 ・ある事柄が究明されて行途中の段階では、その事柄を説明する理論が、ふつう複数存在する。 ・がんの場合にも、あくまですべての早期がんが「がん」であるという立場をとこともできる。しかし論理則に従えば、相反する理論がある場合には、どちらかが間違っているのである。 ・それらの理論の優劣は、「どれが現実によく合うか、どちらが矛盾を含むか」によって決められるべきである。 ・このような観点からは、がん検診を有効とする早期発見理論がまだ生き延びているのは驚くべきことだ。 ・スピードがんは、早期に見つかっても助かるのは難しい。 ・また、のんびりがんがスピードアップして致死性になるという前提も、非常な無理をしている。 ・そして、治療してもほとんど無益なこのスピードがんと、治療がほぼ不要なのんびりがんが、ひとくくりに「早期がん」と診断されている。 ・複数の解釈が可能なとき、一つの解釈だけを取りいれて他を排除し、現実に具体的なシステムを構築してよいとは思われない。 ・しかしがん検診システムは築かれ、その結果、臓器切除までされているのだ。 ・人体にメスを入れるなら、本来はどんな反論も許さない理論を作ってからにすべきである。 科学を装う「クジ引き人体実験」 医者になって最初の仕事が人体実験 ・日本ではこれまでにも、無数のクジ引き試験をしてきた歴史がある。薬の実験がそれである。 ・薬は原則として「 ・一つの薬の実験が数百人の患者さんを対象にしたとすれば、たくさんの実験で実験台となった人は無数にいるはずである。それなのに、周囲に経験者が一人もいないのは、どういうわけだろうか。 ・欧米では、一人に五種類以上の薬を処方すると「犯罪的」と評価される。ところが、日本では、初診したその日に一〇種類も処方するのは日常茶飯事である。 ・最近、院内感染が問題となっているMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)も、手術後の感染予防に第三世代セフェム系抗生物質を、一週間も一〇日間も使用してきた外科医や整形外科医などの愚行に発した問題である。 ・たいていの術後感染予防は、第一世代の抗生物質を一日も使用すれば十分なのだ。 漢方をすすめる「西洋医」の矛盾 素人の気を引く無責任な医者 ・西洋医学でも、抗がん剤や手術だけですべてを殺せるとは考えていない。抗がん剤や手術で、がん細胞の数をまず少なくしておいて、あとは自然治癒力が最後の一細胞まで殺すのを待とうというのである。 |