
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年08月29日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
54 |
17/06 |
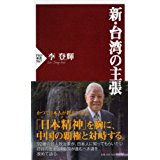 |
新・台湾の主張 |
李登輝 |
PHP新書 |
◎ |
はじめに ・アメリカがかつての覇権を失い、多極化する「Gゼロ」の世界において、日本が生き抜くための改革を成し遂げるには、日本人一人ひとりが志をもって行動することが不可欠だ。その前提となるのが、自国の歴史と文化に対して誇りと自信をもつことである。 ・それが結果的に東アジアの安定に繋がり、日本と台湾によい関係をもたらすことになろう。 ・日台の絆は歴史に基ずくものだ。しかし、過去の日台が歩んできた道について知らない人がいかに多いことか。 ・日本と台湾は生命(運命)共同体である。日本がよくなれば台湾もよくなり、その反対も然りである。 第一章 日本精神に学ぶ 映画「KANO」のこと ・台湾人が好んで用いる言葉に「 ・これは日本統治時代に台湾人が学び、日本の敗戦によって大陸からきた中国人が持ち合わせていない精神として、台湾人が自らの誇りとしたものである。 ・「勇気」「誠実」「勤勉」「奉公」「自己犠牲」「責任感」「遵法」「清潔」といった精神を表す。 ・この「日本精神」に触れることをとおして、台湾人は中華思想の呪縛から脱し、「公」と「私」を区別する武士道的な倫理に基づいた民主社会を確立しなければならない。 台湾近代化の基礎を築いた後藤新平 ・日本は台湾を近代化させた。日本統治によって、台湾は伝統的な農耕社会から、近代社会に変貌したのである。 ・欧米諸国には植民地を近代化しようという発想はなかったから、日本統治の方法はたしかに異質であったといってよい。 ・後藤新平が台湾で働いた八年七ヵ月で、台湾は未開発社会から近代社会へと「一世紀にも等しい」といわれるほどの開発と発展を遂げる。 ・台湾近代化の基礎を築き上げた後藤の功績は、非常に大きい。 ・台湾開発にあたって、後藤がまず断交したのは人事の刷新と登用である。 ・後藤は台湾に着任するや、高等官も含めて能力の低い千人余りの官僚を日本に追い返した。当時の役人は、台湾でひと稼ぎしようとする者ばかりだった。 新渡戸稲造による製糖業発展の基本方針 「嘉南 近代日本が失敗した原因 ・結局、真珠湾攻撃はアメリカの挑発に乗ってしまったのだと私は考えている。少数の犠牲をもとに、戦争の大義名分を得る。 第二章 台湾民主化への道 「犬が去って、豚が来た」 ・一九四五年九月、大陸の国民党は陳儀を台湾主席に任命。 ・台北に進軍している国民党軍を台湾人は当初歓迎するつもりであったが、あまりにもみすぼらしい軍装に愕然とする。 ・一糸乱れぬ規律ある日本軍の行進になれた台湾人にとっては、国民党軍はあまりに乱雑なものにみえたのである。 ・それまで台湾に住んでいた者を「 ・台湾接収後、国民党は「日本化されたもの」を抹殺する政策をとり、反日教育を行った。 ・国民党は中国人の観点による歴史文化を注入し、台湾人を「中国人」に変えようとした。 台湾人を恐怖の底に陥れた二・二八事件 ・一九四七年二月二十七日の夕刻七時ごろ、台北の太平町で闇タバコを販売していた四十歳の寡婦が、専売局台北分局に所属する取締官や警官にタバコと売上金を没収され、銃の柄で頭を殴打された。 ・これをみていた周囲の民衆は憤激。騒ぎが大きくなると、取締官は民衆に向けて発砲し、死者が出る。 ・翌二十八日、抗議の市民デモが行政長官公署に向かうと、国民党の兵士は広場の民衆に対して一斉射撃を始め、多数の死傷者を出す惨事となった。 ・これに怒った民衆は同日午後二時すぎ、新公園に集まると、台湾放送局に入り、抗議の放送を開始。こうして騒乱が台湾全土に広がることになった。 ・三月八日、陳儀からの救援要請を受けた国民党軍は基隆と高雄に上陸。各地で武力を用いた掃討と鎮圧を行なった。 ・民衆を二万八〇〇〇人以上惨殺し、台湾人を恐怖の底に陥れた。 ・事件の発端になったのが二月二十八日だったので、「二・二八事件」という。 ・この事件の開明が進んだのは、私が相当に就いた一九八八年以降のことである。 仲間と古本屋を経営 ・マルクスによれば、革命が起こるのは高度に資本主義が発達した国である。当時の中国はそうした段階にはほど遠かった。革命の担い手となるような労働者階級も育っていない。 ・結局、中国共産党は皇帝型の専制政治の手段として、マルクス主義を謳っているにすぎないと気づいたのである。 三十八年間に及んだ戒厳令 ・四九年五月二十日、台湾省の警備司令部は治安維持を名目に戒厳令を布告。言論、出版、集会、結社などの自由を制限した。 ・この戒厳令は八七年七月十五日に解除されるまで三十八年間実施され、世界史上例のない長さとなる。 ・いかに台湾人が不安と恐怖のなかで長い年月を過ごさなければならなかったか、想像できるであろうか。 ・いわゆる国共内戦は、中国共産党の勝利に終わった。四九年十月、中国共産党は中華人民共和国の建国を宣言する。 ・一方、大陸から追われた国民党政府と国民党軍は台湾に逃れてきた。 ・以来、「反攻大陸」を国策とした国民党は独裁体制をつくり上げ、多数の反対分子を逮捕して投獄、殺害するなど、迫害を繰り返した。 総統になったのは「歴史の偶然」 ・蒋経国総統は台湾の民主化、ないし国民党の本土化(台湾化)を進めなければ、未来はないと考えるようになっていたと思う。 ・台湾で資本経済が発展したのは彼の功績であろう。 ・蒋経国総統時代の八七年七月、三十八年間にわたって施行されていた戒厳令がついに解除された。同時に、政党結成とメディアの規制も撤廃された。 ・すでに前年の八六年、民主進歩党(民進党)が結成されている。蒋経国総統はこれを事実上、黙認するかたちをとった。 「国家統一綱領」を定めた真意 ・この綱領は「統一」の条件として、次の三つを掲げていた。 一 中国の政治が民主化されたとき 二 中国が自由経済になったとき 三 中国が公平な社会になったとき ・この三つの条件がそろったときに、初めて「中国側と話し合いを始める」ことにしたのである。 台湾省の凍結を決定 ・四七年に設置された台湾省は、当時まで残っていた。いつの日か中華民国は「中国全省」を中国共産党から奪還するという建て前からである。つまり台湾省とは、自己満足のための見せかけにすぎなかった。 ・台湾省を凍結するということは、古い利益誘導政治にメスを入れるのと同時に、中国の「台湾は中国の一省」という虚構を突き破り、台湾の主体性についてより多くの人が目覚める結果になった。 ・台湾は台湾である。中国の一部ではない。真実はそれ以外の何ものでもなかった。 真っ先に到着した日本の救助隊 ・地震発生後、真っ先に到着したのは、日本の救援隊である。人数もいちばん多かった。 ・規律ある行動は、さすが日本人で組織された救援隊だった。 ・遺体が発見されるたびに敬礼、黙祷を捧げ、「救助できずに申し訳なかった」と家族に詫びる姿に、「日本精神」のなんたるかをしったのであろう、日本隊が帰るとき、空港ロビーは期せずして台湾人による盛大な拍手に包まれた。 ・小池百合子衆議院議員は仮設住宅の提供を申し出てくれた。小池氏は阪神・淡路大震災後の再建活動に参加しており、台湾大地震にも大きな関心をもっていた。 ・彼女は「台湾の官民による救助活動への参加と資源活用の効率のよさは、日本より優れている」と語った。 ・さらに、当時曽野綾子氏が会長を務めていた日本財団は三億円を寄付してくれた。 ・自らお見舞金の授与式に来られた曽野氏に対して、もし将来日本で何か起こったら、真っ先に駆け付けるのは台湾の救助隊であることを約束した。 第三章 新台湾人の時代へ 「李登輝転向」? 週刊誌の曲解報道 ・「李登輝転向」「台湾独立を放棄」――台湾の大衆向け週刊誌『壹週刊』(二〇〇七年)にこんな見出しが載った。 ・私の真意はこうであった。「台湾はすでに独立国家であり、いまさら独立を宣言する必要はない」。 ・戦後の台湾は国民党という外来政権による一党独裁の支配下に置かれていた。 ・しかし、九六年の総統直接選挙では、国民が自ら国家の指導者を選べるようになった。つまり台湾は、外来政権による支配から解放されたのである。 ・まして当時は、台湾生まれの台湾人による民進党政権の時代である。であれば、なおさら台湾は「完全な独立国家」であろう。 ・すでに台湾は独立国家なのに、いまさら独立を主張する必要はない、といったのである。 ・私がこのように述べたのは、与野党の無意味な権力闘争をやめさせるためであった。 ・民進党と国民党は「台湾独立か、統一か」というテーマを掲げて権力闘争を繰り広げるばかりで、国民生活を顧みようとはしなかった。 ・私は今まで一度たりとも「台湾独立」を主張したことはない。 ・台湾はすでに実質的に独立しているのだから、ことさら国際社会に摩擦を起こすような発言をする必要はなく、むしろ台湾が台湾として「存在」することこそが重要だと考えているからである。 台湾の国家正常化とは何か ・よく台湾の政治勢力は、独立派と統一派の二つに分けて見られる。しかし、そもそも台湾には中国との統一を望む国民などほとんどいない。 ・じつに八割以上が中国と台湾の両岸関係について「現状維持」を望んでいる。 ・台湾の現状とは何か。中国に隷属しない、独立した状況である。 ・台湾の国家正常化を計るには、まずこうした民意を踏まえなくてはならない。 ・独立か否かの神学論争は無意味なだけではなく、国民を二分させ、対立を激化させるだけである。 ・それによって政治の停滞は、国民に計り知れない損害を与えることになる。 ・たしかに台湾の国家形態は、国際社会のなかでは前例のないものである。 ・私は、台湾と中国の関係は「特殊な国と国の関係である」と明言した。 ・外国からどう見られようと、「台湾は独立国家である」という否定できない現実を内外にはっきり示したわけである。 ・国際社会に対して「台湾は独立国家である」ことを明示してみせたことで、国家正常化への「第一歩」を踏み出した。 ・台湾の国家正常化とは何か。それは国号を中華民国から台湾に正し、台湾の現状に即した憲法を台湾人自らが制定することである。これは簡単なことではない。 ・この作業を可能にするための不可欠な第一歩が「台湾は一つの主権独立国家である」との "コンセンサス"を確立することなのである。 民主化進展を阻む台湾固有の問題 ・さらに台湾には民主化進展を阻む固有の問題がある。「反民主」イデオロギーを抱く古い体質の政党があり、このなかに中国共産党と手を結ぶ「反台湾派」がいることである。 ・台湾には、自国の主体性が台湾海峡対岸において中国の併呑野望に左右されるという事情がある。 ・私は、論文のなかで、「台湾の併呑は中国共産党の国事である」と書いた。 ・実際に二〇〇五年三月十四日、中国は反国家分裂法を制定し、台湾を侵略する正当性を確保しようと試みた。 経済的に独立した「台湾モデル」こそ上策 ・現在の台湾に必要なことは、国家指導者が台湾はどのような存在なのか、どこへ向かおうとしているのかについて、確固たる座標軸を打ち立てることである。 ・改めて台湾という「我」を問い直し、自分たちの運命は自分たちで決めていくという心構えと備が必要だ。 ・現在の中国による台湾への優遇策とは、政治的意図に基づく一種の補助金漬けであり、それを頼りにしてしまうと、国からの補助金、交付金頼みの日本の地方行政のように、台湾は次第に弱体化し、経済的競争力が長期的に失われてしまう。 ・台湾は台湾として、一個の独立国家として独自に成長していく「台湾モデル」を確立すること。これが中国という機会を活かしつつ、中国の動向に翻弄されずに済む上策と考える。 ・なにより大切なのは、台湾の政治体制が中国の政治体制よりもよいと台湾人自身が認識、理解し、台湾の国家指導者もそのことを国民に訴え続けることである。 ・日米欧の先進諸国が台湾に抱く連帯意識も、台湾の民主的で市民の自由や人権を尊重する政治体制があればこそだ。 ・したがって、自由で民主的な政治体制に磨きをかけ、一人ひとりがいっそう尊重される社会、すなわち、自由と人権と民意が尊重される国家を建設する王道政治を実践し、台湾政治のさらなる近代化を進めることが求められる。 「新台湾人」というコンセプト ・私が一連の民主改革を進める過程で打ち出したのが「新台湾人」というコンセプトである。 ・われわれが台湾で達成した民主改革は、何千年来の封建思想並びに社会体制を打破したものであり、新しい歴史のはじまりといっても過言ではない。 ・そのうえで、省籍や族群、出身地の違いを乗り越えた新台湾人(新しい時代の台湾人)として団結し、台湾という「生命(運命)共同体」の絆の強化に力を合わせようと呼びかけた。 ・中国は長らく経済利益を餌に台湾国民の歓心を得ようという統一戦争を仕掛けてきたが、近年、これとは裏腹に「自分は台湾人である」という台湾意識が高まっている。 ・「台胞」とか「台商」として中国に親族訪問、あるいは投資をしてきた人たちが大陸の現状をじかに見るにつれ、かつての中華幻想を捨て、台湾こそ自分の拠り所だと再認識しはじめている。 ・結局のところ、台湾の地に腰を据え、実直に生きてきた台湾国民にとっては、自らの台湾意識に帰着することが自然の理といえよう。 ・新台湾人であるならば、台湾は中国とは別の国であり、中国の属国ではない事実をはっきり認識できる。 ・そして新台湾人であるならば、中国と統一に関する対話をすべきではないのも、また当然のこととなる。 第四章 日本と台湾の国防論 日本の集団的自衛権行使を歓迎する ・二〇一四年七月、日本は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行なった。 ・アメリカやオーストラリアはもちろん、インドネシア、フィリピン、ベトナムなどASEAN諸国の一部も賛同の意を示した。 ・中国は尖閣諸島や南シナ海の問題でもはや軽率な行動に出られなくなり、安倍首相の決断が東アジアの安定に大きく寄与することは間違いない。台湾にもよい影響をもたらすであろう。 ・経済力を背景に、ベトナムから西沙諸島を奪い、南沙諸島でフィリピンが領有していた地域に手を出し、そして日本領土である尖閣諸島の領海、領空侵犯を繰り返す中国は、札束の力を笠に着て威張り散らす「成金」の姿そのものである。 ・現在の中国のGDPがアメリカに次ぐ世界第二位といっても、一人当たりのGDPは七〇〇〇ドル、日本の六分の一でしかない。 ・貧富の差は極端で、総人口の一%にすぎない富裕層が個人資産の三分の一を独占している。 ・近年の中国は、自国民の不満を逸らすため、周辺国に覇権的な干渉を繰り返しているが、こうした動きは今後も続くのではないかと、国際社会は危惧している。 ・中国の軍事的膨張と実力行使により、アメリカは大きな負担を強いられているが、中国側はアメリカ単独では東アジアの安定を維持する力がないことを見抜いている。 ・日本はこれまでのように、何でもアメリカ頼みの政治姿勢を改める必要がある。あくまで対等なパートナシップを築くことを優先し、日米同盟は新しい時代を迎えたと考えるべきだ。 なぜ人類は戦争を繰り返すのか――トルストイの箴言 ・集団的自衛権や軍備の問題を忌避する人びとは、結局のところ、人類の歴史は異なる国や組織、権力間の興亡の繰り返しであることを無視している。 ・たんに「戦争はいけない」「人道に反している」と口先でいっているだけでは、平和はけっして実現されない。 ・外圧に対してどう平和を保つのか。その具体的手段を考えるのが、指導者の務めなのである。 ・ロシアの文豪・トルストイが書いた『戦争と平和』で彼は述べている。 「何のために数百万の人間がおたがいに殺し合ったのか、世界の創造の時から、それは肉体的にも、精神的にも悪だということがわかっているのに? それが必然的に必要だったからであり、それを行いながら、人間たちはミツバチが秋になる頃おたがいに殺し合い、動物の雄たちがおたがいに殺し合う、あの自然の、動物学的法則を実現していたからである。それ以外の答えを、この恐ろしい問いに答えることはできない」 武力の必要性 ・国際政治では、個々の国家に対して強制力を行使しうる法執行の主体は存在しない。国連のような国際機関にもそのような強制力はない。 ・自国の国防や安全を委ねる主体が国際政治には存在しない以上、各国は武装して存立を保つほかに選択肢がない。 ・それぞれに主権を主張し合う国家が軍を保持することで、互いに対抗し続ける世界としての国際政治が現出する。 ・国家によって分断された国際政治の現実とは、互いに主権をもつ国家が国益を最大にするべく、闘争を繰り返す過程なのである。 ・戦争はいまでも国際政治における「現実」である。その現実を冷静に見つめて軍隊を保持しつつ、戦争に訴えることなく秩序を保ち、国益を増進する方法を考えるのが、もっとも有効な見解だといえる。 台湾の地政学的重要性 ・現在の状況からして、中国が日本や台湾のような民主国家になるのは「無限に遠い先」のことであろう。 ・中国に対しては、台湾やアメリカ、日本、オーストラリアといった民主国家が連携して人権抑圧などに歯止めをかけることが鍵になる。 ・台湾が中国の侵略を受けた場合、いちばん打撃を受けるのは日本である。 ・台湾海峡には一日四〇〇隻の船が通っている。日本はシーレーン(海上交通路)を中国に押さえられてしまい、喉元を締め付けられるように屈服を余儀なくされる。 ・そして台湾の次は尖閣、琉球(沖縄)、朝鮮半島と、一歩ずつ日本に迫ってくることだろう。 ・日台両国は人権と平和を重視する価値観を共有するアジアでもっとも民主的な国家である。 ・また両国はともに海洋国家であり、たとえばシーレーンなど多くの点で利害が一致している。 ・日台両国は一緒になって東アジアの安定と平和を守る必要と義務がある。そのためには、安全保障上の対話が不可欠だ。しかし残念ながら、両国はそうした協力関係を築けていない。 ・日本人の多くは台湾が日本の生命線であることを理解し、台湾との関係を重視している。 ―― 完 ―― |