
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年08月18日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
58 |
17/07 |
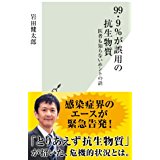 |
99・9%が誤用の抗生物質 |
岩田健太郎 |
光文社新書 |
◎ |
はじめに 抗生物質は、よくも悪くもない ・抗生物質「そのもの」は価値中立的です。 ・抗生物質が不要な人に抗生物質を飲ませるのは間違いです。抗生物質を必要としている人に抗生物質を使わないのも、やはり間違いです。 ・抗生物質を使うこと「そのもの」は悪でも害でもありません。問題は、その使われ方です。 問題は、使われ方――どこが、どのように、なぜ間違っているのか ・ここでいう抗生物質は、細菌を殺す薬のことです。 ・しかし、現実には、細菌感染症以外の病気にも、抗生物質はしばしば使われています。ひとつは、「予防のため」。 ・たとえば、かぜ。かぜは細菌感染症ではありませんが、かぜをこじらせて肺炎(細菌感染症)になるといけない、というので、予防目的で抗生物質が使われてきました。 ・しかしながら、こういった抗生物質の使い方の多くは、間違った使い方なのです。 抗生物質の4つのリスク ・すべての抗生物質は人間に害を及ぼす可能性があります。そこには4つのリスクがあります。 ひとつめは、「副作用のリスク」。 ふたつめは、「耐性菌発生のリスク」。 みっつめのリスクは、「お金のリスク」です。 最後は、「ロジスティクスのリスク」です。 ・世界にあるタミフルの7割くらいが、日本で消費されているといいます。 ・本当にタミフルを必要としている病人や体に弱った方に、タミフルを供給できなくなってしまうリスクが存在します。 ・この4つのリスクを理解して、そのリスクをはるかに上回るような利益が期待されるときに「だけ」、抗生物質の使用は正当化されるのです。 第1章 かぜに抗生物質は必要ない かぜに抗生物質を処方していないか? ・そもそもかぜとは何か。 「感染症によって起きる、急性の上気道感染症」で、「くしゃみ、鼻水、鼻詰まり」、のどの痛み、頭痛、咳、微熱が出て自然に治ってしまうもの。 「かぜ」という現象に与える効果は、「ちょびっと」だけ ・抗生物質をかぜにおいて使用した場合、非常に微々たる「ちょびっと」な利益しか提供しません(もしあるとしても)。それでは、生じるリスクとのバランスがとれません。 ・よって、かぜには抗生物質は使わないほうがよいのです。その原因微生物が細菌であろうが、ウイルスであろうが、関係ないのです。 第2章 21世紀の感染症の世界 急性中耳炎、急性副鼻腔炎に「抗生物質は原則必要なし」 ・肺炎球菌は、急性中耳炎とか、急性副鼻腔炎の原因にもなります。 ・じつは、「抗生物質は使わない」が原則なのです。 ・多くの急性中耳炎も、抗生物質なしで自然に治ってしまいます。 ・重症だったり、症状が長引く場合は、例外的に抗生物質を使いますが、そうでない場合は、対症療法と呼ばれる痛み止めなどの治療でOKなのです。 脾臓の大切さ――患者になにが起きているか、「コト」を判断する ・脾臓を失ってしまうと、とても感染症を起こしやすくなるのです。脾臓は感染症に対抗する免疫機能を持っているのです。 ・とくに、肺炎球菌に対して強い免疫能力を持つのが脾臓です。 ・肺炎球菌を攻撃する免疫タンパクの主役は「抗体」と呼ばれるものですが、その抗体を作る免疫細胞(形質細胞)が成熟する場所が脾臓で、抗体かくっついた肺炎球菌を除去する場所も脾臓なのです。 CRPは測定しなくても困らない ・CRPは「C反応性タンパク」の略で、肝臓で作られるたんぱく質の一種です。 ・細菌感染症のときにCRPはたくさん作られ、血中濃度が増加することが知られていました。そこで、日本の多くの医者は、CRP濃度を測定して、細菌感染症の診断に使うようになったのです。 ・興味深いことに、CRPを臨床に使っている国は、そんな多くありません。 CRPに依存してはならないわけ ・感染症の多くは、炎症という現象です。炎症という現象は、患者が熱を出していたり、赤く腫れていたり、痛みがあったりして察知することができます。その炎症という現象を数値化したのがCRPです。 ・それは患者を仔細に見ていれば分かることなのですが、その作業を省略しているだけなのです。 ・CRPを乱用していると、患者の診察を省略するようになります。 ・とりあえず広域な抗生物質を使っとけば、なんとかなる、という考え方は、「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」的発想なので、それではうまくいかない事例が必ず出てくるのです。 CRPは間違いやすいうえに、診断も役立たない ・CRPが上昇するのは、細菌感染症だけではありません。関節リウマチのような、いわゆる膠原病でもCRPは上がりますし、心筋梗塞のような心臓の病気でも、上昇することが分かっています。 ・多くの医者は、ウイルス感染症ではCRPが上らないと思っていますが、そんなことはありません。たしかに細菌感染症に比べると上がりづらい傾向はありますが、2009年のいわゆる「新型インフルエンザ」流行のときにも、インフルエンザでCRP値が上昇していたことが確認されています。 ・CRPが「間違えやすい」というのは大きな欠点です。 ・しかし、それ以上に大きな問題は、CRPが一般的なマーカー過ぎて、病気の診断にあまり寄与しないことです。 ・CRPの数値が高くても低くても、「どの細菌」が「どこ」に感染症を起こしているのか、分からないのです。(というか、そもそも感染症かどうかも分からないのですが)。 CRPの上昇・下降と抗生物質の効果は同義ではない ・感染症が治療され、炎症がおさまれば、CRPは低下する傾向にあります。 ・しかし、抗生物質はあくまでも「細菌を殺す薬」であり、血液中のCRPを中和してなくしたりする作用はありません。 ・抗生物質で細菌を殺すとCRPが下がりますが、それは抗生物質が直接CRPを下げているわけではないのです。 ・ここを理解していないと、抗生物質を間違って使うようになります。 ・CRPがゼロにならないからといって、いつまでもダラダラと抗生物質を使い続けるケースをよく見ます。 ・じつは、肺炎の治療が終わって1カ月たっても、CRPはまだ陽性なことが多いことが研究で分かっています。 ・細菌は抗生物質で殺され、病気は治り、患者は元気になっているのに、肝臓はまだCRPを作り続け、血中にはCRPが残っているのです。 ・CRPばかりを見ていて患者を忘れてしまうと、患者はとっくに治っているのに、CRPだけを抗生物質で治療する、という滑稽な事態に陥ってしまいます。 ・抗生物質には「CRPを治療する」効果なんてないのです。 CRPが下がっても、抗生物質を止めてはいけない場合もある ・感染症が治っておらず、細菌も死んでいないのに、「CRPが下がった」という理由で抗生物質を止めてしまう例も多い。 ・CRPが下がらないからといって、抗生物質を続けてしまう。CRPが下がったといって、まだ必要な抗生物質を止めてしまう。どちらも同じ根拠で間違っています。 ・抗生物質は細菌を殺す薬で、CRPは炎症のマーカー、両者は異なる部位で異なる作用をしており、直接のリンクがないことを理解していれば、こういう間違いは起きないのです。 第5章 経口三世代セファロスポリンは、99.9%が誤用 99.9%の三世代セフェムの処方は、間違いである ・歯科領域でも、予防や治療に抗生物質がよく用いられています。 ・歯肉炎の治療は、歯科治療や局所の抗菌薬療法が推奨され、「飲み薬」は一般には必要ないとされています。 飲んでもほとんど吸収されない抗生物質 ・皮膚などの感染症(いわゆる「トビヒ」など)は、抗生物質など飲まなくても、局所療法で治ることがほとんどです。 ・そもそも、抗生物質(第三世代セフェム)は、消化管からの吸収がとても悪いのが特徴です。 ・吸収されない抗生物質は、感染部位には到達できません。感染部位に到達できない抗生物質は、全然効きません。あたりまえです。 日本のいい加減な臨床試験 ・日本では、「有効率が非常に高かった」と主張する論文が多いのですが、とても問題です。 ・抗生物質を与えた「から」よくなったのか、それとは全然関係なく「勝手に」よくなったかは、分からないのです。 ・もし本当に抗生物質のおかげで病気が治ったのかどうかを確認したいのなら、プラセボとの比較試験でなければいけません。 ・日本では昔から、「使った、治った、だから効いた」という「サンタ論法」が用いられてきました。しかし、これは典型的な、前後関係と因果関係の取り違えです。AのあとでBという事象があることは、Aが原因でBが起きたことを意味するとは限らないのです。 ・「そこに菌がいる」と「それが病気の原因である」は同義ではないのです。 「本当に効くか」が実証されないままに、薬が使用される ・日本では、ドイツ流の演繹法的な考え方から、「このように治療すれば患者は治るはずだ」と治療してきました。 ・しかし、「本当に効くかどうか」という実証は、なされていませんでした。 ・実証は、治療した群と治療しない群を比較した臨床試験によって行なわれるのですが、長く日本では、このような比較試験を「非論理的だ」として認めてきませんでした。 ・その理由は、そこに治療薬があるのに、それを使わない群が設定されるのは、倫理にもとる、というわけです。 ・その治療薬が効くかどうか分からないのに、患者さんに使うほうがよほど非論理的だとぼくは思いますが。 ・自然治癒する「かぜ」や急性気管支炎に、抗生物質を飲ませて、「治った」とみなす誤謬が非常に普遍的になりました。 ・もちろん、患者さんのほうも、「先生が出してくれた抗生物質のおかげで治った」と信じますから、次にかぜをひいた時にもやはり、「先生、あのときのお薬を」となります。 ・ある研究では、抗生物質を使った小児でも、使わなかった小児でも、熱が下がるまでの時間はまったく同じでした。のどにいる菌を殺しても、患者さんの治り方はまったく変わらなかったのです。 ・ここでも、「モノ」たる細菌と、「コト」たる病気=感染症の混同があるのです。 経口カルバペネムなんてもってのほか――いい加減に、目を覚まそう ・「念のため」「もし何かあったら」という理由で、抗菌薬を使う医者は多いですが、「念のため」「もし何かあったら」の論理は、つねに双方向性に働きます。 ・「副作用が起きないように念のため」「もし副作用が起きたら」という言い方も同等に正しいのです。 ・リスクはつねに双方向的にみなければいけません。 ・点滴薬の三世代セフェムは、細菌性髄膜炎や急性喉頭蓋炎といった命にかかわる感染症に使う大事な武器です。そういう武器をムダに不要に垂れ流し、耐性菌を増やし、いざというときの効果を減じてしまっています。 ・こういう抗生物質を「本当に」必要としている患者さんは、日本ではほぼ皆無、ぼくら専門家でも、めったにお目にかからないまれな患者さんです。 ・ぼくらはもう、これらの抗生物質と診療現場を切り離し、これらと決別し、そして患者さんの安全を守る必要があります。 第6章 日本感染症界の「黒歴史」 「効かなくてもよいから副作用だけは起こすな」的発想 ・日本では、質の高い抗生物質を、数多く開発してきました。しかしながら、臨床現場での使用方法が間違いだらけでした。薬理学的に妥当でない、過度に少ない量に設定されてきたのです。 ・ここにも、臨床医学を甘くみる伝統的な日本の考え方が透けて見えます。 ・また、「効かなくてもよいから副作用だけは起こすな」というお役人的な発想も透けて見えます。 ・戦後、日本の医薬品審査・承認は厚生省が行なってきましたが、その質は非常に低いものでした。 ・その結果、ペニシリン・ショックや再生不良性貧血のような「薬害」が生じてきました。 ・それに対する厚生省への批判が起きました。そして、お役人の責任回避的な態度が生じてきました。 ・「とにかく副作用は出さないように」という点が最優先になり、薬効はお留守になってきたのです。 少量長期投与の功罪 ・子どものマイコプラズマ肺炎の治療は、耐性菌の増加のために(比較的)安全な抗生物質が使えなくなってきており、リスク覚悟で、副作用の問題がある抗生物質の使用を強いられつつあります。これは大きな問題です。 「右肩上がり」の考え方に決別を、そしてもっと危機感を ・イギリスでは薬剤耐性菌の問題は「テロリズム並みの国家に対する危機だ」と認識されています。 日本でもこのくらいの危機感をもって臨むべきなのです。 ―― 完 ―― |