
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年07月29日 土曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
59 |
17/07 |
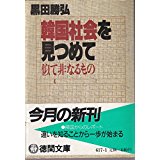 |
韓国社会を見つめて |
黒田勝弘 |
徳間文庫 |
◎ |
序章 韓国文化とは 韓国式相撲と生け花戦争 ・韓国にも相撲があって「シルム」といいます。 ・この「スモウ」と「シルム」という言葉はお互いSとМの音が共通していて、何かしら近い感じがするではありませんか。 ・日本の相撲は「ノミノスクネ」が始めたと巷間伝わっていますが、ひょっとするとこの人物も当半島からのいわゆる渡来人だったのかもしれません。 ・当地では ・そのほか、お花しかり、お茶しかりで日本文化の源流はすべて当地といった感じの起源論がこのところ韓国では盛んで、国民に自信を持たせようというのでしょうか。新たなナショナリズムの時代という趣です。 ・韓国の生け花は頭が痛くなるほどに花が華麗に飾られているのが特色です。 なぜ頭が痛いかというと、韓国の生け花はあまりに花が多すぎるのです。 ・まさに花を見せる生け花なんですね。 ・ところがこれに比べると日本の生け花は、花と花の間の空間を見せる感じです。 ・花をあまり使わない、見方によってはむしろぜいたくなのですが、花を捨てる、あるいは枝葉を落とすかたちで美的空間を形づくる日本の生け花には、韓国人は「寒々としている」として美的刺激を受けないようなのです。 「待てない」社会 ・当地では漢字とハングルは今でも戦争をしていまして、ハングル専用論、あるいは漢字併用論がたえず論争的に語られており、ハングルこそは南北の体制をこえてナショナリズムの象徴になっているといってもいいぐらいです。 ・日本では漢字とカナは以前から平和共存していて、漢字追放など問題にもなりません。 ・韓国はハングル型の独創文化で、日本はカナ型の変容文化ということもいえそうです。 ・韓国のシルムは相手を倒すか手を土につかせるかしなければ勝ち負けがつきません。つまり土俵があって、押し出し、つき出し、寄り切りのある日本の相撲とは基本的に違っています。 ・一応かなり広い円形の砂の土俵があるにはありますが、この円形のワクは勝負には関係なく、、単なる試合場を意味するものにすぎません。 ・この土俵のあるなしもかなり重要な問題を含んでいるように思いました。つまり土俵があるということは、運動空間に限界があるということです。 ・日本の相撲はこの限界のなかで勝負をつけるわけですから、力はかなり凝縮したかたちで発揮されることになり、そこから型の発想も出てくるのではないでしょうか。 ・日本の文化はしたがって限界性文化ということになりそうですが、韓国のシルムは土俵がないため、いわば無限の運動空間を持ち、動きはより奔放性があるといえます。そのかわり限界がないため緊張感に欠けることは明らかです。シルムでみても、韓国の文化は独創と広がりをもった型のない無限性文化といえそうです。 ・日本の美というのはやはり様式美です。 ・日本の相撲は ・韓国人の個性の強さ、すこし具体的ににはその自己主張の強さは、韓国経験のある日本人には相当に印象的です。 ・韓国人は日本人よりよほど自由であるように見える。 ・組織との関係で自己抑制が弱いということは、それだけ組織に対して自由ということですから、彼らは日本人と比べるとはるかに組織からの束縛観はないといえます。 ・日本人は制度的には自由だが個人的にはかなり不自由であるのに対し、韓国人は制度的には不自由だが、個人的には大そう自由である。 ・韓国人にとって最大の不自由というのは、家族あるいは血縁という伝統社会の 3 韓国的「文化大革命」 日本人のコワさ ・韓国人が日本で、ついスピードを出しすぎ、交通警官に止められた。 ・くだんの警察官はあくまでていねいで、礼儀正しく、ニコニコ笑顔で応対してくれました。そしてひとしきりなごやかな会話があったあと、交通キップを切ったのでした。 ・彼は、警官が終始ニコニコしながら柔らかい物腰で、しかも ・彼曰く、「ちゃんと罰金をとるのなら、はじめからそういってくれればいいのに。何かだまされたような気分でしたね。あれは "恐怖の笑顔" ですよ。日本人はコワい」 ・駅のホームで電車を待ってている乗客のようすが実に見事だというのです。電車が来るまで人びとは静かに列を作り、しかも新聞や雑誌、本などを読んでいます。 ・この、電車が来るということに何の不安や疑念もないようすで本を読みふけっている姿は、感動的でさえあったそうです。 ・そのうえ、さらに感動させたことは、本を読みながら電車を待っている人々の列のところに、寸分たがわず電車が来てとまったことでした。 ・あの駅のホームの乗客風景は、日本社会を象徴しているのではないか。 ・つまり、日本人が電車という動く相手を待っているにもかかわらず、その相手の動向を全く気にすることなく、本を読むという小さな個の世界に沈潜、没入できる。 ・もちろん相手の電車も期待にたがわず、ちゃんと予定の時間、予定の位置にやってくる。 ・相手やまわりのことを気にせず、電車を待つというしばしの時間でも個的小世界にひたれる日本社会というのは、何と組織的で安定的社会なのだろう――。 6 韓国暮らしはボディー・ブロー なじみやすい風景、なじみにくい人間 ・日本人は相手の話に自分を合わせようとする傾向にあるのではないか。 ・日本文化は「イエスの文化」であって「ノーの文化」ではない。 ・相手の話に対しその中身の当否にかかわらず、まずわれわれは「そう、そう」とうなずくんですね。しかし、うなずいたからといって賛成しているわけでは決してなくて、まず話を受け入れてから吟味するという感じです。 ・その場で賛否を明らかにするのがわれわれは苦手です。 ・うなずきながら換骨堕胎して自分の話にもっていったり、「そう、そう」といながら「だから……」を付け加えて実は別の方向に結論をもっていったり、とにかく、うなずき合いながらでもできるだけ波風立たせずに話を進行させるわけです。 ・こうした日本人に比べると、韓国人はずいぶん自己主張が強いのではないかと思います。 ・韓国人の場合、数人が話している風景では、うなずくことより他人の話をじっと聞いていて自分の主張をいうチャンスをうかがっているふうなんです。 ・いや、じっと聞いているというよりも、むしろ虎視たんたん、発言の機会をねらっているという感じでしょうか。 ・韓国人の場合、議論が拡張してなかなかまとまらない。 13 説教強盗の論理 ヨコのあいさつに欠ける社会 ・ 「儒教は父子・君臣・夫婦など特定の関係にある個人と個人を考えるだけで、社会や集団全体に対する公共的な道徳というものをあまり考えない」 「韓国の社会倫理は儒教がもたらした家族社会の家族倫理である」 「韓国の道徳は家父長制的な家族を中心としたものである。家族成員間の人倫関係を規定する道徳が道徳の全体であるような印象を与え、この道徳は孝というものによってその頂点に達する」 「(儒教は)身分関係を重視する一方、身分のない者、つながりのない者には苛酷あるいは無関心であるのが常である」 「儒教的倫理は人間を社会的上下関係から見るものである。またこの関係だけを倫理的に浄化したものである。社会的義務としては支配者が被支配者に、上官が部下に、父兄が子女に、教師が弟子に課するものなどがあるが、いずれもこのような個人的関係によって形成された人間的な畏敬・尊敬・義務だけを認めるものである」 「私的な特殊対人関係、父・年長者・夫・上司などのような特殊な対人関係ではなく、どんな人間関係にも妥当する普遍的な倫理が確立されねばならない。儒教が教える家長的、階層的な意識、すなわち外形的に従順を要求することよりは、より一層客観的で妥当性のある秩序が要求される」 ・当地で暮らしているとむしろ近代化――つまり知らない者同士がつき合わざるをえない状況変化のなかで、依然として残っている儒教の影響の強さに、大そう困っているというのが実感です。 ・中国系シンガポール人記者の話 「心にもない感謝なら、口に出さない方がいい。これがわれわれの哲学です」 ・やはりこれは儒教の問題ではないか。 日本人は「親切」か ・韓国人が日本に行って帰ってきて日本をほめるコトバのなかに「日本は清潔だ」というのとともに「日本人は親切だ」というのが意外に(?)多いのです。 ・この日本人評をもうすこし詳しくいうと、おそらく「日本人は ・日本人は一見、親切だけれど腹のなか、心はわからない。 ・親切だからといって、グーッと入っていこうとすると何かカベを感じたり、逆に迷惑がられることもある。 ・この親切というのは心の問題ではなく、ひとつの礼儀、人間関係の潤滑油みたいなもの、あるいはひとつの形式、 ・韓国人はそこのところが分離されてなくて、心がモロに外に出てしまうのではないだろうか。 ・したがって心にもないことはいえない、やれない。 ・そして自分がそうだから相手にもそれを求める。表に出たものが心と思うから、近づきすぎて迷惑がられる。日本人の親切さを誤解するんですね。親切にしたためえらい目にあったという日本人によく出くわします。 日本帝国主義の思い違い ・一人の特派員は言う。 「やっぱりわれわれは帝国主義なんだよねぇ」 「何かこう、つい 「その意味では韓国(人)に対するわれわれの帝国主義は西洋の帝国主義とはちょっと違ったところがあったのじゃないか」 「だから逆に韓国人サイドからも同じ顔・形をしたヤツがなんだということになるわけだ」 「顔・形が同じで外国(人)としての違いの認識というのは、お互いかなりシンドイと思うよ」 ・日本帝国主義のこの地に対する植民地支配の悲喜劇は、この地の人びとを日本人にしようとしたことではないかという気がします。これはある種の深刻な思い違いだったわけです。 14 教科書戦争 8・15でまず日本を思い出す国 ・戦前の歴史について、たとえば「悲惨な戦争体験」あるいは「暗く苦しかった戦時生活」というかたちで日本国民を被害者として位置づける教育を戦後われわれは受けてきたようです。 ・これは戦後の歴史教育が例の「権力と民衆」という二元論で説かれる左翼的なものだったせいと思います。 ・つまり戦前の歴史――戦争についても加害者=悪モノは権力であって、民衆つまり一般国民はその被害者であった。戦争でも植民地支配でもいいですが、悪はひと握りの権力(者)であったというわけです。 ・したがってたえず被害者としての実態が強調され、そのなかで加害者が浮き彫りにされて、加害者である権力に対する批判の眼を育てるというのがわれわれの受けた左翼的な戦後教育だったのです。 ・その結果、日本が加害者として行なったいろいろなことが相対的に弱められることになったようです。 ・被害者として歴史をみる傾向は戦後教育のおかげで相当強いことは事実でしょう。 ・そこから加害者としての歴史認識や、八月一五日が国際的大事件であったといった認識は意外にすっぽり抜けてしまうわけです。 ・結果的には左の方の被害者史観と右の方の加害者かくしが奇妙にいっしょになって、歴史の真実をごまかしてきた感じですね。 ・それに国際というと相手はアメリカだけみたいな感じ方がこれまた一般的で、8・15が朝鮮半島や中国大陸、東南アジアなどをふくめた一大国際的事件であったといううけとめ方があまりありません。 ・今回の教科書問題をソウルからみていると、日本政府や自民党の動きがまるで国内感覚であって、その国際感覚のなさは驚くべきほどでした。 ・8・15以前の日本の存在が大変に国際的存在であって、侵略にしろ進出にしろ、あるいは植民地支配にしろ、国際的行為そのものであり、他国、多民族とのものすごくシビアな関係のなかで日本(人)が存在したということが忘れられていた感じがします。 反日で "国論統一" して克日へ ・特定の国を意識することによってナショナリズムが刺激されるというのはどこでもよくあることだし、ナショナリズム自体もともとそういう性格をもったものかもしれません。 ・しかし相手がいなければ気勢が上がらないナショナリズム、あるいは何か特定の相手を見たてないと有効な国民統合が果たせないというのは、きわめて都合がいい反面、苦労なことでもあります。 ・つまりトラブルがあるときは効果的ですが、平時には弱いわけです。しかし現実は平時の方が多いわけですから、ナショナリズムとしてはもひとつ物足らないといえるかもしれません。 ・韓国のナショナリズムが「日本」あってのものという感じを与えるのは、それだけ韓国にたいする日本の影が過去および現在にわたって大きいということだと思います。 ・だから反日にしろ克日にしろ日本、日本、日本という "日本の影" に対し、大衆はともかく、知識人のなかにはイラ立ちを感じる人もいるようです。それはそうでしょう。 ・ナショナリズム(民族意識)から国民統合まで「日本」のお世話(?)になるわけですから腹立たしいわけです。 ― 完 ― |