
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年08月08日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
60 |
17/07 |
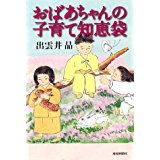 |
おばあちゃんの子育て知恵袋 |
出雲井 晶 |
産経新聞社 |
◎ |
第一章 「自分とは」「人間とは」いったいなにものですか 自分がわからない若者たち ・世の中に適応できる子、できない子のわかれ道は、その子にかかわるおとなたち、親や先生自身がまず、人間が生きているとはどういうことなのか、人間とは、自分とは、いったいなにものなのかを正しく知ることなのです。 ・悠久不変の目にみえない大いなるもの、いちばんたしかに存在するものに目をむけるか、むけないかで決まるのです。 ・それをわが子、教え子におし広めていくことから始まるのではないでしょうか。 ダーウィンの進化論の罪 ・国の中では、国会議員が嘘を言った、一流といわれた会社が談合した、脱税したと告発され、宗教家の詐欺事件までが、報道されています。 ・お金と権力のために、魂を売った人々! ・若い人たちは、そういう人たちがリーダーであった世の中に絶望してしまうのでしょう。 ・つまり若い人たちが、自分がわからなくなり、世の中がわからなくなるのは、いまの世の中を動かしている人々の心が信用できなくなってしまったからではないでしょうか。 ・戦後の教育は、それまでの日本文化、とくに民話や日本神話を断ちきる教育でしたから、日本人の心や誇りを教えられないままのでした。 ・当然、日本人として生まれたことの心の豊かさを、どこに求めていいかわからなくなりました。 ・その空白を埋めてくれるものがありました。目に見える物の豊かさです。 ・物質的な豊かさは、ずらり並んだ百科事典などの情報、そして高度な教育も実現させましたから、それが心の豊かさであると、思わされてきたところがあります。 ・いまの若者の祖父母世代は、お年寄りは大切にされ、親孝行は人生のひとつの目的でした。 ・人間としての誇りとは、いのちをいただいたことに感謝し、成長して、社会に貢献しながら、親や愛を注いでくれた人に報いることだ、ということを知らず知らずのうちに知っていました。だれもがです。 ・とても単純なことですが、誇りというものは、そんなものではないでしょうか。 ・いま、日本に生まれたことの誇りももてない若者をどんどん生んでいることは、見えない心をないがしろにして、見える物質を優先してきた、戦後のマインド・コントロールの結果なのではないでしょうか。 ・いのちへの感謝を、日々、教えられてこなかったからです。 ・日本の国のすばらしいなりたちを伝える日本神話、日本の民話を伝えられなかった。 ・歌っていると、自然の中にとけこんでしまうような幸せを感じさせてくれる「ふるさと」「赤とんぼ」「夕やけこやけ」などのなつかしい動揺も、みんなみんな消されてしまった。 ・ご先祖や親を大切にする姿を、親たちがみせてこなかった。 これでは、親や日本が好きになれない、したがって自分自身にも誇りをもてないのは、当然だと思います。 ・占領されていたころ、ラジオは毎日、日本は悪い、悪かったと、日本悪玉論を、これでもかこれでもかと流しつづけました。 ・このころに憲法がつくられ、東京裁判では、負けた日本がすべて悪かったのだと、国民に徹底して植えつけました。 ・自由と権利はなにより大切という考え方は、よいことですが、同じように大切な義務は軽くみて、利己主義をはびこらせ、日本歴史の否定、そして国家とか共同体意識を否定する。 ・これらを、いわゆる進歩的文化人があおりたてました。 ・ところが、占領は、五十年前に終わっているにもかかわらず、日本人の多くは洗脳、マインド・コントロールから解けていない。 ケモノと人間は違います ・ご先祖さまがいてくださったおかげで、おじいさん、おばあさんがいてくださったおかげで、お父さん、お母さんが私を生んでくださったおかげで、自分はいま、ここに生きている、つまり、「永遠の今」を生きているということです。 ・このことに対する深い感謝の思い、それこそが「ありがとう」の心です。 ・老いた親と切りはなした核家族の自分たちだけが幸せであればよい、という考え方はおかしなことなのです。 ・自分たちだけが、自分の核家族だけが幸せであればよいと、エゴイズムな世の中になっています。 ・子どもがすくすくと育ってほしいと思えば、親がその親を大切に、子どもにも祖父母を大切にと教え続けることが、自分の子どもが幸せな一生をおくるための、一番大切なことなのです。 「なぜ?」「どうして?」のすばらしさ ・子どもを愛しているつもりで、過保護になんにでも口を出してしまったら、結局なにも決められないひよわな子にしてしまう。 第三章 長い目でみて人生の選択を 自殺だけは絶対にしてはいけません ・死ねば、この病苦から、莫大な負債から逃れられる、楽になれると、自殺した人がそう言いましたか。そんなことが、聞こえるわけがありません。 ・死んだら苦がなくなり楽になるなんて、証明されてはいないではないですか。 ・人間が死ぬとは、肉体が死ぬのであって、本物の人間である魂=霊魂とは生き通しだそうです。 ・宇宙の法則、正しい道理にそむいて、自らの生命を勝手に絶つことは、とても大きな罪なのです。 ・肉体が死んでも死ねないで生き通している魂は、その自殺したときの姿そのまま苦しみの意識が残っていて、苦しみ続けなければならないとか。そんな残酷な、地獄の苦しみが永遠に続くのでは、死ぬ意味がないでしょう。 ・それなら、死んだつもりで生きるのです。 母親の離婚は子どもにとって不幸せ ・結婚して子どもが生まれた以上、なんとしても離婚だけはしない、という一大決心が父親にも母親にも必要です。どうしてもむりなら、せめて子どもが成人するまでは離婚しない、してはいけないのです。 ・男も女も、それぞれが自己中心的にしか、物ごとを考えられなくなったのです。考え方がとても狭くなっているのです。 ・父親に引きとられるにせよ、母親と暮らすにせよ、子どもにとっては心の半分がもぎとられ欠けることになるのです。幼い心で、うつろになった部分をどうやってうめればよいのでしょう。到底、不可能なことです。 ・自分が変われば相手は必ず変わります。 ・人生とは、家庭とは、それぞれの魂の修業の場であるのです。 ・一日、二日と、この努力をつみ重ねていくとき、お互いの歪んだ仏頂面が少しずつまともに戻り、日が射すように笑顔が家庭に戻るでしょう。 ・その妙薬は、「ありがとう」の言葉であり、「あなたのおかげで、私、幸せ」の感謝の心と言葉です。 第四章 学校に過大な期待をしてはいけません 戦後教育のねじれ現象が "いじめ" に ・戦後、「日本人が悪かった」「戦前戦中のすべてが悪かった」という意識を占領軍にうえつけられ、日本人の考え方は歪められました。 ・私たち日本人は昭和二十年八月に戦争は終わったのだと思いこんだのです。ところが、戦争は終わっていなかった。 ・そこから、サンフランシスコ講和条約が調印・発効されるまでの六年八か月のあいだに、武器による戦争よりこわい思想戦で、日本人のものの考え方、見かたをかえる "ウォーギルト・インフォメーション・プログラム(戦争贖罪情報宣伝計画)" が着々と実行されていった。 いじめる側の子どもには ・いじめる側の子どもには、自分がしてほしいことを、友だちにもすることが大切なことと、親が真ごころをこめて愛をこめて、くりかえし話きかす。 ・相手をいじめるなど、意地悪をすると、いつか、それは自分にかえってくるという、現実の世の法則である、因果応報を教えこむ以外にありません。 ・人によろこびを与えれば、自分のよろこびとなってかえってくるのです。 ・だれも知らないと思っても天がみている。お日さまが、大地がみている。一番、知っているのは、自分自身だということです。 ・私は毎年、ひと夏を札幌の祖母の家ですごしました。祖母は早朝のお寺参りに出かけます。 ・お寺にいくのは、同じ年ごろのいとこと私二人だけでした。 ・大きな地獄絵図、極楽絵図がかかっていました。極楽絵図の印象は残っていません。 ・地獄絵図の、現世で悪いことをした人たちが釜茹での場面や、火攻めや、えんまさんに、うそをついたがために舌をぬかれる場面など、子ども心に強烈に焼きついたものです。 ・そんなものを見せる善し悪しの議論はいろいろあるでしょう。しかし、人の道にはずれた悪いことをしてはいけないのだな、うそをついてはいけないのだなと、心の底にたたみこまれたことは事実です。 ・幼いころからの宗教的情操教育は、かかせないものだと思います。 自分の子がいじめをしたら ・いじめられっ子より、いじめっ子のほうが、はるかにまわりの人たちの愛情に飢えているのです。とくに母のやさしい言葉や励ましの言葉に。 ・愛に飢えた心はほしがっていることに、お母さん早く、気づいてください。 ・母の愛のほとばしりほど強いものはないのです。 ・ですから、いままでに、そのような ・良心はめざめて、いじめなどが、いかにつまらぬ、はずかしいことかを、おのずと理解します。いじめは自然に止まってくるものなのです。 ・しかし、いじめっ子に、そのことをわからせるのは、とてもむずかしいことなのです。 ・なぜか。それは、その母親自身に問題がある事が多いからです。 ・だいたいが傲慢です。夫を尻にしいて唯我独尊のタイプ。やさしさに欠けています。虚栄心がつよく見栄っぱりです。 子どもにも、自分の見栄のために、子どもの能力以上のことを強要します。 ・こんな母親に限って、お宅の子がいじめをしているといっても、なかなか信じようとしません。もちろん、あやまろうともしません。 ・もし、いじめられた子の名まえなどあげようものなら、あることないこと、その子の非を打ち鳴らします。 ・反省がありません。ヒステリックです。子は親の鏡というとおりです。いじめっ子は知らず知らずのうちに、そんな親を見習っているのです。考えてみると、いじめっ子のほうが、気の毒です。 ・かつて私の友達にも、とても嫉妬心の強いじめっ子たちがいました。その多くは、幸せとは遠いくらしをしています。神仏はみているのです。 私の小学校の先生体験記 ・テレビ番組をつくる方にお願いです。悪いことをした政治家や役人が出ると、どの番組もどの番組も、これでもか、これでもかと、その人間の悪を言いたてます。居並ぶ男女のコメンテーターが、口をそろえて悪の大合唱です。 ・キリストは、おおぜいの人が一人の売春婦の罪を言いあげたとき、「なんじらのうち、罪のない者が彼女を打て」と申したとか。 ・テレビがすべて裁判官化した番組ばかりでは、世の中を暗くします。 ・テレビが、自分たちの意図する方向に視聴者をひっぱっていこうなどという野望を、もし抱いているのなら、大変な心違いです。 ・ "人のふりみて我がふり直せ" とことわざにもあります。 不登校児多発――家庭の問題 ・この問題の基本は、家庭での規則正しい生活がすべてだと思っています。 ・小学生であれば夜九時には、「おやすみなさい」とあいさつをして、ベッドに入る習慣をつけることです。 ・子どもたちの就寝時間がだんだんおそくなったり、不規則になってきていることが、不登校児をふやす、かくれた大きな原因です。 ・子どもが本当に寝入ったあとは、少しくらいテレビをみてもいいでしょうが、読書をするとか、趣味の勉強に時間を使うなり、親が、おとなが人生にまじめに生きているすがたは、子どもにとってなによりのお手本です。 ・また、学校から帰ったら、なんでも話せる雰囲気をつくっておくのが理想的です。 ・たとえば、子どもがクラスの友だちとうまくいかないといっても、「ぐすぐず言わないの、ほかにも友だちはいるでしょ」などと、子どもの気持ちを考えない ・そんなに簡単にいかないから、子どもなりに悩んで打ちあけたのでしょ。 ・お母さんでもわかってくれない、と子どもは心を閉ざしてしまいます。 ・不安がつのり、学校へいこうとすると、おなかが痛くなるなど心身症の症状まで出てきます。 ・冷たく突き放すのではなく、子どもの気持ち、子どもの身になって「どうしたらいいんだろうね」と、いっしょに悩み考え解決していく態度が大切です。 ・思春期には、はげしく揺れ動く子どもの感情に、親がふり回されがちです。体の変化、進路への不安、自分の勉強や才能に自信をなくしたり、自分で自分がコントロールできない。 ・心と体のアンバランスをもてあましてしまうのが、思春期でしょう。 ・本当は親にたより甘えたい。ところが反発してしまう。最近の子どもは、中学二年をさかいに、急激な内面の変化におそわれるといわれています。 ・しかし、家庭のなかが、平素から父親を中心にまとまり、母親の気配りが春風のようにめぐっていれば、子どもは悩みながらも自分で解決して、独立心を付け、自信をつけていくものです。 不登校児多発は戦後のこと――学校の問題 ・敗戦によって占領軍からうけたわが国の被害の最大のものは教育であった。 ・かつては、子どもは先生を神聖視していました。なんらかの尊敬の念をもってみていました。これでこそ教育は成り立つのです。 ・先生とは、ただ子どもに知識を、切り売りするのが仕事ではありません。 ・どんなに社会が物とかお金とか、経済一辺倒になっても、学校の先生と親が、悠久不変の大宇宙の法則にのっとった、次元高い理想に燃えていれば、さらに高く、さらに美しくと、子どもたちの内面の宝石に磨きをかけるような授業ができているのです。 ・子どもは、その先生を尊敬しあこがれます。そんな先生が一人でもいれば子どもにとって、学校はどこよりも楽しい生甲斐の場となるでしょう。 ・悲しいことに戦後は、先生が、自分たちでその神聖をかなぐり捨てました。労働者だと宣言しました。 ・額に汗して働くことは、とても大切なことです。しかし、そうした考え方と、教師が労働者の権利だけを声高に主張することとは、まったく違います。 ・子どもとは夢のかたまり、理想のかたまりです。その夢の理想を、大きく成長させてやるのが先生の使命です。 ・自分たちが生をうけ、日々守られてくらしている自分の国のことは、「おかげさまで」と感謝し、愛し大切にする心を育てあげてこそ、先に生まれた先輩としての値打ちもありましょう。 ・それを 第五章 古来からの日本の親の躾 お弁当の楽しみ ・昔は聞いたことのなかった摂食障害と拒食症なども、母親との愛情の交流が円滑にいかなかった結果ではないでしょうか。 明治生まれの親は「勉強しなさい」とは言わなかった ・勉強しなさいとは言われなかったけれど、躾は厳しかった。 ・いまは長寿社会です。子育て中の母親は家にいて、学校から帰ってくる子どもに「おかえり」と、あたたかい声をかけ、細やかな愛情で育てる。子育てを終えてから後に、社会に働きに出てもおそくはないのではないでしょうか。 ・政治家や役所の人々は子育て中の母親が働かなくてもよい社会をつくることこそ、いま求められている賢明な処置だと思います。これによって子どもの非行化・不良化はずいぶん減ると思うのです。 ・女性の政治家が、もっと本来の女性の幸せを考えてほしいものです。 ・男女共同参画社会などと、保育園の数をふやして母親を労働力として駆りだすという考え方は、女性をただの労働力としてしか見てはいません。 ・女性を労働力としてあつかったのは、もとは共産主義国の考え方でした。共産主義では人間も ・見知らぬ人と知り合うための "出会い系サイト" からの "勧誘メール" などがあり、中学生、高校生が出かけてしまう・・・。 ・そんな子どもは、親の愛情に飢えていたから癒しを求めて難にあったとも考えられます。 ・夫婦共働きの家庭で、乳幼児期から保育園、幼稚園で育てられるのが当たり前の社会状況が遠因になっているのです。 ・しかも自己の権利が、なにより重要だと叩き込まれた親世代です。親自身が、自己中心になっていることにさえ、気づいていません。 ・子育てよりも自分のしたいことが先に立っています。 ・子育ては片手間になってしまいます。 ・子どもたちは物は豊かに、テレビゲーム、人形、おもちゃとふんだんに与えられながら、心はひどい飢餓状態におかれているのです。 ・親に甘えたいのに甘えられない子どもは、いつも心が落ちつきません。心のなかに、不安や不満の 夕方から「おやすみなさい」まで ・言葉の豊かさは、その国の文化を高いものにしていきます。そのために大切なのは、 "本を読む" ということでしょう。 ・物を考える力も、考えたことを表現する力も、結局は言葉をどれほど多く使いこなせるかにかかっています。 ・本を読むことが、どれほど深く広い人生の広がりにつながるかを実感してほしいのです。 第六章 四季の行事と遊びのなかでの躾 お正月は神仏とのかかわりがある ・家族でいっしょに遊ぶときは、子どもたちに、社会の秩序やルールを守る子に育てる絶好の機会です。 ・一人が自分勝手に、遊びだからと傍若無人な振るまいをすると、自分もふくめて楽しくなくなります。がまんすること、他の人と協調していくことを、遊びのなかで自然に身につけさせていくこと、そのためには親の心がけが大事です。 ・親のやさしい眼ざしと言葉が、子どもたちに平等にいきわたるようにすることを、つねに忘れてはいけません。これは、やさしいようでむずかしいことです。子どもを介しての、親の人生修養そのものです。 秋の行事と遊び、そして運動会 ・運動会の徒競走、足の速い子は遠くから走り、みんないっしょにゴールインさせるというのです。 ・子どもはみんな平等でなければならない、という考えからだというのです。 ・子どもには、それぞれに長所もあれば短所もあります。足の速い子もいれば、遅い子もいる。徒競走でビリの子でも、ほかのところで足の速い子が真似のできない長所をも去っている。 ・それぞれ、その子でなければできない宝ものを持たせて、この世に誕生させていただいたのです。それぞれが、その人間に合った仕事をして世の中のために尽くすようにと。 ・このような悪平等を強いるような人は、先生とはいえません。教育のいろはのいの字のところさえわかっていません。 ・こんな教育をうけた子供たちが、何事もなくスムーズに学校で過ごしているとしたら、そんな子供たちもおかしいのです。荒れて暴れて、学級崩壊がおきて登校拒否になって当たり前です。 ・伸びたい盛り、学びたい盛りの子どもたち。その子どもたちの、内なる生命の発露を押さえつけるなんて、教師にあるまじき行為だと思うのです。 ・一方で、足の遅い子にもまことに無礼な考え方です。 【私見 : 学校は、足の遅い子を人間として劣っているものとして捉えているのではないか。劣っているから庇ってあげなければいけないという上から目線の見方になっている。足の速い遅いは単なる特徴、個性であって、速いからいい、遅いからダメというものではない。】 ・走るのは遅くても、速い子にない得意なものを内に秘めている子は、たくさんいます。それを認めてやっていれば、徒競走はビリでも、精いっぱい走ること、がんばることに意義があると教えることができます。どの子もえらかった、素晴らしかったとほめて指導できるのです。 ・それなのに最初から、速い子、遅い子とわけいてしまっては、なんにもなりません。 ・世の中へ出れば、すべて競争原理が支配しています。甘やかされて学校や家庭で生活しても、世の中はそんな甘いものではありません。 ・どんなときでも、人生の落後者にならないように指導するのが先生であり、学校であるということを忘れないでほしいと思います。 第七章 アメリカ・イギリスの教育事情 自由主義の国・アメリカの厳しい規則 ・規則を守ることが、自分の尊厳につながるという自覚をもつことが大切です。 毎朝、星条旗に宣誓するすばらしさ ・日の丸の丸い円は、太陽のシンボル、円満、和を愛する心。燃えるような誠の心(赤誠)、情熱をあらわしています。白地は純真、純潔、自由な国民性をあらわしているとか。 ・どの国の国旗・国歌も、長い歴史のあいだには明も暗も背おってきます。暗さだけに目をやり、自分の国の誇りまで否定するのはかしこいことではありません。 アメリカで求められる家庭教育の内容 ・アメリカでは教育心理学者が、人は二、三歳から七、八歳までに、一生を支配する人間性、人格が形成されるといっています。それでアメリカでは家庭を重んじ、教育に熱心です。 ・アメリカでは、小学校入学前に家庭で躾ておく大切なことは、 "他人に迷惑をかけない" "共同生活ができること" であり、これを家庭教育に求めています。 イギリスの宗教教育は道徳教育 ・イギリスでは、文部省も地方教育当局も、学校で何を教えるべきかという規則をもっていないのです。各学校の校長の自由裁量にまかされています。 ・しかし毎朝、必ず朝礼をすることと、宗教教育を実施することの二つは、国で決められています。 イギリスの「紳士になれ、淑女になれ」 ・イギリスの教育方法で見のがせないのは、訓練主義、訓育主義です。法や秩序の権威、団体の規律、公衆道徳というようなことは、小さいときから家庭、社会、学校で訓練されています。 イギリスの家庭教育はマナー教育 ・子どもの躾は厳しくて、話しあう "声の大きさ" から、学校や外出からの "帰宅時間" "他人の会話歩の差し出口 " まで、いちいち厳しく注意します。 ・特に、 "朝のお祈り" については、必ず毎朝夕、共に実行します。 ・子どもの "学校外の行為はすべて親の責任" と、はっきり自覚しています。 ・それで土曜の午後はもっぱら、 "家庭の躾の日" ときめています。土曜と日曜は公的な会合はいっさい行いません。 ―― 完 ―― |