
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年08月20日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
61 |
17/07 |
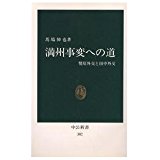 |
満州事変への道 |
馬場伸也 |
中公新書 |
◎ |
まえがき ・日本が中国侵略へと妄進し、その結果、数百万の中国人死傷者を出した責任は当時の指導者――とくに軍部――のみにあったのではない。それは、つねに「強硬政策」を主張した一般大衆にもあった。 ・すでに満州事変の時点で「反対意見なき、全員一致型の事変支持の世論の成立」があった。 一章 田中義一 ―― その思想と行動 二 軍人として ・日本には昔から、「一か八かやってみる」とか「当って砕けろ」といった慣用句がある。 ・そしてそういう慣用句があるということは、そうした「直接行動的」な行動パターンをとる人々がかなりいることを物語っている。 ・田中の日露開戦への奔走には、この傾向が如実に見られた。 ・田中には、日本は勝てるという自信はあった。けれどもそれは、まったく理性を超越した日本の精神主義に依存するものであった。 ・彼は合理性や緻密な理論――それは幣原外交に見られた――よりも、つねに情念にもとづく直接行動に訴えようとした。 ・昭和の軍国主義者たちもまた、理性を超越した日本の精神主義を信じて、太平洋戦争に猛進していったことである。 ・合理主義者にとってその行動は、「国民総ハラキリ」的にも見え、「ドン・キホーテ」的でもあった。 ・こうした超国家主義者の思考過程と田中のそれには、いちじるしい類似点が見られる。 ・田中が『戦略と政略の一致』の中で、 「消極的に国土を防備するだけに止まらず、もっと積極的に攻撃においても絶対の兵備をもたなくてはならず、否、むしろ攻撃こそ戦略の‹本領›である」 とするのである。 ・日露戦争後、日本の戦略は大きく転換した、と田中はいう。それまでは、いかにして本土への敵の侵入を防ぐかに全力をつくしてきたが、日露戦争を境にして、「全然作戦の本領が変った」。 ・今後の「我帝国の ・ここには、小さな島国日本にあきたらず、大陸攻略に夢はせた豊臣秀吉や吉田松陰と同じ思想が田中の頭のなかに潜在した。 ・周知のごとく、松岡洋右は日本が国際連盟を脱退(一九三三・三・二七)して「自主外交」を推進する主役を演じた。 ・彼の自主外交は西欧的な価値――とくにそのころ国際政治を支配したアングロサクソン民族の価値――に拘束されない、否むしろそれと対立した、日本民族の特殊的な価値――天皇制を中心とした日本のもろもろの伝統的価値――を日本独自の外交方針とし、しかもそれを世界におし広めてゆかんとするものであった。 ・この思想はさらに超国家主義者たちにうけつがれて、日中戦争(一九三七・七・七)を契機として「東亜新秩序建設」「八紘一宇」の思想に発展し、日本外交の指導原理となった。 ・一般に日本が「自主外交」を推進するようになったのは、満州事変以降、とくに連盟脱退後とされているが、「自主外交」の構想はすでに田中外交のときに見られた。 四 政治家として ・シベリア出兵問題 ・ロシア革命は、列強にさまざまな複雑な問題を提起した。 ・フランスは、大正六年(一九一七)十二月二日、連合国パリ会議で、日米連合軍をもってシベリア鉄道を占領する案を提議した。 ・つづいて十二月二十六日には、セシル英外務次官が珍田(捨巳)駐英大使に、ウラジオストックへの日本軍隊上陸を打診してきた。 ・日本政府は、当初、出兵に反対であったが、一人この案に真っ先に飛びついてきたのが、参謀次長をしていた田中義一であった。 ・それには、主に三つの理由があった。 ・第一に、田中は日露戦争後、つねづね、日本は「大陸国家」として飛躍せねばならぬ、との信念を抱いていた。革命による帝政ロシア軍の崩壊と政治的麻痺は、この希望を実現するのに絶好のチャンスであると思ったこと。 ・第二には、将来ロシアの南下が「必然」である以上、この際一挙に満蒙と朝鮮を結ぶ強力な緩衝地帯を形成するのが得策である。 ・あわよくば、シベリアをロシアから切り離し、そこに自治独立州を建設し、その上、可能ならば、日本の傀儡政権をうちたてようとの構想が、彼の頭のなかに浮んできたこと。 ・第三に、ボリシェヴィーキ政権にいま一大打撃を与えねば、将来社会主義の東洋への進出は、日本の国体に脅威となるのは勿論のこと、東洋的伝統も破壊されるであろうと懸念した。 五 帰国 ・田中の「積極進取」をモットーとする排外的自主外交は、列強からのきびしい批判をうけるところとなり、中国への武力を背景とした威圧的内政干渉は、同地にすさまじい排日運動を惹起させる結果となった。 ・加えて、張作霖爆殺(一九二八・六・四)後、後継者の張学良は蒋介石のひきいる国民政府との提携に走り、昭和三年(一九二八)十二月二十九日、満州の地に青天白日旗を掲げるにおよんで、田中が宣伝してきた「満蒙第一主義」の政策もついに失敗に帰した。 ・こうした「田中外交」の破綻はまた、田中内閣に対して各方面からのいっせい攻撃を将来することになった。 二章 幣原喜重郎 ―― その思想と行動 ・田中が日本の伝統を維持し、国体や皇道の促進を図ろうとしたのに対して、幣原は、日本の国家目標は真の自由主義と民主主義を確立することにある、と確信していた。 ・一方は国粋主義者であり、他方は、「平和共存」を念願する国際主義者であった。 ・田中が、派閥や地縁あるいは親分子分といった特殊的排他的な人間関係にからむ義理人情を重んじたのに対して、幣原はそうしたことにはとらわれず、つねに合理的普遍的な思考過程をたどった。 ・したがって外交指導に関しても、前者が国益増進を日本と中国あるいは満蒙との関連において極地的にとらえようとしたのとは対照的に、後者はそれをもっとグローバルな観点から考察した。 ・外交方針をたてるに際しても、幣原は日本を「外」から眺めていたが、田中は逆に世界を「内」から覗いていた、と言いうる。 三 国益と外交官の役割 ・幣原はつねに、国益はあくまでも平和的手段によって国際協調のもとに追及されなくてはならない、とう信念があった。 ・この信念を表現するのに、彼は次の三つのスローガンをしばしば用いている。 ・すなわち、 「世界人類とともに戦争なき世界の創造」 「平和共存」 「正義の支配するところには、武器の必要はない」 がそれである。 ・最初のスローガンは、国際主義者としてのユニバーサリスティックなものの考え方を、その次のは、彼の民主主義的精神を、最後のスローガンは、理性を重んじる彼の道義的態度をあらわしている。 ・そしてこの三つのスローガンに流れる共通のものは、すべての国家は世界平和を維持するために努力しなくてはならず、それこそが、各国の根本的でかつ究極の外交目標でなければならないという信念である。 五 政治家としてカムバック ・世に新憲法はマッカーサー憲法ともいわれるが、戦争放棄を明記した前文と第九条に関するかぎり、発案者は幣原であったことを、マッカーサーも当の幣原自身も認めている。 三章 「大正デモクラシー」から「昭和維新」 ・関東軍が満州事変を引き起こし、それを契機としてしだいに超国家主義者たちが跋扈するにいたったのも、そうした傾向を支持する社会的心理状態があったことを見逃してはならない。 ・どの新聞も「右へならえ」式に事変を支持していたのであった。 二 大正デモクラシーから昭和維新へ ・大正時代はまた「大衆の時代」ともいわれるように、一つの顕著な現象として、大衆の抬頭があった。 ・東京市電六千名のストライキや、「大正の政変」(一九一三)では、憲政擁護を叫ぶ民衆が議会を包囲し、桂首相は辞職を余儀なくされた。これは大衆運動によって内閣がたおされた最初の事件であった。 ・過激な市民運動が展開された。 ・軍閥、官僚の間でたらいまわしされる政権に反対した憲政擁護運動は、ますます多くの民衆を動員して一大運動に盛り上がった。 ・こうした一連の大衆運動を集大成するかのように発生したのが米騒動であった(一九一八)。 ・いったん政治的に目覚め、動員された大衆は、さらに普通選挙請求運動へ、あるいはもっと組織化され、イデオロギー的にも裏付けられた労働組合運動、小作争議運動へと発展していった。 ・この社会現象にみられる一般的風潮は、ブルジョア・デモクラシーと自由主義の精神であった。 四章 国際環境の中での中国問題 一 国際情勢と世論 ・人口問題、食糧問題を一挙に解決する絶好の対策として、大きく浮かび上がって来たのが満蒙の広大な土地と無尽蔵の始源を利用し、その開拓と人口問題解決の一石二鳥をかねて、移民を行ない、そこに日本の産業の振興を計るというアイデアであった。 ・現に『朝日新聞』ですら、その社説に、日本の人口食糧問題を解決するには消極、積極二つの方法しかなく、一つは産児制限を励行するか、あるいは満蒙方面に移出をはかるかであると述べている。 五章 幣原の対中国政策 一 第二次奉直戦争 ・一九一七年七月、段祺瑞は張勲をおさえ、北京に武断政策による統一政権をうちたてようとした。 ・これに反対した直隷派の曹錕と呉佩孚は、一九二〇年七月、段政府を倒し、北支の天下をとった。奉天軍の首領張作霖はもちろんこれを好まず、一九二二年の春から第一次奉直戦争が始まった。 ・張の敗退で一時は戦争も治まったが、勢いをとりもどした張は、ふたたび直隷派に戦争をいどみ、ここに第二次奉直戦争が一九二四年の初秋から開始された。 ・それまで日本政府(外務省筋、軍部とも)は、第一次奉直戦争のときから張作霖を支援していた。 ・関東軍の中国政情に対する干渉の意図は、すでにこれ以前から、外務省や参謀本部と比べてもっと積極的であった。 ・第二次奉直戦争が勃発するやいなや、張作霖は日本の出先機関を通じて、幣原外相に、あるいは、児玉関東長官にと、しきりに援助を要請してきた。 ・張の主張によれば、英米が呉佩孚を支援し、ソ連も北京政府や孫文の広東政府に影響を与えて中国の赤化を計っている以上、満蒙の地に特殊利益を有する日本は当然張を援助すべきだ、というのであった。 ・幣原は、こうしたさまざまな動きの中にあっても、絶対内政不干渉主義をとっていた。 ・幣原は児玉関東長官に、 「満蒙の特殊利益と言われるが、日本は、その他、 「わが官憲が一党一派に偏することは、 と伝えた。 四 南京・漢口事件 ・対外強硬政策を唱える国内世論の「幣原外交」に対する批判と不満はますますつのっていった。 ・当時もっとも進歩的な新聞とみられていた『朝日新聞』でさえ「幣原外交」を「自由主義かぶれ」と社説で攻撃するありさまであった。 ・幣原のとった一つ一つの事件に対する措置を検討してみれば、それは決して「英米一辺倒の協調外交」ではなく、独自の外交理念にもとづき、日本の実益(とくに経済的)増進を計ろうとする、むしろ「自主外交」の感が強かったが、世論はそうは受けとめていなかった。 ・「軟弱外交」の非難にしても、実際は西園寺も言うように「強硬外交」(意志強固な外交)に等しかった。国内世論に同調し、英米の威圧外交と歩調を合わせたほうが、よほどやりやすかったはずである。 ・なにはともあれ、大衆の外交事象の認識もまた、幣原とは大いに異なるところがあり、「軟弱外交」「迎合外交」の非難がはげしくなるにしたがい、彼らの間には「自主外交論」が高まっていった。 あとがき ・日本と中国は今後二度と「喧嘩」をしてはならないのであって、両国は絶対不再戦の覚悟でのぞむのみならず、ますます友好関係を深めていくよう努力しなければならない。 ・そのための基礎となるのは、やはり「平和五原則」を厳守することであると思う。 ・「平和五原則」とは、もともと中華人民共和国とインド共和国とのあいだで協定された(一九五四・四・二九)、 (一)領土主権の相互尊重 (二)相互不侵略 (三)相互内政不干渉 (四)平等互恵 (五)平和共存 の原則である。 ・もともと「平和五原則」はそのすべてが国際法上の基本原則であり、別に中国からおしつけられたものでも何でもない。 ・日本は過去においても、この原則を遵守すべきであった。 ・幣原はつねにこのことを強調してきた。しかしこれを破ったのは、田中義一や森恪、あるいは軍閥といった一部の人々だけではない。世論もまた、中国の内政干渉を主張し、「満蒙特殊地域論」を唱え、山東出兵を支持してきたのである。 ・パリ和平会議以来、国際政治史上もっとも理想主義的な時代といわれた一九二〇年代の前半には、日本の幣原外相も、アメリカのウィルソン大統領も、イギリスのロイド・ジョージ首相も、同盟条約を会議外交や不可侵条約に切りかえることを目指していた。 ・ワシントン会議で日英同盟が破棄されて、四ヵ国条約に置換されたのは、アメリカやカナダが同条約に反対したこともさることながら、むしろ幣原が率先して「新時代に同盟条約は時代遅れである」との考えから、四ヵ国条約の原案を作ったものであった。 ・一九二〇年代の前半は覇道主義的あるいは帝国主義的外交に終止符を打って、民主主義の精神にのっとった新しい国際秩序建設に夢はせた時代であった。しかしそれは文字通り「夢」に終わってしまった。しかもその夢をこわした大きな責任の一半は日本にあった。 ・現在、国際社会は多極化時代を迎えて、ふたたび新しい秩序建設をめざして模索している状態である。 ・今度は日本が率先して、幣原が唱えていたように、「世界人類と平和世界の創造」と、民主主義精神にもとづいた、各国の自由、平等、独立の建設と、主権の尊重、領土の保全のために努力していかなければならない。 ・そのためには、日本はすべての国々と平等に協調して、グローバルな外交を推進していかなければならない。 【私見 : 「全ての国々と平等に協調」というのは現実的に可能だろうか。米・中・露・欧それぞれ、同盟関係や協調度合に差があり、日本人特有の「八方美人的等距離外交」は耳触りは良いが、もっとも問題を起こし易い態度ではないだろうか。人間関係に似ていて、みんなから嫌われるか足元をすくわれる危険性があるように思える】 ・これこそが日本の「自主外交」の将来の進路であると私は確信する。 ・「外交とは」、幣原が強調していたように、「本来つねに自主的であり同時に協調的なもの」である。田中義一の「自主外交」は特殊的排他的傾向に走って、グローバル外交を忘れ、「満蒙第一主義」に陥った。 ・結局日本は、列国と平等に協調しながら(そのためには平和友好条約や不可侵条約を結んでも、同盟条約は結ぶべきではない)自主外交を進めていくほかに道はない。 ・いや、民族、宗教、イデオロギー、政治体制がそれぞれ異なっても、互譲の精神で各国と友好関係を深めていくこと、このことがとりもなおさず、日本が列国にさきがけてたらしい国際秩序を建設する「自主外交」への道にもつらなることと確信する。 ―― 完 ―― |