
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年08月03日 木曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
62 |
17/08 |
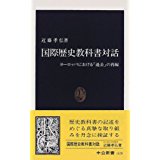 |
国際歴史教科書対話 |
近藤孝弘 |
中公新書 |
◎ |
第二章 鉄のカーテンを越えて――ドイツ・ポーランド教科書対話 ドイツ・ポーランド教科書勧告 ・歴史認識における過去の克服とは、単に加害の事実に目を向けることではなく、そのような侵略行為を正当化することになった当時の歴史認識を再検討することをも要求するものといえるだろう。 第三章 ドイツ・ポーランド教科書勧告の反響 「教科書――爆発するテーマ」 ・設問一 相互理解に向けて、どのような利害が障害になっているか。 設問二 様々な教科書を比較し、その主張が正しいかどうかを自分で判断しなさい。 ・両国のあいだには歴史理解のうえで大きな違いがあることについて具体例をあげて生徒に考えさせようとする教育的意図は、十分に共同教科書委員会の活動の目標の範疇に入るものである。 第四章 歴史教育における "ヨーロッパ" への取り組み 世界史とのつながり ・高校の教科としての世界史は、本質的には様々な外国史の集合体といってよいだろう。それは単なる各国史の並列ではないものの、いわば各国史の枠組みのなかで開発されたパーツを新たに再構成したものである。 ・それに対して国際歴史教科書対話の文脈においてしばしば言及される「世界史」は、最初から世界を一つの単位として見たうえで新たに書かれるいわば人類全体の歴史である。 ・そこでは、既存のナショナルな歴史のなかで重要とされてきた歴史的事実も、そうでない史実も、今日の「世界」が形成される歴史的経緯にとっての重要性という観点から改めて検討され、そのうえで新たに重要性を認められた史実の相互関係について解釈が加えられることになる。 ・一九六五年に、ヨーロッパ評議会は、「中等教育における歴史教育」をテーマにデンマークでシンポジウムを開催している。前もっての質問には次のような項目が見られる。 「あなたの国の歴史教育は、世界全体あるいはヨーロッパにどのくらい関係づけられているか? 自国史の割合は全体の何パーセントか?」 ・かつて植民地を所有していた諸国の教科書では、植民地の歴史も取り上げられていた。しかし、そこで描かれていたのは宗主国が植民地を獲得する過程であり、その後の宗主国から植民地への影響関係であって、植民地化された側の主体性や、植民地が宗主国に及ぼした文化的、社会的影響力については、多くの教科書において相変わらず無視されていた。 ・また、ヨーロッパ文明の拡大という表現による、植民地化プロセスを美化する記述も珍しくはなかったという。 ・ヨーロッパ評議会の下に集まった各国の歴史家の姿勢は明確にヨーロッパ史を指向していたことも事実である。 ・ただし、ここで重要なのは、その際、ヨーロッパ史については重要な二重の留保がつけられていたことである。 ・第一に、それは世界史に向けての暫定的な目標であるということ、 ・第二に、それは早急に達成すべきものではなく、既存の国民史を批判的に検討していく過程でいずれ到達すべきものであるということ、である。 ・シンポジウムの勧告には、次のような記述も存在していた。 各国で共通に教えられるべき単一のヨーロッパ史を考えるなどというのは問題外である。 終章 国家観の変容と歴史の課題 歴史に対する二つの姿勢 ・冷戦体制の解体に至るまでのヨーロッパにおける国際歴史教科書対話の展開を見てくると、一九世紀的な国民史――両大戦間期に最高潮を迎えることになる自国・自民族の栄光を讃える物語としての歴史――が、ようやく少しずつではあるが過去のものとなりつつある様子を、そこにうかがうことができる。 ・そして、とりわけドイツとポーランドの歴史家による対話やヨーロッパ評議会の下で行なわれた初期の多国間対話においては、より開放的・普遍的な性格を持つ歴史理解に再編しようとする意図が顕著であり、私たちの社会が繰り返し経験してきた自国史の賛美という偏狭な思考様式を克服するための景気もそこに見出しうるのである。 ― 完 ― |