
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年08月27日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
64 |
17/08 |
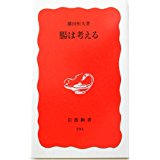 |
腸は考える |
藤田恒夫 |
岩波新書 |
◎ |
1 腸は小さな脳である 腸の「超能力」 ・腸は非常に困難な課題に独自の知恵でとり組んで、実にみごとにそれを処理しているのだ。 化学物質を見分ける能力 ・食物と一緒に有害な毒素が侵入すると、腸はこれに気づいて、腸の壁自身に命じて多量の液体(腸液)を分泌し、毒物を体外へ排除してしまう。これが下痢で、生体の防衛反応としてはきわめて重要なものである。 なんのための中和? ・生体の内部の環境が変化を受けると、元に戻そうという働きが起こる。船の傾きを戻す復原力のようなものを、生体はもっているのだ。 ・この性質はホメオスタシス(恒常性)とよばれる。 ・つまり、生体の船は、ある程度傾いたり揺れたりしているので、正確に同じ状況を保持するのでなく、ある幅をもって、だいたい一定の状態が保たれるのである。 ・こんなわけで、腸の内部のペーハーがほぼ一定に保たれるのも、ホメオスタシスの一例にほかならない。 2 神経かホルモンか ――消化管ホルモン研究の盛衰―― ガストリンの発見 ・胃は食物を吸収しないことがわかっている。 3 センサー細胞の発見 無謀な国際シンポジウム ・シンポジウム(このギリシャ語の意味は「一緒に酒を飲む」ということである) 7 臓器を大きくする消化管ホルモン 酒は胃を強健にする ・ガストリンは胃の幽門前庭のG細胞から出るホルモンで、血中をまわって胃体の胃底腺に作用して胃酸の分泌を促す。 ・酒飲みは一般によく食べ、 ・「酒は百薬の長」というが、酒は消化をすすめ、胃を強くするのである。 ・洋の東西を問わず、キュッと一杯やってから食事にとりかかり、その食事の合の手にも酒を胃に流しこんでいくのは、消化の仕組みにかなった習慣なのである。 枝豆の効用 ・健康な人はもちろん、病人も、ともかく食物を口にすることができる場合は、大豆を食べるのが自然な療法や予防法になるだろう。 ・そこで浮上するのが枝豆である。枝豆は実にうまいし、いくら食べてもあきないし、下痢もしない。 ・そんな枝豆をモリモリ食べることによって膵臓を強くし、消化力をたかめ、糖尿病を治したり、糖尿病を予防したりできたら素晴らしい。 口から食物をとることの意義 ・正常に食事をしていれば――とくにいろいろなセンサー細胞を刺激するようなバラエティーに富んだものを食べていれば――胃腸や膵臓は強く大きく保たれる。 ・逆に食事をとらなくなると、消化器系は細胞分裂が少なくなり、臓器全体として萎縮する。 8 ひろがる細胞の輪――パラニューロン カルシウム代謝の番人たち ・からだのあらゆる細胞にとって、カルシウムイオンが適量に供給されることは死活問題である。 ・血液中のカルシウムイオンの濃度は、血糖のそれよりさらに厳しく一定範囲内に保たれている。 ・カルシウムの多い食物をとれば、血中のカルシウムイオンの濃度は上昇するし、食事をとらずにいれば下降する。 ・しかし、血中カルシウムイオンの濃度が下がりすぎると、副甲状腺の細胞がいち早く感知して、パラトルモンを放出して濃度をもち上げ、血中カルシウムイオンの濃度が上がりすぎると、傍小胞細胞がそれに気づいてカルシトニンを放出して濃度を下げる。 ・カルシウムの貯金は骨の銀行にある。骨の中に多量に蓄積されている炭酸カルシウムと燐酸カルシウムがそれである。 ・この骨銀行のカルシウム貯金を引きおろして血液の中に溶かし出すのが、パラトルモンである。 ・反対に、血液からカルシウムを汲み上げて、骨に貯金する役がカルシトニンである。 ・両者の働きのバランスがくずれて、預金を引きおろし過ぎると、骨がすきまだらけのボロボロになってしまう。これが骨多孔症(骨粗鬆症)である。 ・カルシウムの預金がたまり過ぎるのもよくない。骨以外の場所にまで石灰質が沈着してくるのである。 ・骨のカルシウムを適切に増減しながら、血中のカルシウムイオンの濃度を一定の範囲に保つには、副甲状腺の細胞と傍小胞細胞という二つの内分泌細胞が、鋭敏なセンサーであることが前提なのである。 9 腸のセンサー細胞のルーツを求めて 五億年の遺産 ・腸がどうして食物の化学的情報を認識してこれに反応できるか、ということを研究し、基底果粒細胞が化学的受容のセンサー細胞であるとの考えに到達した。 ・そしてこの細胞が、同類の感覚細胞や内分泌細胞とともに、神経細胞(ニューロン)と共通の性格をもつことから、パラニューロンとして位置づけることになった。 ・ヤツメウナギやナメクジウオの腸には、同じ細胞がみとめられた。 ・昆虫の腸にもまったく同様の立派な基底果粒細胞がみつかり、しかも哺乳類の細胞と同類の脳腸ペプチドを含んでいることが判明した。 ・この細胞と信号物質は、動物界の全体に存在し、腔腸動物の段階で出現していたことが推定され、それはヒドラの研究によって確認されたのであった。 ・ヒドラから高等動物への神経系の進化を考えてみよう。 ・ヒドラにはもちろん脳がない。 ・ヒドラのニューロンは腸のまわりに散らばって、突起の先でつながっているだけである。 ・口のまわりに、鉢巻をしめたように、ニューロンの帯があり、ここではニューロンが密接しているという。これが脳への第一歩にちがいない。 ・動物がヒル、ミミズなどに進化するにつれて、腸のはじまり(食道)のまわりに、ニューロンの密集する神経節というものが現れ、大きくなってくる。この神経節が次第に、食道の上端より上の方に追加されていって、いちばん上部に大きなものがつくられる。これが脳である。 ・こんなわけで、脳はヒドラの腸を包むニューロンが、口のまわりで集合をはじめ、食道のまわりに神経節をつくることによって、発達してきたものだと言える。 ・「脳は腸からはじまった」と言うことができるだろう。 ―― 完 ―― |