
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年08月29日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
66 |
17/08 |
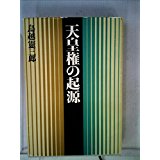 |
天皇権の起源 |
鳥越憲三郎 |
朝日新聞社 |
◎ |
序 ・長い歴史の間に天皇権の危機はいくたびとなくあった。 ・蘇我氏や藤原氏の抬頭をはじめ、もっとも危険であったのは鎌倉幕府の成立のときで、普通であれば天皇の存在は否定されるはずであった。 ・ところが、そのとき天皇は守護・地頭の任免権を頼朝に譲ったが、それは第二次的な政事に関するものであった。 ・頼朝もその上に国家的祭事を執行する天皇の存在を容認したのである。 第一章 大王の誕生 一 祭政の二重主権 神としての首長 ・わが国の古代には、部族の首長が女性であったことを示す記事が散見する。それは後世の女帝のごとき特殊な事情で、一時的に置かれたものではなく、普遍的にみられるものであった。 ・わが国古代にみられる女性の首長は、行政権やぐんじけんをもつ女人政治ではなかった。 ・彼女たちは俗にいう武断的権力というものとは関係なく、祭祀をつかさどる聖なる者として、部族の首長に仰がれていたのである。 ・彼女たちの主たる任務は、部族の繁栄と安泰のために神祭りをすることであった。 ・しかもさらに大切なことは、彼女たち首長が部族全員から、生ける神、すなわち現人神としてみられていたことである。神を祀る司祭者であるとともに、神みずからとして尊崇されていたのである。 姉弟による祭政二重主権 ・現代のわれわれは神を抽象的・観念的に捉えている。 ・ところが古代人は、神を目に見えないものとしてではなく、目に見える神として、具象的・客観的に神を考えていた。つまり、ある女性を真実の神のお姿として拝したのである。 ・わが国の古代社会は母系であったから、その部族の最高位にある家系の女家長を、生ける神の姿として見たのである。 ・そして彼女のもつ神的霊力によって、部族の繁栄がもたらされると信じられていた。そのために、彼女を部族の首長として仰いだのである。 ・わが国古代の統治のあり方は、妹(又は姉)のもつ祭事権の下に、兄(又は弟)の政事権が存していたのである。いわゆる祭政二重主権による統治形態である。 ・第一次的主権は姉妹のもつ祭事権にあり、兄弟の政事権は第二次的なものであった。 ・しかも祭事権をもつ姉妹が現人神としてみられ、神としての彼女の神託によって、兄弟の政事権が保障されていたのである。 ・古代社会にあっては、国土と人民の統治者であることを、神の側から認知される必要があった。 ・その神と王との間を媒介するのが、王の姉妹にあたる女神官であった。 ・しかし彼女は人間として神懸りし、神の言葉を伝達するのではない。彼女は生ける神の姿として見られていたのである。 ・祭事権をもつ女性は直接に政治には関与しないが、その統治権の源が神の側にあるとされていたために、現人神としての彼女たちが、部族の首長とされたのである。 ・そして実際に統治権を掌握していた兄弟の方が、補佐役としての立場におかれた。古代の宗教観念に支配された統治のあり方であった。 ・そのために統治の責任は、究極的には祭事権者である彼女に負わされた。 ・例えば農作物の豊凶や疫病なども、すべて彼女の霊力の如何によるものとされた。 ・それだけに独身を守り、身をつつしむ忌みの生活が強いられたのである。 ・祭事権者はそうした意味において、現実の政治との係わりをもっていた。 男性の祭事権者の出現 ・女性の祭事権と男性の政事権とからなる祭政二重主権のつぎに、祭事権も男性の手に掌握される新しい段階を迎える。 ・俗なるものとして聖所には立ち入ることも許されなかった男性が、祭事権者となり、さらに神的神聖性を認められるようになったことは、宗教観念の上からいって、まことに画期的なことであった。 ・そのきざしは、文献でわかるところでは二世紀まで遡ることができる。。 ・しかも男性の祭事権者の出現が、強力な部族国家が成立しはじめた二世紀半ばと時期的に符合しているところからみると、文化の進んだ部族は、祭事権も早く女性から男性の手へ移したと思われる。 ・またそうすることによって、男性による統治の強力な部族国家をつくることができたのだといえるかもしれない。 ・実際、祭政の両主権を男性が掌握していた部族は、後に王朝をつくるまでに発展した。 ・これに反して、征服された地方の部族は、四世紀末までも女性の祭事権者を有していたものであった。 ・祭事権者は直接政治に関与しなかったとはいえ、首長としての女性は保守的であり、これに対して男性の首長は進取的であったことが、部族の繁栄や勝敗を決定づける結果をもたらしたのかもしれない。 ・邪馬台国は、実は女王卑弥呼の以前に男王が支配する国であった。 ・地方の弱小部族がまだ女性を主張としているころに、強力な部族は祭政の両主権ともに、男性の手で握る統治形態に変わって行ったことは事実である。 ・それは部族国家の強大化するにつれて、シャーマン的な女性を首長としていたのでは、統治権の強化ができないことから、女性から男性への移行が試みられたのかもしれない。 ・邪馬台国は東海の駿河国から、西は九州におよぶ広大な版図を支配していた大国家であった。 ・それがすぐ南の狗奴国によってあえなく邪馬台国は滅亡する。 ・その原因となったのは、案外シャーマン的な卑弥呼が女王であったことによったともいえる。 ・しかも邪馬台国を倒した葛城王朝も、つぎの大和朝廷も、祭政の両主権ともに男性が掌握していた。そのことが天下の権を変えるほどの強国に発展せしめた原動力であったともいえよう。 二 大王の継承権 天皇の起こりは俗なるもの ・文献で知りうるかぎりのわが国古代の統治のあり方は、姉妹のもつ祭事権のもとに、兄弟の政事権が存する祭政二重主権の形態であった。そして祭事権を持つ姉妹が現人神として、部族の首長の地位にあった。 ・これに対し、進歩的な部族では、その祭事権も女性の手から男性に移し、祭政の両主権とも兄弟が掌握するようになった。しかも、そうした道を早くたどった部族ほど強大となって、部族国家から、さらに国家体制へと発展して行った。 ・だがその場合でも、第一子としての兄が祭事権をもち、聖なる現人神として独身を守り、部族の首長の地位にあったことを忘れてはならない。 ・したがって、皇統譜の初期に天皇と称されているものは、実は第二次的主権としての政事権をもつ弟であった。 第二章 諸学説の批判 一 河内王朝説批判 仁徳天皇は聖天子であったか ・仁徳天皇になって初めて都を大和におかず、離れた難波の地に定めた。 ・『日本書記』に記された仁徳天皇の条を見て驚くことは、この天皇がいかに聖天子であったかということだけの記事で満たされていることである。 ・それほど事実をひた隠す事情があったからであろう。 ・ ・そのことは大和の豪族の間にひろまったであろう。 ・そこで大和に都を置く身の危険から、あえて応じ時代の領地であった難波の地に、都を定めて即位したものとみられるのである。 仁徳陵を和泉に造った理由 ・仁徳朝の事績をみると、すべて河内潟をかこむ周辺の土木事業である。 ・河内潟は、洪水ごとに氾濫し、周辺の農地に冠水して、農民に甚大な被害をもたらしていた。 ・そのために難波堀江(現在の天満川)の開削によって、河内潟の水を外海に流し、また ・そのことに関連して脚色された伝承 即位の年に高津宮が造営されたが、宮殿の垣や殿はあら壁のままであった。 また、垂木・梁・柱などにも彩色せず、屋根の茅も軒先を切りそろえなかった。 たとえ天皇でも、宮殿の造営は私事に属するので、百姓の耕作の時季をさまたげないためであった。 また四年には、 そして御自身の衣服や このように、天皇は民の貧困を案じられる御心があったために、三年後には百姓は豊かになり、竈の煙もさわにのぼるようになった。 そこで民の方から宮殿の繕いを申し出たが、なお天皇はお許しにならなかった。 さらに三年後、やっと課役を命じ、宮殿の修理を手がけられた。それには老幼を問わず馳せ参じて、はじめて立派な宮殿となった。そのために人びとは ・この話は、災害のあと、課役を免ぜられたことは事実であろうが、それにしても、これはあまりにも誇張された話になっている。 ・だが、たび重なる災害を土木事業で救済されたことが、難波や河内の人に聖天子としてのイメージをあたえたともいえる。 ・脚色された話とはいえ、これほど地理的に条件の悪い場所に、あえて都をつくらなければならなかったのである。 ・大和の勢力に対抗して、地元の勢力を高めることに、すべてが唐ぜられたのであった。 ・そのために天皇の墳墓も、難波の海の見える丘に築いたのである。 ・全長四八六メートルという巨墳を、生前から築造にかかった。生前に墳墓を築いたのも仁徳天皇だけである。そこには権威をみせびらかす底意がなかったとはいえないであろう。 ・三重に濠をめぐらし、広さでは世界一の墳墓といわれる仁徳陵は、盛土だけでも一日千人が労役したとして、四ヵ年もかかる巨墳であるといわれる。 ・こんなとてつもないものを計画するのは、奈良の大仏と同じく、何かに怯え、虚勢を誇ろうとした時の権力者の妄想をそこに見るのである。 ・この仁徳陵が百舌鳥野の一角に築かれてから、つづく履中陵・反正陵など大小百ほどの古墳が営まれ、いつしか百舌鳥古墳群となった。 ・しかし仲哀陵・応神陵にはじまる古市誉田古墳群にしても、仁徳陵を中心とする百舌鳥古墳群にしても、それらが大和の地に築造されなかったということで、それまでの三輪王朝が倒れ、新しく河内王朝が誕生したと解くのは誤っている。 ・それら墳墓は河内に築かれ、また仁徳天皇の都は特別の事情で難波におかれたが、神功皇后や応神天皇、また履中天皇など前後の世代の都は大和に定められている。 ・大和が政治と文化の中心であったことは、前時代と少しも変わっていないのである。 イリヒコ系・ワケ系の分類に疑問 ・景行天皇には皇子・皇女が八〇人もあったと伝えている。 ・もちろん「八十王」というのは多数の意で用いられたものである。 ・というのは、地方の各支族が天皇家や大和の豪族の系譜につながりをもたすべく、氏族の本系帳を偽作したことである。 ・それによって政治的地位を有利にしようとしたのであるが、その多くは神武から開化に至る葛城王朝の皇子を始祖とした。それは葛城王朝の系譜が明らかでないために、盗用しやすかったからである。 ・実は景行天皇の末裔とする氏族が多いのは、この御代に九州から東国に至る広範な地域が征討されたためである。 ・景行天皇の子たちを「八十王」と記したのも、出自を求めるのに都合がよかったからである。 ・そうした事情を理解してみると、景行天皇の系譜を無謀なものとして、全体の価値まで否定するのは行き過ぎであろう。 二 倭の五王をめぐって 倭五王の解明の糸口は何か ・『三国志』魏志倭人伝には、邪馬台国のことがくわしく記され、数次にわたって魏とわが国との外交関係のあったことがみえる。 ・その魏は西暦二六五年に倒れる。そして新たに晋が興るが、その武帝即位の翌年、すなわち泰始二(二六六)年に、わが国から使者が派遣され、貢物を献上した記事が『晋書』帝紀の条にみえる。 ・これは年代からみて、邪馬台国の女王卑弥呼のあとをついだ女王台与の入貢であったとみてよい。 ・それは新しく樹立された晋朝に対して、祝賀のための使者派遣であったと考えられるが、この記事を最後にして、わが国のことは中国の史書から消える。 ・それは間もなく邪馬台国が滅亡したからであろう。 ・その後に葛城王朝や大和朝廷がありながら、中国の史書にわが国の記事がみえないのは、中国へ入貢するほどの強力な国家体制になっていなかったからだと思われる。 ・邪馬台国のあとをうけた葛城王朝は二、三代で滅び、大和朝廷の時代に入るが、仲哀朝までは全国制覇のための外征に明け暮れていたのである。 ・ところが応神朝以降、全土が統一されて朝廷の権力が確立された。 ・そこで晋の安帝の義熙九(四一三)になって、久しぶりに倭の五王の一人である ・したがって、わが国のことは中国の史書に一四七年間の空白が生じているのである。 ・晋以降の史書にみられる特徴の一つは、男性である大王の名で使者を遣わし、また中国の皇帝から将軍号を賜わっていることである。 ・大王が一国を代表する権力者として、その名を登場させていることは、政治体制に変革のあったことを示すものといえよう。 ・その倭の五王としては、讃・珍・済・興・武の名が見える。 ・済・興・武が、允恭・安康・雄略の各天皇に該当することは間違っていないとみてよい。 第四章 蘇我氏の専横 一 仏教伝来と蘇我氏 大伴金村の引退と蘇我氏の起こり ・天皇家が長く存続してきた最大の原因は、国家的立場において神を祭る家柄としての権威に由来した。 ・一般の常識では、長い歴史の間に、いくたびとなく武力的革命によって崩壊しても仕方がなかったと思う天皇家が、永続してきたのもそのためであった。 蘇我氏をめぐる百済帰化人 ・アスカ、その語源は朝鮮語のアンスク、すなわち「渡り鳥の安住の地」という意からの転訛だといわれる。 二 蘇我政権への道 天皇を弑する馬子の勢力 ・天皇家を倒せるこの機に、蘇我氏が王者にならなかったことが、古来からの朝廷の神祇を温存させ、ひいては現代まで神祇と仏教を両立させる国柄にした根本原因だと思う。 ・実際、宗教学の立場からみると、民族宗教としての神祇と、高度な教理をもつ仏教とを、後には天皇みずからも両立させて尊崇し、国民もそれに従った。 ・世界的にみて、まことに珍しい国柄となったのである。 ・しかし両者の取捨選択を、あえて蘇我馬子はしなかったのである。 三 飛鳥仏教と蘇我氏 三つの金堂をもつ法興寺 ・法興寺は、国家的最高の寺院として、壮大な伽藍をもって建立された。 ・もともと法興寺は、蘇我馬子の誓願によって建立された。 ・馬子は仏法興隆の中心人物であった。 ・一般には聖徳太子によって、仏法の興隆が行われたように思われているが、実際にはそうではない。 ・聖徳太子は馬子の庇護のもとに、みずからも篤く仏法に帰依はしたが、真実の推進力となっていたのは馬子であった。 蘇我の私寺が国家的寺院になる ・はじめて板葺にしたとみられる皇極天皇の板蓋宮と推定されるものが、法興寺址に建つ現在の安居院(飛鳥寺)の南で発掘調査され、切妻・掘立柱の建物であったことが判明している。 ・したがって、それ以前の推古女帝の宮居の建物は、萱葺・掘立柱であったとみてよい。 ・これに対し、法興寺は瓦葺の屋根であった。掘立柱では屋根の重みを支えられないので、柱は礎石の上に立てられた。 ・何も彼もが、それまでの日本建築とは全く異なっていた。 五 推古勅撰の国史 神話は葛城王朝のものが中心 ・古代社会にあっては、部族間の事件を、その部族が奉ずる神と神との関係の物語として伝えてきた。それが神話であった。 葛城王朝と邪馬台国の関係 ・『後漢書』・『梁書』・『北史』に書かれた、二世紀末(一七八~一八三年)の大乱は、邪馬台国によって北九州勢力が征討されたことを示すものである。 ・邪馬台国はすでに男王が治める国となっていた。しかし文化の進んだ北九州勢力の征討は、新興の邪馬台国には至難なことであった。 ・そこで女性のもつ霊的力がのぞまれ、女王として卑弥呼が立てられた。彼女には男弟があったとあるように、女王は祭事権者として、男弟王は政事権者として、姉弟による祭政二重主権の古い統治形態にもどしたのである。 邪馬台国は推古勅撰書が消した ・第八代孝元帝が都を葛城山麓の旧地に後退させたのは、邪馬台国と最後の興亡をかけた戦いのためであったと思われる。これによって邪馬台国はついに倒れ、それは西暦二八〇年ころであったと思われる。台与はそのころ四十歳あまりであるが、たぶん彼女の代で邪馬台国は滅亡したものとみてよかろう。 ・邪馬台国の滅亡と、大和平野全域ならびに河内国・山城国を領有することによって、第九代開化帝は都を現在の奈良市域にまで進出させたのであろう。 ・しかしその段階で、革命によって葛城王朝は亡び、政権は大和朝廷に更迭する。それは四世紀前半であったとみてよい。 ・わが国の文献からみた葛城王朝と物部氏の関係は、そのまま魏志倭人伝の狗奴国と邪馬台国の関係にあてはまる。 ・そして物部氏が築いていた邪馬台国は、葛城王朝の第六代孝安朝から攻勢をうけ、第七代孝霊朝の末期か、第八代孝元朝に滅亡したことがわかるのである。 ・馬子による推古勅撰書が、その後のわが国の歴史を決定づけた。 ・馬子は大胆に、神話と歴史を政治的作為のもとに組み立てたのであった。それは天皇権をしのぐ馬子の実権がなしえたわざであったといえよう。 第六章 藤原政権への序章 二 藤原専制へのきざし 法名に身を寄せた退位 ・飛鳥時代の仏像は中国の北魏様式のもので、大陸的なきびしさの中にも神秘的なものが感じられる。 ・白鳳物はそれを日本人の感覚によって、リアルで柔らかく温かいものにした。そこには律令国家への希望が合った。 ・これに反して、天平仏には強靭さは認められはするが、その中に憂鬱な陰影がひそんでいる。 ―― 完 ―― |