
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年09月10日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
69 |
17/08 |
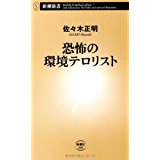 |
恐怖の環境テロリスト |
佐々木正明 |
新潮新書 |
◎ |
プロローグ ・シー・シェパードの代表ポール・ワトソンは、巧みな情報操作と暴力により、2011年初め、調査捕鯨はついに中止に追い込まれる事態となっているが、それは日本社会が長らくこの問題を過小評価し、政府も根本的な打開策を怠ってきたからにほかならない。 ・目的達成のためには法を犯し、所有物を破壊し、人間の生命をも狙う彼らの行為はアメリカ連邦捜査局(FBI)によって「エコ(環境)テロリズム」と定義されている。 第1章 日本叩きで稼ぐ動物愛護産業 再び現れた活動家 ・クジラとイルカは、生物学的にはどちらも哺乳類のクジラ目に属し、体長4メートル以上の鯨類をクジラ、それ以下をイルカと呼んでいる。 第4章 キング牧師、ガンジー、グリーンピース ガンジーも我々と同じ ・「市民的不服従」という言葉、 これは19世紀のアメリカの思想家、ヘンリー・デイヴィッド・ソロー(1817~1862)により提唱された概念であり、抵抗手法だ。 それは「人は自らの良心に基づき、戦争や奴隷制のような悪政、悪習には断固としてノーを言うことができる。たとえ、法律を破ってでも」という概念だった。 ・インドの英国からの独立を求める非暴力抵抗運動やアメリカの奴隷制度と人種差別の撤廃を求める公民権運動、そして、南アフリカの反アパルトヘイト闘争などで実践された抗議手法ともなった。 ・ソローは、勇気を振り絞り、良心に基づいて国家に楯突く行為には、誰かを殺したり傷つけたりすることも「避けられない場合がある」とも主張した。 ・彼はエッセイでこう記した。 「正義を、そして人間としての権利をちゃんと自覚してそれを守るための行動をやり遂げるということ、それによって初めて、物事や状況のありようを変えていくことができる」 ・こうしたソローの抵抗哲学は、環境保護運動が発展していく上で、その一派である過激団体に浸透していった。 動物への罪悪感 ・西洋世界では長らく、動物は人間に役立てられるために存在すると信じられてきた。 ・古代ギリシャのアリストテレスは、感覚を有するが「理性」を欠く動物は、自然界の中で下位のヒエラルキーに位置し、人間の目的のために使える資源だと主張した。 ・キリスト教世界でも、神は自らの姿に似せて人間を創造したのであり、聖書は人間とそれ以外の動物の地位を明確に区別して、人間の優越性や道徳的地位を認めている。 ・イルカ漁や捕鯨に反対するのは、そのほとんどが西洋的な伝統的価値観を受け継ぐ欧米諸国やオセアニアの人々である。 ・彼らは、クジラやイルカは知性が高く、海の中で人間社会のような暮らしを営んでおり食用に殺すのは野蛮だ、という。 ・彼らも1950年代までは、軽工業に必要な鯨油を獲得するために、鯨類を大量捕獲してきたことがすっかり置き去りにされている。 ・逆に言えば、動物は人間のために利用すべきという宗教的価値観はいかにして消え去ってしまったのだろうか。 壱岐のイルカ事件 ・人間以外の動物は理性や知能をもたないとする西洋の宗教的価値観に一石を投じたのは、19世紀の自然科学者、チャールズ・ダーウィンの『種の起源』だったことは疑いようがない。 ・ダーウィンは、人類は長い年月をかけて、他の生き物から進化してきたことを見抜き、動物と人間との間には生物遺伝的な地球の歴史が連綿と受け継がれていることを解き明かした。 黒人への差別、動物への差別 ・オーストラリア出身の哲学者で現在、米ブリンストン大学で教授を務めるピーター・シンガー(1946~)は、1975年、29歳のときに『動物の解放』を記し、その後の環境保護や動物の権利擁護運動に多大な影響を与えたキーパーソンである。 ・シンガーは、黒人への人種差別と女性への性差別の構図と同様、動物に対して人間の恣意的な搾取と抑圧は、「種差別」にあたるという。 ・シンガーはヒューマニズム的観点から、動物へも優しさと特段の配慮を持つべきと考えた。 ・『動物解放論』は1983年、アメリカの哲学者、トム・リーガン(1938~)に受け継がれる。 ・リーガンは、知覚や欲求などの感覚を備える生き物はすべて自由の権利や生きる権利を持ち、人間と同等の権利を認めるべきだとする「動物の権利」論を説いた。 ・こうして、シンガーやリーガン、その後に続く哲学者によって動物愛護派の人々が抱く思想的基盤が確立された。次々に、動物の権利を守ろうとする活動家が生まれていった。 ・その一派の中に、人間の食用や娯楽目的で動物を殺すことは絶対に許さないと考える過激な原理主義者が現れたのである。 ・活動家らは、ソローの『市民的不服従』とシンガーの『動物の解放』、リーガンの「動物の権利」論をバイブルとし刺激的な事件を起こして世論を喚起していった。 第6章 立ち上がった日本人たち シー・シェパードが慈善団体? ・弁護士の西村純一氏曰く、 「日本政府はPRが下手。シー・シェパードとの戦いは情報戦であることを理解して対策を練っていない」 ・ニュージーランドの在留邦人の多くも「なぜ、日本政府はちゃんと反論しないのか」と苛立ちを募らせているという。 ・捕鯨問題の解決や効果的なシー・シェパード対策は、情報の透明性を担保することと、独立したPR部門の設立、そしてエコテロリズムを冷静に分析できる専門組織にある。 ・日本国内でも暴力の論理が広まる可能性がある今だからこそ、過激団体と穏健な団体との間に線を引き、違法行為は徹底して取り締まらなくてはいけない。 ―― 完 ―― |