
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年10月09日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||
70 |
17/08 |
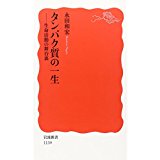 |
タンパク質の一生 |
永田和宏 |
岩波新書 |
☆ |
はじめに――細胞のなかの働き者、タンパク質 ・私たち人間の身体は、その六〇~七〇パーセントが水分であるが、固形成分の約二〇パーセントはタンパク質である。 ・私たちの身体を構成するタンパク質は、二〇種類のアミノ酸が枝分かれすることなく一列につながってできている。 ・食品として摂取したタンパク質を、アミノ酸というその構成要素にまで分解し、再びアミノ酸をつなぎあわせてタンパク質を作り出す。このサイクルこそが生命活動の根本であり、タンパク質は人間の身体を担っているもっとも重要な物質の一つである。 ・ひとつひとつの細胞の大きさは種類によって違うけれども、おおよそ一〇~二〇ミクロン。一ミリの一〇〇分の一から五〇分の一程度である。 ・DNAのヒモは四六本の染色体として核に収まっているが、一個の細胞に含まれているDNAをすべて一直線につなぎ合わせてまっすぐ一本に伸ばすと、約一・八メートルににもなる。 ・ヒト一人の体内にあるDNAをすべて一直線につなぎ合わせるとすると、一・八メートル×六〇兆、すなわち一〇〇〇億キロメートル。 ・六〇兆個の細胞が、それぞれ八〇億個くらいのタンパク質を持っていると言われている。 ・しかも、この八〇億個というのはいったん作られたらそれで終わりではなく、常に分解と生成を繰り返して、新陳代謝をおこなっている。 ・その生成スピードたるや、もっともアクティブな細胞では一秒間に数万個という計算がある。一ミリの一〇〇分の一ほどの大きさの細胞、その一個の細胞が生きていくためだけに、八〇億個ものタンパク質が必要なのである。 ・六〇兆個の細胞の一個一個の中では、毎秒毎秒恐ろしい勢いでタンパク質が作られ続けている。 ・タンパク質は、食物として大切なだけではなく、私たちの細胞をもっとも小さな単位とした「生命」の営みそのものを担う、もっとも大切な働き手なのである。 ・さまざまな病気にも、そのどこかでタンパク質が関わっている。 ・ある場合には、生命活動に必須なタンパク質が欠如したり、異常を起こしたりして、正常な生命活動を営めなくなったり、またある場合には、異常なタンパク質が蓄積して、アルツハイマー病やプリオン病(BSEなど)のように私たちの神経細胞を損なったりする。 ・タンパク質は、まぎれもなく私たちの生命活動の主役であると言っても過言ではない。 ・個々のタンパク質にも、人間の一生と同じような、誕生、成長、成熟、老化、そして死というドラマがある。 ・私たちが持っている数万種類のタンパク質のうち、短いものではわずか数秒の命しか持たないタンパク質も知られているし、長いものでは、実に数ヵ月にわたって働き続けるものもある。 第一章 タンパク質の住む世界――細胞という小宇宙 素材となる「アミノ酸」 ・タンパク質とは、もっとも簡単にいえば、「アミノ酸が一列につながったもの」のことである。 ・おおよそ物質の基本的な構成単位は「原子」であり、原子が集って一定の機能を持つようになった最小単位が「分子」であるが、アミノ酸はタンパク質を構成する基本的な分子である。 ・アミノ酸を作る原子は、窒素(N)・酸素(O)・炭素(C)・硫黄(S)・水素(H)の五種類に限られる。 ・私たちの身体で働くたんぱく質を作っているのは二〇種類のアミノ酸であるが、このわずか五種類の原子が集って個々のアミノ酸を作っている。 数え切れない種類のタンパク質 ・ひと口に「タンパク質」と言っても、その種類は数万に及ぶ。素材のアミノ酸はたった二〇種類しかないのに。 骨格も、酵素もタンパク質 ・たとえば血管は、血管内皮細胞という上皮細胞が管構造を作るが、血管内皮細胞の外側を覆っているのは基底膜であり、これがないと血管は容易に破れてしまって、生物は生きることができない。 ・形を支える、言ってみれば柱や梁のような働きをする線維は細胞の内側にも必要で、それは細胞骨格と呼ばれる。 ・この細胞骨格の主成分のひとつが、アクチンである。 ・細胞外マトリクスや細胞骨格など、細胞や組織の形を支える働きを持つタンパク質を構造タンパク質と呼ぶ。 ・「酵素」という言葉はすでにポピュラーだが、この酵素もタンパク質である。 ・生体内では、単純な分子から複雑な分子を合成したり、複雑な分子を単純な分子に分解してエネルギーを得たり、常に物質の返還がおこなわれている。これを一般に「代謝」と呼ぶが、体内においてこの代謝反応をはじめとして、多くの化学反応を円滑に進めるための触媒が酵素である。 ・私たちの体内では、数知れない「代謝反応」が起こって生命を維持しており、ほとんどの場合に、タンパク質が酵素としてその反応を効率的に進めるために働いている。 ・細胞骨格などの構造タンパク質や、酵素として働くタンパク質を作る時にもまたさまざまなタンパク質が働いている。 ・DNAやRNA、脂質、糖やATPなど、体内で働くほとんどの分子の産生においても、その主役はまさにタンパク質にほかならないのである。 仕事人、タンパク質 ・受精に始まる発生の過程においても、細胞の分裂や、受精卵から種々の体細胞への分化の指令は、すべてタンパク質が担う情報伝達の仕組みによって制御されている。 ・受精卵が雌雄いずれになるかは、よく知られているようにX染色体とY染色体、すなわち性染色体の組み合わせで決まる。X染色体を二本持っているのが女性、X染色体とY染色体を一本ずつ持っているのが男性である。 ・しかし、どうやら受精して七週目くらいまでは、まだ女でも男でもない状態であるらしい。 ・八週目くらいになってやっと雌雄の区別があらわれるが、これは実は精巣決定遺伝子によって作られる、特定のタンパク質が規定しているらしいのである。 ・もともとは雌になるべく発生してきた胎児が、ある特定のタンパク質を造りだした場合にだけ雄になる。デフォルトは雌だったのである。 ・「死」もまたタンパク質がつかさどる。 ・アポトーシスと呼ばれる、自らのスイッチをオンにするシステムを細胞は備えている。いわば細胞の自殺である。 ・タンパク質は、発生から分化、そして死まで、細胞や個体の一生をつかさどる重要な物質であ。 ・細胞や個体の一生のすべてに関わるものがタンパク質であるが、一方で、そんなタンパク質自体にも一生がある。 ・タンパク質にも人間と同じように、誕生があり、成長があり、死を迎えることになる。 細胞生物学 ・六〇兆個の細胞は、目の細胞、皮膚の細胞など、おおよそ二〇〇種類に分かれると言われている。 細胞の構造 ・細胞は、核とそれ以外の「細胞質」とに分かれ、核以外のものはすべて細胞質と呼ばれる。 ・核の機能は、何よりもまず遺伝情報を含むDNAの貯蔵場所として働くことだが、細胞が分裂するときにはDNAを二倍に増やす必要があり、そのためにDNAを複製する場でもある。 ・DNAが損傷を受けた場合には、そのままだとがんになるなどの障害が起こるので、傷を修復するための機構がある。その修復は核でおこなわれている。 ・さらにひじょうに重要なものとして、DNA情報の転写という機能がある。 ・DNAをそのままもているだけではタンパク質は合成できない。核という情報の巨大な保存装置から、まず、核から持ち出し可能なテープに情報を写し取る。 ・このテープにあたるものがメッセンジャーRNA(mRNA)と呼ばれるRNAであるが、この作業を転写と呼ぶ。 ミトコンドリア ・ミトコンドリアは、植物における葉緑体とおなじくエネルギーを作り出すための「発電所」であり、細胞のエネルギー通貨ともいうべきATPが合成されている。 共生細菌がミトコンドリアに ・ミトコンドリアは、元々は何億年も前に私たちの祖先の細胞に侵入して、そのまま共生するようになったバクテリアと考えられている。 ・元をたどれば、私たちとは別の生物だったということだ。 ・ミトコンドリアは、自分自身の遺伝子を持ち、内部で独自にタンパク質を作り、おまけに勝手に分裂までおこなう。 ・ミトコンドリアは、その遺伝子を母親からしか受けつがない完全な母系遺伝であ。 DNAとは何か ・細胞の中には核があり、その中にDNAが収まっている。 ・そして、どの細胞も基本的にはまったく同じDNAを持っている。 ・DNAは染色体という形で核の仲に存在する。 ・ヒトの細胞では、二三本の染色体を必ず対になるように二セット、合計四六本持っており、これを二倍体という。 ・一個の卵子と一個の精子はいわば半人前で、それぞれ一セット(二三本)ずつしか染色体を持たないが、受精してようやく、一対の染色体のセットを備えた一人前の細胞になる。 ・すべての細胞は、この一個の受精卵が細胞分裂することによって増えていくため、一個の個体の中にのすへての細胞はまったく同じ遺伝情報を持つことになる。 ・この情報の総体をゲノムという。 ・逆の言い方をすれば、核を持つ細胞であれば、身体のどの細胞であってもヒトのすべての細胞を作る能力を秘めているとも言えるだろう。 ・受精卵からはES細胞(胚性幹細胞)という細胞を作ることができるが、ES細胞からは皮膚や神経を含めて、すべての細胞腫を作り出すことができる。 DNAの情報量 ・DNAはタンパク質の情報を記録したテープである。 ・その中にたくわえられている情報量は、文字という概念にたとえて言うなら、ヒトでは三〇億文字に相当する。 ・実際にはこの情報はDNAを構成している塩基という物質の配列によって決められている。 ・「生物の文字」として配列を決めてている塩基は、たったの四種類しかない。四つの文字で、あらゆる情報をコードしているのである。 ・コンピュータ言語が0か1かの二種類の文字によって書き込まれているいることはよく知られているが、生物の場合はこれが四種類あることになる。 ・この塩基の配列には個人差というのはほとんどなく、誰もが九九・九%程度は同じである。 すべてはタンパク質のために
・それぞれのゲノムサイズと、遺伝子の数を見ると、その差は想像以上にわずかである。 ・このことは、生命を維持していくためには、必須のタンパク質が多くあり、その生命活動自体は、ハエでも植物でも酵母でもほとんど変わらないということなのである。 ・まして、同じ哺乳類同士ともなればもっと近く、サルとヒトのあいだでは、実際にタンパク質の種類だけでなく、個々のタンパク質のアミノ酸配列、つまり性質もほとんど変わりがない。 第二章 誕生――遺伝暗号を読み解く どれくらい時間がかかるか ・細胞全体としては、一秒間に数万個ものタンパク質が作られているのである。それぞれに多くのステップを必要とする大変な作業が、気の遠くなるようなすばやさ、高率でおこなわれている。 第三章 成長――細胞内の名脇役、分子シャペロン 分子シャペロンの発見 ・生物を形作っている二〇種のアミノ酸を、どれだけ、そしてどのような順序で並べれば、一個のタンパク質として機能を持ちうるものができるかを、情報として保存しているのがDNAである。 ストレスタンパク質 ・ここでいうストレスとはどういうものか、たとえば発熱を考えれば分かりやすいだろう。 ・私たちヒトの細胞は、通常、約三六度程度の温度に保たれている。しかし、たとえば風邪をひいて熱が出たときには、三九度、子供なら四〇度を超えることもしばしばである。 ・一般に熱エネルギーは、運動エネルギーとなって分子を激しく運動させる。 ・冷たい水を火にかけて熱すると沸騰するが、これは熱のエネルギーを吸収した水分子が、それを運動エネルギーに変え、はげしく運動しているのである。 ・タンパク質の場合も同じで、細胞に熱がかかるとアミノ酸を構成する原子の動きが活発になり、せっかく疎水性のアミノ酸を内側に折り畳んで安定した構造をとってきたにもかかわらず、それを作っている原子が熱エネルギーを獲得し、活発に運動することによって全体の安定な構造を壊してしまう。 ・その結果、疎水性のアミノ酸クラスターが分子表面に露出して不安定になり、凝集を起こしてしまうということになる。 ・ヒトの身体において熱がでるというのは異常事態だが、熱によるタンパク質の凝集という出来事には、私達は日常生活で当たり前のように出会っている。 ・典型的な例はゆで卵である。 ・生卵のとき、卵に含まれるタンパク質は水にとけた状態にある。これに熱を加えるとゆで卵になるが、ゆで卵というのは、要するにタンパク質が凝集して固まったものだ、と言えば、「凝集」という現象をイメージしやすいだろう。 ・私達の細胞の中でタンパクが固まってしまうと、細胞は死んでしまう。ならばどうすればいいか。細胞はぬかりなく、この状況に対処するメカニズムを備えている。ストレスタンパク質の出番である。 温熱療法の実際 ・がん細胞自体が血管を誘導する物質を作り、血管を自らの組織内に引き込むことによって栄養を確保し、増殖する。がん細胞はしたたかである。 第四章 輸送――細胞内物流システム 「輸送」の精巧なシステム ・タンパク質が細胞にとって意味があるのは、そのタンパク質が本来働くべき正しい場所で働ける場合である。 ・タンパク質も、作られた場所から、それが本来働くべき細胞内あるいは細胞外のそれぞれの場所に運ばれてゆく。 インスリンの分泌 ・インスリンは、膵臓にあるランゲルハンス島のβ細胞から分泌されるペプチドホルモンである。二一個のアミノ酸からなるA鎖と、三〇個のアミノ酸からなるB鎖が三つのジスルフィド結合でつながれた低分子タンパク質である。 ・インスリンのもっともよく知られた重要な作用は、血液中の糖を利用したり、貯蔵したりするための、細胞への糖の取り込みの促進作用であろう。 ・食物を摂取すると、炭水化物などはブドウ糖に変えられ、血液中の糖の量(血糖値)は上昇する。この血糖値の上昇を感知して、β細胞はインスリンを急激に分泌する。 ・このペプチドホルモンが血液中のブドウ糖の細胞内への取り込みを促進することによって、血糖値を調整しているのである。 ・血糖値は通常は一ミリリットル中に七〇~一二〇ミリグラムの範囲に調節されているが、これ以上に血糖値が上がると糖尿病の危険にさらされることになる。 ・糖尿病は、インスリンが正常に作られなくなったり、分泌に異常をきたしたりすることによって、量的に不足することに起因するⅠ型糖尿病と、インスリンは分泌されているのだが、それが効かなくなること(インスリン抵抗性)に起因するⅡ型糖尿病に分けられる。 コラーゲンの合成 ・コラーゲンは私たちの身体の中でも、もっとも大量に存在するタンパク質であり、実に全タンパク質重量の三分の一を占める。 ・細胞と細胞の間隙を埋めるように存在する結合組織にはⅠ型コラーゲンが、上皮細胞を正しく配向させるためのカーペットのような基底膜にはⅣ型コラーゲンがというように、組織によってコラーゲンの型が異なり、現在二七型まで知られている。 ・量的にも、そして機能的にもそれほどの種類が必要だということである。 ・コラーゲンは発生にとって必須のタンパク質であるから、コラーゲン分子中に突然変異などがあると、さまざまの遺伝病があらわれる。 ・コラーゲンは遺伝病のもっとも多く報告されているタンパク質のひとつである。 ・美容や健康に効果があるとしてコラーゲン入りの健康食品等が多く販売されているけれども、それは本当に効果があるのだろうか。 ・コラーゲンを摂取することで、それがそのままコラーゲンの補充(サプリメント)でもあるかのような宣伝をよく見かけるが、食品として摂取したところで、それは消化器官を通じていったんアミノ酸へと分解されたのちに栄養素として再利用されるので、コラーゲンの形のままで吸収されることはありえないのである。 ・せいぜい原料になるアミノ酸を体内に増やすという効果はあるかもしれないが、複雑な過程を経てコラーゲン線維へと合成されないかぎりは、タンパク質としての機能を持たないことは明白である。 分子シャペロンと病気 ・肝硬変や、肺線維症、動脈硬化、ケロイドといった「線維化疾患」は、コラーゲンが異常にたまる病気であり、現在のところ有効な治療法のない難病中の難病である。 ・肝硬変は、コラーゲンが肝臓に異常にたまってしまう病気である。 ・間質性肺炎が進行すると肺線維症に至るのだが、これもコラーゲンの蓄積が引き起こす病態であり、呼吸困難を起こすとともに予後がきわめて悪い。 ミトコンドリアへの輸送 ・ミトコンドリアは、動物細胞の場合、ひとつの細胞に一〇〇~二〇〇〇個存在しており、そのそれぞれについて、ミトコンドリア内部へとタンパク質を運び込む方法を独自に備えている。 第五章 輪廻転生――生命維持のための「死」 不老長寿の夢 ・いったん作られたタンパク質が分解される(死ぬ)ことがなければ、食料に悩むこともなく、生物はもっとゆったり生きることができそうである。しかし、現実にはタンパク質には寿命がある。寿命どおりに死んでいってもらわねば困るのである。 ・タンパク質に寿命のあることは、常に新鮮な活力のある働き手としてのタンパク質を保証するという意味で、生体にとってきわめて重要なことである。 タンパク質の寿命 ・私たちヒトも含めて真核生物が持つタンパク質は、五~七万種類くらいあると言われている。 ・それぞれのタンパク質の寿命はさまざまで、いま分かっている限りでも、数分というひじょうに短い寿命しか持たないものもあれば、数十日から数ヵ月の寿命を持つものもある。 入れ替わるタンパク質 ・ほとんどのタンパク質が、古いものが壊されて新しく作られたものと入れ替わるという代謝のサイクルを持っている。 ・私たちヒトの身体は、体重のおよそ二割弱がタンパク質であると言われている。 ・さらに一日あたり、そのタンパク質のうちおよそ二~三パーセント、約一八〇~二〇〇グラムが古いものから新しいものに入れ替わっていると言われている。 ・およそ三ヵ月で体内のたんぱく質はほぼすべて入れ替わるということになる。 ・つまり、たんぱく質に関して言えば、私たちは三ヵ月で別人になってしまうということなのである。 日々生まれ変わる細胞 ・細胞のレベルにおいても、一年経つと、身体を構成する全細胞の実に九十数パーセントが入れ替わってしまう。 ・もちろん細胞の寿命もタンパク質同様まちまちで、脳の神経細胞のように、生まれたときにすでに一四〇億個の細胞が完成しており、後はもう増えることも再生することもなく、壊れたらそれまでと教えられてきた細胞もある。 アミノ酸のリサイクル・システム ・タンパク質の原料になるアミノ酸は、タンパク質を分解することによって作られる。 ・私たちが食事を通じて一日に摂るタンパク質の量は、およそ六〇~八〇グラムが平均らしい。 ・ところが、体重七〇キロの人で、一日に作るタンパク質の量はおよそ一八〇~二〇〇グラム。 ・食べたタンパク質がすべて分解され原料として使われたとしても、摂取量より新たに作られる量の方が多いことになってしまう。原料以上の製品をいったいどうやって作るのか? という疑問が生まれるだろう。 ・答えはアミノ酸のリサイクル・システムである。 ・食事によって体内に摂取されたアミノ酸に加えて、体内のタンパク質を分解し、その過程で生じたアミノ酸もまた、ちゃんと原料として再利用しているのである。 ・食べ物から摂取したアミノ酸と体タンパク質を分解して生じたアミノ酸をあわせると、およそ一八〇~二〇〇グラムのタンパク質を一日に作り出している。 ・結局私たちは、分解したタンパク質と同じ量のタンパク質を作り出しながら、体重をはじめとした恒常性を維持しているのである。 「時計の遺伝子」 ・「体内時計」という言葉も知られるようになったが、この体内時計を管理するメカニズムとして、生物は様々な「時計の遺伝子」を持っているらしいことが最近どんどん発表されている。その数は一〇〇個程度もあるらしい。 時刻合わせの装置 ・私たちが海外に行って時差ボケになるのは、タンパク質合成サイクルの変調によるもので、市販されている時差ボケの薬には、このタンパク質を調整することで体内時計を調節しようとするものがある。 細胞の死 ・細胞にも当然のことながら死が訪れる。細胞の寿命自体はさまざまだが、細胞の死には二種類ある。ひとつはネクローシスであり、もうひとつがアポトーシスである。 ・高温や、毒物、栄養不足、細胞膜の障害など、外界からの強制的な力が加わることによって起こるのがネクローシスで、細胞の壊死とも言われる。 ・アポトーシスは生理的な条件下で、細胞自らが積極的に引き起こす細胞死である。 ・比喩的に言えば、ネクローシスがいわば事故死であるとすると、アポトーシスは細胞の自殺に対応する。 ・個体発生や自己反応性免疫担当細胞の除去、がんの自然治癒などで見られるプログラム細胞死もアポトーシスの一種である。 ・オタマジャクシの尾が消えるのはプログラム細胞死の例であるし、紅葉した葉っぱが落ちるのもアポトーシスである。 ・私たち哺乳類でも胎児期のある一定の期間は、指のあいだに水かき様の膜を持っている。進化の名残であろう。水かきは出生までには消失するが、これが消失するのも、水かき様の膜の細胞がアポトーシスによって、ある時期に正しく死ぬようにプログラムされているからである。 ・細胞の死といえども、生命の維持に必須の細胞死があり、その過程に、タンパク質の積極的な分解が関わっているのは興味深いことである。 ・タンパク質分解が細胞死につながる例としてのアポトーシスにおいても、個々の細胞の死を積極的に誘導することによって、個体としての生命活動を円滑に進めるという意味のあることが明らかになった。 ・すなわち、タンパク質の分解=死は、決して意味のない死ではなく、生命維持の一環としての死でもある。 第六章 タンパク質の品質管理――その破綻としての病態 リスク・マネージメント ・細胞の重要なシステムのひとつが「タンパク質製造システム」であるとすれば、小胞体はそのメインの製造工場にあたる。 ・細胞全体の作るタンパク質の実に三分の一は、小胞体で作られる。 工場の品質管理 ・製品の中に不良品が混じっていた場合、第一にとる手段は、ただちに生産ラインを止めることであろう。 ・第二段階として考えられるのは、直せるものはできるかぎり修理して、正常な機能と構造に戻してから出荷しようとすることではないだろうか。 ・どう修理しようもない不良品が溜まればどうするか。人間社会の工場なら廃棄処分。これが、第三の方策 ・工場閉鎖は最後の手段である。 細胞内の四段階の品質管理 ・細胞では見事にこの四段階の品質管理がおこなわれている。 ・生産現場での品質管理は、人間の脳が考え出した方法であるが、細胞の内部でも、これに比肩できるようなタンパク質品質管理機構の発達を見ることは感動的でさえある。 ・進化という生存戦略が、時間のうちに秘めた潜在的な適応能力の凄さを見せつけられる思いがする。 ・まずは生産ラインの停止。タンパク質の場合には、これは遺伝暗号をポリペプチドへと翻訳していく過程を止めることによってなされる。 ・次に不良品の修理・再生については、修理工であるシャペロンをまず緊急に誘導し、シャペロンが変性したタンパク質を作り直し、再生させようとする。 ・しかし元々の設計図に間違いがあった場合、誤った設計図から生まれた異常なタンパク質は、役に立たないばかりか、他の正常なタンパク質にまで被害を及ぼす可能性がある。 ・これはもう廃棄するしかない。分解である。 ・それでも異常タンパク質を処理できないとなった場合、そのままにしておくと隣近所にも迷惑がかかる。こうなれば仕方がない、細胞の場合には、それはアポトーシスである。アポトーシスは、細胞の自殺である。 品質管理の「時間差攻撃」 ・品質管理には四つの戦略、翻訳停止(生産ラインのストップ)、タンパク質の再生(修理)、分解(廃棄処分)、そして細胞の自殺(工場閉鎖)がある。 ・実はこの四つの反応は同時に起こるのではない。この四段階はこの順番に、少しずつずれて起こる。いわば「時間差攻撃」である。 神経変性疾患 ・身体の細胞はどんどん新陳代謝して一年後には九十数パーセントが入れ替わってしまうにもかかわらず、神経細胞はある年齢以降はほとんど増えることはない。 ・神経細胞にも幹細胞があることが明らかにされ、神経細胞の新生もあることが分かってきたが、大部分の神経細胞は活発な増殖をおこなうことなく死んでいく一方なのだ。 ・これは単に物忘れがひどくなるというだけではない。深刻な問題をはらんでいる。 ・何しろ神経細胞に何か変異が起こると、その細胞は変異を抱えたまま長期間生存し続けなければならず、重篤な神経変性疾患として症状が現れることになる。 ・神経変性疾患の代表的なものとしては、アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、などがある。 ・どれも原因は遺伝子、すなわちそこから作られるタンパク質にあり、神経細胞が死んでしまうという点で共通している。 あとがき ・DNAに書き込まれた遺伝情報の総体をゲノムと呼ぶ。 ・ヒトゲノムプロジェクトは二〇〇三年に完成した。三〇億という文字(塩基)によって書かれているヒトのすべての情報、親から子へ伝えられる遺伝情報のすべてが解明されたことになる。 ・タンパク質は遺伝子の情報をもとに作られるが、それではタンパク質についてもすべてわかったことになるのであろうか。答えは否である。 ・タンパク質はまことに個性豊かな存在である。アミノ酸配列の違いは、構造や機能の違いとなってあらわれ、表情も働きも千差万別と言わなければならない。 ・DNAがもっぱら暗号を複写したり、読み出したりしている静かな書斎派だとしたら、タンパク質は自分の体を提供して実際にさまざまの労働に従事している。 ・生命活動のあらゆる作業にタンパク質は必須である。細胞内のすべてのインフラや、タンパク質自身の生産や管理、さまざまな情報の受け渡しや制御と、生命活動においてタンパク質の関与しない部分は一つとして無いと言いきってもいいだろう。 ・タンパク質の一生という、きわめて普遍的で基礎的な研究が、それを推し進めていくと、BSEなどのプリオン病や、アルツハイマー病などを含むさまざまの神経変性疾患などの病態の研究につながる。 ―― 完 ―― |
|||||||||||||||||||||||||||