
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年09月20日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
72 |
17/09 |
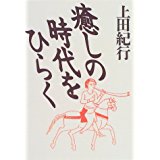 |
癒しの時代をひらく |
上田紀行 |
法蔵館 |
◎ |
序章 ―― 「癒し」ブームの中で 癒しと治療 ・「癒し」と「治療」とは重なり合う部分がありながらも、異なる意味合を持っている。 ・治療が、障害のある部分や機能の回復であるとすれば、癒しとは存在全体に関わる言葉であるということである。 ・治療とは、異常な状態になった身体の部位を正常に回復させる、異常になった身体機能を正常化するといった意味合いがある。そこには、病気でない状態が健康だという、二元論的な発想がある。 ・ところが、癒しにおいては、単に身体が正常に復することではなく、われわれが自分自身の存在のありかを見つけだしているか、それに満たされているかという時限こそが重要であるからだ。 ・十二指腸潰瘍は確かに、十二指腸という身体の部位に起こった異常であるわけだが、目に見える潰瘍という「病気」の向こう側には、目に見えない「病」がある。 ・表面に現れている現象としての病気は、目に見えない人生の病を因縁として持っているのである。それを、目に見える潰瘍だけを対症的に治すのでは、不十分なのではないか。 ・薬で潰瘍を治しても、状況は変わらず、患者は潰瘍を再発するか、他のより重い病気を併発しているかもしれない。 ・そうだとするならば、潰瘍にただ薬を与えて治してしまうことは、「治療」ではあっても「癒し」ではないのではないか。 ・単なる「治療」が「癒し」になるとは限らない。それとは反対に「治療」は失敗しても、「癒し」となることもある。 ・たとえば、末期の病状で治療が及ばず、たとえ亡くなることになっても、「癒された死」を迎えることもあり得る。 ・ホスピスの運動が目指すものは、この末期における「癒し」だろう。 ・それは、ひたすら病気を治療し、延命させることばかり試み、「癒し」を忘れてきた、これまでの医療現場への批判となっている。 ・「癒し」は、人間の本来持つ「自然治癒力」への着目でもある。 ・われわれの体には本来、治る力が備わっている。しかし、その力はこれまでの西洋医学ではほとんど注目されてこなかった。 ・西洋医学は攻撃的な医学であって、強い作用を持つ薬や手術などといった、「外からの」働きかけの方法を発達させてきた。 ・それは確かにたいへん効果的でもあったし、感染症などには劇的に効くが、その効果の大きさに惑わされる部分もあって、「内なる」治癒力を無視しがちだった。 ・実は抗生物質にしても、それらは菌の数と勢いを減らす薬であって、最終的に治癒をもたらすのは、体に備わった治癒力なのだが、表面上は薬が体を治したように見えるのだ。 ・感染症が主たる病気であった時代には西洋医学は大きな力を発揮したものの、成人病などの慢性病が主たるターゲットとなった現代においては、「外から」の治療だけでは不十分であることが明らかになってくる。 ・それらの慢性病は、不健全なライフスタイルやストレスによってもたらされており、「外から」の治療には限界があるのだ。 ・そこでは「内なる」治癒力を活性化させていくことこそが重要なのである。 ・そして、どんな環境やどんな心理状態が自然治癒力を活性化させるのかが問題になってくる。 ・心身医学や精神神経免疫学といった分野が注目されるようになり、それは医療社会学や医療人類学といった「文系」の学問とも結びついていく。 個人と社会を捉え直す ・登校を拒否している子供を単に復学させればそれで一件落着になるのかという議論もある。 ・学校自体が甦り、人間的な場になるという「改革」が、根源的な「癒し」には必要なのであって、単に一般に「正常」だと思われている状態への復帰が「癒し」とは限らないのである。 第Ⅰ章 多重人格という現象 虐待という記憶の封印 ・「幼少期の虐待」が多重人格の大きな要因となっているとの定説がある。 ・また虐待とはいっても、より間接的なものではあるが、子どもらしいケアを受けることができずに放っておかれたり、極端な貧困下で困窮していたりという事例も存在するし、悲惨な死を目撃するといった衝撃的な体験も多重人格の原因となり得る。 ・その意味では、多重人格障害はPTSD(心的外傷ストレス障害)の中でももっとも重いものと言えるだろう。 ・虐待がなぜ多重人格を生み出すのか。それは、その体験が幼い子供たちにはどうしようもなく耐えられないことだからだ。 ・一番自分を愛してくれるはずの親が自分を虐待する。体もずっと大きく、その人に見捨てられたら路頭に迷い、すべてを失ってしまうような「世界の要」の人間が自分を虐待するのである。そして子供たちはそれから逃げることはできない。 ・そのとき、「こんなひどい目にあっているのは私じゃない」「こんな目にあっているのは、ジェーンなのだ」といったように、現実の体験を別人格に負わせることになる。 ・本当の私は、ジェーンの後ろに退き、ジェーンがいじめられているのを背後から息を潜めて見ている。そうやって自我を分裂させ、虐待を他人格に負わせなければ、自分自身が崩壊してしまう。 ・人格の分裂とは、無力な子供たちが、あまりにむごい虐待から自分を防衛する、ぎりぎりのぎりぎりの生き残り戦略なのである。 ・多くの患者が「悪いのは親じゃない。私が悪いんだ」と信じ込んでいることである。 ・チャーター病院では、カウンセラーや医師との個人的な治療と並行して、学校の時間割のように集団での数多くのセッションがある。 ・それらのセッションの一つに「怒りのセッション」がある。 ・過去の怒りをかき立て、表面に出すセッションで、サンドバッグをバットで叩いたり、自分を虐待した人の顔を描いた黒板に粘土の球を投げつけたりするのだが、そこで現われてくる怒りの様相はすさまじい。泣き、叫び、全身の力をこめてバットで叩きまくる。そして「私は悪くない」とか「私のせいじゃない」とか絶叫する。 ・その壮絶さには息をのむが、それは逆に、いかに彼女たちがこれまで、あれだけひどいしうちに対してさえも怒ることができなかったか、ひどい虐待を受けながらも「私のせいでこうなっているのだ」「お父さんが私にこんなことをするのは、私がお父さんを喜ばせてあげられないからだ〉といったように、「自分が悪い」とかたくなに信じてきたかを物語っている。 ・筆舌に尽くしがたい虐待を受けながら、なおかつ自分を責めるという救いようのない心理構造と、多重人格とは表裏一体のものなのである。 ・しかし、怒りの表出は治療の出発点にすぎない。 ・「私の仁政は私のものだ」「私は悪くないんだ」という「私づくり」をしながら、彼女たちは自分自身の中にいる「私」たちを統合していかなければなない。それは大変苦痛な作業だ。 ・悲惨な記憶を封印するために分離した人格を統合するには、その記憶を一度蘇らせ、それを認めたくなかった人格の前にも明らかにしなければならない。幼少時に向かい合うことができなかった痛みに、今度は逃げずに正面からぶつかり合わなければならないのである。 ・さらに彼女たちの多くは、「見捨てられ恐怖」を抱いている。そんな虐待を受けても、親から愛されたい、親から見捨てられたくないという根源的な恐怖である。 「本当の自分」を取り戻すために ・多重人格障害という病いは、表面上はいかに奇妙に見えようとも、その根本は「愛と信頼」の病いだということだ。 ・一番自分を愛してくれるはずの人から虐待を受ける。それも幼少時に。その体験がもたらすのは、われわれにとって一番基本的な「世界への信頼」がまったく失われてしまうということだ。 ・それも、意識が始まる出発点から世界への信頼が欠如し、世界が暴力として立ち現れるということである。 ・物心がつくかつかないかのうちに虐待を受けた場合、自我の確立の前から世界はすでに失われている。 ・一度「基本的信頼感」を得た人は、その信頼感に満ちた時代のことを想い出して立ち直ることができる。 ・しかし、仁政にはじめから「基本的信頼感」が欠如している人はどうしたらいいのか。人生の始まりから、愛はなく、痛みのみが存在するのである。 ・無力な幼児に虐待が加えられたという状況の中で、彼女たちに一体何ができたというのだろう。その暴力を告発することもできず、彼女たちはもうひとりの人格を分裂させ、その人格に虐待を負わせて自分自身は世界から逃避することで、自分自身を痛みから遠ざけ、何とか生き残ろうとするのだ。 ・治療のために彼女たちは「世界はあなたを愛している」「自分は愛されるに足る存在だ」「世界には信頼関係もある」ということを繰り返し学んでいく。 ・仲間との、そしてセラピストとの信頼関係を確かめながら、しかしあるところまで信頼関係を回復する一方で、「絶対に信頼できるはずがない」「世界が私を愛するわけがない」という逆戻りと戦いながら、彼女たちは「本当の自分」を取り戻すために格闘する。 システムが引き起こす日本の虐待 ・日本の場合、「学校」や「教育」というシステムが「子供の虐待」を引き起こしていないかということだ。 ・体罰や心理的暴力はそれでもまだ見えやすい事例だが、それに加えて成績重視や、過剰な受験競争の中で「世界には愛と信頼などというものはない」という考えが、いつのまに子供たちに注入されてはいないだろうか。 ・世界への基本的信頼の欠如、それは私が大学で教えていても感じることだ。 ・他人の目を気にし、世界から何とか愛されようとして、本当にやりたいこともやらず、自分が何をやりたいのかもわからなくなっている若者たち。 ・そした、だからこそ「信頼」や「愛」を教えられ、「これが敵だ」と示されるとオウム真理教や統一教会の信者のように突っ走ってしまう。 ・「いじめ」も「オウム問題」も、子供たちを取り巻くシステムが広い意味では「虐待」のレベルに近づきつつあることを示しているようにぼくには思える。 第Ⅱ章 教組もまた洗脳される――マインドコントロールの構造―― 日常世界のマインドコントロール ・宗教はマインドコントロールだという言説が、繰り返し語られている。 ・それならばわれわれの日常生活ではマインドコントロールは行われていないのか。 多様な生き方や解釈の可能性を、ひとつの恣意的な型にはめ込んで、それのみが真理であり、ある行動規範のみが正当であると信じさせる構造が、マインドコントロールであるとすれば、われわれの日常世界にマインドコントロールが存在するのは、誰の目にも明らかだろう。 すべての信者は被害者か? ・僕は、「宗教はマインドコントロールだ」を連発し、「被害者の皆さん、目を覚ましてこちら側の世界に戻っていらっしゃい」と気色の悪い声で呼びかける論調が嫌いだ。 ・戻ってこいといっても、ある人たちは、こちら側の世界のマインドコントロールから逃れたくて、あちら側へと行ったのである。 ・確かに宗教の中にも強力なマインドコントロールがあるだろう。しかし、日常社会の構造を反省することなしに、あたかもこちら側が天国であるかのように装うのは欺瞞である。 ・また、そうした呼びかけが、相手が判断能力もない幼児であるかのように、かわいそうな被害者像という枠に信者を押し込もうとしているのは、呼びかける相手に失礼であるとともに、責任の所在も曖昧にしてしまう。 ・確かに強力なマインドコントロールで惑わされたということはあるだろう。騙された部分もあるかもしれない。しかし騙す騙されるはどんな判断にもつきまとうことであり、大の大人が自分の判断能力をもって決断したという側面も忘れられてはならない。 ・薬物や監禁といった方法が使用されている場合はともかくとして、すべての信者を被害者扱いすることはやめた方がいい。 ・マインドコントロールと聞くと、すぐに自分がコントロールされる側であると想定するのは、社会全体に蔓延する被害者意識のあらわれであり、自分自身もそれに加担しているという事実から目を背ける結果にしかならない。 ・現実はもっと複雑だ。マインドコントロールという言葉ひとつとっても、それが恐ろしく単純化され、 ‹宗教というマインドコントロール› ― ‹自由な日常› 、 ‹マインドコントロールを行う教組› ― ‹その犠牲者の信者› といった二元論的な陳腐化に陥るところにこそ、硬直した現代のマインドコントロールの構造があるというべきだろう。 第Ⅵ章 「愛と生と死」の癒し――「傷ついた私」をいかに癒すか―― 現代のアイデンティティー ・現代のアイデンティティーは、自分自身の内発的な感覚から構成されているのではなく、他者との比較から導き出される非常に相対的なものになっている。 ・内側からの生命感ではなく、自分に貼られたレッテルで人からも判断され、自分自身も判断する。 ・そしてそれらのレッテルの多くは相対的なものだ。 ・偏差値はこの程度、学歴ではこの程度、収入ではこの程度といった相対的な情報によって構成されるアイデンティティーがそこにはある。 ・しかし、内側から噴き上げてくるような生命の内発性が抑圧されているこのアイデンティティーのあり方からは、実感のある「私」は感じることができない。 ・また、自分自身が相対的な指標の合成であるとすると、私は他者と交換可能であるということになる。 ・現代日本社会はマニュアル化が進んでおり、とくに若者はマニュアルがないと行動できないといった自業自得ともいえる傾向を持つのでいっそうそれは強まる。 ・たとえば彼や彼女がエリートサラリーマンであったとしても、同じくらいの能力と学歴をもつ人と交換可能だ。 ・そしてそうした自己意識の構造が問題なのは、そうしたアイデンティティーのあり方では、自分自身の「かけがえのなさ」を感じることができないということである。 ・本当に「自分はたいしたことないから夢など持てない」と感じている学生は驚くほど多い。 ・そこには「ほんとうに自分のやりたいことをやったら、かならず叱られる」という被害者意識が見え隠れしてくる。 ・あるいは、「本当の自分を出したら、かならず嫌われる」という、本当の自分は絶対他者から認められないという確信である。 ・「自分は他者と交換可能なような相対的な存在で、本当の自分を出せばかならず嫌われ、本当にやりたいことをやったら必ず叱られる」というはてしなく低い自己イメージが蔓延している。 ・しかし、他の誰もがそうだからと納得し、自分は所詮たいしたものじゃないし、たかだかこんなものだと納得し、そしてそれでもけっこう遊んだりしていると楽しいし、といったところだろうか。 ・しかし、表面上の楽しさとは裏腹に、多くの若者は底知れない無力感を感じているし、自分とは何かが分からなくなっている。 ・そして、「癒し」という観点から見逃せないのは、そんな若者、いや若者だけではなく「自分が分からない」と悩む人たちが、同時に「自分は傷ついている」と感じていることである。 ―― 完 ―― |