
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年09月15日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
74 |
17/09 |
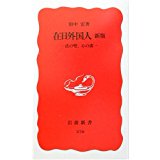 |
在日外国人 |
田中 宏 |
岩波新書 |
◎ |
Ⅳ 援護から除かれた戦争犠牲者 「外国人」の戦犯 ・植民地出身者の戦場における特徴的な仕事のひとつは、「俘虜監視員」であったといわれる。直截銃を持たせることへの不安が日本側にあったかもしれない。 Ⅵ 「黒船」となったインドシナ難民 ベトナム難民の衝撃 ・英紙『ガーディアン』曰く、 「日本人は “純粋な” もしくは無意識の人種差別主義者であり、彼らがこの国にも “人種問題” が存在すること、ないし他民族に対する彼らの態度に何かが欠けていることを認めない限り、事態の改善は望めない」と、指摘した。 Ⅷ 外国人労働者と日本 人種差別撤廃を提議 ・日本の近現代史を振り返れば、そこには送り出した人びとについて、また受け入れた人びとについて、充分すぎるほどの “歴史の教訓” が残されている。 超過滞在者は三〇万人 ・外国人労働者問題を考えるとき、日本ではもっぱら外国人の「就労」にのみ関心が注がれ、その対策にやっきになるが、誰が、なぜ、どのように「雇用」しているのかという、コインのもう一方の面が見失われている。 ・「就労」は外国人の “ひとり相撲” では成立せず、日本側の雇用があってはじめて成立するのである。 ・日本社会の高齢化、若年層の減少、勤労観の変化、アジアとの所得格差の拡大、どれひとつをとっても、すこぶる構造的な問題なのである。 資格外労働は男性が主流に ・「就労先の従業員数」のデータによると、日本人従業員は「なし」または「五人以下」を合わせると、全体の五六・六%を占めている。 ・さらに外国人従業員については、「自分のみ」または「五人以下」とするものの合計が、全体の七六・三%を占める。 ・いずれにしても、きわめて零細な事業所で就労していることがわかる。 ・言葉も不自由なら、風俗習慣も異なる外国人が、そう容易に職につける日本社会ではなかったはずなのに、これだけの外国人が就労しているのは、なぜかと問うてみる必要があろう。 ・建設作業員や工員が大きなシェアを占めていることは、日本における勤労観の変化( “3K労働” の忌避)、若年人口の減少などの反映であろう。 ・空港の新増設、リゾート開発、高層ビル建設は、いずれも土木建設の仕事である。また二四時間営業の店舗の展開も著しい。 ・身近なところでは、新聞配達の仕事もある。かつては、「新聞少年」が七割を占めていたが、一九九三年には二割に減少している。とくに東京では、外国人が一一三二人で、「新聞少年」の二九六人を大幅に上まわっているという。 ・いまや、日本は外国人労働者なしには成り立たない状況になりつつあるのではなかろうか。 【私見 : 就労に関するマスコミの偏向報道が大きな問題だと思う。メディアでは、ホワイトカラーの就職難について、リクルートスーツを着た学生の就職活動ばかりを報道しているが、一次産業、二次産業などの人手不足の分野には全く光を当てていない。だから今の若者は、アルバイトと本職探しを分けてしまって、そちらの方に就職しようとは考えない。しかし需要はあるので、仕方なしに外国人労働者を雇い入れざるを得なくなる。給料の差ばかりではなく、日本人自身の心のなかに職業差別があり、メディアがそれを補完している】 労働者としての権利 ・労働関係法令は、珍しく、差別禁止自由のひとつとして、「国籍」を明文で掲げている。 ・外国人労働者は、たとえそれが「資格外就労」であっても、これらの法令が適用されることはいうまでもない。 ・労働省は、労働基準局長、職業安定局長名で、全国の基準局長および知事あてに、「労働関係法令は、不法就労であると否とを問わず適用されるので厳正に対処すること」と通知したが、それが具体的に機能しているとは思えない。 ・なぜなら、その後段にある「資格外活動、不法残留等入管法違反に当たると思われる事実が認められた場合には、出入国管理行政機関にその旨情報提供すること」の部分に力点がおかれた感が否めないからである。 ・この点、外務省条約局法規課編『わが国における外国人の法的地位』は、「外国人の就職、均等待遇は適正な在留資格を得て在留する外国人に限られることはいうまでもない」と、こともなげに書いているが、それは明らかにこの労働省通達に反している。 ・リクルーターは、有料職業紹介を禁じている職業安定法三二条に違反していないか、 労働者派遣業法四条が認めていない業務に外国人が派遣されていることはないか、 ・さらに、職業安定法六三条で処罰の対象とされている「身体の自由拘束による労務提供、公衆道徳上有害業務への就労」にあたることはないか、 労働基準法五条の「強制労働の禁止」、同六条の「中間搾取の排除」などの規定は守られているのだろうか。 ・入管、警察当局による外国人労働者の取り締まりのみが先行し、こうした労働関係法令を活用して雇用主側にメスを入れ、外国人の権利を擁護することは後廻しにされてはいないだろうか。 ・出稼ぎ女性のなかには売春行為に追い込まれる者も多いといわれる。 ・日本も加入する「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」は、たとえば「売春を目的とする国際人身売買の被害者が、その本国への送還に関する措置を完了するまでの間、生活に困窮するときは、それらの者の一時的保護及び扶養のための適当な措置を講ずる」と定めているが、日本政府がそうした措置をとっているとは思えない。 ・進行する国際的な労働者の移動のなか、国連総会は一九九〇年一二月、「移民労働者権利保護条約」を採択し、事態に対処しようとしている。同条約は、 “非合法移民” をも、その保護の対象としている。 ・外国人労働者は「労働力」ではなく「人間」であるとよくいわれるが、はたしてそれが実感できる体制を日本は築きえているであろうか。 ・かつて、多くの移民を送り出し、国際社会に人種差別撤廃を訴えたみずからを想起し、いま増加しつつある外国人労働者を、かつて受け入れた朝鮮人の子孫と重ね合わせながら、日本社会を “ともに生きる社会” に変革することを、現実はすでに迫っているのである。 ―― 完 ―― |