
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年10月30日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
79 |
17/09 |
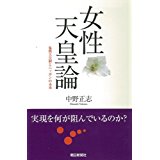 |
女性天皇論 |
中野正志 |
朝日新聞社 |
☆ |
序 新しい視座からの探求 ・天皇制を廃止したければ、ただ待っていればよい。 ・皇位継承者を男系男子に限定した今の皇室典範を変えなければ、後継者はいなくなってしまう可能性が大なのである。 ・戦後、天皇は「象徴」に変わったものの、国事のほか、憲法上は国事や、私事とのボーダーラインといえる公務、さらには私的な行事ではあるにしても祭事をこなさざるを得ない。仕事量は膨大だ。 ・次期皇太子には、幼少期から象徴となる特別な教育が必要とされる。 ・それらを考えてみれば、皇位の継承順位者を決めるには、悠長に構えて等いられなくなってきている。 ・戦後、国民主権のもとでの象徴天皇制に変わったわけだから、天皇制の「立枯れ」を待つのは、「主権」を持つ国民としては無責任としかいえない。 ・さらにいえば、護憲派は論理的に破綻するしかない運命に立つ。現行の憲法では、象徴天皇制に変わったものの、現行憲法でも第一章は天皇の規定に当てられているから、空文化した憲法を守るという矛盾に見舞われるからである。 ・とすれば、現実的な選択肢は二つしか残らないことになる。象徴天皇制を断念する道を選ぶのか、女性も結婚後も皇室に残す道を開いて象徴天皇制の存続を図っていくかである。 ・天皇制というシステムを掘り下げていく過程で、平成時代の天皇家の方々に同情せざるを得なくなっていった。 ・基本的人権の多くは奪われ、過剰ともいえる「皇室外交」や公務をおしつけられ、自由を抑圧されてきた現在の皇室の姿は、どこか変だ。 ・皇室の適応への努力で疲れ切り、体調を崩した雅子妃の「お疲れ」に触れて、「人格を否定するような動きがあった」などとする発言である。 ・私には、民間から嫁いだ美智子皇后や雅子妃を、次々に失語症や「お疲れ」に追い込んでいったのは、現行の象徴天皇制に内在されている矛盾から出たように感じられた。 ・近代の先端を疾走してきた方が、硬直したシステムとの間で「適応障害」に陥られたのは当然の帰結だと思われた。意外性は感じなかった。 ・感銘を受けたのは、皇太子の異例ともいえる発言だった。 ・まさか、皇太子から、「個」の尊厳と人格の自由についての問題提起があり、「忘れられた戦後の希望と理想を不意に思い出させ」られることになろうとは、予測してはいなかった。 ・国民主権の下での象徴天皇制とはどのようなシステムであるべきなのか。それを問い続けることは、主権者の義務といえる。 ・発言の自由を封じ込められている皇族の方々こそ、抜本的な議論を望まれているのではないか。 第一章 雅子妃「お疲れ」の深層 ・第二次大戦後、天皇を主権者とする大日本帝国憲法は改正され、国民主権に基づく日本国憲法が成立した。 ・天皇は、統治権の総攬者から、すべての国事行為は内閣の助言と承認に基づかねばならない存在へと変わった。 ・他方、皇室典範は、戦前の憲法と並ぶ「家法」から憲法の下位法に代わり、宗教色が省かれたり、庶子の皇位継承権は認められなくなったりはした。 ・だが、男系男子に限定された基本的な枠組みには変化がない。明治以来の男系男子による「万世一系説」が、そのまま温存された。 ・雅子妃の「お疲れ」問題の基点は、この「ねじれ」にあるように思われる。 3 逆転した「抑圧」の対象 ・天皇にも、皇太子にも、即位の辞退も退位も認められていない。精神的な重圧がかかっていることは間違いない。 5 「近代化」へと向かう西欧の王室 ・王位が男子限定だったスウェーデンでは、一九七九年、男女を問わず第一子を王位継承者にすると改めた。 ・オランダでは、八三年に王位継承に関する男子優先主義を廃止した。 ・男子しか王位につけなかったベルギーでは、九一年の憲法改正で男女別をなくし、独立以来の原則を変えた。 ・日本の皇室は、現代化からも取り残されたままだ。皇室典範という強い縛りがあるからである。 ・女性には、皇位継承権が認められていない。皇太子には、皇室離脱は許されてはいない。 ・憲法上から見ても、皇族は、基本的人権を定めた憲法第十一条や個人の尊重を唱える第十三条の保護規定の多くから実質的に除外されている。 6 現天皇夫妻の努力 ・憲法第一条では象徴天皇の地位について、「主権の存する日本国民の総意に基づく」と定めている。 ・だが、第二条は「皇位は、世襲のものであって」ともある。 ・他方、第十四条では、法の下での平等を唱えている。 ・また、第四十一条では、国会が「国権の最高機関」と規定されている。 ・つまり、すべての人たちが平等であらねばならないし、天皇の「地位」は国会が決めるはずなのに、天皇制は世襲に支えられている。論理的には整合していない。 ・象徴天皇制の成立は「『妥協』の所産」であったため、「『妥協』的な論理」にならざるを得なかった。 ・日本社会の現代化が急展開する中で、やがて象徴天皇制は、外と内の矛盾にさらされる縮命を帯びていたともいえる。 ・外の矛盾は何か。憲法上は元首ではないのに、海外では元首扱いされ、「皇室外交」を強いられてきたこと。 ・加えて、政治的な発言は許されてはいないのに、先の戦争による海外の犠牲者に対し、「お言葉」問題を通じて詫びる必要に迫られたことである。 ・憲法上は定義がされていない公務も増える一方である。 やっと皇室典範改正が政治課題に ・内なる矛盾とは何か。国民主権のもとでも、明治以来の男系男子による「万世一系説」が、戦後の皇室典範に温存されていることである。 ・「お世継ぎ」誕生を求める宮内庁と、その束縛から解放され、キャリアを国際親善に生かしたいという現代女性との格差。 ・制度上は、皇太子妃には、「お世継ぎ」誕生しか期待されてはいない。 ・雅子妃の悩みの背後には、定義があいまいなまま戦後温存されてきた象徴天皇制の矛盾が重くのしかかっているように思われる。 ・なぜ、女性天皇を認める道が険しいのか。 ・体制側が女帝問題を後回しにし続けてきたのは、なぜ天皇制なのか、という議論に至ることを避けたいから。 ・宮内庁の関係者は「女性天皇を論じることは、パンドラの箱を開けることになる。天皇とは何か、天皇制とは何かという根源的な問題にぶつかる」と指摘している。 第二章 矛盾を抱えてスタートした象徴天皇制 1 天皇に厳しかった国際世論 米上院では天皇の戦犯責任を追及 ・なぜ、昭和天皇は訴追を免れ、天皇制は天皇大権を剥奪されたものの、象徴天皇制として延命し得たのか。 四つのポイント ・ポイントの一となるのは、天皇とマッカーサーとの初回の会見の評価である。 ・ポイントの二となるのは、翌一九四六(昭和二十一)年の元日に出された天皇の「新日本建設に関する詔書」、通称「人間宣言」である。 象徴天皇制への地ならしへと結びつくこの詔書は、だれの主導権でどのような意図から発表されたのか。 ・ポイントの三は、四六年一月二十四日に行われたマッカーサーと幣原喜重郎首相との会見の内容である。 憲法第九条の起源となる戦争放棄規定の設定は、だれが発案したのか、議論は分かれてきた。 ・ポイントの四は、日本国憲法の「押し付け」説は成立するのかどうかである。 2 マッカーサーと天皇の不思議な意気投合 情報操作に使われた天皇の発言 ・なぜ、天皇の発言はまちまちに伝えられるようになったのか。 ・マッカーサーが情報操作をしていたとしか思われない。 ・当時、マッカーサーには、両面作戦が必要とされた。占領政策の遂行のため、絶大な貢献をなす天皇を、戦争責任を追及しようとする他の連合国から守るため戦犯から除外して、在位させねばならなかった。 ・そのために、対米開戦は、対外的には自らが開戦に反対したのに、潔く責任を認める高潔な人物としてアピールする必要があった。これが「表舞台」である。 ・そして、「裏部隊」では、来るべき東京裁判に備え、出廷に追いやられて天皇の戦争責任が問われた場合には、かばいきれなくなるのを避けるため、東条英機らの軍閥に抗しきれなかったと事前に釈明させておかねばならなかった。 ・天皇を出廷させてはならないと日本側にも覚悟させておく必要もあった。 昭和天皇の悩み ・大元帥であった天皇は、自らの戦争責任を明言すれば、訴追される可能性があった。 ・他方、天皇が戦争責任を免れようとするならば、東条ら旧指導者に「戦争責任があることを明言しなければならない」。 ・だが、彼らを名指しで非難すれば、「臣下」を公然と非難することになってしまい、「天皇と国民との間の精神的中体が断ち切られる可能性」があったのである。 ・二人の会談で重要なのは、二人ともジレンマを抱えていたが故に、意気投合したという事実ではないか。 ・この会談を機に、「マッカーサー司令部は、天皇擁護論の策源地と化した」。 ・マッカーサーの意向が天皇制の存置に固まったのはこの時期で、昭和天皇の人柄への信頼を基礎にして、天皇を占領統治に利用するしかないという現実的な判断を固めた。 3 いく通りかある「人間宣言」の解釈 米国主導が定説に ・主導したのは民間情報教育局(CIE)だが、内容については宮中グループが一部を換骨奪胎して発表したという説で、ほぼ固まったといえるだろう。 ・CIEの主導だという見方には、状況証拠が大きく左右している。 ・米国政府は占領政策のため、当面の天皇制利用についてはマッカーサーの判断にゆだねていたが、昭和天皇を戦犯にかけるかどうかについてはまだ揺れていた。 ・一九四五年十一月二十九日、米国統合参謀本部からマッカーサー宛に極秘文書が通達されている。 「裕仁は、戦争犯罪人として逮捕・裁判・処罰を免れてはいないというのが米国政府の態度である」 「(天皇の戦争責任についての)証拠の収集は、証拠そのもの、あるいはそのような証拠が収集されているという事実が発覚しないよう、厳重な秘密保持のもとに行なうことが望まれる」 ・こうした状況の中で、すでに昭和天皇の不訴追を決めていたマッカーサーを総司令官に抱くGHQは、猛烈な速度で動き出す。 ・まず第一弾は、十月十一日、幣原内閣に勧告した五大改革である。 ・ここでは、婦人参政権の付与、労働組合結成の奨励、教育の自由主義化、警察国家の廃止と人権を保護すべき司法制度の確立、独占的経済機構の民主化である。 ・続いて年末にかけて、軍国主義教育の禁止、財閥解体とその資産の凍結、皇室財産の凍結、農地改革などの指令が次々に発せられた。 ・CIEは十二月十五日、「神道指令」を発し、国家と神道の分離を要求し、公教育や公文書から神道の教義を排除した。 ・GHQは、天皇制の「聖」と「俗」を切り離し、「民主化された天皇」のイメージを米国や国際世論に訴える必要に迫られていた。 ・宣言を出すにあたって、GHQが自らの強制ではなく、すべてを側近で運ばせようとした意向がうかがえる。 母国に向けたマッカーサーの恫喝 ・アチソン駐日政治顧問は、「私は、仮にも日本を真に民主化しようとするのであれば、天皇制は消滅させなければならないという持論は変えていません」との見解を保ちながらも、「日本を統治し、諸改革を実行するため、引きつづき日本政府を利用しなければならず、したがって、天皇が最も有用であることは疑問の余地がありません」と述べている。 ・米国の政策を天皇制の維持だけではなく、昭和天皇の不訴追を決定づけさせたのは、一月二十五日、マッカーサーが、ドワイト・アイゼンハワー米国陸軍参謀総長に出した緊急電である。 ・マッカーサーは、「天皇が日本帝国の政治上の諸決定に関与したことを示す同人の正確な行動については、明白確実な証拠はなにも発見されていない」と報告した。 ・さらに、「天皇を告発するならば、日本国民の間に必ずや大騒乱を惹き起こし、その影響はどれほど過大視してもしすぎることはなかろう」と述べ、「おそらく共産主義的路線に沿った何らかの形の厳しい画一的管理を志向するようになるであろう」と警告した。 ・さらに、天皇制を排除した占領政策を進めるためには、「最小限にみても、おそらく一〇〇万の軍隊が必要となり、無制限にこれを維持しなければならないであろう。それのみならず、行政官を全面的に補充し、呼び寄せなければならないかもしれず、その規模は、おそらく数十万に達するであろう」と記述している。 ・米国政府は、表向きはGHQの独走をいさめてはいたが、四五年ごろには、昭和天皇の下での天皇制の温存へ傾いていたといえるのかも知れない。 4 だれが戦争放棄を唱えたのか 説得力ある二段階説 ・諸説の中で最も説得力があるのは、憲法学者・田中英夫による二段階説だろう。 ・幣原が戦争放棄を世界に宣言したいと述べ、その発言がマッカーサーを感激させ、後の憲法の骨格となる「マッカーサー三原則」へとつながっていったという解釈である。 板ばさみに見舞われていたマッカーサー ・当時、マッカーサーは一月十一日に国務・陸軍・海軍三省調整委員会(SWNCC)から送られてきた二二八文書「日本の統治制度の改正」に縛られていた。 ・この文書では、「日本における最終的政治形態は、日本国民が自由に表明した意思によって決定」されねばならないとして、GHQの強制による憲法改正を戒めていた。 ・他方で、前年の十二月二十七日に幕を閉じたモスクワでの外相会談では、十一ヵ国から成る連合国の対日管理機関として極東委員会が設置されることが決められ、一九四六年二月二十六日から始動することになっていた。 ・米国は、マッカーサーに「暫定指令」を発する権限を残してはいた。だが、憲法改正や管理制度の根本的な変革には、極東委員会の決定に従うと定められており、米、英、ソ連、中国には拒否権が与えられていた。 ・天皇制に対しては、ソ連だけではなく、オーストラリア、ニュージーランドも厳しい姿勢で臨むことが予想されていた。 ・当時のマッカーサーは米国政府の命令に復さざるを得なくなっているうえ、さらに極東委員会との戦いも余儀なくされつつあった。 ・もし極東委員会が正規に動き出せば、GHQによる改憲の権限は奪われることが必至の状況だった。 ・天皇制を温存しながら、軍国主義の復活を予防するための牙を抜き、国際世論をなだめる手段。その発見が、幣原発言に異様な感動を覚え、直後にマッカーサーに飛躍を決断させる最大の要因となった真の理由であるとみる。 5 押し付けられた新憲法? ・戦後、日本政府が最も衝撃を受けた瞬間は、一九四六年の二月十三日であるといわれている。 ・五日前にGHQに提出した政府の憲法問題調査委員会がまとめた「憲法改正要綱」に対する回答が出されるものだと考えていた。ところが、提示されたのは、密室の九日間で作成されたGHQ案だった。 マッカーサー三原則 ・第一項目は、天皇制から触れられていた。 ・「天皇は、国の最上位(元首)にある」「皇位の継承は世襲による」とあるが、「職務執行および権能行使」については、「憲法にのっとり、かつ憲法に規定された国民の基本的意思に応えるものとする」という内容である。 ・第二項目には戦争放棄、第三項目に封建制度の廃止が支持されていた。 ・この三原則に沿ったGHQ案を受け取った日本側の反応について、GHQ側の記録は次のように表現している。 「日本側の人々は、はっきりとぼう然たる表情を示した。特に吉田氏の顔は、驚愕と憂慮の色を示した。この時の全雰囲気は、劇的緊張に満ちていた」 ・日本政府は、十九日まで閣議を開けないほど混乱するが、二十一日のマッカーサーと幣原首相の会談を経て、翌日の閣議で受け入れを決めた。歴史の歯車は大きく回った。 甘かった日本政府の国際感覚 ・憲法「押し付け」説には、マッカーサーを絶対的な権限を持つ支配者と考えたり、敗戦後の日本政府がどれほど国際感覚に乏しかったか、という点での認識不足が横たわっている。 ・憲法の制定過程で、手続き的な面では「押し付け」があったことは認めざるを得ない。 ・だが、新憲法は、新しい国際感覚や理想主義、さらには明治憲法の痕跡も残された「モザイク模様」から成っており、単純な「押し付け」論はとても成立し得ない。 ・当時の日本は国際的には遮断されていた。厳しい国際環境について、総司令部と日本の認識の違いが大きかった。 ・当時の総司令部側の国際認識は間違っていたとはいえず、迫り来る危険についてのGHQ側の「警告」が、日本政府にとっては「脅迫」として映ったと描写している。 6 新憲法はモザイク模様 自衛権を認めていたGHQ ・一般に「押し付け論」を唱えている人たちの最大の根拠とされているのは、第九条である。 ・確かに当初のマッカーサー三原則では、全面的な非武装と戦争の放棄をうたっている。 ・だが、民政局次長のケーディスは、ただちに「自己の安全を保持するための手段としての戦争も」の部分を削った。その理由について、 「自衛権の放棄をうたった部分をカットした理由は、それが現実離れしていると思ったからです。どんな国でも、自分を守る権利があるからです」 「自衛権や自衛戦争の放棄は非現実的です」 と答えている。 第四章 女帝の世紀 3 三十六年間治世した女帝 異色な孝謙女帝 ・孝謙天皇は、女性では初の皇太子となり、若くして即位が約束された女帝である。 ・父は聖武天皇、母は藤原不比等の娘の光明皇后で、彼らの第一皇女として生まれた。 ・二十一歳で皇太子になったのは、光明皇后に男子誕生の希望はなくなり、聖武と別な妃との子・ 4 「女帝の世紀」は激動の連続 ・六世紀末から約一世紀にわたって、東アジアは戦争と政変の世紀となった。 ・国際的にみれば、六世紀以来、隋・唐の中国や、高句麗・百済・新羅の朝鮮半島での動乱に巻きこまれていた日本が、六六三年の ・国内的にみれば、三段階に分類できるだろう。 ・第一段階は、七世紀当初の推古朝にあたる。冠位十二階や憲法十七条の制定を通して、国家システムの組み換えが始められた。 ・第二段階では、六四五年の ・第三段階は、七世紀後半から八世紀初頭までの律令の制定期にあたる。六七二年の壬申の乱の後、のちの二官八省の原型となる官庁が設けられ、地方には ・国家権力の集中強化は、すでに推古朝から生き抜くための欠かせない条件として自覚されてはいた。 ・だが、律令制が本格的に導入され始めるのは、壬申の乱の後、天武朝になってからである。 5 孝謙天皇以降、性差が強くなった ・古代史学者、水谷千秋の論 「中国では王朝交替の歴史を繰り返してきたが、日本では天皇制というシステムが長続きしてきた理由の一つとして、生前譲位が挙げられる。その、譲位という手段を見つけ、天皇制の継続性を保障してきたのが女帝だ」 第六章 つくられた万世一系 1 新設された皇室祭祀 古き「法」の発明 ・「天皇」という名称そのものが再定義されたのも明治維新であった。 ・宇宙の最高神である天帝を意味する「天皇」という名称は、元来は道教の用語で、七世紀に採用されたというのが通説だ。 ・古来は「 ・外交でも、幕末までは「 神権的な権威性が天皇を軍人化 ・近代氏学者の鈴木正幸は、「男系継承を原則とするわが国の習慣のもとでは、女帝の次の天皇は、女帝の夫の家系の天皇となってしまい、『万世一系』でなくなってしまうことを恐れた」と解釈する。 ・「万世一系説」は次第に国家イデオロギーとして堅固な体裁を整えていく。 第七章 危機に立つ最古のシステム 1 改変された天皇制の定義 ・天皇制は、少なくとも二度、消滅の危機に見舞われている。武家政治にのみ込まれそうになった中世の南北朝時代のころ、そして連合国に命運を握られた終戦直後の時期である。それでも、滅びることはなかった。 唱えられた「神武創業」 ・明治維新では、「神武創業」が唱えられた。 ・大日本帝国憲法(明治憲法)では、天皇は国家元首とされ、「神聖にして侵すべからず」と定義された。 ・かつて朝廷内部で決められてきた皇位の継承が、国家によって成文化されるようになったのも、明治になってからである。 ・一八八九(明治二十二)年、明治憲法の公布と同時に、皇室典範が憲法と同格の皇室「家法」として制定された。 ・「皇室典範 ・典範の第一条では「大日本国皇位は祖宗の皇統にして男系の男子之を継承す」と定められた。 ・天皇の譲位については、生前の退位は否定された。 伝統と近代の巧妙な接着 ・二〇〇三年、憲法学者の奥平康弘によって注目すべき論文が発表された。 2 「天皇の内閣」か「内閣の天皇」か 皇位の安定性に周到な配慮 ・旧皇室典範には、西欧の君主国にはなく、日本独特の特徴となっている一つの大きな特徴がある。側室から生まれた嫡子ではない庶子にも継承権を認めていることである。 ・当時、伝統に基づく庶子側と西欧型の原理に立つ女帝制は相互排除的となっており、庶子の容認と女帝の否認は「裏腹の関係」にあった。 ・もともと皇室の伝統は、一夫一婦 ・江戸時代の百十五代桜町天皇から明治天皇に至るまでの連続八代の天皇の母は側室で、彼らは嫡子ではない。 ・奥平康弘曰く、 一八八〇年代までは、女性天皇の容認は可能性としてあり得た。だが、男系男子による万世一系の観念が膨らんでいく中で、女帝は排除されるようになっていく。 他方で、庶子はどうしても容認せざるを得ない事情があった。将来、皇位継承の行き詰まりが予想されたためである。 明治に唱えられた男系男子の万世一系は、女帝の排除が前提となっているだけではない。庶子の容認とも結びついている。 むしろ庶子の容認こそ、皇位の安定性の面から「万世一系説」を支える根拠となったのではないか、 との理解である。 5 怪しい「固有の伝統」説 親政か不親政かの対立軸 ・共産党は、二〇〇四年一月、党綱領を改定し、天皇制の廃止要求を削除した。 6 複雑に入り組んだ皇位継承の仕組み 疑わしい「血の正統性」 ・南北朝もさかのぼっていけば、 第八章 皇室典範改正試案と憲法の今後 2 三つの考え方 ・皇室典範はどのように見直されるべきなのか。 一つめは、皇族の血を引いた民間の男子をどこかの宮家が養子として迎える道、 二つめは、あくまで男子優先主義を貫き、次善の策として女性天皇を容認する道、 三つめは、直系による長子型を前提に男女別をなくす道、 である。 ―― 完 ―― |