
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年10月15日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
84 |
17/10 |
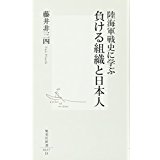 |
陸海軍戦史に学ぶ 負ける組織と日本人 |
藤井非三四 |
集英社新書 |
〇 |
はじめに ・いかなる惨劇でも、それを歴史の ・戦争での出来事を擁護したり、糾弾するばかりでは、本来そこから生まれる教訓というものが導き出せない。これは歴史なのだという冷静な思考があって初めて説得力のある教訓が得られる。 第五章 際限なき戦線の拡大 ◆「 ・日本が開国する前後、さかんに海防が論議されたが、そのポイントは対馬海峡と関門海峡の防衛にあった。 ・海峡をコントロールするためには、両岸を確保するか、少なくとも対岸の勢力が友好的でなければならない。 ・明治維新となり、すぐさま朝鮮との国交問題に手を付けたのは当然のことだった。 ・当時、朝鮮は鎖国しており、紆余曲折の末に一八七六(明治九)年に日朝修交条規が締結された。 ・これによって釜山が開港され、そこに領事裁判権を持つ外交公館が置かれ、大陸進出の第一歩が印された。 ・日本は朝鮮半島の保全を戦争目的に掲げ、明治三十七(一九〇四)年二月、日露戦争に踏み切る。 ・この勝利によって日本は、朝鮮半島における独占的な権利を得て、明治四十三(一九一〇)年八月に日韓併合となった。 ◆説得のしようがない感情論 ・満州事変が始まってから十万人もの戦死者を出してしまった以上、口が裂けても撤兵とはいえない。 ・そういっただけで陸軍の士気は地に墜ち、もはや軍隊といえないものになるのではないかと深刻に危惧した。 ・紛争解決の方策がないのに戦闘を続けること自体、おかしな話しだ。戦闘を続ければ、新たな英霊を生む。その英霊のために、下がれないとなれば講和とはならないで、いつまでも戦争を続けるという奇妙なことになる。 第六章 情報で負けたという神話 ◆探れなかった最高機密 ・ソ連の満州侵攻を読み切れなかった失態。 ・一九四五(昭和二十年)二月上旬のヤルタ会談の内容を、すべて察知できなかったことは仕方がない。 ・しかし、その二月からソ連軍の兵力東送が始まり、ソ連は四月五日に日ソ中立条約を延長しないことを通告してきた。 ・ここまで材料がそろえば、情報の有無にかかわらず、ソ連の対日戦参加は動かせないと見るのが普通だろう。 ・ところが日本の戦争指導部は、なんとそのソ連に和平の仲介を依頼したのだった。 ・首相だった鈴木貫太郎は、「スターリンさんは、どこか西郷翁に似ている」と語り、だから苦境に立つ日本を助けてくれると妄想した。 ―― 完 ―― |