
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年11月13日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
90 |
17/11 |
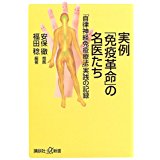 |
実例「免疫革命」の名医たち |
安保 徹・福田 稔 |
講談社+α新書 |
◎ |
第一章 「自律神経免疫療法」でなぜ難病が治るのか 木を見て森を見ない現代医療 ・現代医療では表面化している症状だけを病気と捉えているのです。 ・医師たちは表面的な症状を取去るためにだけ、一喜一憂しているのです。それでは症状は抑えられたとしても、最も本質的な病気の原因を取り除くことはできないでしょう。 ・病気を治療するためには、人間を一個の総体として捉える視点が可決です。 ・さまざまな病気の症状は、それだけが単独で現われているわけではありません。 ・人間は誰でも、心身にダメージを受けると全身の働きのバランスに乱れやゆがみがおこります。その乱れやゆがみは、その人の最も弱い部分に具体的な症状として現れます。それが病気の本質です。 ・当然ながら、どんな病気でも、まず全身の働きを整えることが治療の前提になるのです。 ・しかし、現代医療ではそうした病気の本質に目が向けられることはありません。そして、そのために現実に病気は慢性化し、さらに治癒が困難になっているのです。 ・「木を見て森を見ない」近視眼的な医療姿勢が、さまざまな難病の多発につながっているといってもいいでしょう。 手術では、がんは治らなかった ・人間の体はどんな場合でも、それ自体が一個の総体として働いていること、自律神経こそがその総体を支える枢要にほかならない。 体を総体として捉える自律神経免疫療法 ・すべての病気は自律神経の働きの乱れによって生じているのです。 ストレスが自律神経を狂わせる ・じっさいにストレスはどんな影響を与えるのでしょうか。 ・なかでもはっきりとした変化が現れるのが免疫系で、交感神経が優位になると、白血球の中で免疫機能の中心となるリンパ球が減少し、顆粒球が相対的に増加していきます。 ・そうして体の機能が落ち込み続けるなかで、がんをはじめとするさまざまな病気が起こっていくのです。 ・自律神経免疫療法は自律神経の働き、とくに副交感神経の働きを高めて、自律神経の働きを調整し、生体の働きを高めて、病期を治癒に向かわせようというものです。 ・治療の目的は症状の改善ではなく、その人の体の働きを高めていくことに置かれています。 ・そして、その目的が達成されることで、自然と症状も解消していくのです。 ・治療法はシンプルです。要は手足の爪の生えぎわや頭部にある副交感神経を刺激すればいいのです。 がんもアトピーも改善していく ・ステロイド剤もほかの薬と同じように、薬を使っているうちに、その人の体には薬剤耐性が生じてきます。 ・アトピー性皮膚炎という病気には、ステロイド剤による医原病としての性質もあります。 ・体内に腫瘍があっても、その腫瘍を上回るエネルギーを保ち続けていれば、がんの再発は抑えられます。 ・しかし、そのためにはやはり、治療を続けて副交感神経を優位に保ち続ける必要があるのです。 第二章 温めて体をかえる ――冷えの改善が「自律神経免疫療法」をより有効にする 個々の患者によって病態は異なっている ・同じ病気といっても、個々の患者さんによって病態はまったく違っている。 ・病態というのはさまざまな症状を引き起こしている体の内側の異常。 ・具体的な症状というのは、その病態がある部分に突出した形で現れている現象です。 ・当然ながら、外に現れる症状は同じように見えても、個々の患者さんによって体の内側の状態は、まったく違っているわけです。 ・本来の意味での治療は外に現れた症状を改善するだけでなく、より大きな視点で病態そのものを治していくべきものでしょう。 ・痛みなどの症状を抑えることはもちろん大切です。しかし、それだけに腐心しているようでは、いつまでたっても病気は治りません。それどころか病気が慢性化し、ますます治癒が困難になっていくでしょう。 ・同じ病気であっても、治療方法は個々の患者さんによって変わってくるのが当たり前ではないか。 ・画一的な治療では、やはり一人一人の患者さんに対応しきれないのではないでしょうか。 ・がんという病気は、そうした一人一人の患者さんによって、病態が違っている病気の典型といってもいいでしょう。 ・「自律神経免疫療法」 自律神経の働きとリンパ球を中心とする白血球の変化から、その人の免疫の状態を推しはかるこの治療理論は、実際の治療効果がきわ立っているだけでなく、患者さんの体の状態を理解し、治療の目標を設定するうえでもきわめて有効です。 ・たとえば、がんになって免疫力が低下している患者さんに、「免疫力を高めることが大切ですよ」といった抽象的な言葉を用いずに、「とりあえずリンパ球を二〇〇〇個にまで増やしましょう」と話すことができます。 ・そのことで患者さんは、より具体的な治療目標を持ち、意欲的に治療に向かうことができます。 ・具体的な目標が設定されているからこそ、患者さんたちも積極的に病気に向きあうことができるわけです。 ・そうした前向きな姿勢が、実際の治療効果にも直結している。 目からうろこだった「福田 ― 安保理論」 ・心臓の鼓動を初めとする内臓の働きなど、自律神経は私たちの体内で意識されることなく行われているすべての活動をコントロールしています。 ・その自律神経の働きが改善されれば、体全体の働きも変わります。そして、血液中ではリンパ球が増加し、免疫力が向上していくのです。 末期がん患者が一ヵ月後に飛び跳ねられるようになった ・現代医学では治療の方法がなくなった多くの患者さんの症状が自律神経免疫療法で改善されているのもまた事実なのです。 ・もっとも、治療効果を最大限に高めていくには、患者さん自身に前向きに病気に向きあってもらわなければなりません。 ・どんな病気でもその病気を治すのは患者さん自身です。 ・医師は、個々の患者さんが病気を治すのを手助けする存在にすぎません。 ・患者さん自身が本気で病気と向きあわなければ、治療の効果はあまり期待できないでしょう。 体を温めて免疫を強化する ・この治療法の原理を発見した安保徹教授は、血液一マイクロリットル中の白血球の中のリンパ球数が一八〇〇~二〇〇〇個の状態を二年間維持すれば、進行がんの多くは縮小していくと報告しています。 ・しかし、現実にはこのリンパ球の数を保ち続けることが非常に難しいのです。その点できわだった効果を持っているのが体を温めるという方法です。 ・「湯たんぽ」で体を温める方法 腹部や腰など体の中心部から温めてもらうことで自律神経の働きが副交感神経優位に変わり、リンパ球が増加していくのです。この方法の効果は絶大で、リンパ球の数は面白いように増えてきます。 ・当然ながら、この効果は一時的なもので、体が冷えれば、リンパ球の数も減少してしまいます。 ・ただ、長期的に体を温め続ければ、徐々に体質が変わってきて、あまり加熱しなくても、リンパ球が増えた状態を維持できるのも事実です。 毎晩九時には就寝する ・日々の生活の見直し 食事、睡眠、そしてストレス解消のための余暇活動……。 ・そうした日々の暮らしの見直しをはかり、体が本来求めている自然な生き方を実践することで、その人の自律神経のバランスが整えられます。そして、それが結果的にその人の免疫力の向上につながっていくのです。 ・睡眠のとり方ひとつで、自律神経の働きには大きな違いが出てきます。 ・夜は元来、副交感神経が優位に働く休息の時間です。ゆっくりと眠りにつくことで副交感神経が活発に働き、明日への活力が貯えられるのです。 ・規則正しい本来の自然なリズムに則った生活を送っていると、自律神経は、メリハリのきいた状態になります。 ・交感神経と副交感神経の働きのバランスが整えられ、免疫に限らず内臓の働きも活発になっていくのです。 ・食生活では、肉食をやめて魚と野菜中心の食事に切り替えること。 ・ある程度決まった時間に規則正しく食べること。 ・食べるときには、ゆっくりとよく噛むことが大切です。 ・食生活の改善では何を食べるか、も大切ですが、食べ方が大切です。口の中でかみ砕くことが大切です。十分に咀嚼することで栄養の吸収率が高まり、病気と戦うエネルギーが増加します。 ・「爪もみ」療法はいくらやっても、やりすぎということがありません。やればやるだけ効果が高まっていくのです。 自律神経免疫療法で再発予防 ・がんの再発に対する不安が、体にも影響を与えます。 ・精神的な不安は自律神経の働きを交感神経優位にし、体ばかりでなく、精神的にも緊張させるのです。 ・私が行っている自己治療の方法は、そのまま予防法としても適用されます。 体を温め、生活を改善し、爪もみを行います。 第三章 四種類のがんに高い効果 ――がん治療における「自律神経免疫療法」の有効性 ・ホリスティック医療というのは、西洋医療と東洋医療を融合させ、さらに心の側面も含めた全人的な医療を意味しています。 第五章 病気の連鎖を断ち切る ――免疫を高めてぜんそく、花粉症、アトピー性皮膚炎を治す 全体が理解できない専門医たち ・私たち人間は、体内にあるさまざまな臓器、器官が有機的につながりあって働くことによって、日々の健康を維持しています。 ・病気というのは、そうした体内の臓器や器官のつながりに異常が生じることによって起こっています。 ・とすれば、ある特定の臓器、器官にだけ目を向けているようであれば、病気の本質的な治療はおぼつかないように思えてならないのです。 ・ぜんそくや花粉症、さらにアトピー性皮膚炎などの病気は、病名だけを聞くとまったく違った病気のように思われるかもしれません。しかし、実のところは、これらは根っこの部分で深くつながりあっています。 ・花粉症やぜんそく、さらにアトピー性皮膚炎を治療するには、その根っこの部分を治していかなければならないのです。 口呼吸で異物が体内に侵入する ・花粉症やぜんそく、アトピー性皮膚炎に限らず、すべての病気は生活習慣に起因していると考えています。そして、そこには四つの大きな原因があります。 ・まず第一にあげられるのは口呼吸による弊害です。 ・口で呼吸している場合には、大気中に浮遊している有害物質が呼吸とともに体内に取り込まれることになるのです。 ・私たちの体内ではそうした有害物質は当然のこととして、異物として判断されます。 ・すると、そうした異物から生体を防御するために交感神経が緊張し、自律神経のバランスが乱れることになるのです。 ・第二の原因としてあげられるのは、冷たいもののとりすぎです。 ・体の冷えが自律神経を交感神経優位に傾けさせるのです。 ・また第三に、睡眠不足。眠っている間は体の働きを副交感神経が優位に支配して血管を拡張し、ゆったりとしたリズムで体内の臓器、器官を休めているのです。 ・睡眠時間が短くなると、体内の臓器や器官が休めないだけではありません。副交感神経の働く時間が相対的に減少し、結果的にその人の体は交感神経優位の状態に陥ってしまうのです。 ・その結果、体は疲労し、病気が起こりやすくなっていきます。 ・もうひとつ、食物をよく噛まないということも重要な原因です。 ・食物をよく噛まないということは、それだけ唾液の分泌が減少することを意味しています。 ・唾液には食物を消化する以外にも、たとえば脳の働きを活性化するなど、いくつもの重要な役割があります。 ・そのひとつに口腔内の乾燥を防ぐ働きも含まれます。 ・口腔内が乾燥すれば、口腔内の異物や雑菌は直接、口腔粘膜を攻撃します。 ・そして、その影響は胃や腸にも現れるのです。もちろん、その過程で自律神経にも影響が現れ、交感神経が優位に働き始めます。 対症療法に終始する現代医療 ・花粉症では、多くの場合消炎鎮痛剤による治療が行われます。 ・ステロイドをはじめとする薬剤は生体から見れば異物にほかなりません。その異物が体内に取り込まれると、当然のこととして交感神経が緊張して自律神経のバランスに乱れが生じることになるのです。 ・これらの病気はもともと交感神経の緊張に起因しています。とすれば、こうした対症療法は、長い目で見れば、症状の慢性化につながる危険も見逃すことはではないでしょう。 ・本質的な治療を行うのなら、逆に副交感神経の働きを活発化させる必要があるのはいうまでもありません。 ・私の場合は花粉症やぜんそくに関していえば、肺とつながっている口腔粘膜に影響を与えるために、手足の指の爪の生えぎわに加えて、もみあげのあたりの側頭部にも重点的に刺激を加えるようにしています。 ・この部分は口腔と直接的に繋がっています。そのために口腔を介して、呼吸機能の要である肺に刺激を与えることができるのです。 ・もちろん、こうした治療とともに病気の原因を排除することも大切です。 ・そのために私は、上記の4つの原因に加えて、喫煙やストレスを避けるようにもアドバイスしています。 ・一般的に花粉症の場合は、よほど重症でない限り、数ヵ月、自律神経免疫療法による治療と生活改善を行えば、症状ははっきり改善します。 ・やせ形の体型で、少し話すと、自己表現が苦手である、こうしたタイプはストレスをためやすく、それが原因で交感神経が優位に働く体質になりがちです。 病気の連鎖を断ち切る「自律神経免疫療法」 ・ぜんそくや花粉症を患っている人の多くは、ほかにも何らかの病気を抱えていることが少なくありません。 ・そして、そうした人たちに自律神経免疫療法を行うと、当初の治療目的だった病気はもちろん、それ以外のさらに深刻な病気も改善に向かっていきます。 ・これはとりもなおさず、人間の体内のさまざまな臓器や器官が互いにつながりあっていることを物語っているといえるでしょう。 ・そうした体内のつながりを担っている最も基本的なシステムが、自律神経だと私は考えています。 ・自律神経免疫療法で、さまざまな病気がよくなっていくのも、そのことによるものです。 ・同じことは、がんをはじめとする生命にかかわる難病にもあてはまります。 ・もちろんがんの治療には、抗がん剤や放射線などの現代医療が不可欠になる局面もあるでしょう。 ・しかし、それだけでは患者さんにとって、充分な効果が得られるとは考えにくいのも事実です。 ・現代医療に加えて、患者さん自身の体質を変えるためのアプローチも不可欠でしょう。 ・私は自律神経免疫療法はそうした新たな統合医療の切り札になる治療法だと確信しています。 第六章 体から心を治す ――「自律神経免疫療法」で、うつ病治療に取り組む 急増する心の病気 ・自律神経免疫療法の本質は、自律神経の働きのバランスを整えて、免疫を中心とした全身の働きを高めるところにあります。 ・そうすることで身体に現れていたさまざまな症状も自然と治っていくのです。 ・実は、最近になって急増傾向をみせている「心の病気」の代表的な存在であるうつ病も、この治療法によってよくなっていくのです。 ・腰痛、ひざ痛、肩こり……。 こうした慢性症状に対しては、現代医療はほとんど無力といってもいいでしょう。 ・消炎鎮痛剤、牽引や極超短波などを用いた温熱療法を行っても、効果はその場限りで長続きすることがありません。 ・自律神経免疫療法を用いれば、アトピー性皮膚炎やぜんそく、糖尿病などの難病も簡単に治ってしまいます。 ・リウマチが治るのなら、腰痛やひざ痛はもちろん、ほかの不定愁訴の症状も解消する。 体から心を治す ・うつ病というのは一種の「心の病気」で、仕事や家庭内の人間関係などによる深刻なストレスが、発病の原因として作用しています。 ・心と体は不可分の関係にあります。精神的なストレスを受けると、それが引きがねとなって、体の働きも急激に落ち込んでいくのです。 ・ストレスを受けると、まず脳の働きが自己の防衛に向かいます。 ・そのために自律神経の働きは交感神経優位になり、体内ではアドレナリンが過剰に分泌され、血管が収縮していくのです。 ・そうした体の内側の変化が、不眠、冷え、頭痛、疲れやすさなどの症状をもたらしています。 ・うつ病患者さんの大半が、リンパ球が血液一マイクロリットルあたり二〇〇〇個以下とかなり落ち込んでいることがわかります。 ・体の乱れは心の乱れ。 ・うつ病の場合にも、ほかの身体的な病気の場合と同様、患者さんの体の内側では自律神経のバランスがいびつになり、そうした身体の異常が無気力、倦怠感、イライラなどの心の症状をさらに増幅させているのです。 ・心と体の問題が互いに連動しあって、病気を悪化させているといっていいでしょう。 ・いずれにせよ自律神経の働き方の偏りが、身体の状態をいびつにさせ、うつ病をより深刻なものにしていることは間違いありません。 ・自律神経のバランスを整え、体の働きを活性化することで、身体的な側面はもちろん、精神的な症状もどんどん改善されていくのです。 ・つまり自律神経免疫療法には、身体的な側面から心の働きをも活発化させる効果があるのです。 うつ病患者に共通する冷え ・自律神経免疫療法によって体の働きを活性化させるとともに、その効果をより高めるための生活面でのアドバイス ①睡眠をしっかりとること(早寝早起き) ②食生活では野菜を多くとり、食事の際にはよく噛むこと。また肉食は少なめにすること(玄米菜食) ③体を冷やさないように厚手の下着、靴下を着用し、風呂はぬるめの湯にゆっくりと時間をかけてつかること ④できれば散歩など適度な運動を心がけること ⑤時間があれば、自律神経免疫療法による爪もみを行うこと ・実際、自律神経免疫療法と生活改善が両輪として機能することで、うつ病が改善されているのです。 ・うつ病に限りませんが、病気を患っている人のほとんどは、頭部にうっ血ポイントがあります。 ・そこに出血する程度の刺激を加えることで、血行が盛んになるとともに、全身の働きが活性化するのです。 心と体のもつれた糸を解きほぐす ・心と体は密接につながりあっています。体を治せば心も自然と軽やかになっていくのです。それがまた体に好影響をもたらしていくことになるのです。 ・うつ病は心と体が悪い連鎖でつながっているために、症状がどんどん悪化しているといえるでしょう。 ・人間の体の働きのなかで自律神経を見ると、そこには心と体の橋渡し役という役割が浮かびあがってきます。 ・ストレスを受けて体に異常が現れるのも、また逆に嬉しいことがあると体の働きが高まるのも、自律神経によって心と体が結ばれていることによるものです。 ・とすれば、自律神経を調整させる自律神経免疫療法は、うつ病治療には格好の治療法といえるのではないでしょうか。 第七章 心から体を治す ――心理療法と「自律神経免疫療法」の併用で難病に挑む 深く結びついている心と体 ・最近では、がん治療で、精神面での癒しが効果を及ぼすことがわかってきています。 ・どんな種類のものでも化学的に合成された薬剤は、人体にとっては異物以外の何ものでもありません。体内に入ると交感神経を刺激して、心身をより緊張させる原因になるのです。 第八章 やっかいな慢性病を治す ――腰痛、ひざ痛も「自律神経免疫療法」で治る 病院、治療院を転々とする慢性痛患者 ・がん、アトピー性皮膚炎、リウマチ……。 これらの病気の治療が難しいのは、病気の原因が解明されておらず、有効な治療法が確立されていないことにあります。 ・そのために現代医療では、これらの病気に対して、たとえば鎮痛剤の投与など、痛みをはじめとする表面に現れている症状をブロックするための局所治療に終始しています。 現代医療で慢性痛が治らないわけ ・人間の体を全体としてとらえる視点が欠落していることにあるようです。 ・私たち人間に限らず生物の体は、内臓、血管、筋肉、そして骨格とすべての器官が有機的につながりあって機能しています。 ・病気というのは表面的には、体のある一部分だけに問題が生じているように見えますが、実はそうした全身の機能が低下、衰弱することによって起こっているのです。 ・現代医療にはそうした大きな視野が欠落しているのです。 ・そのことは、医療界のタテ割り構造に端的に現れています。。現代医療では個々の病気は臓器別、あるいは器官別に区分して捉えられています。 自律神経の乱れも慢性痛に関係していた ・いくつもの症状を併発しているケースは専門的には、RSD(反射性交感神経ジストロフィー)と呼ばれています。 ・こうした患者さんは全身の働きをコントロールする自律神経のバランスが乱れているために、さまざまな症状が生じているのです。 二つの治療法の併用で難治性の慢性痛に挑む ・RSDの場合には、何か他の原因によって、自律神経のバランスが乱れ、そのために血行の低下などの全身症状が起こる結果、肩や腰にも痛みが起こっていると考えられるのです。 ・とすれば、乱れている自律神経のバランスを是正すればいいのです。 ・肩こりや腰痛などの慢性痛は交感神経が長時間、緊張を続けることによって起こっています。そうした自律神経のバランスを是正するために副交感神経が活発に働くように、末梢のターミナルを刺激すればいいのです。 解説 生き方を変えれば難病も克服できる ストレスが自律神経のバランスを乱す ・自然治癒力とは、免疫力という言葉とほぼ同義と考えていいでしょう。そして、その治癒力を高めるうえで大きな手助けとなるのが、自律神経免疫療法なのです。 小さな病気が、がんにつながっていく ・ストレスによる影響が最も強く現れているのが、がんという病気でしょう。 ・ストレスが体に蓄積を始めると、自律神経のバランスの乱れをはじめとして、体にはさまざまな異変が起こってきます。その結果、体には病気とはいえないような症状が現れてくるのです。 ・たとえば血管の異変を物語る動脈硬化もそのひとつですし、血糖値や血圧の上昇も同じような現象と考えられます。 ・ちょっとした病気が、がんを発病する過程で現れることもわかっています。その好例が歯槽膿漏と痔疾です。 ・ストレスを受けた後、自律神経のバランスの乱れに始まる体の異変は、その人の最も弱い部分に現れてきます。 ・一般的にいうと体内で最も外部からの刺激による影響を受けやすいのは、バリア機能の弱い粘膜器官です。 ・粘膜によって形成されている歯ぐきや肛門に異常が現れることが少なくないのです。 生き方を変えて、がんから生還する ・病気の予防や治療で何よりも大切なことは、それまでの暮らしを見直し、新たな生き方を構築していくことです。 ・このことはすべての病気に当てはまります。 ・とくにがんの場合は、より重要な意味を持っています。 ・がんが自然寛解した人たちの大半は、がんが見つかった後、それまでの生活を変え、しっかりとした目標を持って、敬虔で無理のない自然な生き方を実行しているのです。 ストレスを排除して自分の生き方を構築する ・病気を克服するには、まず、ストレス要因を排除したうえで、自分に最もふさわしい生き方を模索したうえで、食生活を改善し、適度な運動を生活に取り入れるようにすればいいのです。そこに自律神経免疫療法が加われば、自然に身体は変わってきます。 ―― 完 ―― |