
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年12月01日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
91 |
17/11 |
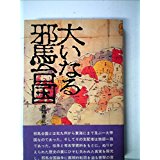 |
大いなる邪馬台国 |
鳥越憲三郎 |
講談社 |
◎ |
第三章 物部一族の東遷 一 河内に上陸した物部 始祖降臨地と物部本宗の本拠地 ・物部一族は、北九州の遠賀川流域に発祥し、そこから東遷して、河内に上陸した。 ・河内国にかなりの期間居住した後に、大和へ遷ったものとみてよかろう。 謎を秘める恩智神社 ・大和朝廷の発祥地は、三輪山の北にある巻向山の山麓である。 河内のどこに上陸したか ・堺という地名の起こりは、その漁村の北半分は摂津堺の北之荘、南半分は和泉堺の南之荘に属し、摂津・和泉の両国の境界にあったからである。現在は南北を合わせて堺市となっている。 第四章 邪馬台国の領域 三 九州の政治分析 筑紫国造の領域は筑後だけ ・景行天皇と神功皇后によって、九州各地は大和朝廷の征討をうけた。そして大和朝廷に服属したのであるが、それによって九州全土は、大和朝廷の新しい政治体制に組み替えられた。その一つが国造の設置である。 四 北九州にみる物部勢力 邪馬台国の広範な版図 ・北九州の西の果てから、遠く東海地方まで、物部一族の国造が分布していた。 ・国造制は後のものとはいえ、五世紀末までには設置されたもので、しかも地元の勢力ある豪族を任命した。 ・ところが物部一族の国造が、北九州から東海地方まで及んでいる事実は、邪馬台国の時代に、それらの地域まで遠く統轄していたことを物語るものだといえるであろう。 ・大和朝廷に先立って、弥生中期後半、おそくとも弥生後期の初頭に、つまり二世紀から三世紀初頭には、すでに九州から東海地方までも治下におさめた一大王国の存していたことを知らなければならない。 ・葛城王朝や大和朝廷に先立って、すでに全国といえるほどの地域を、制覇していた邪馬台国があったということ、このことは日本古代史を大きく塗り替えることになる重大な問題である。 ・これまでの一般の説では、邪馬台国も諸国連合政体の中の一つにしかすぎないものとみられていた。 ・そして魏志倭人伝の「共に一女子をたてて王と為す」という記事も誤解して、各国の協議により、巫女的な女王卑弥呼を擁立したのだと解されてきた。 ・それはまったくの見当違いである。東海地方から北九州におよぶ広範な地域を支配した王国であったことを知らねばならない。 第五章 魏志倭人伝 一 邪馬台国と投馬国 邪馬壹国論を排す ・『三国志』がつくられた三世紀末ごろは、実際「臺」と「壹」の字体は、一見したところでも異なっていて、書写を間違うことはありえない。 ・だが現存する『三国志』の刊本は、もっとも古いもので十二世紀中ごろ、 ・そして現存の字体である「臺」と「壹」になってから後に、それを誤写したものとみることもできるであろう。 邪馬臺国・臺與が正しい ・現存の『三国志』の刊本にみる「邪馬 音韻から考証する ・魏志倭人伝に「其の南に狗奴国あり。男子を王と為す。……女王に属せず」と記されているが、その狗奴国が古くは葛野と呼ばれた地で、後世の葛城地方であったことは確かなようである。 ・ということは、狗奴国が葛城王朝を指したものだといえるであろう。 ・しかも、邪馬台国とは不和の間柄で、いくたびか戦いを起こし、ついに三世紀末か四世紀初頭には、邪馬台国を滅亡に追い込んだ狗奴国、それは葛城王朝の歴史と完全に合致するのである。 投馬国は吉備国 ・吉備国が投馬国であったことは、海路日程からみてもわかる。京から大宰府までの三十日から、京から吉備までの十日を引けば、吉備から大宰府までが二十日となる。 ・それは博多湾から投馬国まで水行二十日、投馬国から邪馬台国まで水行十日という行程と符合する。 ・これまで投馬国の所在地のありかが、大和説・九州説の是非を決める鍵といわれてきた。しかし、日程からいっても、また吉備国の古名がタマノクニ・トモノクニの似音で呼ばれていたことからみても、投馬国は後の吉備国であり、邪馬台国は機内大和であることがわかる。 二 倭人の発祥地 南朝鮮の倭人たち ・魏志倭人伝に北九州の国名としてみえる末羅・伊都・奴・不弥の諸国は、邪馬台国の治下にあったが、それは二世紀末以降のこととみてよい。 ・それ以前にあっては、邪馬台国との政治的な絆をもつことなく、北九州の諸国は朝鮮や中国と交易し、外交的関係をもっていた。 ・つまり朝鮮や中国に知られていた倭人・倭国というものは、北九州を指していたのである。 ・民族移動として北九州へ上陸した倭人たちは、先住の縄文人を討ちつつ、日本列島を東へと居住地をひろめて行った。 ・他方その一派は、朝鮮へ向けてもひろがって行った。 ・ところが朝鮮の情勢は、北方からの漢民族や ・そのため南朝鮮に渡った倭人も、その地に小さな拠点をつくりえただけで、それ以上には進攻することができなかったのだと思う。それが狗奴韓国だとみてよい。 倭人と韓民族との差異 ・倭人には文身(入墨)する者がいると『三国志』にある。 ・文身の風習は南方地域の民族のもので、少なくとも倭人は、韓民族とは異なることが明らかである。 ・後の歴史で、日本が朝鮮から文化の影響を強く受け、また朝鮮からの渡来や帰化が多かったことに惑わされてはいけない。 ・そうした日韓の歴史よりも遠く古い倭人の渡来は、別の角度から見る必要がある。 倭人の源流を探る ・周時代から、倭人と称するものが揚子江の南にいて、朝貢していた事実があった。 ・日本稲は沖縄へは南下の経路で入ったが、それも十一世紀ごろとみてよい。 ・稲作のわが国への渡来経路については、三つの道が想定されている。 ・一つは南方から南西諸島、すなわち沖縄を経由した道、二は中国北部から朝鮮半島を経由した道、三は江南から東シナ海を経て九州に入った道とである。 ・一の道は、考古学的立場からみて誤っていることがわかる。 ・二は、経路の南満州や北朝鮮は畑作地帯で、水稲の行なわれた事実のない地域を越えて、わが国へ伝来したとみるのは無理である。 ・そこで必然的に江南地方からの渡来しか考えられないのである。 ・したがって江南、すなわち揚子江中・下流の南にひらけた広大な平野に、船と稲を持って上流から下った人たちが定住し、彼らが何かの理由で、海を越えて北九州に上陸したものと考えられる。 ・これが稲作をもたらした倭人で、彼らによって弥生時代がはじまるのである。 黒潮に乗って北上した ・弥生文化をもって日本へ渡来した紀元前三〇〇年前後の時季からみると、紀元前三三四年に揚子江下流域にいた越が滅亡して四散したとき、倭人もまた民族移動をしたものとみてよかろう。 ・倭人の故里が、湖南省を中心とした地域であったことは確かである。 ・中国人は、倭人が古く周時代に江南地域にいたことの知識をもっていた。 ・日本へ渡来した倭人の先住地を明確には指摘できないが、いずれにしても湖南省から出て、揚子江周辺の海岸線に住んでいた分派であったことは確かであろう。 ・航海技術に長じた彼らが稲作を持って、楚の迫害からのがれるために、黒潮に乗って北上した。 ・福岡市の板付遺跡は、北九州に上陸した彼らの足跡の一つを示すものであろう。 北九州の分布は人種の差による ・漢代に入貢したのは、博多湾岸の部族であった。それはまぎれもなく倭人であった。 ・そのために中国では、日本列島の住民を倭人と称し、後にはその国を倭国と称するようになる。 ・しかも南朝鮮へ渡って、拠点として ・その狗邪韓国の金海貝塚を中心として、弥生式土器に類する無文の土器が出土することから、多くの人はこれを弥生式土器の祖型と認め、弥生式文化とその民族が朝鮮から渡来したものと主張している。 ・彼らが南朝鮮へ移住したとき、いわゆる朝鮮の ・前期末と推定される金海貝塚の土器よりも、時代的に古いものが南朝鮮で発見されないかぎり、土器の上からでは、弥生式土器が朝鮮から渡来したとはいえないであろう。 ・倭人が南方海域から渡来し、さらに南朝鮮へも進攻しようとしたのと同じように、朝鮮の韓民族も漢民族や扶余族に追われて、北九州へのがれてきた。 ・彼らは倭人の根拠地となり、後に奴国となる地域を避けた西側、すなわち松浦半島を中心としてひろがった。それは佐賀県や長崎県である。 ・倭人の原住地は揚子江南域の湖南省であり、多分その分派の海岸線にいたものが、越の滅亡を契機にした越人の民族移動に合わせ、その地に居住していた倭人も遠く日本列島へ移動したものと考えられる。 ・北九州西部の末羅国や伊都国を建国したものたちには、韓民族の流れが濃い。 ・これら日本列島への渡来者の中で、博多湾岸の倭人がいちはやく奴国を建国した。そして彼らは西暦五七年には漢の武帝に朝貢し、倭国王としての印綬さえ受けた。 三 北九州倭国の滅亡 奴国の滅亡 ・西暦五七年に後漢の光武帝に使者を派遣し、印綬を授かって倭国王と認知された奴国が、いうまでもなくもっとも強大な国であった。 ・その奴国が二世紀末に滅亡する。その事件が『後漢書』にみえる倭国大乱であろう。 ・この内乱で奴国は滅び、邪馬台国が北九州へ勢力をのばし、北九州の諸国を支配下に入れることになる。 四 水行と陸行 倭人の報告によって里程を計算した ・魏志倭人伝に記されている「陸行」を、実際に魏使たちが歩いて経験した里程だとみることは、とんでもない見当違いである。 ・邪馬台国の研究者たちは、この点でいちように大きな誤ちをおかしたのである。 ・『三国志』魏志の編集にあたって、倭国の国々を地理的に説明するために、里程と方位によって示そうとした。 ・北九州の国々は陸続きで、互いに近接しているので、当然それは陸路で示された。しかしその里程や方位は、魏使たちの経験によったのではなく、倭人のもつ知識に負うものであった。 ・ところが投馬国や邪馬台国は「水行」で示されているが、これは遠く離れ過ぎて、倭人には方位や里程では答えられなかったからであろう。 ・そのためもあって、投馬国や邪馬台国の方位は、九〇度も偏差して「南」と記されている。それは当時の彼らの地理観が、日本列島を南北につらなるものと考えていたからである。 ・それならば北九州諸国間の方位も、九〇度の偏差があってよいのに、いちように四五度の偏差である。 ・こうした相違をもたらしたのは、北九州では倭人の見方によったためだと考えられる。 ・末羅国からだけでなく対馬・壱岐から末羅国を経て、伊都国・奴国・不弥国に至る方位がすべて一定した方位で記されている。 ・明らかに夏至のころの太陽を基準にして、方位を見ていたといえる。 ・それは魏使の見方というより、倭人が夏至のころの東を軸として、魏使の問いに対し、方位と行程を答えたのだとみてよかろう。 ・それにしても当時の倭人には、里程を計算する能力はなかったであろう。それを歩きもしない魏使たちが里数で示しているのは、倭人に聞いて、一日の行程を百里に計算したからだとみてよい。 ・陸行とあるのも魏使たちが歩いて経験したものではない。末羅国に上陸した記事があるのは、初めて倭国の本土に着いたための上陸である。 ・それから後の伊都国・奴国・不弥国も、彼らは訪問しなかったと思う。邪馬台国の治下にあったそれらの国へ、儀礼的訪問をする必要はなかったからである。 ・末羅の津から糸島海峡を抜け、博多湾岸にいた一大率の役所まで、船を直行させたものとみてよかろう。 ―― 完 ―― |