
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年11月29日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
92 |
17/11 |
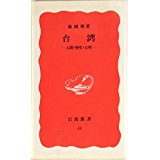 |
台湾 |
戴國煇 |
岩波新書 |
◎ |
Ⅱ 台湾史の原景 6 清朝後期の台湾新政 台湾における洋務運動の展開 ・洋務運動は、一般に第二次アヘン戦争(アロー戦争、一八五六 ― 六〇年)から甲午戦争(日清戦争、一八九四 ― 九五年)にいたる三十五年間において、清朝官僚のうちの買弁的傾向をもった実権派が推進した中国型富国強兵運動をいう。 Ⅲ 日本の植民地支配 1 台湾出兵と日清戦争 台湾出兵 ・台湾出兵は ・一八七一年(明治四年)十一月、宮古島の官民六十九名が年貢を納めるために那覇に赴いたものの、帰途台風にあって南台湾の八瑶湾、牡丹社の近くに漂着した。 ・五十四名がいくたの紆余曲折を経て牡丹社のパイワン族に殺害された。 ・単純な遭難事件が近代日本の最初の海外出兵を引き出した。 ・明治政府は「人民保護義務」を大義名分に、一八七四年五月に出兵し、台湾に上陸した。 ・出兵を利用しながら、対清交渉の結果、一八七四年十月三十一日、北京条約が締結された。 ・日本は多額の賠償金を清朝から獲得しただけでなく、琉球の日本への帰属を認めさせ琉球処分は国際関係の上でも「合法」的に実施したことを、清朝に結果的には承認させた。 ・明治政府が、発足早々の日本の軍事的名声と国家的権威を、東アジアの舞台で国際的に印象づけた歴史的意味は大きい。 日清戦争 ・台湾出兵から二十年後、朝鮮の権益をめぐって一八九四年八月から九五年三月にかけて日清戦争が戦われ、同年四月十七日、下関条約の締結によって戦争が終わった。 ・新興資本主義国日本が諸列強に伍して帝国主義国家になるためには、植民地の領有はぜがひでも必要だった。 4 植民地型開発と台湾住民の抵抗 日中戦争と台湾 ・武官総督制の復活にともない、本格的な皇民化運動が推進される。 ・一九三七年四月一日から、台湾人の母語使用が制限され、新聞の漢文欄も廃止された。 ・民衆の娯楽である伝統的演劇・音楽・武術なども上演と学習が禁止された。 ・さらには台湾人の魂の領域にまで警察権力が踏みこみ、伝統的宗教行事ならびに祭祀に対して制限と禁止を加えた。 ・代って日本語の強制使用、天照大神の奉祀と日本式姓名への改姓名運動が、終戦直前まで強行された。 ・そのいずれも、本格的侵略戦争に対応するために台湾人を日本の皇民に改造しようとした傲慢にして身勝手な営みにほかならなかった。 ―― 完 ―― |