
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年12月26日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
95 |
17/11 |
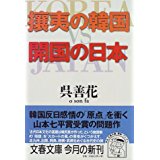 |
攘夷の韓国・開国の日本 |
呉善花 |
文春文庫 |
◎ |
第一章 飛鳥――古代渡来人たちの残像を訪ねて 2 渡来人と在日韓国・朝鮮人 「日本人=国を捨てた韓民族」 ・在日韓国・朝鮮人を、「国を捨て、言葉を捨て、民族を捨てた脱落者としての韓民族」とみなす感覚は、本国の韓国人の間にはかなり広くみられるものである。 ・自らの民族性を忘れ誇りを失い「日本人」になってしまうこと――そこに、本国の韓国人が在日韓国・朝鮮人を差別する根本の理由がある。 3 仏教文化にみる国際都市・飛鳥 飛鳥仏にみる日本の表情 ・飛鳥・奈良の偉大な古代文明を生み出したのは「韓半島人と韓半島文化」なのであって、「日本人と日本文化」なのではない、といったエゴイスティックな民族幻想が、韓国人の間には広くいきわたっている。 4 法隆寺と百済観音が物語る日本人の美意識 法隆寺伽藍の非対称の美 土着化による様式の変容 ・美術史家の上原和氏は、再建された法隆寺では「土着化による様式変容」がなされ、そのために伽藍配置もシンメトリーを崩した非対称のものに変更されたと理解されている。 ・こうした非対称の美は縄文土器、庭、いけ花などにも見られるもので、それは縄文時代から今日に至るまで続いてきた、日本土着の造形感覚ではないか、という考えを提出されている。まったくそのとおりではないかと思う。 ・非対称や歪形の表現は、日本人にとってはきわめて自然な美的表現の一つなのである。 ・幾何学的なバランスとはまた違ったバランスや調和をつくり出すために、いかにさまざまな創意・工夫が凝らされているかには、驚嘆すべきものがある。 ・日本人はことのほか文化や民族のルーツを探したがる傾向が強いが、もう少し「日本」をベースにした創案・自己創造という視点をもって自らの文化を見つめるべきではないかと思う。 百済観音に見るさすらいの女神の面影 ・百済観音像の百済観音というのは俗称で、百済から渡ったものではないかという江戸時代の文献にみられる推測からこれが通り名となった。 ・実際には観音像ではなく ・多くの韓国人にとっての百済観音像は、文字通り、百済から日本へ渡った仏像なのである。 ・しかし、百済観音像にみられる芸術的感性は、現代日本人のそれに通じるものが多々あるのに対して、現代韓国人のそれとはさまざまなところで食い違っていると思わざるを得ない。 ・もしこれが百済渡来の仏像だとしたら、現代韓国人はすでに百済的な伝統をすっかり失っているのである。 ・いまのところ、韓半島で発見された百済の仏像の中に、法隆寺の百済観音像に通じる美をたゆたわせたものを見いだすことができない。 ・私にはこの仏像が、日本の風土性から多大なる成分を吸い上げていまの形に生み出されたものと感じられる。 5 藤原京が象徴する日本的な支配のあり方 城郭なき都城 ・当時の韓半島の人びとにとって、城壁に囲まれない都はなんとも異様な光景と映ったに違いない。 ・そして、この異様な光景が物語るものにこそ、韓半島の人々は自らの地ではけっして手に入れることのできない、大きな魅力を感じたのである。 ・それはいうまでもなく「治安のよさ」であった。ここではもはや外敵の侵入に怯える必要もなく、侵入のために文化や人心の荒廃がもたらされることもない。 ・知識人にとっても技術者にとっても、自らの才能を存分に発揮し、代を後世につなげていくことのできる、天下泰平のユートピアがそこにあった。 日本王権に服属したという渡来人の始祖伝承 ・天皇家を頂点とする宗教的な系列支配の関係にあることが、日本における有力氏族の条件であり、またそのような祖先をもつことが氏族の誉れでもあった。 ・日本に韓半島からの渡来人たちの政治的・文化的な活躍があったことは確かだが、それは彼らが、すでに日本に完成されていた宗教的な支配の系列に入ることによってこそ可能なことだった。 ・だから、現代の韓国で言われているように、韓半島からの渡来人が日本の地で自ら思うままに文化を形づくったのではなく、宗教的な支配関係を通しての融合によって、文化的な寄与を果たしたのである。 ・日本に海外から高度な文化や技術が人とともに猛然と流れ込んだのも、日本にそのような特異な条件があったためではなかったのだろうか。 ・藤原京を始めとする城壁のない外部に開かれた都城は、まさしくそのように、外部へと開かれた当時の日本を象徴的に物語るものであった。 第二章 北九州――ヒメ神信仰の足跡を訪ねて 3 宇佐八幡の神 辛島氏と韓国のシャーマン ・清浄を好む日本の神道の性格は、執拗に穢れや罪を祓おうとする意識のあり方や神の到来を待つ物忌みの習俗などに、すぐれて現われていると言えるだろう。 5 済州島と鐘崎をつなぐさすらいの女神 三女神の婚姻地にて ・伝承によれば、済州島人をこの世に産み出した母は日本国の女王なのである。 ・古代、日本人と済州島人はそれほど遠い存在ではなかったと、そう思われてならない。 第三章 出雲――スサノオ信仰の故郷を訪ねて 5 スサノオからオオクニヌシへ 日本に独特な支配・被支配の構造 ・被支配者の信仰や神々を消し去り、自らの信仰や神々をもって支配するのではなく、吸収したりつないだり、あるいは交換したりしていけば、支配・被支配の区別がつかなくなってくる。 ・そうすると、確かに、自らが原始時代以来延々と続いたこの国の宗主だったと見えて来るし、また人々もそう信じるようになっていくに違いない。 ・たぶん日本は、そうすることによって国内の対立をなくし、平和な単一民族国家の形成を成功させたのである。 ・また、だからこそ、古い歴史を消し去ることなく書き留め、常に歴史をふりかえることのできる遺産を残したのである。 ・その点、韓国も中国も新たな政権によって過去の歴史を否定したり、また消し去ろうとする傾向が強い。それは近年の政治にもよく現れているように思う。 ・歴史的には、スサノオからオオクニヌシに至ってさすらいの時代が終わる。そして太陽女神アマテラスの子孫である天皇の支配がはじまり、渡来人も現地人も区別なく日本化されていく時代になるのである。 ・渡来人にとっては、オオクニヌシの国譲りの神話が象徴しているように、現地人との間に互いの神の威力をもって奉仕し合う関係が生まれることによって、さすらいに終止符が打たれるのである。 ・それを現代的に言えば、地域に溶け込んで生きる、ということだと思う。 第四章 相模・武蔵――高麗若光の伝承を訪ねて 1 相模湾への上陸 黒潮の流れに乗って ・似た者どうしでありながら日本人と韓国人には正反対ともいえるほどの違いが多々みられる。それを押し詰めてみれば、結局は、日本人がより南方的要素を色濃く、韓国人がより北方的要素を色濃く残してきたところに行きつくのではないだろうか。 2 大磯の高句麗人 高麗山頂の案内板 ・大磯の高麗山にある案内板 「奈良時代のころ高句麗は唐・新羅に滅ぼされ、日本に難を逃れた人も多くその中に高句麗王族のひとり 「高麗から高来へ」の謎 ・高句麗人たちは新天地を求めてこの国へ海を越え渡って来たのだ。 ・そして日本に帰化し、日本人としてこの国に開拓の足跡をしるした。彼らは自ら日本人となったのである。 ・戦争をしてこの地を奪ったのでもなく、暴力的に割り込んだのでもない。そんな必要もなく、日本人が彼らを積極的に迎え入れ、優遇された者たちがいかに多かったかは『日本書記』をざっと読むだけで誰にでもわかることだ。 ・日本では新たな移住者は専従者の祀る神(土地の神)を排除して自分たちがもって来た神を祀ろうとはしなかった。 ・出雲でも大和でも、後従者は土地の神の守護を受けることを望み、専従者は後従者からもってきた神を崇めた。 ・それは支配、被支配の関係にあっても同じことだった。 ・そうした日本の精神文化の独特な構造に目をやらないと、高麗の神とか高麗王とかは、渡来人集団としか結びつかなくなってしまう。 ・武蔵国高麗郡(現在の入間市の一部)の南に調布市・狛江市があるが、この一帯の古墳群も高句麗系のもので、六世紀のものと見られている。 ・また、狛江は明らかに高麗を意味する地名である。ということから、高句麗人の関東移入は、高句麗が滅亡した六六八年以前、つまり高麗若光より一〇〇年も前からあったという推測も行われている。 ・このように高句麗人は古くから、大磯から北武蔵の高麗郷までの関東平野の大きな部分を開拓していったとされるのである。 ・だが、それは必ずしもこの地域が高句麗人の土地だったことを意味しないと私は思う。 ・高句麗人の足跡が残っているのはその通りだとしても、彼らがずっと高句麗人であり続けたわけではなく、高句麗の言葉を話し続け、かたくなに高句麗の生活様式を守り続けたわけでもない。日本化して日本人になっていったのである。 ・つまり、高句麗人がこの地域を征服したのではなく、融合して高句麗文化でも土着文化でもない日本文化を作り上げていったはずなのである。 ・少なくとも韓半島的な匂いの漂う人名、地名、社寺名、遺跡などをピンポイント式に拾ってつなぎ合わせて理解してしまうことは危険だ。 ・そのやり方をとれば、恐らく関東全域に、いや日本全土に韓半島からの渡来人の足跡で繋がれたネットワークができ上がってしまうに違いない。 ・そして、関東には韓半島からの渡来人しかいなかったような錯覚を抱かせてしまうに違いない。 ・しかし実は、そのような錯覚を抱かせてしまうところに、日本の精神文化の独特な構造がある、と私は思うのである。 ・目に見えることに飛びつくよりも、その見えにくい構造を解きあかすことから、先になされなくてはならないのではないだろうか。 3 高麗若光の後裔 戦乱の韓半島を逃れて ・高麗若光らの渡来以後、八世紀から九世紀の初頭にかけても、少なからず新羅人や唐人の渡来・帰化があったが、九世紀半ばころからしだいに帰化を受けつけないようになっていった。 ・紀元前後の時代からおよそ一〇〇〇年間に渡って続けられた渡来の歴史が閉じられたのである。 ・韓半島から日本への渡来を促進した最大の原因はなんなのだろうか。 ・他の何よりも、韓半島における絶え間ない戦乱・動乱・政乱の歴史をあげるべきである。 ・韓国人は「われわれは日本に文化を教えて上げた」というのなら、同時に「われわれは日本にたくさんの同胞を引き受けてもらった」というべきなのだ。 ・韓半島から日本への渡来の流れの中で、亡命者・難民の流れは太いものであった。 ・韓半島はいったい、この一〇〇〇年間でどれだけの亡命者・難民を生み出し日本へ流出させたのか。どれだけの人材を切り捨て、どれだけの文化を灰燼に帰していったのだろうか。 ・もちろんそれは、巨大な漢帝国と北方遊牧民の脅威をまともに被るしかなかった、半島という地勢が生み出した悲劇には違いない。 ・ただ、その背後には常世の国への憧れをもった人々の住む日本列島があったのである。 ・この偉大なる器としての日本列島がなければ、この半島はいったいどうなっていたのだろうか。 ・日韓交流の歴史の大半は、実にこの激しく展開された一〇〇〇年間の歴史に集約されている。 ・以後の一〇〇〇年間の歴史とは比較にならない、濃密な文化的・人的な交流関係があったのである。 4 流され王とさすらい人の神 マレビトの座 ・渡来の神は日本の神となり、土着して地域の神として祀られるのである。 ・同時に、渡来人も土着して元からいた日本人と融合し、両者の区別はほとんどなくなるのである。 ・だから渡来人の神でも渡来人が祀り続けた神でもない、 ・伝承はそれが事実かどうかでみるべきものではなく、どのような人々の心が投影されているかでみるべきものだと思う。 ・日本ではどの地域でも客神を祀っている。外来の客神を迎える伝承をもっている。 ・ ・同じように、各地にある新羅川、百済野、高麗山、韓国岳などの地名も、渡来人が故国に因んで名づけた可能性があると同時に、日本人がその外来信仰から名づけた可能性もある。 ・日本では客人をマレビトと呼んで歓待し、村の家々の囲炉裏の周りには、客人が来た時に座ってもらう「マレビトの座」が常に用意されていたという。 ・これは単なる社会的な関係を示す問題ではなく、日本人の精神性そのものを表していると感じる。 ・近代に入っても、居間よりも応接間を優先する考えが長い間残っていたと聞いている。 ・日本の精神文化はいたる所に「マレビトの座」を用意し、いつでもマレビトを迎えられる用意をもって生きてきた。 「在日」の古代と現在 ・外国人に対する差別や区別や排他性はどこの国でもあることだ。 ・私には、日本人の韓国・朝鮮人差別が諸外国よりもいっそうひどうものとはとうたい思えない。 ・「ひどい」と感じる人々が多いのは、何よりもそれが戦前の植民地支配に結びついて「特殊に肥大化」したイメージをもたらすからだ。 ・高麗神社も新羅神社も百済神社も、渡来人が自らの神として延々と祀り続けたから残ったのではない。 ・日本人が、日本に渡来し日本に土着した神として尊重し祀り続けたからこそ残ったのである。 ・そのように祀られた「流された王」や外来の神を、渡来人たちはやがて自らの故国の神や先祖に重ねて共に祀るようになっていった。そこに両者の信仰が習合して一つになった。 ・戦前の日本民族優位主義に立った日本の朝鮮政策が日韓の和合をけっしてもたらさなかったように、戦後の韓民族優位主義に立った韓国の反日教育や歴史理解もまた、日韓の和合をもたらすことはあり得ない。 ・したがって、政治的・民族的な優位性のモチーフを背景に潜ませた「日本文化のルーツ=朝鮮」説の展開が、日韓の文化的・人的な交流に優位な役割を果たすことなどあるわけがない。 ・古代日本列島の渡来人たちがたどった心の足跡は、諸民族の融合というグローバルなテーマを喚起させてくれる未来の物語でもある。 文庫版へのあとがき ・有田の陶山神社には、日本で最初に磁器を焼いた朝鮮陶工 ・その参平が亡くなった一六五五年の翌年、有田の人々が伊万里から八幡神社を ・このはっきりとした歴史的な事実は、渡来人や渡来神を神社に祀ったのは、渡来人というよりは主に日本人自身だったのではないか、という本書の考え方を大きく支えてくれるものと思える。 ・また有田を中心とする陶磁器の発展は、外来の文化・技術を採り入れ、それを自家薬籠中のものとして育みつつ「本家」を遥かに超えた世界性を獲得した。古代日本文化にもそのような展開のあったことを力強く感じさせてくれる。 ・縄文文化と弥生文化の混合が日本文化のベースとなり、「縄魂弥才」をもって日本人は文化を切り開いてきたという。 ・私の思うところ、日本文化の独特な味わいとその魅力は、ことごとくこのベースからやって来ている。おそらく、多くの渡来人たちはそこに吸引されて帰化し、やがて日本の風景に溶け込むように土着していったのだろう。 一九九九年七月一日 解説 呉善花さんのこと 渡辺昇一 ・韓国ではすごい古代日本史観が巾をきかせているらしい。 ・例えば奈良時代の原住民(古代日本人)は人口の四パーセントに満たず、奈良は韓民族の地そのものだったと言うのだ。 ・こんな古代日本史を書いているのが崔在錫という高麗大学教授だと言うのだが、呉さんはこういう史観を空想だとして一蹴する。 ・そしてこういう「空想」を呉さんは考古学の発見なども採用して木っ端微塵にしてしまう。 ・稲作はすでに縄文人の時代から行なわれたことが実証されているのに、韓半島では日本の弥生時代に相当する時期の水田跡など一切発見されていないそうである。 ・呉さんの本は、今の韓国で学問の名で通用している恐るべき無知にもとづく空想を打ち ・呉さんの論法は学問的な証拠をあげていると共に、健全な常識に合っているところが嬉しい。 ・呉さんの繊細鋭利な洞察力は「飛鳥仏の表情」に及ぶ。 ・大陸系・半島系の建築物や彫像は、その基本が左右対称のシンメトリーに美の基礎を置いている。しかし飛鳥仏はそのシンメトリーを微妙に崩すことをわざとやっている。 ・この左右非対称は日本的な美的感覚であると呉さんは断定する。 ・この製作者は帰化人の三世、つまり在日三世である。日本に来て三代にもなると感性が日本的になるのは当然であるとする。 ・呉さんが在日を知っていて、在日三代目は感受性や芸術趣味などにおいて決して半島の韓国人でないことをよく知っている。 ・呉さんをソウル大学が客員教授として招聘する日がこない限り、コリア人の日本研究は幼児性を脱し得ないだろう。 ―― 完 ―― |