
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年12月30日 土曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
96 |
17/11 |
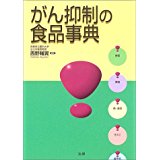 |
がん抑制の食品事典 |
西野輔翼 |
法研 |
◎ |
第1章 がん抑制の野菜類 アブラナ科の野菜 (わさび、ブロッコリー、大根) ・切ったり、すりおろしたときの独特の刺激のある辛味とにおい。この辛味とにおいの成分に、発がん抑制効果があり、中でもわさびには特に強力な抑制物質が含まれている。 Column ・炭水化物、たんぱく質、脂肪、ビタミン、ミネラルに食物繊維を加えた六大必須栄養素は、人間が生きていくのに欠かせません。 ・しかし、遺伝子レベルで考えたとき、健康維持・増進に欠かせないもう一つの大事な栄養素があるといわれています。それが第七の必須栄養素「核酸」です。 ・核酸は細胞の核内に存在するDNA(デオキシリボ核酸)と細胞内の内と側にあるRNA(リボ核酸)の2種類からなる物質です。 かぼちゃ、にんじん ・α‐カロテン、β‐カロテンの発がん抑制効果 ①細胞膜や遺伝子を傷つける活性酸素の作用を抑える(抗酸化作用) ②がん細胞の細胞分裂のサイクルを止める ③ある種のがん遺伝子の発現を抑制し、一方、がん抑制遺伝子の発現を高める ④細胞のがん化を進めるリン脂質の代謝を抑制する ⑤マクロファージ(大食細胞)、白血球の一種のT細胞、ナチュラルキラー細胞を活性化する トマト、オレンジ、にんじん ・トマトに含まれるリコピンには、β‐カロテンの約2倍というとても強い抗酸化作用がある。 ・トマト料理を週に10回以上食べる人は、食べない人と比べて、焼く45%もがんになる危険性が減っていたという報告がある。 野菜(さつま芋、グリーンアスパラガスほか) ・さつま芋やグリーンアスパラガスなどの身近な野菜は、生体内でがんを抑制する化学物質を生産しており、私たちが日常的にそれらを食べることでがんの発生を防ぐことができます。 野菜スープ(にんじん、大根、菜の花、ビタミン菜、にらなど) ・野菜に含まれる発がん抑制物質は、熱せられて初めて細胞の外に溶け出します。その効果は、生野菜の10~100倍と高いことが分かりました。 ・日光をたくさん浴びた露地野菜の旬の野菜は、抗酸化物質やフリーラジカルの中和物質が豊富と言えます。 さつま芋 ・さつま芋に含まれる “さつま芋・ファイバー(食物繊維)” には、食べた発がん物質や腸がんの原因とされる胆汁からの老廃物を体外へ除去し、がん細胞の発生を抑える効果が期待される。 第2章 がん抑制の穀類、豆類 大豆 ・大豆胚軸(※)に大豆本体よりも優れた発がん抑制作用があることが分かりました。主な有効成分は、大豆胚軸中のイソフラボンです。 (※)胚軸 … 種子植物の幼植物(または胚)で、子葉と根の間の部分。もやしは主にこの部分を食べる。 そば ・「そば」には、抗酸化物質のポリフェノールが豊富に含まれていて、がんを抑制する働きがあります。 第3章 がん抑制の果実類 かんきつ類 ・温州みかんなどのかんきつ類に含まれるβ‐クリプトキサンチンに強力ながん抑制効果があります。 Column ・発がんのメカニズム(発がんの2段階説) 1 イニシエーション【始動】がんを発生させる物質(イニシエーター)がDNAと結合し遺伝子に障害を引き起こし、正常な細胞をがん初期化細胞(潜在的腫瘍細胞)に変えてしまう過程。がんはまだ眠っている状態でがんとはいえない。 2 プロモーション【促進】がんを増殖する物質(プロモーター)が初期化細胞をくり返し刺激し増殖を促して腫瘍細胞にしてしまう過程。 この二つの過程のどちらか、または同時に抑制すれば発がんを止めたり遅らせることができると考えられています。 バナナ ・バナナには体内の免疫力を強める効果があり、しかも黒い斑点のあるものほど良い。 ・私たちの体内に異物が侵入すると、白血球などが働き出し、身を守ろうとします。こうした免疫力を高めれば、病気にかかりにくい体をつくることができるわけです。 りんご ・りんごに含まれるアップルペクチンが、発がん物質の活性酸素を非常に効率良く消却するとともに排せつを促すのです。 ・大腸には100種類以上もの細菌が繁殖しており、乳酸菌(善玉菌)と大腸菌やウェルシュ菌(悪玉菌)が勢力争いをしているような状態と考えてよいでしょう。この2つの勢力のバランスを大きく左右しているのが、毎日の食事です。 ・乳酸菌は食物繊維などの糖質を、大腸菌は肉などの食べカスが含まれるたんぱく質をそれぞれ好物にしています。 ・つまり、肉類を摂り過ぎれば腸内に悪玉菌がはびこり、逆に、食物繊維を豊富に摂ればビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌が増え、悪玉菌が繁殖しにくい状況がつくられるのです。 ・食物繊維は、消化されないので栄養にはなりませんが、そのまま大腸に流れて便の量を増やし、それが大腸を刺激して排せつを高めます。排せつが早まるということは、発がん物質を吸収する危険性がそれだけ少なくなります。 ・特に水溶性食物繊維であるペクチンは、大腸の粘膜を保護し、大腸菌を抑える強力な静菌作用があります。 レモン ・焼き魚にレモン汁をしぼると、発がん物質は大幅に減少する。 ・(※)フリーラジカルが注目されるのは、いろいろな臓器の病気や発がんに重大な役割を果たし、動脈硬化などの成人病の原因になっているとともに、老化を進める因子の一つとも考えられているからです。 ・焼いた魚の焼け焦げている部分には過酸化ラジカルというフリーラジカル化合物が多くある。 (※)フリーラジカル : ふつう、物質の分子構造の中で電子は2個ずつのペアをつくって結合し、安定した状態にある。しかし化学反応の途中などで結合する相手を持たない電子が現れることがあり、この状態になっている物質のことをフリーラジカルという。 パパイヤ ・解毒酵素の活性が最も高い果物がパパイヤである。 ・発がん物質が体内に入るとまず肝臓に運ばれますが、そこで遺伝子に突然変異をもたらすような形に代謝され、活性化されます。 ・しかし、活性化されたままだと遺伝子が傷つくので、私たちの体はもともとその活性化された発がん物質を無毒化するための酵素を持っています。 ・それでもがん細胞が発生するのは、いちどに対応できないほどの有害物質が入ってきたり、抵抗力が衰えていて無毒化できない場合です。 ・ですから、発がんの危険性を回避するために、ふだんから解毒酵素の活性を高めておけば、それだけ多くの発がん物質を無毒化することができることになります。 ベリー類 ・アントシアニンを多く含むベリー類は、がんや心臓病の原因になる活性酸素などのフリーラジカルの働きを抑える抗酸化性が高いことが明らかになっています。 第4章 がん抑制のきのこ類 まいたけ ・まいたけの抽出物である「多糖体」の成分が、世界各国でがんの治療に使われ始めています。その物質は「マイタケD-フラクション(MD-Fraction)」と呼ばれます。 ・サルノコシカケ科やキコブタケ科のキノコ類、ヤマビコホンシメジやしいたけ、まつたけなどの食用きのこにも抗腫瘍作用がある。 ・とりわけしいたけからの抽出物質は「レンチナン」という名前の免疫賦活剤として、国内で薬として認可されています。 ・これらの薬用効果は、きのこの(※1)子実体に含まれる「β-グルカン」という化学物質にあるのですが、これは「(※2)多糖体」の一種です。 ・「MD-フラクション」は化学的には「たんぱく・多糖体複合体(ペプチドグルカン)」と呼ばれています。 (※1)子実体 : 菌類において胞子がつくられる部分が集り、かたまり状になったもの。きのこはこの典型。 (※2)多糖体 : 分子レベルでは、糖がつながり合って高分子状態になった化合物。 ・体内で、がん細胞の破壊や増殖防止に役立っているのは、マクロファージ、T細胞、NK細胞などと呼ばれる免疫細胞です。 ・MD-フラクションの働き ❶ マクロファージ、T細胞、NK細胞を直接活性化させる ❷ ❶のような、がん細胞を攻撃する細胞の機能が発揮されやすいようサポートするサイトカインの分泌を促進する ・MD-フラクションは、がん細胞を直接攻撃するのではなく、がんになって低下した免疫機能を回復することにより、がん細胞を殺す作用を持つことを明らかにしています。 ・MD-フラクションは「β-グルカン」という多糖体の一種ですが、もともとβ-グルカン自体には抗腫瘍効果がありません。 ・MD-フラクションが、がんの移植によって体内で起動しはじめている免疫機能をさらに活性化させる。 ・MD-フラクション投与によって主要な細胞性免疫担当細胞が活性化され、増殖を始めたがん細胞の成長を抑えることが確認できました。 ・MD-フラクションの効果 Ⅰ. がん細胞の増殖を抑制する Ⅱ. がんの転移を抑制する Ⅲ. 発がんの抑制 Ⅳ. 抗がん剤(化学療法剤)との併用で、より強力にがんを退縮させる ・がん以外にも高血圧、肝炎、糖尿病、高脂血症、便秘症、肥満症、アレルギー、エイズなどの改善に関与する新たな成分が確認されています。 えのきたけ ・長野県全県のえのきたけ栽培家庭を対象とした疫学調査で、えのきたけ栽培家庭ではがん死亡率が低いことが確認されました。 ・また、風邪は免疫状態の善しあしを判断する目安となりますが、がんをも含む「万病のもと」といわれる風もひきにくくなることが認められたのです。 ・えのきたけは食品中の発がん危険因子を打ち消すだけでなく、逆に防御因子に変えることが分かりました。 ぶなしめじ ・ぶなしめじの抽出成分には、免疫機能を高める活性や(※)抗酸化性(ラジカルを捕捉する=それ自身が酸化することで物質の参加を防ぐ)があります。 (※)抗酸化性 : それ自身が酸化することでほかの物質の酸化を防ぐことをいう。生体内には抗酸化性を持った物質が存在するが、老化が進むにつれ血漿の抗酸化性が低下し、血中に酸化した脂質(過酸化脂質)が増加する。こうした作用で動脈硬化や糖尿病などが生じるともいわれている。 なめこ ・食用きのこは免疫機能を高めて、がんをやっつけるだけでなく、食物繊維が豊富なので、いろいろ優れた生理活性があります。 ・キノコ類が血液をサラサラにしてくれる作用があります。 しいたけ ・しいたけ中の多糖体は、「レンチナン」という薬品名で、がんの治療薬として使われています。 ・その作用メカニズムは、体に備わっている免疫機能を高め、それによってがん細胞の活動を抑制しようとするものです。 第5章 がん抑制の海産物 鮭、えび、かに ・がんは、細胞に何らかのダメージが加わってDNAが傷つき、突然変異で増殖し、悪性化したものです。その発生プロセスの中でDNAの傷を増やしたり、増殖を助けたりする悪役が「活性酸素」です。 ・鮭やえび、かにに含まれる「アスタキサンチン」にも強い抗酸化作用がある。 ・その抗酸化作用は活性酸素の中でも毒性の強い一重項酸素に効果が高く、β-カロテンの数倍もの効果があることも分かったのです。 海藻類(ひじき、わかめ、昆布、海苔) ・ひじきやわかめ、昆布、海苔などの黒っぽい成分であるフコキサンチンががん予防の分野で注目されています。 ・フコキサンチンはがん細胞を殺すのではなく、その活動を抑えると考えられています。 ・ナチュラルキラー細胞(NK細胞) 骨髄で作られる大型のリンパ球で、血液中を巡回するリンパ球群の約15%を占める。活性化されたNK細胞の中には核があり、その周りの細胞質に多くの果粒を蓄えている。体内に細菌やがん細胞などの異物を発見すると、ほかの免疫細胞よりも早く異物へたどり着き、それらと結合して、貯えていた果粒で攻撃・破壊する。 ・海草から抽出したフコイダインがナチュラルキラー細胞を活性化したというデータがあり、免疫力を高めると推測されているのです。 ・また、細胞や動物での実験の結果から、フコイダインにはがん細胞を自然死させる力があるようだ。 青背の魚 ・日本人の食生活が西欧化したことで魚をあまり食べなくなり、それと歩調を合わせるように大腸がんが増えてきた。 ・人間の体の中には、がん細胞などの異物が入ってくると、異物を攻撃して体を病気にしないように働く機能があります。この攻撃する細胞は白血球の仲間でマクロファージ(大食細胞)と言います。 ・がんが発生するのは、マクロファージよりがん細胞が強過ぎて、がん細胞の増殖・転移を許してしまうからです。 海藻(海苔、日高昆布、ほそめ昆布、なが昆布、利尻昆布、わかめなど) ・昆布、わかめ、あらめ、ひじきなどの褐藻類の発がん抑制成分としては、硫酸多糖(フコイダン)が知られています。 ・がん細胞の遺伝子がフコイダンによって分断され、自滅(アポトーシス)を促すというのです。また、β-カロテンと同様に免疫増強作用もあります。 さんま ・魚の脂肪は高度不飽和脂肪酸の(※1)DHA(ドコサヘキサエン酸)や、(※2)EPA(エイコサペンタエン酸)という特異的な脂肪酸で構成されています。 ・さんまに含まれるDHA、EPAが発がんを抑制するのは、がんになりかかった前がん状態の細胞が、がん細胞になるのを防ぐ、つまり発がんプロモーション(がんの促進)を阻害すると考えられるからです。 (※1)DHA : 脳の活性化や血液の流れをスムーズにし、アレルギーを好転させるなどの働きがある。 (※2)EPA : 心筋梗塞や脳梗塞のような血管系の病気予防に大きな効果が期待できる。悪玉コレステロールを減らす効果も注目されている。 第6章 がん抑制の香辛料、調味料 ごま ・がんや動脈硬化などの発生には、活性酸素による体内の酸化が深く関係しています。その活性酸素を除去してくれる食品がごまです。 ・ごまにはセサミノールのほかにも、さらに抗酸化作用を発揮する「セサミン」という物質が含まれています。実験によって、セサミンは肝臓に入ってからその効果を示すことが明らかになっています。 ・また、「抗酸化ビタミン」と呼ばれるビタミンEも豊富に含まれており、セサミノールなどゴマリグナン類との相乗作用で、より強い効果が期待できるのです。 ・さらに、大腸がんの予防効果が報告されているオレイン酸も多く含まれ、ごまの脂質の、実に40%を占めています。 ・ほかにも注目すべき栄養素として、微量ミネラルの一つであるセレンがあります。セレンはβ-カロテンやビタミンC・Eとともに、抗酸化に欠かせない酵素の働きを助け、がんや動脈硬化の予防に重要な働きをします。 スパイス&ハーブ (赤しそ、オレガノ、バジル、セージ、ペパーミント、わさび、フェンネル、純人参粉) 第7章 がん抑制のお茶類 緑茶 ・茶カテキンが、 ◉発がん物質に直接的に働きかけ、その作用をなくす。 ◉発がん物質による細胞の突然変異を防ぐ。また、突然変異を起こした細胞を修復し、正常細胞に戻す。 ◉細胞ががん化の方向へ向かうのを抑える。 など、がん化のあらゆるステージで抑制作用を示すことが分かっています。 ・茶カテキンの作用には「抗ピロリ菌作用」があります。 ・現在行われている抗生物質によるピロリ菌除去療法では、耐性菌(その抗生物質が効かない菌)の出現が心配されています。茶カテキンなら、耐性菌や副作用の心配もないので、新たな胃潰瘍対策や胃がん予防法として期待されています。 ・茶カテキンは、がん抑制効果のほか、血中コレステロール低下作用、腸内細菌のバランスを良くする作用、ダイエット効果(糖分の分解吸収阻害および脂質の乳化吸収抑制作用)などを持つことが明らかにされています。 ・黄紀茶の抽出物とその成分が、抗酸化作用、活性酸素消去作用、過酸化脂質生成抑制作用、がん予防作用(皮膚がん、肺がん、肝がん)などを示す。 ・発がんプロモーション イニシエーション、プロモーションと呼ばれる2つの過程を経由する発がん2段階説が広く認められています。正常細胞から潜在的腫瘍細胞に変化する段階をイニシエーション、さらに潜在的腫瘍細胞から腫瘍細胞へと進む過程をプロモーションと呼びます。現在、がん予防はこのプロモーションの段階で抑制することが重要とされています。 第8章 がん抑制の飲みもの、その他 ビール ・ビールにもがん抑制物質がのあることがつきとめられました。 ◉グリシンベタイン ◉シュードウリジン(核酸化合物の一種) 赤ワイン ・ぶどうには、渋味のもとであるタンニンやカテキン、赤紫色組成成分のアントシアニン、抗カビ活性作用に優れたリスベラトロールなど、豊富なポリフェノールが含まれています。 ・果実のパルプや果汁部分には少ないのですが、果皮や種子に多く含まれているため、果皮や種子ごと発酵させる赤ワインは、特に大量のポリフェノールを含んでいます。 ・血小板凝集抑制作用 血小板はけがをしたときなどに凝集して、出血を止める働きをする血液中の成分。この血小板の作用が不用意に起こると、血液が固まって動脈を詰まらせる血栓症を引き起こします。血栓が脳や心臓の動脈にできると、脳梗塞や心筋梗塞などの原因になりますが、赤ワインのポリフェノールには、血管の中で血液を固まりにくくして、血栓ができるのを防ぐ働きがあります。 梅酒 ・梅酒に含まれる程度のリオニレシノールでも、細胞やDNAを傷つけるフリーラジカル(遊離基)や活性酸素(生物体や細胞に特有のストレス反応を起こさせる化学物質)といった、細胞の老化とがん化に関係する物質の残存率を大きく減らすことが確かめられました。 ―― 完 ―― |