
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年01月15日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
1 |
18/01 |
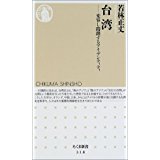 |
台湾 |
若林正丈 |
ちくま新書 |
◎ |
第1章 「海のアジア」と「陸のアジア」を往還する島 ――東アジア史の「気圧の谷」と台湾 ✝「四大族群」と多重族群社会 ・現在の台湾では、「エスニック・グループ」に相当する言葉として「 ・民主化以後、台湾社会の文化的多様性を直視しようという主張が台頭し、この言葉を使って台湾社会の「四大族群」という言い方がなされるようになった。 ・四つの族群とは、「原住民」(先住民族)、「 ・「四 ・「四大」というのは、この言い方が台湾社会における文化的多様性の相互尊重をうたう、台湾住民のナショナル・アイデンティティについての理念を下敷きにしているからであろう。 第2章 「海のアジア」への再編入 ――清末開港と日本の植民地統治 ✝日本の植民地支配 ・日本軍の占領行動は、当初激しい抵抗に直面した。 ・一八九五年、日清戦争の結果割譲された台湾の統治は、平地の漢族居住地域では、土着勢力のゲリラ的反乱を制圧するのに一九〇二年までかかった(この間日本側統計に現れた台湾側戦死者約三二〇〇〇人)。 ・山地先住民族地域(「蕃地」)に対しては、一九一〇年からいわゆる「蕃地討伐五箇年事業(約二二〇〇名の戦死傷者を出して、先住民から約一八〇〇〇丁の銃器を押収)を敢行した。 第3章 「中華民国」がやって来た ――二・二八事件と中国内戦 ✝戦後東アジア国際秩序の再編の中で ・一九四五年から四九年までのわずか四年間が、台湾が中国大陸と同じ政治的境域内にあった期間であった。 ・この間、中華民国が二度台湾にやって来た。一度目は、台湾をその一部とする中華民国として、二度目は、事実上台湾のみを支配する「中華民国」として。 ・一度目で、台湾は中華民国の一省、台湾省として編入された。台湾住民の多くは、これを「祖国復帰」として歓迎した。 ・しかし、二度目はそうはいかなかった。「祖国復帰」まもなくの四七年には二・二八事件が発生していた。 ・二・二八事件は、今も台湾と中国をともに苦しめる、戦前からの台湾住民と中国ナショナリズムとの不協和の歴史的根源となった。 ・さらには、中国内戦があった。共産党と国民党の内戦は、結局四九年に共産党が勝利して中国大陸に中華人民共和国を打ち立て、中華民国政府(国府)と国民党は台湾に逃れた。 ・これが、二度目にやって来た「中華民国」である。 ・そして、五〇年朝鮮戦争が勃発すると、アメリカは朝鮮半島に大量派兵すると同時に台湾海峡で第七艦隊の常時パトロールを開始し、国府支援も再開、以後台湾海峡を隔てた中華人民共和国と「中華民国」の対峙が固定化することとなった。 ・アメリカの庇護下で国民党政権は、共産党との内戦の態勢を堅持したまま国家を再編し台湾統治の体制を固めた。 ・中国内戦と東西冷戦とが台湾海峡で結びついたのである。 ✝「本島人」から「本省人」へ ・「光復」=中国語で自民族の土地・人民を取り戻すこと。 ✝「犬が去って豚が来た」 ・苛酷だが規律があった日本人官吏・警察官に代わり登場した無規律の兵士と警察官、はびこる縁故採用、そして無能の官吏の下で、社会秩序は一気に悪化した。 ・一九二〇年代以来初めてコレラの流行がぶり返したのがその端的な現われであった。 ・社会の風紀も悪化し、絶えてなかった学校の先生に生徒が賄賂を贈る悪習が蔓延し始めた。 ✝「いつ暴動が発生してもおかしくない」 ・陳儀は、台湾の「光復」にあたり、当然のことながら、半世紀にわたり日本の植民地統治を受けてきた台湾住民の中国国民への統合を目標として掲げた。 ・この目標そのものが問題だったのではない。 ・問題は政策の実施方法の、実状を無視した性急さと杜撰さにあった。焦点となったのは、言語政策である。 ・「光復」は台湾住民にとって日本語にかわる新たな「国語」の学習を意味した。 ・本省人も熱心にこれに取り組んだのであるが、問題となったのは、第一に、国語未習熟であることが政府機構に本省人を任用し難いことや地方自治実施延期の根拠とされたことである。 ・国語普及政策の性急な実施のもう一つの側面は、日本語の禁圧である。 ・同じ漢族であった台湾の本省人と国語(中国標準語)との間には二重の距離があった。 ・一つは、同じ漢語ながら中国北方語を基礎として作られた中国標準語と南方語である台湾住民の母語(福佬語、客家語)との距離である。両者は通じない。 ・もう一つは、台湾住民の教育を受けた層にとって、学校教育の普及により日本語が知識の吸収、意見の表明の道具となり、さらに台湾の他の族群との意思疎通のための共通語としての意義を有するようになっていたことである。 ・陳儀政府においては、こうした日本語の存在は国語普及の障害として受け止められ、「光復」一年後を期して、マス・メディアでの日本語使用が一律に禁止された。 ・来台外省人官僚から見れば、台湾人の日本語使用は「日本による奴隷化教育」の証でしかなかった。 ・新たな国語の習慣が間に合わない時期に日本語が禁圧されたことは、本省人エリート層の発言を封じる結果ともなり、また、われわれは植民地時代に日本人の同窓生と張り合いながら近代知識を身につけてきたのだ、という、かれらの誇りを傷つけるものだった。 ・本省人エリートにとっては、これらは「光復」に対して抱いていたかれらの期待に反する、思いがけぬ政治的、文化的さらには経済的価値剥奪であった。 ・こうした価値剥奪に直面して、本省人エリートがとった手段は、かつて日本に対抗した時と同じく、自治運動を展開することであった。 ✝二・二八事件 ・国府軍の弾圧の犠牲になった人の正確な数は、依然不明であるが、一九九二年李登輝政権下で発表された調査では、一万八〇〇〇人から二万八〇〇〇人と推定されている。 ―― 完 ―― |