
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年03月02日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
15 |
18/02 |
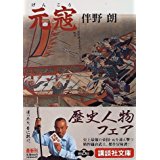 |
元寇 |
伴野 朗 |
講談社文庫 |
◎ |
プロローグ ・長崎県北松浦郡鷹島町は、 ――元寇の島。 として知られている。 ・文永十一年(一二七四年)十月、高麗を発した元軍が、この島を襲った。モンゴル、女真、漢人と高麗の混成軍であった。 ・対馬、壱岐を襲奪したあとでの襲奪であった。殺戮と略奪が繰り広げられ、生き残ったのは、島民の老婆二人だけだった、と伝えられている。 ・さらに七年後の弘安四年(一二八一年)七月、またもや元軍が襲来した。 ・元に滅ぼされた南宋軍を主体とした「江南軍」であった。 ・鷹島周辺の海上には、日本攻略を目指す元軍十四万人を乗せた四千四百隻の軍船がいた。 ・日本攻略を号令したのは、元帝国の世祖フビライである。 ・だが、元との交渉の機会は多々あったのだ。日本はその一切を無視し、交渉のテーブルにつこうとしなかった。 王者 ・南宋は、貿易奨励を国是としており、熱心であった。 ・日本では、平清盛が福原京(神戸)をつくり、そこを根拠地として南宋貿易で大きな利益をあげた。 ・南宋の宿敵は、なんといっても金であった。北宋を事実上の滅亡に追い込み、南宋を南に追いやった憎っくき相手である。 ・南宋の基本戦略は、まず積年の仇、金をどう討つかであった。だから、新興のモンゴルがしきりに金を圧迫しはじめると、南宋はモンゴルと組んで、金を挟撃した。 ・端平元年(一二三四年)、金は滅んだ。 遠征 ・キントを総司令官とする日本遠征軍約三万が九百隻に分乗して、合浦を船出したのは、至元十一年(一二七四年)十月三日であった。 ・基幹兵力はモンゴル兵三千を中心に、中国華北、東北出身の漢人兵九千、女真兵三千。この蒙・漢・女真混成軍一万五千と、高麗軍八千の二万三千であった。 ・モンゴル兵は、対馬の地頭宗助国の躰に群がり付き、首、胴、手足をバラバラにしてしまった。その残虐さは、日本では考えられぬものであった。 ・元軍が壱岐に去ったあと、住民たちは助国の遺体を拾い集め、それを首塚、胴塚、手足塚、太刀塚に分けて葬った。 ・助国のこの四つの塚は、佐須川上流の ・『新元史』は、対馬でのモンゴル兵の所行について、 ―― と、描写している。 ・温度が急激に下っていた。低気圧が近付いている兆候である。 ・陽暦十一月末は、台風の季節ではない。それは、高麗人も経験則として知っている。だが、玄海灘には、冬季の大陸旋風の影響で、突風が吹くことがある。 ・「帰国する――」 北上するには、ちょうどよい強い追い風が吹いていた。 キントの考えはこうである。 ・遠征軍は、所期の目的は果した。対馬、壱岐を蹂躙し、鷹島を これを、大勝利といわずしてなんというか。 ・副司令官の劉復亨が負傷し、すぐ手術を行わないと、一命が危ない。彼の命を救うには、帰国以外にない。 ・ちょうど帰国には、おあつらえ向きの追い風が吹いている……。 そこで、彼の気持ちは固まったのである。 ・その時、事故が起った。 ・旗艦に従って九百隻近い船が、舳を北に向けた。 ・風が強過ぎた。数ヵ所で船同士がぶつかった。それが障害になり、後続の船が突っ込んでいく。 ・闇夜で、接近するまで船影が認められないことも、この悲劇に輪をかけた。 ・遠征軍の船は、堅牢であったとはいい難い。正月に建造を命令され、十月までに間に合わせた急造の船である。 ・しかも、高麗の反モンゴル地下組織の手によって、かなりの手拭き工事がなされていた。 ・戦船が次々と引き裂かれていった秘密は、ここにある。 ・高麗に辿りついたのは、約四百隻に過ぎなかった。九百隻の大半が、海底に沈没、一万三千五百が溺死した。 ・だが、キントは決して、 ――日本に負けた。 とは思っていなかった。彼らの認識は、凱旋中に気まぐれな玄界灘の突風にたまたま遭遇した、ということだった。 ・キントの認識はこうである。 この第一次日本遠征で、元王朝そのものはたいした損害を受けていないのだ。沈んだ船は、皆高麗が自分の費用で建造したものである。 人的にも、半分は高麗軍で、元軍とはいっても、モンゴル族のほか、漢族、女真族の混成軍団であったのだ。高麗に比べ元朝の受けた被害は微々たるものであったのだ。 滅亡 ・――国使を斬る。 という例は、蛮勇が売りものだったモンゴルにもない。 ・当時は、国際法として明文化されたものはなかったが、それでも、国と国との交渉ごとにおける慣習的な不文律は存在した。 ・そこでは、 ――国使は互いに尊重する。 ことは、常識となっていた。 ・時宗は、表向きには日本の断固たる意思――元とは修好しない――を示すため、元使を処刑しようとしたのだが、これはまったく筋違いの処置であった。 ・この時宗のとった常識はずれの処刑を止める者がいなかったということも、日本、元両国にとって不幸であった。 ・日本国内では、 ――元使処刑。 のニュースは飛び交った。 ・昨年、文永の役で手痛い被害を受けたことを知っている軍民は、こぞって幕府のとったこの措置を歓迎した。 ・とくに九州の武士や民衆は拍手喝采し、大いに留飲を下げた。 ・だが、これがどんなに高い代価となってはね返ってくるか、と危惧した人々は少なかった。 【私見 : 日露戦争後~第二次大戦終了までの間の、日本の国民とメディアの雰囲気と全く変わっていない! 日本人の気質はこの時代から連綿と続いていたのだ。】 前夜 ・北条時宗がまずやったことは、高麗遠征計画の立案だった。 ・高麗は蒙古の手先きとなり、フビライの使者を案内しては、わが国に干渉した。先の文永の役においても、高麗兵が襲来した。どうも目障りな存在である。 ・異国征伐のための動員令は、いつの間にか立ち消えとなった。その代わりに出てきたのが、博多湾一帯に対する防塁築造令であった。 ・建治二年(一二七六年)三月に始まった防塁築造の範囲は、博多湾岸の東は香椎から西の今津まで約二十キロに及んだ。 ・この防塁は、当時、 ――石築地。 と呼ばれた。 ・日本遠征時、高麗が負担すべき軍兵や船艦が提示された。 ・正軍一万、水手一万五千。戦船九百隻、兵糧十一万石。 ―― 完 ―― |