
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年04月10日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
18 |
18/02 |
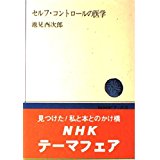 |
セルフ・コントロールの医学 |
池見酉次郎 |
NHKブックス |
◎ |
はじめに ・文明の進歩も、それが物質面に偏るとき、一見、人間の幸福や健康に、めざましく貢献するとみえて、根本的なところで、人間性をそこない、人類の存在そのものさえ脅かすものであることが、近年、いよいよ明らかになってきた。 ・そこで、そのような物質文明のひずみを ・さらには、極端な物質文明への反発として、一種のスーパー精神主義(神秘的、カリスマ的)が、巷で人気をよび、人の心はしばしば、これら両極の間を揺れ動いているのが現状といえよう。 ・しかし、問題の本質をなすものは、「物質」か「精神」かということではなく、デカルトの物心二分の哲学以来、近代文明を支えてきた物心二分の考え方なのである。 ・すなわち、心という非合理で主観的な世界のことは、「神」や教会にあずけて、日常生活は合理的な物質主義に徹するという、西欧的な文明の中での人間たちの二重生活に、今日の危機の根源があるわけである。 ・いいかえると、科学の客観主義(人間性無視)と宗教の主観主義(科学無視)の不幸な分裂に、その端を発している。 ・ところが、今世紀にはいって、 ・一方、これも今世紀にはいってからのことであるが、精神の探求についても、前世紀的な不可知論を脱して、心という暗黒の大陸に科学の光をともす研究が、急速に進歩してきている。 ・また、超越者(神)を立てることなく、人間を包んで宇宙的な広がりをもつ、 ・医学に目を転じてみると、現代の物質主義、一九世紀的な科学主義に基づくひずみが、ここでも年ごとに深刻化してきている。 ・ここでも、病める器官への機械的な部分修繕に偏り、人間の心を忘れ、病める人を無視しがちな心身二分の医療のひずみが、まざまざと表面化してきた。 ・西洋では、心身二分の医学への反省として、およそ五〇年前に心身医学なるものが生まれ、西ドイツでは、すべての医科大学で、心身医学が必修科目として法令化されている。 ・私どもは、二十数年前から、わが国における心身医学の開拓に専念してきているが、その間に、身体病の多くもまた、「人が肉体的、精神的、社会的に生きてきた人生体験の結晶である」ということに気づいてきた。 ・したがって、心身医学には、人間の不幸の実体を医学の目を通して科学的に見きわめるという、従来の治療医学の限界を越えた、大きな使命があることに、次第に深く思い至っている。 ・しかも、心身二分の医学の弊を矯めようとする努力の中で、育まれてきた心身一如の人間観は、現代の危機を救うものとしての、物心一如の科学の中核をなすものであるという、重大な事実に、開眼しつつある。 ・現代の危機を脱するための物心一如の人間観ないし世界観の形成は科学者の社会的責任でもある。 ・私にとって宗教とは、私自身が ・かつて、「宗教とは阿片である」と批判してきた科学そのものが、人間の幸福という、本来の目的を離れて、阿片化しつつある現代にあっては、それを乗り越えるための何かを明らかにしようとする科学者もまた、かつて宗教家がそうであったように、科学を考えながら、同時に、自己の人生そのものを語りうるものであらねばならないであろう。 ・そのような立場で語られた科学の言葉のみが、ようやく、現代の「阿片」であることを免れるであろう。 ・『催眠――心の平安への医学』出版の目的は、治療法としての催眠によって得られる一種のASC(リラックスと統一の状態)は、一般に誤り考えられているように、病的なもの、ないしはオカルト的なものでは、決してないことを、精神生理学的に説き明かすところにあった。 ・ところが今日では、催眠の場合のように、他者の力をかりて、ASCに入るのではなく、自らその状態に入ろうとする瞑想法が静かなブームをよんでいる。 ・「瞑想」の効果をひと口にいうと、現実生活のストレスに ・したがって、これは超越的、神秘的なものではさらさらなく、各人にとって最も正常かつ純粋な状態といえよう。 ・術にかかるとか、超能力が出てくるとかいうことではなく、現代生活の ・宗教の本来の役割は、全体世界の秩序への気づきをふまえたセルフ・コントロールのあり方を教えるところにある。そのねらいや方法は、今日の科学化された心身医学、さらには人間回復の医学(人間の実存に則した医学)と相通じるものである。 第一章 宗教について 現代科学の盲点 人間不在の医学 ・古代の医学は、人間を心身一如の存在としてとらえ、全人的な立場からの治療を行なうものであった。 ・すなわち、病気を特定の器官の病態としてだけとらえるのではなく、人間としての存在のあり方のひずみに起因するものとしてとり扱っていたようである。 ・こういった観点から、近年東洋医学が見直されつつある。 ・ところが、医学の世界でも、分析的思考に基づく研究が支配的となってきた。 ・このような傾向は、医学の急速な細分化を促し、それぞれの専門分野では、すばらしい進歩がもたらされた。 ・しかし反面では、人間の内なる自然がもつ統合的な営みを忘れがちな現代医学の弊害が、次第に切実な問題となってきている。 ・たとえば、病める人たちは、さまざまな専門家の間をたらい回しにされて、個々の器官について多くの診断名をつけられるが、それらが本人の全体的な健康のあり方にどのような意味をもつかについての総合的な判断と治療方針については、どの医師も責任をもっていないことが多い。 ・また、個々の症状に対して数多くの薬が与えられるが、それらが生体全体にどのような副作用をもつかについては、しばしば、充分な説明がされていないようである。 ・さらに、心身の症状という形で表面化している各人の生き方のひずみについて、筋道をたてて教えられることは、皆無といってよいほどである。 ・多くの、いわゆる現代病の病根が現代生活のひずみあることを考えれば、個々の器官や症状のみを対象とする現代医学のあり方では、真の病根にはふれることなく、症状とのいたちごっこをくり返すといった結果を招くことも多いようである。 ・いかに進んだ科学的な診断の技術も、いかにすばらしい現代の化学薬品も、病める人への全人格的な理解をふまえて活用されることによって、その威力を十分に発揮し、その副作用を最小限にとどめうるものであることを強調してやまないのである。 人間性を忘れた医学的処置 ・自ら意識するとしないとに関係なく、すでに ・宗教家は、それを神仏の啓示としてとらえ、芸術家は、造形、色彩、メロディーなどとして表現する。 ・宗教や芸術の世界の天才たちによって、科学以前の直観によってとらえられた人間としてのあり方の法則(道)が、今日なお人間の心を支える真実として、ゆるぎない力をもっている理由も、このようなところにあるといえよう。 万物の霊長 ・チャールズ・ダーウィンは『種の起源』で進化論を唱え、以来、進化の最頂点に達したのが人間であるとされている。 ・そこで、人間は万物の霊長と自認していたが、単に機械や文字を扱うのが文明生活と、思い違いをしたところから、今日の不幸が始まっている。 ・人間は、その偉大なる脳を誇っているが、融通がきくという点では、動物の脳は、人間の脳と比べものにならない。 ・たとえば、両棲類や爬虫類では、脳機能の修復は、日常茶飯事であり、人間のように脳卒中をおこして半身不随になったカエルなど見たことがない。 ・脳にかぎらず、体の各部に再生力が豊かなのである。 ・すなわち、脳を含めて全身的に見た場合、人間の体のように分化の進んだものでは、破壊に対する代償力は最も弱くなるようである。 ・したがって、環境の変化に対する適応力も最低と思われる。 ・人間は、環境の変化に強い動物だと考えるのは、明らかに思い上がりである。 ・人間が、果たして、万物の霊長というに値するかどうかは、 第二章 セルフ・コントロール 表面的な対応 ・一般にセルフ・コントロールという言葉は、現実の環境に適応できるように自らを統御することを意味している。 適応病 ・アレルギー症状も、実は、生体がもつ一種の防衛本能の現われなのである。 ・アレルギーを起こす物質(抗原)が体内に入ってくると、体の中に、それに対抗する物質ができ、そこに再び抗原が入ってくると、抗原と抗体との戦いが始まる。これが、ぜんそくやジンマシンなどのアレルギー症状が起こる基本的なからくりをなすとされている。 ・抗原という敵軍に対して、抗体という味方の軍隊が立ち向かい、その戦争が気管支を中心にして行なわれると、ぜんそく発作になり、皮膚で行なわれるとジンマシンが現われるといった工合である。 ・いいかえれば、近年のアレルギー疾患の急増は、現代文明による生活様式や生活環境の急テンポな変化に人体が適応しきれなくなったためであるともいえよう。 セルフ・コントロールへの道 心身一如の医学 ・病気も、事故や外傷、家庭の不和、事業上の失敗などと同じように、人間の「不幸」の現われだということである。 ・したがって、心身医学は物心一如の科学の中核をなすものであり、この医学を通して科学的に探りあてられつつあるセルフ・コントロールの理論と方法は、病気以外の「不幸」の解決にも活用できることがわかってきた。 ・わが国でも一流の医師たちが、正面きって医学を説くときには、「病気の真因は人にある」ことを強調するにもかかわらず、実際の治療(医術)になると、部分修繕に偏りがちなのが現状である。 社会環境と医学 ・人間における心身一如ということも、けっきょくは心も脳も身体諸器官も、一見、相互否定的でありながら、全体として有機的な調和ある営みをするということにほかならない。 第三章 医学から見た人間形成 脳の構造と働き ・人間の心の営みは、 ・そこで、主として新しい皮質と古い皮質に活を入れる働きをする網様体が、このような人間の心のあり方を左右する大切な役割をする。 脳(心)と体を結ぶルート ・神経系には、中枢神経系(脳・脊髄)と末梢神経系とがある。 ・末梢神経系は、中枢神経系と身体の諸器官とを結ぶ役目をするもので、はたらきの上から植物神経系(自律神経系)と動物神経系(体性神経系)とに分けられる。 ・植物神経系は、消化、吸収、血液の循環、排泄および生殖など、生命を保つのに欠くことのできない体の働きを調節し、人間の生命活動の中で植物的な部分を受けもつものである。 ・一方、動物神経系は、人体を環境にうまく適応させ、いろいろな危険から身を守り、周囲に働きかけていく、動物的な生命活動を可能にするものである。 ・植物神経系の作用のほとんどが、無意識的、自動的に行なわれるのに反して、動物神経系の働きは意志によって行なわれるのが特徴である。 自律神経系(植物神経系) ・交感神経系と副交感神経系とに区別され、これら二つは多くの場合反対方向に作用するが、臓器によっては協力的にも作用する。 ・たとえば寒冷にあったり、大出血したり、外敵に出会って戦うか逃げるかしなければならないといった非常の事態にさらされた場合、あるいは恐怖とか怒りとかの強い精神感動を起こした場合、交感神経系の働きによって瞳孔は開き、心臓の搏動数はふえ、気管支は拡張し、循環血液、赤血球が増加し、肝臓のグリコーゲン(エネルギー源となる糖原)が動員されて血糖が上昇する。 ・また戦いや逃走に必要な器官である骨格筋、心臓、脳などには十分な血液が送られる。 ・このように、交感神経系は体内に貯蔵されたエネルギーを動員して、生体が活動しやすい状態をつくる方向に働くものである。 ・これにたいして、副交感神経系の主な役割は、交感神経系の興奮によってひき起こされた諸器官の変化を元にもどし、消耗されたエネルギーを補充するような方向に働くところにあるとされている。 ・すなわち、胃腸の働きを刺激して食物の消化吸収を高め、肝臓にグリコーゲンをたくわえ、血圧を下げて脈搏数を減らし、気管支を閉じるなどの働きをする。 動物神経系 ・この神経系は、脊髄を仲介として脳と体の諸器官との間の連絡にあたるもので、全身の骨格筋や感覚器を支配して、意志による運動と感覚をつかさどっている。 ・ホルモンというのは、内分泌腺によってつくられ、血液、リンパ液中に分泌され、微量でも遠くに離れた部位によく作用するような化学的な物質を名づけたものである。 ・神経と内分泌腺は、神経的な調節とホルモンによる化学的な作用によって、人間の生命活動全般を調整する役割を果たしている。 ・脳下垂体は、多くのホルモンを分泌して副腎、甲状腺、性腺など多数の内分泌腺の指揮にあたっており、この脳下垂体は間脳を介して大脳皮質とつながっている。 免役 ・免疫の働きについて述べるにあたっては、まず進化をとげながら存在してきた、人類の外界と内界について考えねばならない。 ・外界としては、おびただしい真菌(カビ類)、細菌、ウイルスなどによって作られる強烈な敵対関係の環境が問題になる。 ・内界の条件としては、人体の細胞は、絶えず複雑きわまる進化をとげてゆく運命にあり、しかも、それぞれ思い思いの方向に、絶えず進化することを必要としている。 ・このような人体の内外で起こる二つの異なる流れをコントロールして、人体の営みを調和させるものが、免疫の ・すなわち、人体に接触した九〇パーセント以上の菌体は、皮膚の表面で死滅してしまう。 ・辛うじて体内に侵入した菌体も、人体の体液成分とリンパ球によって、たちどころに溶かされたり、貪食されたりして、体内から消滅させられる。 ・たとえば、ウイルスに対してはインターフェロン(ウイルスの活動を抑える)、補体(抗原抗体反応を促すなど)、免疫グロブリン(抗体としての働きをもつ)などの体液成分やリンパ球などがその役割を果たす。 ・さらに免疫グロブリンとリンパ球は、補体の助けをかりて、実は巧妙な自己と非自己を弁別する能力を発揮して、侵入してきた異種族に由来する蛋白、同種族に由来するものでも非自己と見分けられた蛋白、あるいは、自己に由来するものでも、奇形になったもの、不必要、不都合になった蛋白や細胞成分を消滅させる働きをする。 ・このさい、微妙な蛋白の攻勢の差異を厳格に見分けて、その蛋白(抗原)に特異的に作用する抗体をつくって、抗原抗体反応によって処理したり、リンパ球による貪食作用を発揮したりなどして、それらの非自己を体内から消滅させる。 ・このような免疫による個体の維持の ・免疫の働きは、非自己を見分けて、処理することによって、人体の自己を守りぬき発展させるという、まさに生理学的なセルフ・コントロールの鍵を握るものであることがわかってきている。 ・したがって、自律神経系、内分泌系とともに、人体のホメオスターシスを支える三本の柱の一つと見なされるに至っている。 ・しかも、免疫の営みは脳の働きと密接な関係にある。 ・そこで、免疫と関連の深い感染症、アレルギー疾患、免疫病さらには、癌などの悪性腫瘍の発生や経過と、脳(心)の働きとの深い結びつきについても、科学的な裏づけを固めてゆく体制がととのいつつある。 ・たとえば、癌などでは、非自己的に変質した細胞が体内で際限なく増殖して、人命を脅かすものであり、老化によって、このような非自己を弁別し処理する免疫の力が衰えたりすることも、癌の発生に関係する可能性が考えられている。 ホメオスターシスとふれあい ・ホメオスターシスというのは、恒常性という意味である。これは、外部環境がいろいろと変化しても、人体の内部環境が、それによってかき乱されることがないように、常に安定した状態を維持するという、生体の巧妙なしくみを意味している。 ・ホメオスターシスを保つのに、最も重要な働きをしているのは、自律神経系とホルモン系であり、自律神経とホルモンの中枢である視床下部が、その中心的な役割を果たしている。 ・このようなホメオスターシスの原理は、同じ視床下部や古い皮質で営まれる情動の心、すなわち、快、不快、怒りや恐れの心についても、当てはまるとされている。 ・ふれあいということについて わが身を保つための食欲、種族を保存するための性欲、それに集団欲、これら三つの本能的な欲求の中で、一番基調になるのは集団欲であるといわれている。 ・この本能があるからこそ、人間たちは、しのぎをけずるような厳しい人間関係をもちながらも、一方では、絶えずいろいろな集団を作って生活していないと落ち着けないのである。 ・このような集団欲が、一番原始的な形で現われるのが、「肌のふれあい」、「スキンシップ」などと表現されるものである。 ・近年、赤ん坊の心身の成長に、このようなふれあいが、精神的な栄養としても、とくに重要な意味をもつことが注目されている。 ・たとえば、母親とのふれあいが得られない赤ん坊では、体の成長も遅れ、ひどい場合には、愛情欠乏症の発育不全が起こるとさえいわれている。 ・赤ん坊の心が触れ合いによって安定していると、成長ホルモンの分泌がよくなるという報告もあるくらいである。 ・このように子どものときには、肌のふれあいといった形で働く愛情の交流も、人が成長するにつれて、次第に心のふれあい、すなわち、思いやり、認める、褒めるなどの形へと発展してゆく。 ・動物はその種族保存本能に従ってわが子を育て、同じ種族の中の争いでは、牙や爪を血にぬらすようなことは決してしないといわれる。 ・こういった動物がもつ、本能としての種族保存の欲求も、人間が手を加えると、ゆがめられてしまうことがあるようである。 ・たとえば、ライオンが動物園で飼育されていると、ジャングルの中で生活していたときのように、わが身を養うために、餌食を求めてさまよわなくてもいい状態になる。毎日大きな肉のかたまりを投げこんでもらえるからである。 ・ところが、このような生活に慣れてくるにつれて、ライオンの母親はあまりわが子の面倒をみなくなるそうである。 ・自己保存能力があまり満たされてくると、種族保存本能が衰えてくる。 ・これと似たような現象が、人間の母親たちに現われていることはご承知の通りである。 ・身を養うことが楽になってくると、子を育てることがわずらわしくなってくるようである。 ・生まれてすぐの子猿を、六ヵ月間ひとりぽっちに隔離して育てた後で、ふつうに育った子猿の中に入れると、もはや一緒に遊ぼうとしなくなるそうである。 ・また六ヵ月以上隔離された雌猿が、成長してから、雄猿にムリに妊娠させられて子どもを産んでも、その子を放りなげ、自分に近寄らせまいとしたそうである。中には、子猿をかみ殺した母猿もいた。 ・集団欲やふれあいと、種族保存本能との間には、深い関係があるようである。 ・疎外された孤独な環境で育った人間の母親たちにも、近頃はこれと似たような悲しむべき母親像がみられるようである。 ・人間をこのような動物的な本能にまでさかのぼってみても、自己保存の欲求と、種族保存ないし集団の欲求があり、個を指向するものと集団を指向するものとの二つの方向があることがわかる。 ・いわゆる自然治ゆ力ということも、ホメオスターシスの営みが基本になって発揮されるものである。 愛の原点 ・知性の文化によって洗脳された現代人の心からは、動物にみられる本能的な母性愛さえ忘れられつつある。 マイナスの意志力(しつけ) ・脳の前頭葉の働きの一つに意志の力がある。 ・ここでは、自主的な活動を強めるような働きかけと、それとは逆に、活動を弱め、抑制するような働きかけとが行なわれる。 ・すなわち、この力がプラスの方向に働くと、やる気、意欲、創造の営みが起こり、マイナスの方向に働くと、我慢、忍耐、抑圧などの心の営みが起こる。 ・これらのプラスとマイナスの心の働きをいっしょにして、意志力とよんでいる。 ・近頃の青年たちでは、意志の弱さ、気まぐれ、近道反応による衝動的な行動などが問題になることが多いようである。 ・このような我慢の力を強化するためには、くり返し訓練する必要があり、「しつける」という言葉には「くり返す」という意味があるそうである。 ・アメリカの非行少年の大部分には、子供の頃の基本的な生活習慣である、食事、睡眠、排泄、着衣、手を洗い歯をみがくなどの行動が、よく身についていないということである。 ・アリストテレスは「人間の偉大さは、その抑制によって示される」といっているが、自制心を身につけるしつけが不充分になっているところに、現代人の弱点があるようである。 人間としての基礎工事 ・幼い頃、とくに三歳ぐらいまでに、親や養育者との間に安定した愛情関係をもつことができないと、往々にして人間愛の原点が培われないままに、成人することになる。 ・赤ん坊が、母親からの愛情をオッパイや肌のふれあいなどを通してくみとることによって、人間や人生に対する「基本的な信頼感」が、赤ん坊の心にうえつけられるのである。 ・これがうまくゆかないと、人間や人生に対する基本的な不信や不安がうえつけられやすい。 ・この信頼と不信のいずれもが、人の一生にわたって、心のあり方に重大な意味をもつとされている。 ・米国の精神分析医で小児科医であるブルック女史は、人間では、乳児にたいする母親の授乳の仕方が誤っていると、赤ん坊のホメオスターシスの発展が妨げられる、と唱えている。 ・赤ん坊の心と一体になれるよき母親は、赤ん坊の泣き方によって、赤ん坊が求めるものが母乳なのか、不安で抱っこしてもらいたいことなのかを鋭敏に感じとって、適切な反応をするであろう。 ・一方、自己中心的なまたは、育児に専念できない母親の場合は、赤ん坊が泣くと、わずらわしいので、いつでも乳房をふくませるといった無差別な反応をする可能性がある。 ・そのような育て方をされた赤ん坊は、正常な空腹感と精神的な空虚感などとの区別がつかなくなるというのである。 ・近頃は、思春期の女性で生きがいがなくて心が空しくなると、やたらに物を食べたり、極端に減食したりする食欲異常症という病気がふえているが、その遠因の一つは、このようなところにもありそうである。 ・新聞の社会面を騒がす非行青少年たちが、愛のない家庭に育ち、自分自身と自分以外の人間や社会に対する基本的な不信感や不安のために、罪を重ねている場合が多いことは、一般にもよく知られている。 ・西欧流の精神分析では、成人後も両親からの精神的な分離がうまくいっていない人たちに対して、「分離のおさらい」をさせることが、その大切な役割とされている。 ・また、西欧の子どもたちが、幼い頃から自主的で独立的なあり方を教育されていることは、ご存知の通りである。 偽りの独立 ・「母なるもの」との一体感を充分に味わうことが、自分という存在を、生命の大地に根を下ろさせ、それがひいては、人類愛、万有愛を発展させる芽ばえになる。 母なるもの ・本当の意味での愛というのは、自他の区別がつかない没人格的なふれあいではなくて、相手を一個の人格として認め合いながら、お互いを隔てる区別を自覚しながら、ふれあいを保とうとする、あるいは、ふれあいを保たずにはおれない心ではなかろうか。 第四章 「心とからだ」の医学 人生相談――カウンセリング ・「相手に成長をもたらすような話しあいの仕方、人間関係のもち方」としての広い意味のカウンセリングは、今日のように人間関係が貧しくなった時代には、誰しもが心得ておかねばならないことの一つといえそうである。 ・カウンセリングでは、ただひたすらに来談者の語ることに傾聴することが強調されている。 ・アメリカのファックス博士の言葉 「ともかくこの一年間、ウン、ハアと相手のいうことをひたすらに聞いてごらんなさい。すると、奇跡に等しいようなことが起こるから。そして、もしうまくゆかなくても、それはあなたが笑われるだけで、相手を傷つけることは絶対にないから。」 信仰による治ゆ ・信じる相手が治すというよりは、こちらの「信じる心」によって、治る可能性が考えられる。 ・子どもは精神的に親と一体であり、親たちが不安にかられると、子どもも不安になり、いっそう病状が悪化する。 ・信仰による治ゆについての注意点 ①信仰によって治る多くの病気は、神経症や機能的な身体病変が主体となる心身症と思われる。病気の種類について正しい診断が行なわれず、信仰を万能と考えるところに常に危険が伴う。 ②教祖や教会に対するつよい依存状態ができると、症状は一見治ゆしたようにみえても、精神的には教組や教会の奴隷になっていることがよくある。悪用されやすい。 ③信仰による治ゆの実体が見落とされ、教組にマカ不思議な霊能があるかのように思いこまされることによって、患者の人間的な成長が妨げられ迷信のとりこになる恐れがある。 ・私の経験では、宗教でガンが治ったという場合、そのほとんどが診断の誤りであっった。 ・医学的な考え方だけでは、信仰による治ゆの、ごく一部を説明できるにすぎない。 ・だからといって、現在の科学で説明できない現象はすべて否定するという態度をとること自体、むしろ非科学的ではなかろうか。 ・現代医学が急速に見失いつつあるもの ①人間に本来備わっている治ゆ力への信頼 ②治すものと治されるものりとの信頼関係 ③治療における愛や希望のもつ力 ・これらは、主として薬や手術の効果に対する過信に基づいている。これこそが、現代医学の盲点をつくものではなかろうか。 第五章 人間回復の医学 実存主義 死への存在 ・人間としての実在を深く見つめれば見つめるほど、その存在がはかなく有限で、無に対面していることを、身につまされて知るものである。 ・この有限性が最も端的に現われるのは死であり、人間は「死への存在」である。 ・生きているかぎり、瞬間ごとに、死に向かっており、「死に先行して覚悟をきめている」あり方、これこそが、人間が最も本来的な自己でありうる姿勢である。 ・この覚悟をきめた上で、今ここの現実、日常生活へと立ち戻り、しかも日常態にはまりこむことなく、過去を自分に固有なものとして受けとり直し、自らの責任として引き受け、今のあり方こそが将来を左右するものとして、過ぎ去った過去と、まだ来ない将来に捉われずに、「今」に生きることになる。 独特の養生訓 ・養生訓というものは、いうはやすく、なかなか実行しにくいものである。 ・タバコが悪いことは百も承知していながら、やめられない人がいる。それは、「好きなタバコまでやめて、たいせつに長もちさせるに値するほどの生命を、みずから生きていない」からなのである。 死を忘れた文化 ・会報『人間』の編集者であった藤井義正氏曰く、 「現代は、科学や医学が進歩し、私たちはその恩恵に浴しながら生きている。これはありがたいことである。ありがたいことだが、その代り、苦しいことや危機に対する精神的肉体的耐性は、すっかり脆くなってしまった。暑ければ冷房、寒ければ暖房と、不快なことは科学が排除してくれた。病気になると医学が治してくれる。それが当然と思うようになった。事実、これまで不治と思われた病気も治るようになった。そういうものに対する心の準備を忘れてしまった。だから現代人は病気になった時、やっかいな患者になるのである。」 「私は、病気の人が病気を受容し精神的な苦痛から解放されるためには、こういう現代の死を忘れた文化を土台にした人生観、価値観から解放されることがなにより必要だと思うのである。」 死の臨床 ・『死ぬ瞬間』の著者で、女性心理学者キュプラー・ロス曰は問いかけている。 「医学は、人道的で尊敬される学問でありつづけることができるのか。それとも、人間の苦しみを和らげるよりも、命を延ばすことだけに役立つ、新しい非人間的な科学であるべきか」 ・死んでゆくということも、生の営みの一つであり、うまく生きさせるだけでなく、より安らかに死なせることもまた、医療の本質にふれる大切なことであるはずである。 癌患者の心理 ・中川俊二医師は、国内で癌の自然退縮を起こした二一例について調査し、その中には、人生観の大きな転換が関係していると思われる例のあることを、発表した。 大死一番 ・咽頭癌と診断されてから、一四年間も生きつづけて宗教家として活躍されたK氏の子息曰く、 「癌になったことで、それまで長年信仰を続けながら、どうしても越えられなかった生への執着を離れて、自分に与えられた一日一日を有り難くおしいただいて生きるという、人間として一番真実な生き方に近づくことができた」 ・注目すすべきことは、K氏がこのような心境になったことが、癌の進行をストップさせたことにも関係がありそうだということである。 ・この人たちは、癌の宣告によって初めて、死という人間の実存に立ち向かう姿勢が確立し、それに徹することによって、本来的なセルフのあり方に迫る生き方をしておられる。 身体としての私(体得の原理) 身体の知恵 ・東洋思想の中では、いわゆる「身体の知恵」が尊重されてきており、伝統的な東洋医学の基本原理は、自然にそなわる「身体の知恵」を保持させ、刺激するところにある。 ・日本では、「体得」という表現がふつうに用いられており、これは体を通してものごとを会得するという意味である。 ・このようにして、能、剣道、柔道、茶道、華道、弓道などは、精神的なセルフ・コントロール、自己実現、さらには「悟り」というレベルにまでも高められてきている。 手の勉強 ・花森安治氏曰く、 「ナイフで鉛筆を削るのは大切な手の勉強です。今、たいていの小学校では鉛筆削り器で削らせ、手の勉強を取り上げてしまっています。」 ・ナイフという小さな危険を、子どもたちから取り上げたために、もっと大きな危険が待ち構えていたようである。 ・交通事故にあったり、ボールを芽にててケガしたり、科学実験ですぐ機械をネジ切ってダメにするような子が多いのは、「危ない危ない」と世間の風にも当てぬ過保護な幼児教育が関係しているようである。 ・手や体を使って、ほどよい感覚をつかむ早期訓練をしないと、人は退化してゆくようである。 腹も身のうち ・不摂生による被害を直接こうむるのは、私ども自身の胃や腸なのである。すなわち、自分の ・ここのところがほんとうにわかると、いわゆる胃腸病は、ほとんどなくなるといってもよいくらいである。 ・さまざまな胃腸の薬にたよる前に、私どもは「腹も身のうち」という諺を、よくかみしめる必要があろう。 ・自分の胃の調子に応じただけの食事をとり、自分の体に合うような食べ物を選ぶ、といった自然の知恵は、われわれの体にもともと備わっているものである。 ・これは医学的には、「体の知恵」といわれ、健康になるための基本は、この「体の知恵」への気づきを鈍らせないことである。 ・つまり、「体の知恵」に沿って、ものの食べ方、体の使い方、生活のあり方などを調えることである。 ・「腹も身のうち」を心にとどめて生活している間に、食事の量がしだいに減ってきて、必要最小限のものを一口一口、味わいながらよくかんで食べるようになってきた。 ・そうなると、自然に自分の胃の調子に対する気づきが深まり、必要な量と質を備えた食べ物をちゃんと食べると、自然に箸がおけるような習慣がついてきたのである。 ・「一病息災」という諺がある。何か一つの大きな病気をもっていて、それをコントロールするために生活を調えていると、生活全体が健康的になる。そのため、健康に自信をもちすぎている人よりも、かえって長生きする場合が多いのは、こういった原理によるものである。 心身二分の近代文明 ・人間の孤独感と人間同士のあつれきが強まるのは、われわれが他者から物化され道具化されるときである。 ・われわれは根源的に他者と結ばれた存在であり、他者を介することによって初めて自己として存在し始めたものであるからこそ、自己を孤立した存在として意識すればするほど、ますます孤独を感ずるのである。 ・自我の目覚めが深まる思春期は、また孤独を深く感ずる時期でもある。 ・現代医学は、人間の身体をバラバラに分割し、身体に宿る生きた意味を捨て去った断片に還元することによって、純粋の対象として、つまりは物体と化せしめている。 ・しかし、このようにバラバラにされた断片としての身体は、もはや、心身一如の本来の人間を離れて孤立した意味をもつことはできないはずである。 ・たとえば、血圧の上昇、心拍数の増加、呼吸の促進、発汗、胃液や唾液の分泌減少などが現われても、それが不安や怒りによる生理的な反応であることを知るのには、心臓や胃などの個々の器官だけでなく、その人を知らねばならないものである。 根源的な我の実体 人間の生命そのものはまことにもろく、朝露みたいなものであるが、宇宙を理解する知恵をもっている。 ・生きるとは何か、死ぬとは何かということを考える知恵と能力をもっている。これが、人間を偉大にするものである。 ・ここで言う「考える」というのは、世間的な損益を計算したり、人間関係を巧みにあやつるといった「考える」(知性の働き)だけではない。自分の存在の意味、生きるとは何か、死ぬこととは何かを考える(理性の働き)ことである。 ・理性によって知る存在の意味、これを、バイブルではロゴス(神の言)、仏典では般若の知恵と表現されている。 ・人間が万物の霊長といわれるのは、一人一人が創造する存在であり、存在の意味を考えるものだからである。 ・他の動物には個性がなく、自然の理法に盲目的に服従して生きているだけである。 第六章 セルフ・コントロールの秘訣 ――万人のための自己統制法―― 「本当の私」を ・貝原益軒の養生訓 「養生の根底をなすものは、医者でない素人が自分の体のことについては専門家になることである」 ・各人が心身統合体としてのセルフへの気づきを深めること、心身一如の立場よりする健康の根本理念を身につけることが、まず大切ではなかろうか。 ・検査は診断のためだけにあるのではなく、患者自身が一つ一つ検査の結果をよく理解することによって、各人の生活の無理やひずみが、どのように身体に反映しているかについての気づきを深めることが何よりも大切である。 ・血圧の高い人は、一日何回か決まった時間に、自分で測定することである。そうすれば、生活態度と血圧との送還への気づきが深まり、血圧を高くしないような方向への生活改善のあり方を、自ら会得できる可能性が出てくる。 むすび ・心身二分論に基づく現代の科学思想、今日の医学に問題があることは、近頃では、すでに万人が気づいているところである。 ・国民が心身両面での不養生のかぎりをつくしておいて、薬で治せと迫り、その結果が芳しくないと国や会社や医師を追及するのでは救いがない。 ―― 完 ―― |