
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年01月16日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
2 |
18/01 |
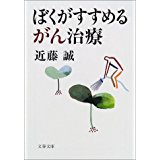 |
ぼくがすすめるがん治療 |
近藤 誠 |
文春文庫 |
◎ |
第二章 手術の問題点 がんは取ったら治るのか 世界の趨勢は臓器温存 ・世界の趨勢は、多くの種類のがんで、臓器を温存する方向にあります。 第三章 化学療法のメリット、デメリット 抗がん剤は必要か 乳がんの標準的治療ということ ・同じ乳がんでも、初回治療をうけたあと臓器移転のかたちで再発した乳がんは治りません。 タキソールにかわる第三の道 ・現在卵巣がんで開腹手術が標準的治療とされているのは、その有効性を確かめたからではなく、手術がすぐれているはずだ、という一種の「思い込み」が根拠になっていることを端的に示しています。 ・ならば、根拠がないか薄弱な治療はおこなわないという医療の原則にもどって、卵巣がんでは開腹手術をしないことを原則としたらどうか。 肺がんなどに延命効果がある、という意味 ・臓器転移がある場合、乳がんは化学療法では治らない。それが専門家たちの一致した意見ですが、現実の医療の場では、転移がある人たちに化学療法がおこなわれています。 ・その理由は、化学療法ががんの進行を遅らせる、つまり延命効果があるからなのでしょう。 ・しかしじつは、再発・転移した乳がんに化学療法をおこなった場合、患者さんがどのくらい延命するのか、確たるところは専門家たちにもわかっていないのです。 ・なぜかといえば乳がんでは、かなり以前から化学療法が当然のようにおこなわれており、無治療群とのよい比較データがないからです。 ・実際に化学療法をうける前に考えてみてほしいのは、患者さんは延命効果を実感することができない、ということです。 ・なぜならば個々の患者さんにおいて、化学療法をしなかった場合の寿命がわからないからです。 ・たとえば化学療法をしたあと、二年間生きながらえることができたとしても、本来一年の寿命が二年に伸びたのか、本来三年の寿命が二年に縮んだのか、わからない。 ・他方、副作用は全員が経験します。 ・だとすると患者さんには、副作用で苦しむ期間が増えたという実感しかわかないのではないか。 胃がん、大腸がんの場合には ・手術後に化学療法をおこなうのを、術後補助化学療法といいますが、その有効性が一応認められているのは、乳がんしかありません。 ・胃がんの術後補助化学療法については、論文のなかでも否定的に紹介されていますし、有効すなわち生存率を上げたものは何もない。 ・術後補助化学療法をおこなえば生存率が数%向上するらしい、というのが現在の到達点です。 どうやって化学療法から逃れるか ・厚生省が組織した、抗がん剤の専門家たちからなる「抗がん剤市販後研究班」の報告が、一九九一年以前に承認された抗がん剤の大半を、「延命効果、生活の質の向上効果が確認されていない」と指摘したのです。 ・その何が問題化というと、効果が確認されていないと結論された抗がん剤は、認可を取り消すのが理論的帰結のはずです。 ・しかし、認可は取り消さずにおいて、手術後に使うすべての抗がん剤について改めて効果を確かめる臨床試験を初めてみようと提案しているのです。 ・効果がはっきりしないものが、日常診療の場で使われ続けるのを放置しようというのです。 ・これでは、専門家たちは、患者のほうを向かずに、製薬会社のほうを向いている、と評価せざるをえません。 第五章 再発・転移 「原則として治らない」ときどうするか ・がん患者の三分の二が再発・転移のために亡くなっている。 第七章 臨床試験とホスピス 理想と現実のはざまで 治らない患者に毒性試験をするのが「治験」 ・第一相試験の被験者にならないかと担当医から誘われた場合には、「もう治らない」とのお墨付きが出たのと同じです。 ・治らない人に毒性試験をするの゛、と驚かれるかもしれませんが、その通りです。 ・健常人では駄目で患者さんで、となる場合、治る可能性がある人より治らない人を優先したほうが「倫理的」である、というのが化学療法医の理屈なのです。 第八章 セカンド・オピニオン 医者の腕前をどうやって知るか 上手なセカンド・オピニオンの得方 ・癌研の内科部長の丸山雅一さんは述べる。 「現在、胃がんを根治できる抗がん剤はありません。抗がん剤の目的は、あくまでも延命効果を得ることです。早期がんに抗がん剤は必要ありません。進行がんの治療の基本は外科手術です。 手術でがんを全部取りきれなかった場合や、手術のあとにがんが再発した場合、手術ができないほどがんが進行した場合などに抗がん剤を使います。 なにもしないでいるよりは抗がん剤を使ってみる、という考え方は間違いです。抗がん剤は、延命効果を期待できる可能性が高いと判断されるときにのみ積極的に試みるべきです」 第十二章 諸臓器のがんの治療法 家庭の医学書の秘めた狙い ①日本は世界の趨勢とかけ離れて手術偏重である。 ②海外では、手術のかわりに放射線治療がのびてきている。 ●咽頭がん ・家庭の医学書の問題点は、まず、とても断定的に書かれている。 ・また、手術の合併症に関する記述が甘いので、患者さんは楽観して道を誤るでしょう。 ・そしてなによりも、世界の趨勢を無視している。 ・咽頭がんに関して、家庭の医学書の記述に問題が多くなる原因は、執筆者が耳鼻科医に偏っていることにあります。 ・放射線治療医に依頼すれば、相当違った記述になります。 ・要するに読者は、家庭の医学書を鵜呑みにしないほうがよい。 ●下咽頭がん ・下咽頭がんは、喫煙・飲酒の愛好者に多い。 ・ひとくちで言えば、タバコの毒が酒にとけて、下咽頭粘膜を刺激するからでしょう。 ●食道がん ・喫煙歴があることが共通しています。 ●肝臓がん ・肝臓がんは少数の例外をのぞき、肝硬変を母地にして発生します。 ・肝硬変というのは、簡単に言えば肝臓が小さくなってしまう病気で、患者さんは一見元気そうにみえても、肝機能が低下しています。 ・わたしは、肝硬変があったならばそれだけで、肝機能の如何をとわず、非手術的方法にしたほうがよいと考えています。 ●肺がん ・治療として、本当に手術が妥当なのか、放射線治療で同じ生存成績を得られるのではないか、そうだとするとそのほうが合併症が軽度なのではないか、という問いには、世界をながめてもきちんと答えられていないのです。 ・それどころか、症状がないのにがん検診や人間ドックで発見されたような肺がんを、そもそも治療する必要があるかどうかにも疑問があります。 ―― 完 ―― |