
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年02月25日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
3 |
18/01 |
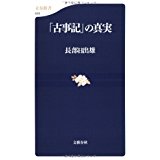 |
「古事記」の真実 |
長部日出雄 |
文春新書 |
◎ |
一章 阿礼は ・稗田阿礼について、宣長は【天ノ 上代のストリップティーズ ・稗田阿礼=男性説を、現代において代表するのは、皇學館大学の第六代学長、 ・その女性説を現在代表するのは西郷信綱で、かの有名な天の岩屋戸の場面で、アメノウズメが神 ・当方が女性説に与したいのも、まずはこの一点にある。 訓読者か暗誦者か ・歌人で、和歌と和語をこよなく愛する天武帝が、やんごとない皇統とともに、無類の価値を秘めた古歌と古語の伝統を、なんとしても守り抜いて後世に伝えなければ……とおもいつめられた。 ・その危機感が、天武帝をして朝廷の公式の修史作業である『日本書記』とはまた別に、新たな制作意図にもとづいて自分のおもい通りに『古事記』を編もうとする個人的な作業へと駆り立てた。 ・そのために欠くことのできない絶好の助手として選ばれたのが、稗田阿礼である。 『古事記』は「作家」の作品 ・複数の学者によって編まれ、「 ・それを裏づけるように、本居宣長は、太安万侶が ・当方は『古事記』を、天武天皇と稗田阿礼の共作と想定する。 ・稗田阿礼を共作者とする理由は、作中のいたるところに、女性しか持ち得ない視点が存在するからである。 声は男で、心は女 ・太安万侶は、愚直なまでに忠実な筆録に徹する朴実な性格の持主であった。 ・天武天皇と稗田阿礼と太安万侶。三者三様の群を抜いた個性と才能と努力の奇跡的な組合せが、わが国の文学史に比類のない傑作を生み出したのだ。 ・なかでも阿礼が果たした役割は、これまで考えられていた以上に大きいといわなければならない。 ・稗田阿礼は日本最初の女性作家としても、決して奇矯の言ではないと考えられるのである。 二章 日本語の父は天武天皇 ・実在が証明された太安万侶を、『古事記』の「編者」と認識している人は、いまも少なくない。 ・そうではない、と考える当方には、動かし難いとおもわれる理由が幾つもあって、その第一は、撰録がふつう考えられないほどの短時間で完成を見たことである。 ・僅か四箇月余りで、天地の開闢を有史以前の遥かな昔から、推古天皇の時代に至るまで、首尾の整った物語に仕立て上げることが、果たして可能であろうか。 ・『日本書記』のほうは、じつに三十九年の歳月を要している。 ・だいたい皇統の正統性の証明を必要な目的のひとつとする史書を編修するにあたり、その基本線に沿った話柄を膨大な資料から取捨選択して一本の筋にまとめる裁量の権限――いい換えれば想像力の自由が、一介の官僚(安万呂)に許されていたなどということが、土台あり得るだろうか。 ・そう考えれば、安万呂が撰録に着手したとき、文字化される以前の「原古事記」はすでにほぼ完成されたかたちで存在していた。 ・すなわち太安万侶のまえに『古事記』の真の編者がいたということである。 ・「編者」どころか、天武天皇と 本文は古代の日本語文 ・みずから秀れた歌人である天武天皇が、いまのままでは圧倒的な漢語文化の流入と影響に押されて、やがて消え去ってしまうかもしれない運命にある古語と古歌を惜しみ、これをなんとか保存して後世に伝える方法はないものか……と苦慮して、さまざまな方法を創案したであろうことは、『古事記』が達成した卓抜な成果から考えて疑うことができない。 歌人大海人と漢詩人大友 ・天照大御神を皇祖神として祀る伊勢神宮を、国家的信仰の対象とする構想は、壬申の乱に勝利を収めて天皇に即位した直後から実行に移された。 ・毎年の収穫後、天皇が皇祖神とともに新穀を食して、王=神としての再生を果たす祭祀を ・天皇の神格化は、天武朝において明確な形となったのである。 ・文字によって記されるまえの和歌は、おそらく旋律を帯びた声楽であったろう。歌人は歌手(シンガー・ソングライター)である。 ・『古事記』のもとになった天武天皇の ・八十八の音節を持つその朗誦を、太安万侶はひとつの例外もないほど文字を厳密に使い分け、どこまでも忠実に筆録することに徹底した。 「日本語」の誕生 ・文字を知る前の近代大和が、いまとは比べものにならないほど、複雑で豊かな陰翳を持つ音声言語の世界であり、壮大な詩的言語の宇宙であったことは、『万葉集』によって今日の目にも歴然としている。 ・天武天皇は、後世に伝えることを主眼とした『古事記』の制作意図からして、とうぜん撰録までを視野にいれていたはずで、その場合、漢字を ・とすれば、稗田阿礼はその方針も詳しく筆録者に伝えたであろう。 ・だからこそ四箇月余での撰録が可能であったと見るのである。 ・その基本的な指示を実現するためのさまざまな工夫に、かれは愚直なまでに細かく気を配って苦心惨憺したのに違いない。 ・その結果として起こったのは、八世紀初頭の当時から二十一世紀の今日までつづく話し言葉(音声言語)と書き言葉(文字言語)の双方の働きをそなえ、公用語として官民の別なく国民全般に通用する和語――すなわち「日本語」の誕生であった。 ・日本人の ・漢字という異国の文字を受け容れることからはじまったこの言語の再創造は、他者を包容することによって進化するわが国の文化の二元的な構造を、何よりも具体的に示す根本の規範といってよいであろう。 ・天武天皇がそれまでになかった文語としての日本語の父であり、難産のすえに健やかな第一子を無事出産した太安万侶が母であるといっても、決して過言ではないと考えられるのである。 三章 天武天皇の 壬申の乱の遠因 ・わが国の古代史における最大の内乱で、結果として「日本」という国家の原型を生み出すもとになった壬申の乱の遠因は、中大兄皇子=天智天皇の近江遷都にあったようにおもわれる。 ・ ・官民双方の反対を押し切って、大津に造営された新京は、壬申の乱における近江朝の敗北によって滅び去った。 近江朝廷は異国 ・蘇我氏と物部氏の二大豪族の対立と抗争がつづくなか、開明派=国際派の蘇我氏が、仏教の受容に賛成したのにたいし、保守派=国粋派の物部氏が反対て、激しい争いが生じたとき、鎌足が出た ・仏教の受入れをめぐる開明と保守の思想的な対立ばかりでなく、もとからあった二大豪族の根強い対抗意識が、いっそう互いの敵意を熾烈なものにしていたものとおもわれる。 ・書記によれば、けっょくは崇仏派の蘇我氏の勝利となる構想のなかで、中臣 ・ところが推古天皇の崩御後、皇嗣をめぐる争いが起こったときには、傍系とおもわれる中臣連 ・神職の家系に生まれながら、かれは長男の ・仏教の興隆に尽くした聖徳太子(厩戸皇子)の在世中に幼少時をすごした鎌足は、崇仏派――というよりは、仏教に象徴される先進国唐の文明に、ひたむきな憧憬の念を寄せる開明派になっていたようだ。 ・かれは十八歳のときに唐から帰朝した僧 ・そのうちかれの胸底には、当時世界最高の大帝国唐に倣って、「新しい国家(天皇を中心とし律令を基本とする中央集権国家)を建設したい」という理想と、そのためにはまず専横を極めている「蘇我入鹿を除かなければ……」という決意が生じてきたものとおもわれる。 ・中大兄皇子と組んだ決起が成功して、新政府が成立したとき、ともに渡来人の子孫で、大陸留学三十二年の ・大化改新の設計図を書いたのは、鎌足であったろうが、そのもとになっていたのは、唐の政治体制であった。 ・三十二歳で古代史上最大の政治改革の道を開いた鎌足は、五十六歳の死の前日、天智天皇から大織冠(後の正一位に相当する最高の位階)を授けられ、藤原の氏姓を賜わった。 神と仏の共存 ・昔の日本では、どの家にもたいてい、神棚と仏壇が両方あった。そのような形を最初に定めたのは、天武天皇であったのだ。 ・和語と漢字の見事な融合。神社と仏寺、神と仏の ・壬申の乱が、「日本」という国家の原型を生み出すもとになった……というのは、そういう意味なのである。 四章 楽劇としての古事記 高い音楽性と演劇性 ・『古事記』は、文学か歴史書か、というのは繰り返し論じられてきた問題だが、ほかにもうひとつどうしても見逃せない重要な性格がある。 それは『古事記』が持つ芸能としての側面である。 総合芸術の台本 ・『古事記』は文学か歴史書かについていえば、その両方であって、なおかつより包括的で多元的な総合芸術の台本として遇せられるべきものである。 五章 森鴎外と津田左右吉の苦衷 民衆と皇室の共生 ・昭和二十一年一月に創刊された「世界」の編集部に寄稿を求められた津田の力作が、「日本歴史の研究に於ける科學的態度」という題で掲載された。 ・軍国主義の跳梁にともない、それと結合して急速に力を獲得し、歴史を政略の具として、思想界に暴威を振るった「固陋の思想」「虚偽迷妄の説」「氣ちがひじみた言論」が、国民を惑わし、起こすべからざる戦争を起こさせ、かつそれを長びかせる一因となった……と明快に解き明かし、皇国史観の学問性を完膚なきまでに否定し去ったのである。 ・だが、つづく第四号に寄せられた「建國の事情と萬世一系の思想」は、編集部の期待に著しく反するものとなった。 ・編集部にとって到底受け容れ難いとおもわれた結論部分の要旨。 ……武力を用いず、政治の実務にかかわらない(上代の)天皇にあったのは、宗教的任務である。民衆のために呪術や祭祀を行ない、神と人の媒介をする巫祝であったことが、天皇を「 日本の昔に天皇崇拝ということはなかったと考えられる。 天皇が神を祭られる、そのことがなにより人であることの明らかなしるしで、呪術や祭祀を行なう地位と任務にたいする人びとの尊敬と感謝が、精神的権威のもとであった。 皇室の永続性は、みずから政治の局に当たられなかったことと、造作された神代史の中心観念である――皇室の祖先を宗教的意義を有する太陽としての日の神とし、天皇をその天つ日つぎとする宗教的、精神的権威から生まれた。 こうして、一方において皇室が永続し、一方において政治の実権をにぎる者がつぎつぎに交替して行くという、世界に類のない二重政体組織の国家形態が、わが国には形づくられた。 政治の実権をにぎらなかったために、外国のような王朝の更迭がなく、時の権力者にたいして、つねに弱者の立場にあられたことが、皇位を永続させた。 ところが(先進の諸外国が開国と通商を求めてきた)十九世紀の世界情勢は、日本に二重政体組織の存続を許さなくなり、政府は朝廷か幕府かのどれかひとつでなければならなくなった。 このとき、天皇親政を唱えて政治の実権をにぎった藩閥は、天皇の権力を強くして、国民の働きを抑えようとする守旧思想にもとづいて憲法を定め、それとともにヨウロッパの一国(プロイセン)に学んだ官僚制度が設けられて、行政の実権が漸次その官僚に移り、幕府と封建諸侯から取り上げた軍事の権がすべてに優越する地位を占めて、天皇と国民のあいだに大きな距離が生まれ、国民は皇室にたいして親愛の情を抱くよりは、その権力と威厳とに服従するように仕向けられた。 神代の物語を歴史的現実のように説いて、万世一系の皇室を戴く国体の尊厳を教えこみ、天皇崇拝の儀礼を学校において行わせたが、それは現代人の知性や精神とは相容れぬものであった。 その結果として、敗戦後の今日に生まれた天皇制廃止論、それと反対に天皇制維持の名のもとに民主主義の実現を阻止しようとする思想傾向は、ともにじつは民主主義をも天皇の本質をも理解せざるものである。 皇室が権力をもって民衆を圧服しようとせられたことは、長い歴史において一度もない。 じっさいの政治上において、本来皇室と民衆は対立するものではなかった。 民主主義によって、国民が国家のすべてを主宰することになれば、皇室はおのずから国民の内にあって国民と一体であられることになる。 具体的にいうと、国民的結合の中心であり国民的精神の生きた「象徴」であられるところに、皇室の存在の意義があることになるのである……。 驚愕する「世界」編集部 ・津田が到着した結論 ――國民みづから國家のすべてを主宰すべき現代においては、皇室は國民の皇室であり、天皇は「われらの天皇」であられる。「われらの天皇」はわれらが愛さねばならぬ。國民の皇室は國民がその懐にそれを抱くべきである。二千年の歴史を國民と共にせられた皇室を、現代の國家、現代の國民生活に適應する地位に置き、それを美しくし、それを安泰にし、さうしてその永久性を確實にするのは、國民みづからの愛の力である。國民は皇室を愛する。愛するところにこそ民主主義の徹底したすがたがある。國民はいかなることをもなし得る能力を具へ、まだそれをなし遂げるところに、民主政治の本質があるからである。さうしてまたかくのごとく皇室を愛することは、おのづから世界に通ずる人道的精神の大なる發露でもある。(一九四六年一月) ・津田が書いてきたのは、これ以上ないほど熱烈な皇室擁護、天皇に対する徹底した親愛の情の表明であった。 ・新憲法が公布される一年近くまえ、津田はすでに「象徴」という言葉を用い、その条文と全く同じ理念を、だれからの押しつけでもなく、日本人みずからの主張としてか書き記していた。 ・いまになって読むと、そのあと長い時間を経るあいだに、国民のなかにほぼ定着した象徴天皇制の実情と、あまりにも具体的に符節を合しているのに、むしろ驚かざるを得ない。 権力と権威の分離は英知 ・わが国の歴史を虚心に見れば、天皇が古代からいつの時代にも一貫して、行政と軍事の実権をすべて一手に握る絶対的な権力者であった等という考えは、明治以降の教育によって作られた官製の歴史観と国家観が、明治以前の時代にまで遡って投影されたところから生じた幻影にすぎないのは、大方の目に明白であるはずだ。 ・遥かに遠い昔から、邦家と民衆の無事と繁栄を祈って、祭祀と儀礼を敬虔に司るのが、わが国の天皇のもっとも伝統的な任務であった。 ・国王が行政と軍事の全権を掌握して臣下を従わせる、ヨーロッパのような絶対王政は、わが国にはある短い一時期をのぞいて、ほとんど存在しなかったといっていい。 ・そこに形としては君主の大権を重んずるプロイセン型の憲法が作られた。 ・天皇以外の人たちのやったことが、天皇の名において絶対化される。世界に類例がなく、わが国の歴史にも前例のない、きわめて特殊な「絶対天皇制」がここに生まれた。 ・わが国古来の伝統に反する権威と権力の一元化によって、天皇は極度に神格化された。 ・二十世紀以降の世界に起こった幾つもの巨大な悲劇(ナチズム、スターリニズム、マオイズムなど)は、共通して権威と権力の一元化、最高権力者の神格化から生じた。 ・いかなる一元論にも、決して絶対的な権力を与えてはならない。 ・権力と権威を切り離した――津田左右吉のいうわが国古来の「世界に類のない二重政体組織」、単一の原理を唯一絶対のものとしない独特の二元論には、人類にとっても英知と呼んでいい貴重な価値が秘められていたのである。 十章 天照大御神の誕生 太陽神は普遍神=至高神 ・津田左右吉は述べた。 「民衆のために呪術や祭祀を行ない、神と人の媒介をする 「これは天皇が神に代わって政治を行なったとか、自信が絶対的な神であったということを意味するのではない」 「天皇が神を祭られる、そのことがなにより人であることの明らかなしるしで、呪術や祭祀を行なう地位と任務にたいする人びとの尊敬と感謝が、精神的権威のもとであった」 「皇室の永続性は、みずからの政治の局に当たられなかったことと、造作された神代史の中心観念である――皇室の祖先を宗教的意義を有する太陽としての ・一万年近くつづいた縄文時代の生活様式に、革命的な変化をもたらす弥生時代は、水稲耕作と金属器の渡来からはじまった。 ・大陸や半島からの新しい文化の流入と、渡来人の増加は、それまでになかった混乱と争いを引き起こさずにはおかない。 ・稲作の進展にともなう領土の保全と拡大が、部族の命運を分ける重大な問題となって、戦いがはじまる。『後漢書倭伝』のいう倭国大乱(2世紀後半)は、そのあらわれであろう。 ・時代はその深部において、混乱と争いを終結させ、さまざまな種族と宗教を統一できる、新しい神と宗教を必要としていた。 ・そうした時期に、自分たちの祖神を、太陽神と同一化させる、という驚くべき着想を具体化し、現実化した部族がいた。 ・祖神と日神を一体化した「天照大御神」という新しい神の発明と、その血筋を引く長を崇めて仕え奉る自分たちは一族である、という主張が、長を天皇たらしめ、部族を天孫族たらしめたのである。 ・つまり、天照大御神の発明が、今日までつづく天皇制の起源であるといってよい。 ・日清と祖神の一体化――簡単には考えられない理想を実現したものは、海の彼方から渡ってきた鏡である。 ・倭人がそれまでに目にしたことがない舶来の鏡を、呪具としてもちいたことが、日神と祖神の同一化を可能にした。 ・原大和朝廷の ・見る人の網膜と脳裡には、唯一神、至高神である太陽を、女性として人格化した「天照大御神」の像が結ばれた。 ・稲作を豊かにする太陽への感謝は、天照大御神への崇敬となった。 ・その信仰は、豊作を祈願するさまざまな儀礼や呪術と結びつき、しだいに複雑でかつ洗練された内容と様式を持つ宗教となって発展する。 ・祖神と日神の同一化は、一族の長を天照大御神の血統を継ぐ天つ日嗣とし、自分たちは同族の天孫族であるという意識を生み、そこから時代を遥かに遠く遡って、天孫降臨の神話が考え出された。 十二章 われわれにとって「カミ」とは何か 「神」と「漢意」 ・いまの日本がおかしくなっているのは、物のあわれを知らない「心なき人」がふえたのと、天地自然にたいする原初的な畏敬と畏怖の念を失ってしまったからなのではあるまいか。 ・そして「心なき人」の増加と、天地自然または目に見えないものにたいする畏敬と畏怖の念の喪失は、おそらく唯物論が骨絡みになった現代の底部において、分かち難く連動しているようにおもわれてならない。 ・目には見えないものへの畏敬と畏怖の念を、ぼくは幼いころ近所の友だちといつも遊び場にしていた神社の境内で育まれたことをおもい出す。 奪われた信仰心 ・そもそも終戦当時、多くの日本人にとっては、「 ・日本人が信じてきたのは、「カミサマ」であり、そのもととなった「 ・それは文字通り「 ・「産土」とは、「ウブ‹産›スとナ‹土・地›との結合したもの。ウブスはウムスと同源」「人の生まれた土地。生地。本居」の意味で、「産土神」とは、「生れた土地の守り神。近世以後、氏神・鎮守の神と同義になる」――。 ・つまり、元々「国家神道」や「皇国史観」とは何の関係もないもので、それまで全否定するのは、自分たちの先祖代代の歴史を根こそぎ抹消するに等しい。 ・だが、敗戦直後の日本人にとって、軍国主義の悪は、余りに明らかであったから、それに協力した神社は勿論、そこからだいぶ遠かった無数の民幣小社にまで ・古くから一軒の家のなかに、神棚と仏壇を両方置いて平気なくらい、世界にも類のない寛容で融通無碍でこだわらない(一神教を信ずる人からすればまるで無原則で無責任な)信仰心を持つ日本人は、「神道指令」を「宗教弾圧」であるとはまるで考えもしなかった。 ・このように日本人が占領軍の「神道指令」を唯唯諾諾と、あるいはそれ以上の過剰反応と拡大解釈で容易に受け入れたことが、他の宗教にたいするキリスト教の優越を信じて疑わないアメリカの原理主義者によって引き起こされたイラク戦争の、いまなお果て知れない惨憺たる悲劇を生み出す重大な一因になったものとおもわれる。 ・「神道指令」は、日本人の草の根の信仰心――それは人間にとってきわめて大切なものだ――を根こそぎにした。 ・いまや都市と地方の格差拡大が大問題になっているが、ひとつには「生れた土地の守り神」で日日の暮しに生き生きとした活力をもたらしてくれる無数の、目には見えない多元的な産土神をみずから切り捨て、なによりも効率を至上の価値とする「利潤」という名の新たな唯一絶対神に、一元的に集中して帰依したことに端を発しているので、それはまさに「罰当り」といっていい忘恩の背信行為であった。 ・日本人は、この列島でもっとも古くからそれによって守られてきた八百万の神への信仰を捨て去り、忘れ去ってしまったのである。 ・全国の民幣小社と鎮守の森が、見る者に敬虔な祈りの心を呼び起こす美しさと豊かさを昔以上に復活させないかぎり、都市と地方の格差は解消せず、日本の蘇りはあり得ない。 救国の処方箋 ・太陽を ・自分たちを生かしてくれる天地自然を崇拝し、守ってくれるなにものかに五穀豊穣や家内安全や商売繁盛を祈願し、生きる営みのすべてを「カミサマ」の御心に適う「天職」と考え、食卓に向かうたび「頂きます」と日日の糧を天智の恵みとして有り難く頂戴し、暮しに歌と笑いを重んじて、楽しみながら毎日を元気にすごす。 ・そんな風に生きて行く人びとがふえれば、かならずや日本人の最良の資質が、世界に向かって示されるに違いない。 ・これが日本最古の古典『古事記』に学んだぼくの考える――救国の処方箋である。 ―― 完 ―― |