
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年04月20日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
31 |
18/04 |
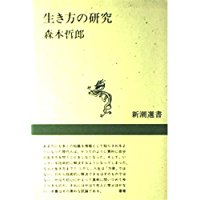 |
生き方の研究 |
森本哲郎 |
新潮選書 |
☆ |
序 生き方の探求について ・文学作品というものは、それを読む年代、動機、こちらの心的な状況によって、さまざまに姿を変えるものである。 人生の短さについて――セネカ ・人生は短いのではない、とセネカは書いている。「われわれがそれを短くしているのだ」と。 ・「われわれは人生に不足しているのではなく(人生を)濫費しているのである」 ・「人生は使い方を知れば長い」 ・人びとは、まるで「永久に生きられるかのように生きている」というのである。 ・彼は「毎日毎日を最後の一日」のように思いつつ生きることをすすめる。 ・それは明日を頼りにして今日を失わないことである。 放浪について――ロビンソン・クルーソー ・孤独になれる能力、そして魂を内面へ向わせる努力、それが人間の幸福を決めるのだ。 迷いについて――陶淵明 ・心が自由であろうとすれば生活は苦しくなり、暮しを楽にしようと思えば精神は束縛される、という二律背反が人の世の常だ。 ・人生は二物を与えてくれはしないのだ。 生涯の最も大切な時期について――ファーブル ・人間の生き方は三歳からせいぜい六、七歳までのあいだにきまってしまうのではないかと私は思う。 ・どんな人もこの期間に自分の全生涯の “下書き” をし、 "予告編" を無意識のうちにつくりあげるのだ。 ・しかし、人生のなかでいちばん大切なこの時期は、当人にとってはまったく意のままにならない、いわば、 ・ただ置かれた環境に甘んじ、与えられた条件に忍従する以外にない、そういう時期なのだ。 ・だから人生とは、まさしく運命というほかない。それを考えると、子供に対する大人の責任がいかに大きいか、そら恐ろしくなる。 ・にもかかわらず、大人たちはこの時期の子供たちの環境にさして関心を払わず、教育といえば、もっぱら小学校、中学、高校といった義務教育機関での教化を、ただ技術的に論議しているにすぎない。 ・そして、人間にとって、何より大事な幼年期は無反省のままに放置されている。荒廃というなら、教育の荒廃の根源はそこにある。 ・子どもを ・しかし、大人たちがやたらに ・三歳から六歳ごろまでの子供にとって、何よりも大切なのは、さしでがましい大人の干渉を受けずに、自分で自分の能力を開発するということである。 ・つまり、自分で遊びを工夫し、あれこれ思案し、探索し、存分に好奇心をふくらませることだ。 ・そうした自発性が現代では教育技術によって、ああ、なんと無残に圧殺されてしまっていることだろう。 ・親たちは、一刻も子供を放っておかない。教師も子供から目を放すことがない。そして、その合間にはテレビが子どもたちにとってこの上なく貴重な "退屈の時間" をごっそりと奪い取っている。 ・こうして、現代の子供たちは、およそ ・だが、退屈することのできる自由な時間、あり余った時間こそが、子供たちを様々なものへの探索へ向わせ、好奇心を育て、創意工夫の才を芽生えさせるのである。 ・その貴重な時間を取りあげられ、ただやたらに大人から与えられたものに ・少なくとも、私たちの子供のころには、いやというほど退屈する時間があった。 ・大人たちはほとんどかまってくれなかった。大人の会話などに口をさしはさもうものなら、「子供のくせに」「あっちへ行け」と、こっぴどく叱られ、追い払われるのが関の山だった。 ・子供には子供の世界があり、親には親の領分があった。 ・大人の領域には侵入できなかったかわりに、子供たちには大人の干渉を受けぬ自由な宇宙があったのだ。 ・だから子供たちは思う存分、好奇の目を輝かせながら、その宇宙を飛び回ることができた。 ・そして、それが子供たちにとって、自分の人生の " ・巣立つための飛ぶ練習はこの時期に充分に行なわれたのである。 ・このような準備をたっぷり持たないと、子供は教育を受ける条件を身につけることができない。 ・教育とは、いうまでもなく教育 ・いくら教育技術が進んでも、教育される側の条件がそろっていなければ、それこそ「馬の耳に念仏」であろう。 ・だが、現代の教育論議はあまりにも教育する方法ばかりにとらわれており、かんじんな教育される条件を等閑に付している。 ・ところが、教育の成果とは、教育するほうよりも、むしろ教育される資格にかかっているのだ。 ・大切なのは、いかにすぐれた教育をほどこすか、より、どれほどうまく教育されるか、そのされ方にあるといってもいい。 ・この出発点が現代ほど無視されている時代はかつてなかった。 ・学問とは、読んで字のごとく、問うことを学ぶことである。 ・幼年期、それにつづく少年期が人生でいちばん大切というのは、この時期こそ、心から問いを発する、そして、問うことを自分で学ぶ年齢だからである。 ・この期間に問うことを学びそこなうと、問いの情熱はもう一生戻ってこない。 ・だが、情報化社会といわれる現代の子供たちには、問う前にすでに答がある。答だけが無数に与えられている。子供たちは答だけをきかされて育つのだ。そんな環境のなかで、どうして子供たちは問うことを学べようか。 規則正しい生活について――カント ・私たちが往々にしてそんな生活から逃れたいと思っている「規則正しい」生き方が、じつは彼の思想を育てたのだと考え直すとき、私はあらためて、自分で自分を律して生き抜く生活というものが、いかに強靭な意志の力を必要とするか、つくづく思い知らされるのである。 男の純情について――在原業平 ・私は日本人の「辞世」という "儀式" が、いかに詩的であるか、あらためて心打たれざるを得ない。 ・飛ブ鳥アトヲ濁サズというが、日本人は美しくあの世へ旅立つのである。 意志と情熱について――シュリーマン ・シュリーマンは、トロイアの遺跡を掘りだした。 ・この人生では、どんなことでもできるのだ、ということを実証した人間、それがシュリーマンだったといってもいい。ただし、やろうと思えば、である。 ・シュリーマンを支えつづけたのは、その「やる気」であった。 ・誰にだって「やる気」はある。だが、それを生涯にわたって、どんな境遇にあっても、いかなる不幸が見舞っても、断乎として抱きつづけることは、けっして容易なことではない。 ・シュリーマンの偉大さは、死ぬまで、それを手放さなかったことだ。その激しいエネルギーは、まさしく「情熱」という以外にない。 ・人間を偉大にするのは、往々、偉大への意志以外の何ものでもないことがある。 金銭について――井原西鶴 ・ひところ、「昭和元禄」という言葉が大いに流行った。 ・「神武以来」とも評されたあの高度成長期の日本の世情は、たしかに元禄時代に酷似している。 ・ということは、日本人の性格は、江戸時代もいまも、さして変っていないということであろう。 ・あるいは、現代の日本人の肖像は、江戸時代、なかんずく元禄期に形づくられたと見るべきかもしれない。 ・そして、その性格とは、日本人の金銭に対する独特な態度である。 ・独特な態度とは何か。一言でいうならば、金銭に対するあくことのない執念、と同時に、金銭に対する徹底的な蔑視、このふたつが併存しているということだ。 ・その最もいい例は、「可愛さあまって憎さ百倍」というように、愛情がとつぜん憎悪に変るといった愛憎の変化であろう。それがそのまま、金銭に対しても投影されるのだ。 ・元禄を代表する二人の人物がその両極を担っている。一人は芭蕉、もうひとりは西鶴である。 悟りについて――正岡子規 ・「死ハ恐ロシクナイノデアルガ ―― 完 ―― |