
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年05月16日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
33 |
18/04 |
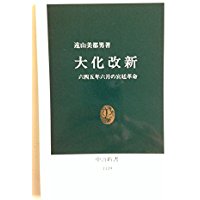 |
大化改新 |
遠山美都男 |
中公新書 |
◎ |
Ⅰ章 国家形成と王権継承 一、首長・王権・王権継承 王権と首長 ・王とは、その原初的形態において特定の集団を「代表」する首長であった。 ・農耕社会を形成した日本列島内には無数の集団が発生し、各集団を「代表」する首長も多数存在した。 ・集団相互の利害を調停する必要から、一定の領域内で相対的に優位を占める集団の首長が、諸集団の上位に立ち、諸集団を「代表」していくことになる。 ・日本列島全体を「代表」する最高首長の地位は、諸地域を「代表」するこうした首長相互の利害の統合によって誕生する。 ・これら多数の首長たちのうち、一定以上の領域を「代表」する者は、それ以下の首長たちとは明らかに別格の固有の称号(首長の地位や能力の称賛に由来するもの)でよばていたであろう。 ・だが、日本列島内部の諸集団を単独で「代表」する最高首長、すなわち「倭国王」の地位は、中国王朝に対する従属関係という強烈な対外的契機によって、はじめて誕生することになった。 ・首長が、外部との交渉を独占することで配下の集団を支配しえた。 ・我が国を「代表」する最高首長としての王は、中国皇帝への臣従関係、すなわち後漢との冊封関係の中から生まれた。 ・西暦五七年、光武帝より印綬を下賜された「倭奴国王」や、一〇七年、安帝に「生口百六十人」を献上した「倭国王師升等」がそれである。 三、二つの大王家――倭の五王の王位継承 「倭国王」、再生 ・三世紀の末から四世紀初頭にかけて、各地の政治的統合が結集して、前方後円墳をシンボルとした汎列島規模の連合体を結成した。 ・この連合体の最高首長は、名実ともに日本列島全体を「代表」する存在であり、五世紀に至って中国南朝の宋の冊封関係に入ったことにより、「倭国王」として承認されることになる。 ・彼はもともと、のちの大和国の東南部を本拠とした首長で、大和を中心とする地域の政治的統合の最高首長であった。 ・彼を中核に日本列島は「統一」された。 ・四世紀に入り、各地の首長たちは、配下の農民に対する自己の地位を強化するのに鉄製の武器や農具を欲したので、その需要を満たす鉄資源の獲得のために、大和の最高首長は彼ら諸首長を動員・組織して朝鮮半島南部への軍事的進出を開始した。 ・軍事的威圧を背景に入手された鉄資源は、最高首長の手を通じて列島内の諸首長に分配された。この分配権こそ、大和の最高首長の地位と、彼を中心とした連合体の結束を強める要であった。 ・加えて朝鮮半島南部への侵攻は、高句麗との軍事的対立を引き起こすとともに、高句麗王の隷属下にあった百済王・新羅王との間に正式な外交関係を成立させた。 ・さらに五世紀に入り、朝鮮南部に対する軍事支配権の承認をめぐって中国南朝の宋との間に本格的な交渉がはじまったので、列島を「代表」して、これらの王や皇帝と交渉する外交的手腕も最高首長の選出条件として重視されるようになった。 ・五世紀後半の倭王武の時代になると、武は、南朝宋の皇帝の権威と軍事力を背景に、各地に割拠していたかつての政治的統合の内部にまで、その支配力をつよめていくことになる。 ・ここに倭王の支配領域が「天下」として画定され、倭王の国内的な称号としての「治天下大王」号が生れた。 王統譜を編み上げる ・『宋書』倭国伝には、いわゆる倭の五王(讃・珍・済・興・武)が南朝の宋に代々朝貢を果たしたことが記されている。 ・この五人の倭王たちこそ、ほぼ列島全体をおおう連合体の最高首長であり、もと大和東南部を本拠とした首長一族の子孫であったと考えられる。 六、大兄と女帝と 大兄と大后の相互補完機能 ・大兄と大后(女帝)は、世代内継承につきまとう紛争や矛盾を未然に緩和・抑止するという役割を負う存在であった。 ・大兄の制度は、王権継承を期待された世代に属する皇子たちの中において、有力な王権継承候補をあらかじめ幾人かに限定しておく機能があった。 ・大兄の地位は、世代内継承がはじまった当初から定立されていた。 ・次に、大兄として特定された有力な王権継承候補者たちの中から、人を指名すれば紛争の激化が不可避の場合、大后が女帝として即位することによって紛争を緩和し、事態の鎮静下をもたらすことが期待されたのであった。 ・大后の地位は、世代内継承が始まって間もなくして定められたものである。 ・大兄によって、あらかじめ王権継承候補を何人かに絞り込み、そして、彼ら相互の競合が収拾のつかない紛争に発展する危険性がある時には、「第三の立場」にある大后の登極により危機を未然に回避する。こうして世代内継承は、円滑かつ安定的に行なわれることになる。 ・大兄と大后が、決して後世の皇太子や皇后と同一視できるような地位ではなく、六、七世紀の王権継承固有の課題を解決するのに不可欠の制度・地位であった。 七、世代内継承、その後 女帝、再び ・六五四年、孝徳天皇が難波宮に没すると、皇極女帝が斉明天皇として再び即位(重祚)した。 ・譲位と重祚は、七世紀の女帝の基本的属性と関係があるようである。 ・皇極重祚の理由としては、まず支配層の多くが、なお欽明天皇の曾孫の世代に王権継承の正当性をみとめていたということが考えられる。 ・それに加えて、孝徳死後の段階において王権継承資格のある皇子として、中大兄皇子、 ・いずれかを次期大王に決定すれば紛争の発生が必至と見られたので、王権継承の紛争を未然に防ぐために、女帝という切り札が再び用いられたのであろう。 ・「乙巳の変」は女帝の譲位問題を中心に発生した事件と見られる。 ・唯一の王権継承予定者を確定しておく皇太子制という装置をもたないこの段階の支配層にとって、一口に譲位といっても、それは、一体いつ、何を契機に、どのような手段で行なうのかという点で、解決しなければならない問題を多数内包しており、非常に困難を伴うものであった。 「吉野盟約」以後 ・六七二年の壬申の乱を経て、列島各地の首長層配下の農民たちを彼らが住んでいる場所で把握し、それを領域的に編成することが格段にすすんだ。 ・その結果、大王に対する貢納・奉仕の内容ごとに農民を把握するシステムであった伴造・部民制が完全に廃棄され、天皇の地位も、農民の領域的編成の頂点に位置し、それを一括して把握する存在となった。 ・天皇に集中された権力の他者への譲渡が比較的容易となり、天皇生存中に次期天皇をあらかじめ確定しておくことが可能となってきた。 ・ここに、皇太子制が成立する前提がようやくできあがったのである。 Ⅱ章 王権と藤原氏の歴史 二、「黒作懸佩刀」――王権と藤原不比等 藤原氏の誕生 ・葛城の血を継承した稲目が世襲王権の確立に立ち会い、世襲王権の円滑な再生産を補助する役回りを独占して、蘇我氏という新しい特別な氏族を興した。 ・同様に、王権との身内的な関係を独占する特別な氏族としての藤原氏が成立したのは、鎌足の死後、壬申の乱を経た天武朝以降、蘇我の血を継承した不比等一代における出来事であった。 Ⅳ章 検証「乙巳の変」――発生と展開 一、皇后臨朝、心に必ずしも安からず――事件の起点=山背大兄王の殺害 なぜ女帝統治が心に不安なのか ・女帝については、当時の王権の世代内継承の矛盾を未然に抑止するための一種の「安全弁」として登場した存在であった。 ・我が国最初の女帝、推古天皇が即位におよんだのは、大王を出す世代が欽明の子の世代からその孫の世代に移行する時期に当たり、欽明の孫の世代に押坂彦人大兄皇子・竹田皇子・厩戸皇子という有力候補がおり、いずれとも特定しがたい状況があったからであった。 ・三皇子を収拾のつきがたい紛争の中で失うという愚を避けるため、ひとまず欽明の子の世代の王族として、推古の即位となったのである。 ・女帝の存在は、同一世代に属する王権継承候補の対立、あるいは鼎立という世代内継承を追及すれば、避けることのできない混乱を未然に防ぐ役割を負うものであった。 ・だが、推古の在位は予想外に長期化した。 ・大王が終身の地位であるという慣行に規定され、女帝の退位の機会と条件について、支配層間で十分な合意がられないあいだに、欽明孫である三皇子は推古より先に相次いで早逝してしまった。 ・果てしのない王権継承の争いから皇子たちを守り、王権継承候補たちをプールする「安全装置」であったはずの女帝が、皇子たちの即位の機会を奪ってしまったのである。 二、臣、罪を知らず――入鹿暗殺 三韓の進調は本当にあったのか ・「調(ミツキ)を ・倭国の支配層は、朝鮮半島の諸国を倭国に朝貢する「蕃国」と見なし、朝鮮諸国に対しても、この服属儀礼を伴った調の献上を強制していたのである。 ・だが、百済・新羅はともかく、高句麗を倭国の朝貢国に設定しようとする企ては、倭国の支配層の一方的な押し付けに終わったようである。 ・「三韓」という語自体、朝鮮半島が日本の天皇に朝貢する「蕃国」であるという支配層の国威認識を背景に、律令制国家の成立期に作り出されたものであった。 結章 「乙巳の変」のあとにくるもの――古代王権最大の分水嶺 一、「乙巳の変」の展開と結末 クーデター前夜 ・六四一年、舒明天皇が亡くなった。 ・この段階で王権継承資格をもつ皇子が複数存在し、いずれか一人を特定すれば混乱・紛争が避けがたいと判断されたため、舒明の大后だった皇極女帝の即位となった。 ・史上二人目の女帝皇極には、その即位早々から大きな課題が課せられていた。 ・すなわち、推古の予想外の長期在位の結果、有力な王権継承候補の皇子たちがすべて死に絶えてしまった反省から、女帝の在位を長期化させてはならないということであり、複数の王権継承候補の中から、いずれか一人を特定できる客観的状況を早急に作り出し、何らかの機会をとらえて、しかるべき方法で譲位を実現するということであった。 ・皇極即位の時点で、王権継承候補としては次の皇子たちがいた。 ・一人は厩戸皇子の長子で山背大兄王。二人目は皇極女帝の同母弟、軽皇子である。三人目は舒明の皇子、古人大兄皇子。四人目、古人大兄の異母弟、中大兄皇子。 ・皇極女帝の在位二年目の六四三年の末、山背大兄王がその斑鳩宮を急襲され、一族ともども自殺して果てたのである。 ・王を襲ったのは、軽皇子を次期大王に押す一派と、古人大兄皇子を次期大王にと策す一派であった。後者の中心人物こそ、蘇我入鹿であった。 ・彼らは、それぞれの支持する候補の即位を阻む「共通の敵」として、山背大兄とその一族の打倒・粛清にふみきったのである。 ・事件後、次に予想される事態は、共同して山背大兄を倒した両派がどのように互いの利害・主張を調整しうるのか、ということであった。 ・結局、先制打を放ったのは、軽皇子を擁立する一派だった。 六月十二日 ・六四五年六月十二日早暁、古人大兄と蘇我入鹿は、突然、皇極女帝から召集を受けた。 ・飛鳥板葺宮の「大殿」まで参入せよという。 ・二人が着座して間もなく、突然、数名の刺客が殺到、言葉を発する間もなく入鹿は斬殺された。 ・古人大兄は、刺客たちの凶刃を辛うじて避け、そのまま自身の宮のある大市へと一目散に逃げ帰った。 ・古人大兄を取り逃がしたものの、入鹿の殺害に成功したクーデター派は、当初の予定どおり、皇極女帝と軽皇子を伴い、板葺宮を出て飛鳥寺に入り、そこを本陣と定めた。 ・のこされた蘇我蝦夷との対決と同時に、甘橿丘の蝦夷と大市宮の古人大兄との連絡を遮断するためである。 六月十三日 ・翌六月十三日、古人大兄皇子は出家。 ・昨日以来の一連の古人大兄の行動に絶望の思いをつよくしていた蝦夷は、古人大兄の決定的な離反を聞き、ほどなく一族を一所に召集、静かに最後の時がきたことを告げた。 ・蝦夷らは自決を前に、本宗家の財宝類に火を放った。 六月十四日 ・翌十四日早朝。皇極女帝や軽皇子は飛鳥板葺宮に戻り、当初の予定どおり、そこで軽皇子の即位礼を執り行なった。 「乙巳の変」の国際的契機 ・「乙巳の変」とよばれるこのクーデターが、六四五年に発生したことについては、皇極朝固有の事情ばかりでなく、それを刺激したところの当時の東アジアの情勢を軽視することはできない。 ・唐と高句麗の対立は両国の全面戦争の危機をはらみ、開戦前夜の国際的緊張は、朝鮮三国で頻発する政変と内乱となってあらわれた。 ・そうした激変する国際情勢に対応し、国内の支配層を強力に結集できる人格・資質をそなえた大王の擁立は支配層全体の念願するところであった。 ・「皇后臨朝、心に必ずしも安からず」という認識は、早晩、譲位が予定されている女帝は不安定極まりない存在であるということだけでなく、早急に譲位を行ない、しかるべき人物を大王に立てることが、東アジアの動乱の中で支配層全体の利益を守りぬく唯一の道である、という判断があったことを端的に物語っている。 ・唐・高句麗間に戦端がひらかれたのは、六四五年の四月のことであった。 ・「乙巳の変」は、唐・高句麗が全面戦争に突入して間もない時期に発生した。国際的緊張が、クーデターの決行を促進したことは間違いない。 国政改革の青写真の存否 ・「乙巳の変」とは、軽皇子を次期大王にと推す一派が、武力行使によってその障害物を除去し、皇極から孝徳へという我が国史上最初の計画的な生前譲位を断行しようというものであった。 ―― 完 ―― |