
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年06月19日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
35 |
18/05 |
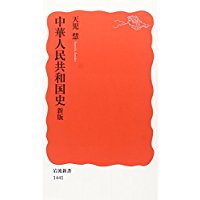 |
中華人民共和国史 |
天児 慧 |
岩波新書 |
◎ |
第一章 人民共和国前史と新国家の誕生 1 ウェスタン・インパクトから辛亥革命・国民革命 清朝末期の苦渋 ・一九世紀中葉以降を ・このような状況は唯一中国に限るものではなかった。おそらく、一九世紀後半は、日本を含む大部分のアジア諸国において、国内体制が様々な矛盾をはらみ、これらを増幅させ、そうした中で侵攻してきた欧米列強の「砲艦」に強烈な揺さぶりをかけられ、あるものは「植民地化」を強いられ、あるものは懸命に「泥沼」からの脱却を試みていた。 ・「ウェスタン・インパクト」(西洋の衝撃)これがアジアにおける近現代史の始まりを決定づけたのである。 アヘン戦争から義和団事件へ ・清朝体制に衝撃を与えた最初の大事件はアヘン戦争(一八四〇~四二年)であった。 ・対外的には、これによって清朝が固辞し続けていた「 ・国内では清朝の旧体制を揺さぶる新たな勢力台頭の重要な契機にもなった。 ・一八五〇年、 ・さらには社会革命とも言える「アヘン禁止」「 ・太平天国は、やがて深刻な内部抗争、 ・しかしそこには以後の中国史のダイナミックスを生み出す二つの核心的要素が含まれていた。 ・第一は平等主義、反植民地民族主義を主な内容とする「革命」の要素であり、第二は近代的国家、近代的社会に踏み込もうとする「近代化」の要素であった。 ・前者は二〇世紀に入って中国革命の主流となる孫文革命、さらには毛沢東革命に少なからぬ影響を与えている。 ・後者は、とくに運動の鎮圧者であった曾国藩・李鴻章らによって軍事・造船・機械産業の面で近代化が取り組まれた。 ・その考えは中華の伝統思想を価値・体制の支柱としつつ、西洋の科学・技術を応用するという「中体西用」論に基づいた近代化であり、「洋務運動」と呼ばれた。 ・しかし日清戦争(九四年~九五年)によって、洋務のシンボル「北洋艦隊」が壊滅し、この運動は挫折した。 ・この結果、清朝を擁護しながらも西洋の制度・思想を積極的に取り込み、中国を近代国家に変えるべきと説く「変法自強」の主張が ・しかしこの改革も、西太后ら保守派の反撃に会い一〇〇日あまりで失敗に終わった(百日維新)。 ・ほぼ同じ時期、山東省において反キリスト教運動として始まり、やがて欧米列強や日本の中国分割に抵抗した農民反乱・義和団事件が起こった。 ・それは原初的ではあるが明確に反帝ナショナリズムの色彩を強く有し、広く共感を勝ち取り華北一帯に広がった。 ・しかし、列強八ヵ国連合軍は北京を占領し(一九〇一年)、義和団運動も鎮定された。 孫文と辛亥革命 ・洋務から変法自強へと続く改良的な近代化の試みも、太平天国運動や義和団運動にみられるある種革命的な民衆運動も、出口の見えないまま「挫折」を余儀なくされた。 ・こうした中で興中会、光復会、華興会など反清朝的な秘密組織を糾合し、東京において一九〇五年統一的な組織を結成した人物がいた。 ・その人物こそ後に「中国革命の父」「国父」と呼ばれる孫文であり、その組織こそ後の中国国民党の源とも言える中国同盟会であった。 ・孫文は政治目標として民族・民権・民生の実現を図る「三民主義」を掲げ、さらに「排満興漢」をスローガンに清朝の打倒、共和国の樹立を図った。 ・やがて一九一一年一〇月、武昌に端を発した辛亥革命が勃発し各地の省が独立を宣言し、中華民国臨時政府が結成され、孫文が臨時大総統となった。 ・清朝により鎮圧の命を受けた実力者・ ・辛亥革命は、たしかに従来の中華帝国とは異なった共和国「中華民国」を生み出した。 ・一九一二年、孫文の考えを色濃く反映した臨時約法(憲法)が制定され、近代的な国家建設の道を歩むかに見えた。 ・しかし、実際には袁世凱を代表とする北洋軍閥と孫文ら革命派との妥協、反清で結集した各地方のエリートたちの野合によって成立したものであった。 ・孫文ら国民党指導者は大総統の地位を袁世凱に譲る代わりに、議会主導型の国家体制を構想し彼の独裁を牽制しようとした。 ・これに対して袁は、やがて議会解散など弾圧に乗りだし、さらには北洋軍閥の軍事力を背景に強力な中央集権化を進め、一五年には共和政を廃止、帝政を復活させ、自ら中華帝国皇帝となった。 ・しかし、直ちに反袁、反帝政の護国運動が各地で展開され、一六年袁は失意のうちに病死し帝政は廃止された。 ・袁の死後、中国は統一に向かうどころか逆に遠心力が働き渾沌とした状況が形成された。まさに「軍閥割拠」とも言われる状況であった。 第一次大戦とロシア革命 ・国際関係からこの時期を見るなら、「火薬庫」バルカン半島から始まる第一次世界大戦はヨーロッパ全土に拡大し、列強の関心は非欧米世界から離れていた。 ・軍事力を高め朝鮮を拠点にした日本は、この間隙を利用し中国大陸に触手を伸ばした。一五年に北京政府に突きつけた「対華二一ヵ条要求」、連合国への支援を口実に行われた山東省におけるドイツ権益・租界への攻撃などがそれである。 ・日本はこの頃から中国にとって最大の脅威国となり始めていた。 ・他方、ロシアでは、一九一七年に「ロシア革命」が勃発し、社会主義ソビエトが樹立された。 ・一九一〇年代後半から二〇年代にかけて、この二つの国際的な動きに中国は敏感に反応している。 ・沿岸各都市では反日気運が高まり、同時に北京を中心に始まった新文化運動=五・四文化革命は、次第に社会主義運動の色を強めた。 ・こうした状況下で一九一九年第一次世界大戦が終結しヴェルサイユ講和条約が結ばれた。 ・しかし、ここで中国におけるドイツの利権が中国に返還されず、日本に譲渡されることが承認された。 ・これに憤慨した北京の学生らの抗議に端を発し、「五・四運動」がと呼ばれる全国規模の反日愛国のナショナリズム運動が沸き起こった。これらは従来の変革運動を一段と急進化させた。 ・新文化運動の基本的な主張は「デモクラシーとサイエンス」であったが、これは伝統的な中華思想、儒教を全面的に否定しようとしたものであった。 ・さらにロシア革命以降、北京、天津、上海、広州など大都市で社会主義・共産主義に共感する青年が急速に増大していった。 ・一九二一年七月、コミンテルンの強い影響の下で中国共産党が結成され、上海において第一回の党大会が回刺された。 ・しかし当時の党員はわずかに五七名、党大会に参加した代表者も一三名という小規模な非合法組織でしかなかった。 ・思想的にも無政府主義から改良主義に至る様々な傾向を含んでいたが、コミンテルンの指示によって当時の最大政党・国民党との協力・合作を追及した。 国共合作から北伐へ ・国民党も混迷を続けたがロシア革命以降、徐々にソ連に接近し、二四年第一回全国大会が開かれ、コミンテルンの援助を受けながら改組に踏み切り、「連ソ、容共、労農扶助」「反帝、反封建」を鮮明に掲げた。 ・その下で、少数の共産党員は、同時に国民党の党籍も有して国民革命に参加するという第一次国共合作が正式に成立した。 ・この頃から、都市における労働運動、農村における農民運動が次第に広範に展開されるようになり、国民党・共産党の指導下で不平等条約撤廃、租界回収、主権回復、全国統一を目指した国民革命は一大ナショナリズム運動となっていったのである。 ・しかし、共産党と国民党の蜜月は長くは続かなかった。 ・二五年三月、偉大な領袖・孫文が死去し国民党は左派と右派が主導権を争い、やがて軍を背景に右派の蒋介石が実権を握った。 ・二六年七月、孫文の遺訓を継ぎ「北伐」が宣言されると蒋介石は国民革命軍総司令官に就き、北京に向けて北上を開始した。その途上上海で二七年四月、共産党を徹底弾圧・排除するいわゆる「四・一二クーデター」を起こした。 ・共産党はそれでも汪兆銘ら国民党左派との合作をもとめたが、まもなくそれも分裂し、勢力を大きく後退させながら農村の辺境地に拠点を移し国民党との全面対決の道を歩むこととなった。 ・蒋介石に率いられた国民革命軍はさらに北上し、翌二八年四月北京を占領し北伐を完成させ、一〇月に蒋は南京国民政府主席に就任し、形の上では全国統一を成し遂げた。 2 国際緊張の高まりと国共対決 日本の大陸侵略 ・しかしこの時期、第一次世界大戦後の一時の平和・国際協調を実現したワシントン体制は終わりを告げた。 ・一九二九年の世界恐慌前夜から、国際社会は不況と混乱を強め、ドイツでヒトラーのナチズム、イタリアでムッソリーニのファシズム、日本で軍部勢力が台頭し、英、米、仏などを中心とする既存の国際秩序に敢えて挑戦する空気が強まった。 ・こうした中で、日本は金融恐慌・不況に苦しみ、中国における勢力拡大を加速した。 ・すなわち幣原喜重郎の協調外交から田中義一の強硬外交に転じ、統一中国の出現を牽制した二八年の山東出兵、張作霖爆殺事件から三一年の満州事変へと、中国大陸への侵略を強めていた。 ・さらに中国国内では、各地の反蒋勢力は依然活発な動きを見せた。 ・こうした中で蔣介石は「安内攘外」(まず内憂を解決して外患‹=日本›にあたる)政策をとり、二九、三〇年には反蔣勢力を攻撃し、事実上の勢力下においた。 ・蔣介石は国内安定のため、さらに江西、湖南、広東の農村一帯で、勢力を拡張し始めていた共産党勢力の掃討戦を展開した。 毛沢東の農村戦略 ・三一年一一月、中共は江西省 長征・西安事件 ・三〇年代に入って日本軍の侵略は一段と加速した。三一年九月の「満州事変」、三二年三月のいわゆる「満州国」の樹立、続く熱河、河北への侵攻と勢力拡大は留まるところを知らなかった。 ・そうした日本の動向にもかかわらず、蔣介石にとっては依然「内憂」掃討が当面最優先の懸案事項であった。 ・三四年、蔣介石は自ら最高司令官となり一〇〇万の軍を動員し、第五次共産党包囲討伐に乗りだした。 ・この時、毛は「留ソ派」と呼ばれる主流派との党内抗争に敗れ政治・軍事の指揮権を失っていた。 ・圧倒的な国民党軍の一歩一歩包囲を取り込んでいく作戦に中共は苦しみ、ついに三四年秋江西省の中央根拠地を放棄し、西に向かってあてのない脱出の旅を余儀なくされた。 ・非戦闘員を含む一五万人余りの大移動は、戦闘と飢えと厳しい気候に苛まれながら、一年余り続いた一万二五〇〇キロにも及ぶ旅で、陝西省山岳地にたどり着いた。その時わずか八〇〇〇名足らずであった。 ・後に驚嘆と畏敬の念で語られ神話化されたこの大移動こそ「長征」と呼ばれるものである。 ・この長征途上三五年一月、貴州省の ・一九三五年七月、コミンテルン第七回大会で決議された「反ファシズム国際統一戦線」の結成の呼びかけに呼応し、中共は内戦停止・一致抗日を呼びかけた。 ・同年一二月、河北へのさらなる侵攻に対し、北京の学生・青年を中心に大規模な抗議行動「一二・九運動」が発生した。 ・国共が和解し、中華全民族が一致して日本に対抗しようとする声は知識人・資本家・労働者・市民・婦人各界に広範に広がり、自発的な抗日団体も続々と組織され、各界の抗日救国運動へ発展していった。 ・にもかかわらず執拗に中共攻撃の手を緩めない蔣介石に国民党内部からも異議の申し立てが起こった。 ・三六年一二月、「共匪掃討」の現地視察のため西安を訪れた蔣を東北出身の将軍張学良らが軟禁し、一致抗日を迫った「西安事件」である。 ・蔣は中共との和解を「条件」に釈放され、三七年七月の盧溝橋事件勃発後まもなく、正式に内戦が停止された。 3 日中戦争と国共内戦、そして人民中国の誕生 抗日戦と「持久戦論」 ・日中戦争は盧溝橋事件以後、全面戦争の様相を呈し、前段階では日本軍は破竹の勢いで進撃し、三八年一〇月末の広州、武漢占領によってわずか一年で沿海の主要都市と鉄道沿線をほぼ制圧した。 ・しかし広範で執拗な民族抵抗は次第に日本軍の勢いを鈍らせ、やがて戦線は対峙・膠着の状態に陥った。 ・それでも日本は全体の戦線を東南アジアさらには南太平洋へと拡大し、戦力を拡散させた。 ・その結果中国大陸でも主要都市部の占領にとどまり、広範な農村では抗日ゲリラに悩まされ不安定の様相を強めた。 ・中国側も必ずしも、民族的に一致団結し抗日にあたったというわけではなかった。 ・蔣介石の中共不信は決して緩和されることなく、勢力を再び拡大し始めた中共に対し、四一~四三年にかけて対日抗戦にも劣らない精力をかけて攻撃を行うようになった。 ・中共は国民党の厳しい封鎖攻撃の中で戦力の後退を余儀なくされながらも、大生産運動、 ・毛沢東は日中戦争開始後まもなく、この戦争の性格、戦争を取り巻く国内外の情勢、敵・友の戦力比較などを分析し、敵の侵攻、味方の防御の段階(積極的防御)、敵と味方の前線の膠着の段階(対峙)、敵の疲弊、味方の反撃の段階(積極的反抗)の三つの段階に分け、それぞれの段階の特徴となすべき任務、さらに時期的予想を設定した。 ・これは後に、「持久戦論」として毛沢東の輝ける軍事戦略論の一つとなった。 ・驚くことに毛の読みは最終段階の中国側の攻勢と見とおしが幾分異なっていた他は、ほとんど的中していた。 ・さらに毛は四〇年に中国革命の現段階と将来の展望に関して論じた「新民主主義論」を発表した。 ・彼はここで、中国革命を古い型のブルジョア民主主義革命でも社会主義でもない新民主主義革命として、中国のめざす政権を米国型のブルジョア独裁でもソ連型のプロレタリア独裁でもない第三の道の政権として位置づけた。 毛の新国家構想 ・内戦の最終段階は、国共の対立の中で中国側の戦力も消耗したが、他方日本側も太平洋に戦線を拡大し米国と全面対決し、本土攻撃も受けるようになったため、休息に戦力を低下させていた。 ・やがて、広島、長崎の被爆があり、日本は無条件降伏を吞み、中国大陸での戦闘も停止した。 ・中国は満身創痍になりながらも抗日戦を勝ちぬいた。まさに辛勝だったのである。 再び国共内戦 ・四五年八月末より蔣介石・毛沢東の巨頭会談が重慶で実現した。 ・しかし、中共統治の地方政権、中共軍などの扱いをめぐって、さらに日本が支配していた東北地域の行政機構、軍事力、工場などの接収をめぐって両者は対立を深め、翌四六年七月、国共は再び全面内戦に入った。 ・内戦当初の戦力比は、大雑把に見積もって、国民党対中共は四対一であった。 ・しかし、毛沢東はここでも持久戦、遊撃戦を展開し、敵軍を農村、山岳の奥に引き込み攪乱し徐々に消耗させた。 ・毛の基本戦略は「持久戦」「遊撃戦」の基盤となる人民を巻き込んだ「人民戦争論」、広範な中間層そして時には一部をも味方に引き入れる「統一戦線論」、党の絶対指導下にある軍・政府を保証する「根拠地論」から成り立っていた。 ・内戦を戦う一方で、農村では地主の土地を奪取し貧しい農民に分け与える土地改革を実施し、多くの大衆を味方に引き入れた。 ・都市では蔣介石政権の腐敗、独裁を暴き、日本に代わって侵略を企てる米帝国主義の手先となっていると煽り、貧しい農民、中間層を取り込んでいった。 ・同年九月から一二月にかけての ・四九年一月北京は無血開城され、五月以降国民党政府は台湾移転を開始し、戦局は決着した。 ・六月、新たな国家を建設するため、国民党系を除く全国各界の重要人物を集めた新政治協商会議準備会議が開かれ建国の基本方針が討議された。 ・さらに九月正式に中国人民政治協商会議が招集され、ここで国号を中華人民共和国、首都を北京と改名、中央人民政府の基本的な構成(中央政府主席=毛沢東、政務院総理=周恩来など)が決められた。 4 新民主主義共和国としてのスタート 戦時体制下の建国 ・アヘン戦争から数えて約一〇〇年、清朝崩壊からでも約四〇年の歳月を経て一九四九年一〇月一日、ようやく「統一」した新国家が誕生した。 第二章 社会主義建設の模索 7 彭徳懐事件と大挫折 廬山会議 ・今日死者の数を伝える正確な記録、資料は残されていない。しかし様々な形で伝えられる数字は、実に一五〇〇万人から四〇〇〇万人に及んでいる。 ・総人口の二・五%から六%に及ぶ餓死者から推計すると、当然餓死線上の人々はその数倍に及ぶであろう。 ・毛の野心的な大躍進が如何に悲惨な「大挫折」に終わったかがこの数字からだけでも理解されるのである。 第三章 プロレタリア文化大革命 1 経済調整と毛沢東の危機意識 文革とは何か ・文革の犠牲者は、正確にはわからないが死者一〇〇〇万人、被害者一億人、経済的損失は約五〇〇〇億元とも言われるほどであった。 ・狭義には、六六年から六九年の中共第九回全国大会までの中央から末端に至る、「紅衛兵」、労働者、農民らをまきこんだ激しい政治闘争を指す。 ・毛沢東を頂点とした指導者層が抱いた国内・国際情勢に対する強烈な危機意識、権力的確執と同時に、学生、労働者、農民ら一般庶民の間に芽生えていた社会的不平等への不満など社会の構造的矛盾に目を向け、それらの共鳴現象として、その激しさと規模の大きさを捉えるべきでる。 革命家毛沢東 ・毛は少年期より自我の強い性格で、青年期以降は社会と深く関わることによって自我は強い信念に変わった。 ・彼の信念を構成する最も重要なファクターは、ナショナリズムと革命であった。 ・彼は生来、既存の強い権威に対する反逆児であった。 ・しかし彼自身が権威を持つことは皮肉にも否定しなかった。 ・毛沢東思想を高く掲げ、個人崇拝をあおることを認めた。最大の権威者になりながら他の権威に反逆するという矛盾した毛のビヘイビアが、毛を建国以後独裁的な革命者にしかつ悲劇を大きくした要因の一つであった。 2 反撃に向けての毛の戦略と体制作り 「実権派」打倒へむけて ・林彪は、六四年に赤い小さな本『毛主席語録』を刊行した。 ・彼は、「毛沢東思想はマルクス・レーニン主義の最高峰」などと称え、「毛主席語録を読み、毛主席の話を聞き、毛主席の指示に従って仕事をし、毛主席の良き戦士になろう」と呼びかけ、毛沢東の権威回復に大きく貢献した。 3 紅衛兵と劉少奇・鄧小平の失脚 大字報と紅衛兵 ・五月二九日、精華大学付属中学の約四〇人の学生によって紅衛兵とよばれる組織が誕生した。 第六章 脱鄧小平と富強大国への挑戦 7 米中関係と二一世紀の国際秩序形成に向けて 大国化志向を越えて ・何故世界の反対にもかかわらず核実験を強行し核大国化を目指すのか。「国の大小を問わず、公平・平等」論理を重視するならば、自国の核保有を容認した上で何故他国の核保有を否定できるのか。少なくとも右の論理を核拡散にならない方向で実践しようとするなら、自ら具体的に核軍縮、核廃棄の行動に踏み込むことこそ重要であろう。 ・あるいはまた、国連安全保障理事会の一層の「公平・平等」を目指した改革に、実際には中国が消極的なのは、「五大常任理事国」という既得権益バランスの確保と無関係ではあるまい。 ―― 完 ―― |