
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年05月11日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
37 |
18/05 |
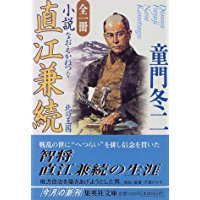 |
直江兼続 |
童門冬二 |
集英社文庫 |
◎ |
小田原の陣 ・秀吉のいわゆる "東北仕置(処分)" は、小田原攻撃に参加したかしないかが基準になる。参加した者は領土を安堵され、しなかった者はすべて領土を没収された。 ・素早く駆けつけた津軽氏は、元は南部氏の家来筋に当たった(南部側の主張)。それが、この小田原参陣によって独立した大名として秀吉に公認された。 ・「主家への裏切りだ」として、現在も青森県では津軽系・南部系の確執の底流になっている。歴史的怨念というのは複雑で、なかなか消えない。 ・人間は自信が出ると謙虚になる。 与板の女 ・兼続は言う。「戦さをするのは、早く戦さを終わらせるためだ」 【私見 : この矛盾をどう考えるか。近現代の戦争にも通じるが、巷で言われるただ単に『戦争反対』というのはおかしい。戦争は平和な社会を作るためとして行なってきたのだ。では、戦争を仕掛ける人が良い人かどうかで決まるものなのか。】 米沢三十万石 ・会津の元の領主である蒲生氏郷がこの国に入った時の、部下への土地の配分方法の話が、各大名家に "氏郷の名将ぶり" のひとつとして伝えられていた。 ・蒲生氏郷は、全武将に告げた。 「各人、いままでの功績を書いて、自分の功績はこのくらいの給与に相当すると思います、という自己申告を出せ」 ・武将たちは思い思いに書いた。 ・申告書をまとめて計算してみると、新たにもらった会津九十万石の二倍もあった。 ・氏郷に報告すると、 「そのまま認めてやれ」といった。 「とんでもありません。要求額は収入の倍です」 「何とかしてやれ。おれは一石もいらん」 ・武将たちは感動し、 「そこまでご心配をおかけしては申し訳ない。もう一度考え直します」 といって申告書を書き直した。 ・この時、 ○ お互いの功績をお互いにチェックする。 ○ 功績に見合う給与のモノサシをつくる。 ○ 全体が、氏郷の収入も勘案して九十万石におさまるようにする。 という方法をとった。 ・これが後世の「予算制度」のハシリだといわれる。 ・「入る(収入)を計って、出ずる(歳出)を制する」というシステムを考え出したのである。 ・それまでは、収入なんかおかまいなしに歳出は出るにまかせていた。 ・そして呆れたことに、徳川時代にこの悪弊がまた復活し、明治時代までつづく。 ・明治になって、維新の功労者たちと大喧嘩をしたあげく、これを完全に正したのは、一時大蔵省の役人になった渋沢栄一だ。 ・蒲生氏郷は近江商人の育ての親であっただけに、経営感覚の鋭さにかけては、出色の大名だった。 ―― 完 ―― |