
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年05月30日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
42 |
18/05 |
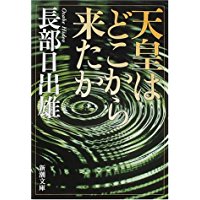 |
天皇はどこから来たか |
長部日出雄 |
新潮文庫 |
◎ |
第九章 卑弥呼は日御子か ・江戸時代の上田秋成が、すでに明晰で理性的な認識を示していたのに、近代の知識や学問が大量に流れこんだあとの昭和初期に、世の中が ・卑弥呼は女王の尊称で、実名ではない。姫尊すなわちhimemikotoの転訛であろう。 ・卑弥弓呼は卑弓弥呼の倒置で、hikomikotoが省略されたもの。これも狗奴国王の実名ではなく尊称で、当時九州の倭人は、邪馬台国の女王を卑弥呼すなわち姫尊、狗奴国の男王を卑弓弥呼すなわち彦尊と尊んで称したものとおもわれる。 ・鹿児島湾沿岸から来た天孫族は、延岡の河口の平野に住んで水田を広げ、五ヶ瀬川を遡って達する神秘的な山峡の地に神域を設けて、これまでにない新しい宗教と文化を作り上げた。 ・そしてまず宗教的な権威を先に立て、あとから武力と政治の専門集団がついて進むかたちで、大和へ向って行ったのでは……と想像するのである。 第十一章 「日本教」の解明 高度の道徳性を備えた人人 ・世界に類のないわが国の治安のよさと、ガバナビリティー(統治可能性)の高さは、大和朝廷が確立されるずっとまえ、少なくとも弥生時代の後期あたりからのものであったようだ。 宣教師たちの見た日本人 ・ザビエル 「日本人は、わたしがこれまで遭遇した国民のなかで、いちばん傑出している。名誉心が強烈で、かれらにとっては名誉がすべてである。ほとんどが貧乏だが、武士と平民を問わず、貧乏を恥辱だとおもっている者は、一人もいない」 「金銭よりも名誉を大切にし、侮辱や嘲笑に黙って忍ぶことをしない。武士が領主に服従するのを誇りとして反逆しないのは、それが名誉だからで、罰を恐れているからではない」 「日本人の生活には、節度がある。ただ飲酒はいくらか度がすぎる。大部分が読み書きでき、学ぶことを好む。窃盗はきわめて稀。死刑をもって処罰されるからである。かれらは、盗みの悪を非常に憎む」 「古人を尊敬する。太陽を拝む者が多い。理性的な話を喜んで聞く。邪悪なことを、自然の理性に反するがゆえに、罪だと断ずれば、かれらは諸手を挙げて賛成する」 「日本人ほど理性にしたがう国民は、世界中で見たことがない」 ・フロイス 「国民は親切で優しいが、一方、傲慢で戦を好み、武を重んずる。 文化が進んだ地方では、男女ともたいてい読み書きができ、上流階級の人は、礼儀正しく、好奇心と知識欲がさかんで、外国人に喜んで会い、きわめて細かな点まで異国のことを知ろうとする。 道理に明るく、盗みをもっとも憎み、各人が自家の司法官であるばかりでなく、盗んだ者は殺されてしまうので、道理と恐怖の両方によってよく統治され、治安がたいへんいい」 ・ヴァリニャーノ 「下層の人人にもヨーロッパ人のあいだに見受けられる粗暴さや無能力がなく、一般にみな理解力に優れ、仕事に熟達している。 きわめて忍耐強く、飢餓や寒気、あらゆる不幸や不自由を耐え忍ぶのは、幼少から苦しみを甘受するように習慣づけられているからで、これは身分の高い人でも例外ではない。 家、服装、食事、その他すべてが清潔で、美しく調和が保たれ、日本人全体がまるで同一の学校で教育を受けたかのように見える。 礼儀正しさと理解力において、日本人がわれらを凌ぐほど優秀であることは否定できない」 ・治安とガバナビリティーのよさ、平均的な教育水準と仕事の熟練度の高さ、好奇心と知識欲の旺盛さ、マゾヒスティックなまでの忍耐強さ、清潔好き、そして画一性……等等は、戦国時代の真っ只中にあったこのころ、すでに全部そなわっていたのがわかる。 ・これらのなかの基本的な特質は、古代から一貫したものであったのかもしれない。 最も過激な日本教の体現者 ・豊臣秀吉が実行して、いまも両国のあいだの禍根となっている朝鮮侵攻と、その先の明国経略を、最初に構想したのは信長である。 第十二章 天皇の来た道 ・神はいて、神社はあるが、教義がはっきりしない。けれども、ご神体はたしかに存在していて、それは鏡である。 ・日本教は、海外から渡ってきた新しい文明の象徴ともいうべき鏡をご神体として出発した。 「象徴」が意味するもの ・現代の民主国家には、なにかふさわしくないようにも感じられていた象徴天皇制が、じつは遥かに遠い古代からの長い歴史とさまざまな経験によって洗練され、成熟してきた世界でも数少ない知恵の果実のひとつである。 史上に先例のない今後の道 ・いま将来に予想される危険のひとつは、わが国の政治が批判勢力のない翼賛体制になることだ。 ・もともと冷静な批判精神に乏しく、過剰に同調性が強いわが国は、みんなが同一方向へ走りだすとき、チェック機能とブレーキを失って、恐ろしい破局に突き進む。 ―― 完 ―― |