
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年07月17日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
47 |
18/06 |
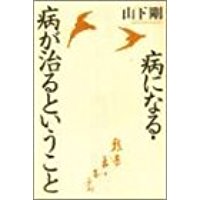 |
病になる・病が治るということ |
山下 剛 |
草風館 |
◎ |
序章 ●ホリスティック医学 ・ホリスティック医学の定義 一、ホリスティック(全的)な健康観に立脚する。 二、自然治癒力を癒しの原点におく。この自然治癒力を高め増強することを治療の基本とする。 三、患者が自ら癒し、治療者は援助する。 ・治療よりも養生が、他者療法より自己療法が基本であり、ライフスタイルを改善して患者自身が「自ら癒す」姿勢が治療の基本となる。 ・患者の中には病気は医者が直してくれるものと思っている者がいる。医者にできるのは「手当て」だけである。 ・同じ病気の再発を繰り返す者がいる。生活の仕方、ライフスタイルを替えない限り病気から逃れることはできない。 四、さまざまな治療法を総合的に組み合わせる。 五、病いへの気づきから自己実現 ・たんに病気を否定すべきもの、治ればそれで終りととらえるのではなく、病気の自分への「警告」の意味に気づき、これを契機により高い自己成長・自己実現をめざしていく。 ●花粉症からの解放 ・杉花粉症は、鼻の粘膜にある肥満細胞に、杉花粉がとんでくると、抗原抗体反応を起こして、肥満細胞が破れ、ヒスタミン様物質が放出され、それがアレルギーを引き起こして鼻炎となるものです。 ・杉の林のなかで育った人間が、はるかに杉の木の少ない東京に住んで、しかも十年も二十年も経ってから杉花粉症になる。 ・杉花粉は本当に悪者なのでしょうか。 ・杉花粉症の人が、杉花粉に出会わなかったら、アレルギーを起こしていないことも事実ですが、その前に、なぜその人がアレルギーを起こす要因をもつようになったかを考えて、その原因をたださなければ、対症療法だけでは、いつまでたっても泥縄式でおわってしまいます。 ・鼻炎には痒みをともないます。蚊に刺されても痒くなります。蚊は私たちの身体を刺すとき、蟻酸をいれますが、蟻酸がはいると、血が固まりにくくなるので、生体の防衛反応として、蟻酸の周辺にヒスタミン様物質が集まってきて、蟻酸の働きを遮ろうとします。このヒスタミン様物質が痒みの原因となるのです。 ・蟻酸が体内に増えるような生活を続けていると、アレルギーを起こしやすい状態ができあがることになります。 ・体内に蟻酸を増やすような生活の一つには、砂糖の摂取があげられます。 ・砂糖は、果糖 ― 酢酸 ― 蟻酸と変化します。そこで砂糖の摂取を断つような生活を指導すると、アレルギーがだんだんと起こりにくくなってきて、ついには杉花粉症から解放されることになります。 ・人間が病的状態に陥る原因に、外界からの影響も大きく関わっています。 ・感染症などは、その代表のように考えられています。 ・感染症は外界から私たちの身体に起炎菌がはいりこんできて、病を起こす原因となります。 ・一方で伝染病が流行してもそれに罹らない人たちがたくさんいることも事実です。 二章 健康と病 ●ストレス ・ストレスから胃潰瘍ができてしまった患者さんに、潰瘍治療剤をげることには、あまり意義がありません。もしそのことで、仮りに潰瘍が消えても、またすぐ再発させてくるでしょう。お薬をあげるよりは、生命を維持する本能とでもいうべき、周囲と「融合する」ことを教えてあげれば済むことなのです。 ・現代医学の問題点は、身体に生じた病を、身体のみの問題として取り扱う点にあります。科学の成り立ちがもつ性質上、身体と機械と同じようにみなして、身体が心・精神と融和した一個の生命体とみない点にあります。 ・しかし、どのような病気も、精神的な面を大きくもっています。それどころか、精神的な現象として肉体に表現してきたのが病であるとさえいえるのです。 ●ボケの周辺 ・癌細胞は幼若細胞といわれているように、私たちの身体を構成している組織の細胞が、本来あるべき機能を忘れて、先祖がえりした結果起こってきたものです。 ・ですからなぜそのような退行性変化を起こさねばならなかったかを考察して生活を指導してあげると、自然退縮(癌がかってに消えていくこと)をきたす例をずいぶんみることができます。 ●間違った日常生活 ・病を治すにはライフ・スタイル(生き方)を変えることがどうしても必要です。 三章 食養のすすめ ●栄養の誤解 ・砂糖・果物など単糖類を取り過ぎた結果、体内に蟻酸が増えると、身体にアレルギー準備状態ができあがります。そこに蛋白質がはいってくると、抗原抗体反応を起こすことが可能になりアレルギーの立役者が揃って、アトピーに限らず喘息、鼻炎などを含めたアレルギー疾患を起こすのです。 ・抗原抗体反応に必要な蛋白は、それがどのような種類のものであろうと、ほんの少しあればこと足りるのです。 ・米、そばなどに含まれる蛋白でアレルギーを起こす人たちもたくさんいるのは、常々アレルギーの準備が完了しているからなのです。 ・田植えも終って、これから稲が育ってゆこうとするとき、肥料を与えすぎたら、どうなるでしょうか。稲は期待通りに太く長く育ちます。実りの秋がきても、稲穂は小さく、それでいて、台風でもこようものならかんたんに倒れてしまいます。立ち枯れを起こしてしまうのです。当然根は小さく、申し分けのように存在するだけです。 ・肥料がたっぷりとあると、根は大きく拡がらなくても、稲を育てるに充分以上の栄養を摂りいれることができます。ですからどんどんと生長して、老化を早くして、稲穂の頃には、もう枯れ始めるのです。立ち枯れです。 ・子供時代に高蛋白、高カロリーで育てられると、稲の根が充分張らないのと同じように、消化吸収機能が十分に発達せず、立ち枯れ的育ちかたをすることになります。 ・子供は、しっかりと根が張れるようにな育てかたをしなくては駄目です。そのためには、素食、少食、よく噛むことが基本になります。 ●水 ・水分の摂り過ぎでは、水分が体から汗や小便などとなって外に出てゆくとき、塩分を持ち出すので塩分不足になってしまいます。 ・怠け易く疲れ易いのは、水分の摂り過ぎによる塩分不足のような気がするのです。 ●よく噛むこと ・よく噛むことによって、唾液が自然に出てくる。この唾液に発癌物質を加えて、その効果を調べた実験結果は、大体三十秒くらいで発癌物質の毒性が八〇%以上消えたということでした。 ・しかもそれまで消化酵素とは考えられておらず、無用の長物とされてきたベルオキシターゼが、制癌作用の主役をなしていることが認められたのです。 ・また唾液を出すのは耳下腺、顎下腺、舌下腺の三つですが、この耳下腺からパロチンというホルモンが出ます。 ・このパロチンが老化防止に役立つ。 ・よく噛むことによって、パロチンの分泌が良くなり、血管の老化を防ぎ、皮膚もきれいになってくるのです。 ・健康でいたかったら食べ物をよく噛むことが必要です。 四章 心と病とエネルギーと ●白隠さんの病気に対する考え方 ・病気になったのは自分の姓であるから、仮に死んでも誰も怨むようなことはできない。そうしたら、自分が悟るしかない。 ・人間どう生きるべきかが判ってくるにつれて病も楽になっていった。 ・病をもったお陰で人間として成長できた。 五章 イノチとホメオスタージス(自己治癒力) ●ストレスに屈服する弱い人たち ・うつ的状態に陥ってしまうのは、ストレスに立ち向かってゆく個人の抵抗力が弱いからです。 ・若いときから苦労を知らずに甘やかされて育ったり、自身の能力以上の自我をもとうとしたり、人格以上の知識をもったりする、心のアンバランスは、ストレスに対する弱さとなって現われます。 ・このようなストレスからくる病をもつ人たちには、ほんの少しノルマを与えて、私たち医療者が援助する、誘導する。それで身体が良い方向、気分の良い方向に変化してきたら、もうちょっと頑張ってと、ノルマを増やす。こうして気長につきあって、ストレスを追い払う自信をつけさせてあげるのが、医療のように思えます。 ・単に身体を楽にしてあげるだけでは、またふたたびストレスがかかったとき、すぐ手をあげてしまう弱い人間をつくることになってしまいます。 ●イノチを取りまくホメオスタージス ・健康人といえども癌細胞のいくつかはもっている。 ・ですがこの癌細胞は増殖して集団となり、私たちが癌として認めうるまでには至らず、そのほとんどが消えてゆきます。 ・私たちの身体が癌細胞が育つに適していなくて、心身ともに健康体であれば、癌細胞は淘汰されてゆくのです。 ・このような働きは、イノチの働きで、その現象を、私たちはホメオスタージスと呼んでいます。 ●死を受け入れる ・死ぬことを受けいれると、病も、それが重症でも、いずれは死んでゆく、その過程だと思えます。 ・皆なが通ってゆく、当たり前のコースのひとつにしか過ぎないわけです。どうってこともありません。そんなに怖いものでもないのです。 ・こう考えてみると、病気をしながらでも、比較的楽に過ごすことができるようになるはずです。 ●生きることの喜び ・癌になられた方の闘病記より 「私のように何度もこの病気をしたものは、いよいよこれが最後ではないかと考えるものです。しかし結果が生であっても、死であっても、それを受け入れようという心境に達したとき、緊張や、心配から解き放たれます。そのことに治療的な効果があるといえましょう。癌とかその他、皆さんが恐れている病気になったからと云ってすぐ絶望する必要はありません。癌も初期なら治療できますし、ある種の癌は薬によって、数年間進行を食い止めることができます。しかし、心に本当の平和を得るためには、死の可能性を直視する必要があります。これは誰もがいつかは直面しなければならないことなのです。私たちの行く先に、何が起ころうとも、それを受けいれていこうという気になったとき、そのときから、恐れず、思いまどわされず、毎日毎日を大事に生きてゆくことができます」 ・死を受け容れることは、一見受身のように感ぜられますが、積極的に受けいれることもできるのです。 ―― 完 ―― |