
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年06月29日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
54 |
18/06 |
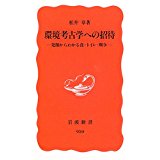 |
環境考古学への招待 |
松井 章 |
岩波新書 |
◎ |
第1章 食卓の考古学 サケの利用法 ・『延喜式』には、信濃の中男作物として、 魚料理と包丁 ・日本料理の原点は、鎌倉時代に確立したのではないだろうか。 第2章 土と水から見える古代 いろいろなヒトの寄生虫 ・現代人の花粉症をはじめとするさまざまなアレルギーは、日本人が寄生虫を宿さなくなり、体内の抗体が減少した結果だという説がある。 トイレの歴史――第一期 ・集落の周辺で用を足し、自然の分解作用にまかせていた時期。 ・青森県の ・回虫は縄文人がもともと持っていた寄生虫ではなく、弥生時代が稲作と共に連れてきた可能性が高くなった。 トイレの歴史――第二期 ・集落の周辺を囲む環濠や、傍らを流れる河川に糞便をたれ流した時代。 ・弥生時代の代表的な環濠集落の一つ、池上曽根遺跡では、人口が急増する弥生中期になると、多くの井戸が掘られ、飲み水は井戸から、下水、 ・溝や河川に建てかけられた「 ・明確な遺構を伴うのは、三世紀の纏向遺跡の導水施設のような便器?付きトイレで、その後、藤原京、平城京、そして一三世紀の鎌倉では、私が「 ・それは道路側溝を流れる水を邸宅内に引き込み、その上で用を足したり、トイレ掃除の下級女官である トイレの歴史――第三期 ・汲み取り土坑式トイレの時代――七世紀、藤原京にはじまり、古代、中世、近世の都市内に作られる大部分のトイレ。 ・藤原京の建設により、人工的な古代都市が建設されるようになり、人口の集中がさらに進むと、従来の川屋式、樋殿式の垂れ流し水洗トイレでは、環境汚染がますますひどくなっただろう。 ・そこで、人びとは穴を掘って便槽とし、中身が溜まると汲み出して遠くへ捨てる、汲み取り土坑式のトイレが出現したのだと思う。 ・すでに藤原京では、樋殿式と汲み取り式の両方が発掘されており、そのまま一三世紀の鎌倉まで両者が併用されたまま存続する。 ・この頃には都市住民の屎尿が、周辺農村の肥料として価値を持ち、イエズス会のルイス・フロイスが記したように、日本では農民が都市住民の屎尿を金を払って買い取る行為が一般化していたと考えられる。 第3章 人、豚と犬に出会う 食用になった弥生犬 ・縄文犬は人と共に墓地に埋葬されているが、弥生犬は散乱状態で溝に捨てられたままの例が多い。 ・弥生時代のイヌたちは食用にもされていたのだ。 第5章 人間の骨から何がわかるか 『古事記』と人骨 ・『古事記』の登場人物が、敵を倒す時、何のためらいもなく殺害した相手を切り刻むとある。 ・そのまま死体を残していたのでは、魂が戻って再生する危険性があるからである。 ―― 完 ―― |