
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年04月01日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
6 |
18/01 |
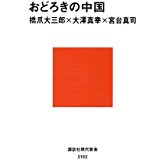 |
おどろきの中国 |
橋爪大三郎 大澤真幸 宮台真司 |
講談社現代新書 |
☆ |
第1部 中国とはそもそも何か 4 中国的生存戦略の起源 大澤 ・中国人の車の運転の仕方は、我が我がという感じで自分の欲求を通そうとして、めったに譲ろうとしない。とにかく、日本人にはめったに見られないレベルでエゴセントリックだ。 宮台 ・ある中国人曰く、「中国には交通ルールはない。強いて言うと、事故を起こさないというのが交通ルールである」と。これは究極の帰結主義です。 ・帰結主義とは「終わりよければ、すべてよし」という考え方です(別名は行為功利主義)。 ・帰結主義の反対は規範主義で、これは「帰結はどうあれダメなものはダメ」という立場です。 ・ちなみに規則功利主義と呼ばれる立場もあって、「規範があるのは、そのようにするともっとも良い社会的帰結が得られるからだ」とするものです。 ・中国社会にはどうもダメなものはダメという規範主義的な様相がすごく希薄だ。規則功利主義のニュアンスさえあまり感じられない。 ・日本人は秩序を維持しようと考えたら、まず、こういう時はこうするものだという自明な枠組みをつくりあげますよね。 ・「事故を起こしさえしなければ何でもあり」という具合にもっぱら帰結だけに照準するよりも、ルールや空気など、その手段に当たる枠組みの維持に注意を集中するんじゃないでしょうか。 ・それに対して、中国では、そういう枠組みを共有することについては無頓着で――無頓着であるがゆえに、まさにエゴセントリックに見える。 ・ギリギリのところで問題を引き起こさなければいいのである、という究極の帰結主義によって秩序を保っているように感じられます。 橋爪 ・中国の人びとはたしかにアグレッシヴに見える。個人主義的で、ルールなんかまるで守っていないように見えるけど、それは、日本人がそう見るからなんです。 ・ルールがないと見えるいっぽうで、彼ら相互の、行動の予測可能性はきわめて高いでしょう。相手がどう出てくるか、正確に理解し、予測し合っているわけです。 ・アグレッシヴだけど、文明的な状態なんです。 ・この、中国の人びとの行動様式を、個人心理に還元して、自己主張が強い連中だとか、考えてはいけない。国民性の違いに還元しても、文化のせいにしてもいけない。 ・もっとスパンの長い、歴史の蓄積のなかで育まれた、中国の人びとの基本フォーマットなんです。 ・この中国文明の系譜の全体を受け止めないと、表面的な反応になってしまう。 宮台 ・中国では自動車同士だけでなく、歩行者と自動車も日常的にチキンゲームをやっていました。 ・そこにはお互いの行動についての趨勢的な期待がけっこう堅固に存在する。 ・これは、規範や道徳ではないという意味で、ルールでもなければ文化でもありません。 ・いわばゲーム理論的な均衡ですが、その均衡を再帰的に意識し合うことで、秩序が破れないようにしているわけですね。 ・ルールでもなく、文化でもなく、独特の均衡状態への再帰的な意識。それが中国の「文明」なのでしょうね。 橋爪 ・生存戦略なんですね、一人ひとりにとっての。生存は、根本的なことだから学習せざるをえない。日々の体験を通じ、わがものとして身につけるわけですよ。 ・この起源は、とても古くて、深いものだと思う。 ・その起源について、コムギが入ってきて、最初につくられたのはコムギ畑と町なんだけど、町はすぐさま、都市国家になります。 ・コムギ畑と町は略奪の対象なんです。周囲には、腹を空かせたやつが大勢いる。 ・そこで、コストをかけて町の周りに城壁をこしらえる。武器も必要だ。材料は、青銅です。 ・青銅は、とても高価。 ・青銅製の武器で武装できるのは、ひと握りの貴族に限られる。彼らが軍事力を独占し、大多数の農民を支配する社会がうまれる。 ・都市国家には貴族がいて、軍事力によって、相互に覇権を競うという状態になった。 ・そこへ今度は鉄器が出てくるわけです。 ・鉄が登場すると、ふたつのことが起こる。 ・ひとつは生産力が向上する。鉄は安価で豊富にあるので、農具を鉄製にできる。 ・耕地面積も収量も増える。 ・もうひとつは、鉄製の武器ができること。 ・安価な鉄で、農民が武装し、密集歩兵集団をつくって、戦車や騎馬に対抗できる。 ・結果、貴族が没落し、農民の社会的地位が上昇するのです。これが、春秋戦国時代。 ・春秋戦国時代は、統一政権への過渡期みたいなもので、農業と軍事力を基盤にした戦争マシンのような社会をつくり出した。 ・で、これらが厳しく競争し、最終的に、競争するローカル勢力のパワーバランスが崩れて、統一政権ができあがった。 大澤 ・それが秦だった。 橋爪 ・ちなみに日本は、青銅器時代はないです。鉄器時代もない。青銅も鉄も、いっぺんに入ってきた。戦車もない。 ・中国が世界標準の文明だとすると、日本は周縁的で、都市国家さえもない。奴隷制もない。 ・ですから、私たち日本の歴史的常識で中国を理解しようとしてはいけないんです。 5 儒教はなぜ歴代政権に採用されたか 大澤 ・法家も儒家も諸子百家の中から出てくるわけですが、それぞれについて。 ・法家のやり方の基本は、平等で厳格な信賞必罰の原理です。命令通りにちゃんとやった者には褒美を与え、命令に反した者は罰する。とくに、後者の罰する、という契機が大事だと思う。 ・儒家は、家族や親族の秩序に基づくイデオロギーです。 ・法家は、家族の関係だからといって、これを重視したり、優遇したりしないので、ここに儒家と法家の大きなちがいがある。 ・儒家で大事だとされることは、君主への忠誠であり、家族・親族における年長者への服従、とりわけ父への服従ですね。 ・前者が「忠」で、後者が「孝」。両者のうち、より大事なのは孝の方で、もし忠と孝とが矛盾する場合には、孝を優先させるべき、というのが儒家です。 ・法家は、家族・親族をむしろ解体するように作用するのに対して、儒家は、これらをベースにして、強化するように作用する。 7 科挙と宦官の謎 橋爪 ・君主が世襲だと、政治が安定する。ブレーンをつとめる行政官僚が有能だと、政治が機能する。そのふたつを異種配合することによって、純粋の能力主義でも、純粋の血縁主義でもない、新たな性能がうまれる。 第2部 近代中国と毛沢東の謎 9 冷戦が終わっても共産党支配が崩れなかった理由 橋爪 ・官僚制は、人間が相対的に多く、ポストが相対的に少ない状態だから、必ずそこに対立と矛盾がある。 ・そうすると、誰がそのポストの上位に進んでいくのかを処理するのが一番大事ですね。 ・誰かを抜擢し正当化するということは、誰かを排除し非正当化するということなんです。 ・排除し非正当化するためのロジックを、毛沢東はたくさん生み出した。 ・まず、「 ・こうした摘発の根拠になる恐ろしいシステムが、個人 ・档案は、公文書という意味なのですが、そのひとつに個人档案というのがある。これは、履歴書みたいなものです。 ・でも履歴書とちがって、自分で書くことができないし、見ることもできない。書いたり見たりできるのは、上司です。 ・そして農民にはなくて、都市戸籍の人、とくに役人や知識人にはあります。 ・大学に入学すると、入学と同時に個人档案が教務課につくられて、成績が書き込まれる。そのほか、いろんなことが書き込まれる。 ・上司は採用した学生の档案を見て、「親戚に国民党がいるのか!」と思ったりする。そして、本人の人事記録をさらにいろいろ書き加えていく。 ・上司も自分の档案を見ることができず、見ることができるのは上司の上司。 ・中国中の档案を見ることができるのは、中国共産党のナンバーワンただ一人、ということになっている。 ・この仕組みを仕切っているのは、中国共産党の組織部というセクションで、档案を資料に、組織をまたがった抜擢人事を行なうことができる。 ・いたるところに党組織があるので、抜擢人事は縦横無尽。いまの党中央も、そうやって昇進してきた。中国全体が一つの組織なんです。 ・個人档案には良い事と悪いことが書いてあるから、抜擢するには良いことを理由にするが、妥当する必要があるときには悪いことを理由にする。 ・文化大革命のときにはこの個人档案の情報が紅衛兵に漏らされて、それで紅衛兵が目当ての役人の自宅に押しかけて、打倒する事件が頻発した。 ・この個人档案は、 ・新中国は国民党と内戦を続け、台湾とはいまでも内戦状態にあるから、いわば戦時なんです。人民は潜在的にスパイだと考えなければならない。 ・そこで、こうやって個人情報を管理している。こういう仕組みがある限り、政治的自由はえられにくい。 ・冷戦が終結したあと、ソ連や東欧の社会主義政権は総崩れになったけれど、中国はビクともしなかった。 ・それは、単位制度や個人档案制度のように、党組織と人事システムがしっかり確立しているからだと思います。 11 日本よりも合理的な面 橋爪 ・個人档案制度は、共産党の一元的な組織管理と表裏の関係にあるので、簡単にやめられないと思う。 ・もっともしばらく前に、やめになったという話もある。 ・中国共産党から言えば、抜擢システムがその本質ですから、抜擢を可能にするための情報を、中国共産党の組織部が握っていなければならない。 ・かりに個人档案の名前がなくなっても、かたちを変えて存続すると思う。 大澤 ・おそらく、個人档案を組織部が掌握するという共産党の原理と、自由な労働市場を含む普通の資本主義の原理との葛藤が、しばらく続くのでしょう。 宮台 ・元財務官僚の高橋洋一氏曰く、 「現在の財務省には、財政再建路線というものは存在していない。存在するのは、天下り先ポスト増大をもたらす増税路線だけであり、それは財務省の中では完全な常識だ。逆になまじっか財政再建を成功させてしまえば、増税がいらなくなって、自分の権益が拡大しないので、実は財政再建をいろんな手練手管で妨害している。そのことは財務官僚であれば誰もが知っている」 と。 ・日本にだって、ばかげているとわかっていても、いまそれをやめるという選択肢は現実的にはありえないと思い定めて生きるということが、エリートにさえ――エリートだからこそ――ありえます。 ・だから、中国的な「裸の王様」システムの存在は、理解できないことではない。 橋爪 ・中国と日本のどちらが現実的か、愚かかですが、日本のほうがなお愚かだと思う。 ・なぜ、財務省が省益ばかりを考えて、日本国のことを考えないでいられるかと言えば、中国共産党がないから。 ・中国共産党は、国家を指導する唯一の組織で、国家を構成する個々のパーツの局部的な利害を、必ず越え出ている。 ・中国のどんな組織だってバッサリ切ることができる。中国共産党が生き残るということは、中国が生き残ることとほぼ同じなんです。そういう意味で、合理性がある。 ・それに、個人档案は、たしかに人権を侵害し、プライバシーもない。そういう側面を見れば不合理だけど、この根本には、個人の業績を個々に記述することが可能だ、という考え方がある。 ・だから、抜擢人事も、降格人事もできるわけ。つまり、人材の合理的な配置が可能になる。 ・これと共産党の権力を組み合わせるならば、日本よりはるかにはるかに合理的な機能集団を構成できるではありませんか。 ・どんな組織も、ぬるま湯の共同体であってはならない、なんです。 第3部 日中の歴史問題をどう考えるか 1 伝統中国は日本をどう見ていたか 橋爪 ・日本は、悪意の中国侵略者だったのか、それとも善意で、欧米の勢力を追い払う解放者だったのか。ほんとうはどっちなのか、じつは日本人自身がよくわからない。 ・その点を突き詰めず、わざとあいまいにしていた。 ・侵略者だという自覚があれば、それなりの覚悟も自己正当化も必要ですが、その準備がなかった。 ・その程度の中途半端な意識で、のこのこ中国に入り込み、好き勝手にふるまって、大きな損害を与えたわけです。 3 日本が大陸に進出した動機 橋爪 ・日本がアジアに出て行ったのは、防衛的な動機だったんです。最初は。 ・ロシアが朝鮮半島をおさえたら大変だ、と危機感をもった。 ・日清戦争の開戦理由は「朝鮮の独立」ですが、それは口実にすぎない。 ・日本の行動が侵略かどうか。 ・「侵略」を定義してみると、 ・軍隊が相手国に侵入するだけで、領土的な野心がなければ、侵略とはいわない。 ・ヨーロッパは国境が入り組んでいるので、戦争になればすぐ、軍隊が相手国の領土に入ってしまうんです。それを侵略とはいわない。島国の日本の感覚がちがう。 ・日本の「侵略」が非難されているのは、戦争それ自体もさることながら、その「意図」なのです。 ・これに抗弁したければ、侵略の意図がなかったと論証しないといけない。でもその論証に、いまも成功していない。それが、歴史問題が解決しない理由でしょう。 大澤 ・実際問題として、日本人は、かなりあいまいな意図で軍隊を進めていたのではないでしょうか。 ・日本人自身が、そもそも、なぜ日本の軍隊が大陸に進出していったのかをいまいち理解していないように思います。 橋爪 ・日清、日露戦争までは、それなりに明確だった。そのあと、おかしくなった。 ・日清戦争のとき政府は、「朝鮮の独立」を保全すると言っていた。 ・清国が「宗主国」として、朝鮮の内政に干渉する。ロシアは朝鮮を属国化しようと狙っている。肝心の李氏朝鮮は、独立を守る気概がなく、フラフラしている。ここは軍事的に介入しないでどうする、という理屈だった。 ・これで日清戦争を戦った。 5 満州国の建国 大澤 ・建前上は、日本も完全な独立主権国家として自己主張しているわけだけど、実際のところは、列強の掌の上にいた。 ・「どうしてもと言うなら、少しはロシアと喧嘩してもいいよ、その方がオレにも都合がいいから」とイギリスが日露戦争に許可を出し、この喧嘩で日本が予想以上に優勢だったから、アメリカが「ちょっと待て、そこまで日本に許していいのか」と止めに入る。 ・当初、想定していたよりも日本が勝っちゃったから、多少、日本の取り分を少なくして、秩序を保とうよ、みたいなことを、当事国の日露ではなく、第三者である列強諸国が決めてしまう。 ・日本は自力で何かをしているつもりでも、基本的な土俵は列強が決めていて、その中で動いていた。 橋爪 ・日本外交は最初から、列強とのせめぎ合いでした。 ・最初は、日米和親条約、日米修好通商条約を、江戸幕府が結んだ。 ・列強は、天皇と将軍のどちらが君主なのかすら、よくわからなかった。 ・でも条約が結ばれたからには、主権国家として認められたわけで、素晴らしいことだった。ただ中身は、不平等条約だった。 ・この不平等条約を、どう改正するか。半人前の扱いからどう脱却するか、それが明治政府の国家目標になった。 ・そこで、大日本帝国憲法を制定し、日清戦争、日露戦争も戦って、やっとのことでロシアに勝利したあと、不平等条約が解消された。 ・国家目標が実現した。ここで日本の、列強モードが完成したんですね。 ・で、そのつぎにどんな国家目標を定め、どういうアジア政策を進めるか。軍と政府の足並みが乱れていくのです。 ・軍は、ロシアとの再戦を覚悟している。そこで焦点となるのが、満州。いまでいう東北三省です。それを日本は、勢力下に置こうと企んだ。 ・満州は当時、中国かどうか、わかりにくい地域でした。 ・満州は、伝統的には、韓民族の地域ではなかった。 ・中華民国は、満州を自国の領土だとしたけれど、実際に満州を支配していたのは、軍閥の張作霖だった。 ・日本は、満州がこういうあいまいな場所であるのに目をつけた。 ・そこで、張作霖を暗殺して、満州をまるごと手に入れてしまえというのが、日本の関東軍(もともと遼東半島と南満州鉄道の付属地の警備を担当する部隊の名称)の一部軍人の陰謀だったわけです。 ・それを政府や、陸軍首脳にも相談しないで実行した。 ・張作霖の爆殺事件(一九二八年)のあと、今度は満州事変(一九三一年)が起こった。 ・満州事変は、周到に準備された、関東軍の組織的な作戦行動です。 ・柳条湖で鉄道が爆破された(日本軍の自作自演)のを口実に、関東軍が満州全域をあっという間に制圧した。 大澤 ・張作霖爆殺事件はソ連の特務機関の謀略だったという説も最近はあります。 橋爪 ・満州事変で日本は、国際社会のルールに違反したのです。 ・中国は列強によって、植民地化されているでしょ。だけど、それは必ず、戦争をし、講和条約を結ぶとか、借款を供与してその見返りにとかで、中国に権益を認められるという手続きを踏んでいる。 ・こうやってイギリスも、フランスもドイツもロシアも、特殊権益をもっている。 ・アメリカだけはそうした権益をもっていない。アメリカはもともと植民地だったのが、独立戦争で独立した。 ・そこで海外に、植民地をもたないことを国是にしている。 ・そこで日本は、列強のなかでもロシアに対していちばん警戒心を、アメリカに対していちばん親近感を抱いた。 ・これが今日にいたる、日米関係の基礎になっている。 大澤 ・満州国を日本が占領した最大の意図は、やっぱりソ連に対する国防上の理由だ。 6 日中戦争とは何だったのか 宮台 ・満州国樹立は “ソ連対策” でしたが、政府は列強の抵抗を意識して、満州事変を旧国際秩序打破=世界再分割開始だと、過分に位置づけます。 ・意図せざる列強権益侵犯と、意図せざる持久戦化に、内外への申し開きの必要を感じた第一次近衛内閣が、苦肉の策で持ち出したのが、亜細亜主義者の十八番だった「東亜新秩序の建設」です。 ・くわえて、第二次近衛内閣で持ち出されたのが「八紘一宇」。日中戦争を天皇の徳を世界に及ぼす聖戦だと位置づけたのです。 ・八紘一宇も亜細亜主義過激派とも言うべき日蓮主義者の言葉でした。 ・暴戻支那の膺懲(勝手な中国への懲罰)から「東亜新秩序」を経て「八紘一宇」へ。 ・政府のお題目の変遷に、①日中戦争の無方針拡大と、②言い訳としての亜細亜主義の動員というご都合主義、という二側面が見てとれる。 ・日本は日中戦争で何がしたいのかだんだんわからなくなり、わからなくなるほど天皇に言及する抽象的御題目が登場し、そのことに気付いて声をあげた者は不敬な輩として黙らされた。 橋爪 ・国民党政権は、南京が陥落しても降伏するどころか、首都を武漢に、さらに重慶に移して、徹底的に抗戦するかまえをみせた。 ・世界の同情は中国に集まり、日本は孤立した。 ・侵略者のレッテルを貼られ、国力が疲弊し、とうとうアメリカから最後通牒を突きつけられた。 ・ソ連と戦争するはずだったのに、アメリカと戦争しなければならなくなった。中国の完璧な、戦略的勝利です。 ・陸軍も海軍も、自分のことばかり考え、日本の国益などそっちのけです。 大澤 ・日華事変の端緒になった盧溝橋事件は、明確な意志の裏付けのないまま偶発的に起きてしまった。 ・本来は、宣戦布告のようなことがなされてしかるべき。 ・しかし、そんな重大なプロセスが、誰のどういう意図によって決断されたのかまったくわからないままになっている。 ・当時の日本人は、こういうことをやるにあたっての基本的なコンセプトを、あまりにも理解していない、ということです。 ・最前線で戦っている軍人でさえも、いったい自分たちが何をやっているのか、何のために戦っているのかよくわかっていない。 ・日中戦争というのは、壮大な「意図せざる結果」のように思います。 ・中国の内陸に攻め入った日本軍は、戦争の意味に関して、自覚が乏しかったと思う。 ・謝罪をしたり、責任をとったりするには、大前提として、「こういう意図のもとで行なった。しかしこういう結果になった」という認識が不可欠です。しかし、そうした認識が日本側であやふやだ。 ・南京で何人の犠牲者が出たかということの前に、そもそも、南京で戦いが「何であるか」を意味づけるフレームワークがない。 ・だから、どう責任をとったらよいのかはっきりしない。 ・中国からすると、これほどのことがなされているのだから、日本側によほどの意図があったはずだ、と見なされるわけですが、日本の方からすると、その肝心な部分が空虚なままなので、応答しようがない。 7 日本人の傾向 大澤 ・歴史問題については、もう何度も謝罪しているのに……、という気持ちが日本人には少なからずあると思います。 ・でもよく考えてみると、謝罪は、「ごめんなさい」とだけ言えばすむわけではない。 ・「こういうことをして、こういう間違いをしたから、ごめんなさい」としなきゃいけない。 ・でも、肝心の何をやったか、何を間違えたかという部分を、日本人自身がよく理解していないんですよ。 ・当事者でさえも、自分が何のために中国と戦争しているのか、十全には理解していなかった。そこに問題の源泉があるように思いますね。 宮台 ・ふつう補給線について考えながら作戦を評価するのが当たり前なのに、レイテ戦とかインパール作戦では、武器・弾薬はおろか水や食料の補給もなかったので、死者の内訳で餓死者や病死者が九割を超えるといったデタラメが横行していた事実があります。 ・つまり、補給線という観点から言えば、日本軍の戦いは、持久戦となった途端に勝算がなくなるということなのです。 ・そのことは、誰もが知っていたはずなのに、なぜかそのことを議論した形跡がない。 ・で、極東国際軍事裁判になると、いわゆるA級戦犯のほぼ全員が「自分には権限がなかった」「いまさらやめられないと思った」「空気に抗えなかった」と言った証言をし出すわけですよね。 橋爪 ・日本の兵士は補給がないので、自分の裁量で中国の農家に出かけて行って、物資を調達した。 ・相手は丸腰の農民で、こっちは武器をもっている。早い話が、強盗です。 ・無理やり物資を奪い取り、拒めば殺害する。ついでにやりたい放題の暴力行為に及ぶ。 ・日本軍はそういう状態を、中国全土につくりだした。 ・その結果、数千万人単位の中国の人々が、命を落とし、財産を奪われ、人間の尊厳を傷つけられた。 ・南京事件の何十倍、何百倍もの被害です。だけど、それらはあちこちで散発的に起こっているので、証明がむずかしい。 ・そこで、これら全体の象徴として、南京事件の被害は三十万人と、中国政府は言っているのです。 ・その南京事件すら否定するなら、日本人は、過去の犯罪行為をまるきりなかったことにしようとしている、と受け取られる。 大澤 ・南京事件を、戦争全体の文脈から切り離して、それだけを見てはだめなわけですね。 ・南京事件が、日中戦争の全体を隠喩的に圧縮している、そんなふうに考えないといけない。 8 過去を引き受けるために 橋爪 ・歴史を学ぶ意味は、過去、ある行為をした人びとや集団と、現在の自分たちとが、どういうつながりがあるかを学ぶこと。その一体感がないと、歴史は学べない。 ・歴史は過去との連帯責任の感覚なのです。 ・日本は戦前の中国を侵略した世代と、現在の世代とのあいだの、連続性を設定することに失敗している。 ・失敗しているから、過去について謝れない、実は。 ・謝れないのに謝れと言われるから、謝る。何回でも。でも内心は、謝っている実感がないから、失言も出てくる。そういうことなんです。 宮台 ・靖国問題は東京裁判と一体です。 ・この裁判は、国際法違反や倫理道徳違反についての罪を、もっぱらA級戦犯が悪かったという虚構を打ちたてて手打ちとし、天皇と大半の日本国民から取り除いて、日本の戦後復興への国際協力を可能にするための工夫でした。 ・もちろん、ほんとうはA級戦犯だけが悪かったのではない。 ・でも、A級戦犯は悪くなかったと言えば、天皇や国民が悪かったということになり、天皇の戦争責任問題が沸騰すると同時に、国民も何も尻ぬぐいをしてねえぞという話になる。 ・だから、A級戦犯がもっぱら悪くなかったにせよ、靖国神社に合祀してはならないし、私的神社として勝手に合祀したのなら政府首脳は参拝してはならない。 ・でもこれは顕密体制みたいなものだから、忘却症だったり鈍感だったりする人たちがA級戦犯は悪くなかったと頻繁に噴き上がるのです。 ・ちなみに、日中国交回復の際も、周恩来首相は東京裁判の虚構を踏襲することを宣言し、日本国民は騙されただけで悪くなかったとしています。 ・ぼくは東京裁判という虚構図式の踏襲が合理的だと考えています。 ・だから、謝罪といっても、単に「日本が謝罪する」というあいまいさを避け、「A級戦犯が指揮した作戦行為や戦闘行為は悪かったし、それらの行為が悪かったことを政府や国民は理解しているし、A級戦犯を自力で取り除けなかったことを悔やんでいる」と言えばいい。 ・現にそれが「日本国民は悪くなかった」と語った周恩来首相が望んでいたことでしょう。 ・謝罪の内容が未規定だから、プライドにさわると騒ぎ立てる人たちが出てくるんです。 ・謝罪の内容を規定するのであれば、これ以外の仕方はないはずです。 大澤 ・ぼくらは過去のことについて謝らなければいけないわけですよね。 ・しかも、過去と言っても、自分がやったことではなくて、自分が生まれる前のことについて責任があると言わなければならない。 ・そうすると、そこに過去からの何らかの連続性を立てないといけない。 ・過去において南京で中国人を虐殺した兵士と自分とのあいだには、ただの他人ではない関係があると引き受けなくてはならない。 ・そのために歴史というものがある。歴史は、過去と現在のわれわれとのつながりを納得するためのものですよね。 ・一般には、こうしたつながりを理解することが、現在のわれわれの自尊心や尊厳の感覚を強めてくれるわけです。 ・われわれの先祖がいかに立派で、そのおかげで現在のわれわれがいる、ということを理解することになりますからね。 ・逆に言うと、そういう自尊心や尊厳の感覚を全面的に否定し、ずたずたにしてしまうような歴史と 第4部 中国のいま・日本のこれから 3 中国の資本主義は張り子のトラか 橋爪 ・中国人が、個人主義的で合理主義的でプラグマティックなところは、実はアメリカ人とよく似ている。日本よりもよく似ているんじゃないかと思う。 大澤 ・日本で資本主義が早くから成功したのは、日本人がすごく西洋化したというよりも、日本人的なライフスタイルやものの考え方が、資本主義の中で、非常に適応的だった、という面があった。 宮台 ・日本は、「まかせて文句をたれる作法」であって、「引き受けて考える作法」ではない。 ・で、まかされる側は、残念ながら知識や合理性を尊重する作法ではなくて、空気に縛られる作法ですよね。これが組み合わさると、なかなか合理的な意思決定はなされません。 4 共産党の支配は盤石か 橋爪 ・そもそも儒教国家なるものは、儒教を体現した行政官僚が国家をつくっていて、そこには複数政党(道教とか、法家とか、別な考えの人びとが対立候補として存在する)という発想がない。二千年以上にわたってこの考え方でやってきた。 ・もしこれが、儒教国家ならば、キリスト教的に翻訳すれば神政政治です。 ・いまの共産党政権は、政党である共産党が他の党を弾圧して一党独裁をしているのではなく、たんに中国的な意味での神政政治なのであって、対立政党は存在しえない。こう考えたらいいのではないか。 7 日本は米中関係の付属物にすぎない 宮台 ・最終的にはアメリカ側について、アメリカを相対的に重視する方向でやっていかざるを得ない。 ・これは、世界の大半の国々が、中国覇権よりもアメリカ覇権のほうがマシだと考えて、凋落するアメリカ覇権につっかえ棒を提供するからです。 ・しかし、最終的にはアメリカ側につくということと、日常的に対米追従外交をつづけることとは、区別されなければなりません。 橋爪 ・「アメリカについていく」というのは、それは、アメリカの言いなりになるとか、アメリカにマインド・コントロールされるとか、アメリカに何を言われてもハイハイと従うとか、いいように騙されるとか、そういう意味では全然ない。 ・小さな国ほど外交では、情勢を正しく分析し、十分リスクをわかったうえで、最善の選択をし続けなければならないんです。 8 台湾問題 橋爪 ・普天間の海兵隊とか、沖縄の米軍は、北朝鮮もにらんでいるけれども、台湾海峡もにらんでいる。 ・この微妙な軍事バランスが崩れて、万一のことがあれば、どれぐらいの損失が生じるかというと、人命だけでも何千、何万です。 ・それから、米中関係が破壊されることによるアメリカの不利益、とばっちりを受ける日本の不利益、そして中国の被る膨大な不利益。改革開放の成果など一瞬で吹っ飛んでしまうでしょう。 ・これを食い止めてね、中国に、軍事的な選択肢はないと国内向けに言い訳できるようにしてあげる。 ・そしたら、台湾を何とかしろという中国民衆の圧力を、北京政府はかわすことができるんです。 ・悪いのはアメリカだ、そして日本だ、と言えばすむ。このことの利益がどれぐらい大きいか。 ・だから、沖縄をめぐって、日本とアメリカがぎくしゃくすることがどれだけ大きなリスクか、よくわきまえなければならない。 ・基地があっても、沖縄にはいいことなんかほとんどないが、同時にそこに、日本はもちろん、アメリカや中国や世界の大きな利益と人命がかかっているということも考えなければならない。 10 日本がとるべき針路 橋爪 ・わが国と中国のあいだを考えてみると、考え方や価値観がちがうのみならず、個人的な信頼関係もほぼ皆無なんです。これはおもに日本の責任だと思う。 ・だって、アメリカ人と中国人のあいだに個人的な信頼関係が築けるのに、なんで日本人と中国人のあいだに個人的な信頼関係が築けないのか? ・それは、日本人の発想や行動様式があんまり日本的で、中国のやり方と似ていないからです。 ・日本が中国をリスペクトしないとすれば、それは日本側の偏見によるのです。 ・個々人としての中国人と、個々人としての日本人を比べてみると、たいていの場合、一対一だったら力負けすると思う。とくにリーダー同士の場合。 ・中国のリーダーは、ひとりの人間として、自分の拠って立つ価値基盤とか人生の目標とか仕事上の責任とか世界観とかを、自覚的・意識的に構成している。他者に対して自分の行動をどう説明するかも、いつも意識している。 ・それは、本人は意識しないかもしれないが、儒教の行動原理。儒教は、個人プレーの集まりなんです。 ・それに対して、日本人の場合はそういう習慣がない。大事なことは集団で決め、組織として行動するから、自分の考えや行動を相手に説明もできないし、自分でも納得できない。これでは、負けてしまう。 ・だからね、もっと中国の個々人や、それの集合体である中国という文明の伝統を、日本人はよく知ってリスペクトしなくちゃいけない。 ・アメリカをリスペクトするんだったら、あんな二百年の歴史しかない国より、もっと中国を知るべき。中国は日本のルーツでもあるんだから。 大澤 ・いまのところは、米中が基本的には対立しているということから、漁夫の利を得ているというのが日本のポジションだと思うんです。 ・ほんとうは、中国を理解するということに関しては、日本人のほうが、アメリカ人よりはるかにアドバンテージがあるはずなんです。 ・だって、日本の文化は中国に影響されながら今日まで来たわけだし、文字だって、かなり共有しているわけだし。 ・日本はそういう意味で有利な立場にあるわけですから、中国との関係において、アメリカがまず仲良くしなければいけないのは日本なんだという構造をつくることが、いま重要だと思いますね。 宮台 ・中国にとって、アメリカと良好な関係を保とうとすれば、日本と仲良くするほうがコストが安くつき、アメリカも中国と仲良くしようと思うときに、日本と仲良くしたほうがコストが安くつくというポジションをとることで、日本はアメリカと仲良くしながら、国益を失わず、アメリカと中国が仲良くすることの利益を獲得することができるということです。 橋爪 ・相手を理解する努力を日本がすべきです。中国は大きい国で、アメリカも大きい国なわけですから、両国をしっかり理解しないとダメ。 ・「しっかり理解する」とは、知識の問題ではなく、こちらが人間として高まることを意味します。 ・たとえば歴史問題を例にとると、歴史についてギャアギャア言われるので、日本人は、言い訳をしようと考える。そうじゃなくて、これをメッセージとして受け取らないとダメなんです。 ・中国がなんで歴史問題をいろいろ言うか。それは「歴史問題さえ片付けば、一緒にやりたいことがたくさんありますよ」といっているんです。 ・それなのに日本が言い訳するから、相手は当惑する。そんなことを聞きたいのではない。言い訳もいいが、問題はその先なのに、全然ピンと来てないひとたちだ、と中国では思っている。 ・靖国問題だってそうです。中国が靖国神社への「公式参拝」をうるさく非難し始めたのは、A級戦犯が合祀されてから。 ・中国は、東京裁判を日中関係の基点としているから、A級戦犯にこだわらざるをえない。 ・日本人にとってはうっとうしい話ですが、でもこれは裏を返せば、日本の一般国民が靖国神社に参拝することに、中国は文句を言っていないし、A級戦犯が合祀されていなければ、首相が公式参拝してもかまわない、ということなんです。 ・中国としては注意深く、ハードルを下げているつもりなんです。 ・中国人はどういうときにどう行動するか、中国の歴史に照らして、その類推で現在の彼らを見るなら、わかる。 ・中国人は互いにそういう読解をしながら、中国社会を生きている。そして、中国はまだローカルな文明で、世界化されていないから、外国に対してもいつも同じようにふるまってしまう。 ・たまたまアメリカとは波長が合うから、ある程度わかり合えるんだけど、日本人はわからない。 ・もう一歩進めて、中国が困っていることを日本がよく分析し、理解して、中国に代わって世界に向けて言ってあげる、なんていうのもいい。日本が中国を代弁してあげる。 ・中国が困っていることの一例。炭酸ガスを山のように出している。 そこで中国が何をしているかというと、植林をしている。 いまはまだ、森林が成長の途中だけど、ゆくゆくは、最大約五千億トンもの膨大な炭酸ガスを吸収する計算になる。 これをポスト京都議定書の温室効果ガス排出規制の協定を結ぶときに、森林吸収の控除として計算することにしようと、日本が提案してあげる。 ・日本には森林はたくさんあるけど、新規の植林はほぼゼロですから、炭酸ガス勘定には関係しない。 ・いっぽう中国は、植林がカウントされると、大きな利益をうる。 ・でも中国がそれを言うと、自国の利益のために主張しているとみられてしまう。 ・だから日本が、これを大きな声で言うべきだ。 ・中国は当然、日本が中国のために言ってくれているとわかるし、第一これは正論でしょう? ・そうすると中国は恩に感じて、お返しをしようと思う、もう本能的に。日中関係は、良好な方向に一歩進む。しかも日本は、一円もかからない。 ・中国に出かけていって、「日中友好」と何回言っても、意味がない。レストランで宴会をやって、それで終わり。 ・そうじゃなくて、中国が困っているときに手を差し伸べ、よりよい信頼関係をつくる。そういうアイデアをいくつ出せるかということなんです。 ・日本は中国のことをわかってくれていると、中国が思えば、日本の利益になる。 大澤 ・日本はアメリカがどう反応するかを見てから言おうといつも思っているから、ダメなんです。 橋爪 ・香港と中国の関係を考えてみると、毛沢東は、中華人民共和国の成立後もこの香港の、イギリスの権益を承認した。イギリスは帝国主義ですよ。植民地主義ですよ。でも中国は、香港に指一本触れなかった。 ・イギリスはどうしたかというと、お礼に、中華人民共和国を承認した。 ・これは、中国の国際的地位を高めるのに役立った。中国の国連加盟問題でも、アメリカがどんなに反対しようと、中国の肩をもち続けた。中国に恩を売ったわけだ。これは大人の関係でしょ? ・その間日本は、アメリカにくっついて反対票を投じた。 宮台 ・日本はいくら「べき論」を言っても、空気が動かなければ何も動かないという問題を抱えています。 ・しかも現在の空気は、中国脅威論の一辺倒です。そしてこの一辺倒は、オヤジメディアの疑似的な絆ツールのように機能している。いわば、習合的な「弱い犬ほどよく吠える」状態です。 ・アメリカの法学者キャス・サンスティーンによれば、昨今は民主主義が集団的な極端化を招きがちで、その背景にあるのは、第一にグローバル化がもたらす格差や貧困などによる不安や鬱屈、第二に不完全情報です。この二つの条件がそろうと、不完全な情報しかない領域で極端な発言をすることで、自分や周囲の溜飲が下がり、集団内での承認も得られることになります。 ・ではどうするか。グローバル化がもたらす不安と鬱屈を取り除くのは大変だから、不完全情報の状態を完全情報化にむけてシフトさせて、 ‹溜飲厨› や ‹承認厨› の影響力を排除しよう。そのためには、情報公開と、立場の異なる専門家同士の公開討論と、専門家を排除した熟議を通じた決定が不可欠だ――これが、単なる熟議じゃ役に立たないという彼の議論です。 ・完全情報化というところでは、日本でもいろいろできることがありそうですよね。 橋爪 ・日本からのいいサインは、中国研究所をつくることです。見栄えがいいプランで、「中国をこれから重視するから、研究所をつくります」といって、予算を出す。ついでにアメリカ研究所もつくる。これだけでも大きなサインになるんです。 ―― 完 ―― |