
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年08月16日 木曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
63 |
18/07 |
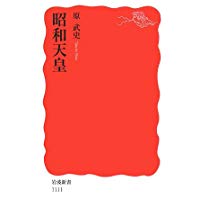 |
昭和天皇 |
原 武史 |
岩波新書 |
◎ |
序章 1986年の新嘗祭 戦前と戦後の連続面 ・占領期の昭和天皇は、連合国最高司令官との会見を通して政治的意思を表明し続けたほか、日本国憲法で象徴とされてからも、戦前から続く内奏に対する下問を通して、政治力を保とうとしたことがわかっている。 第1章 「万世一系」の自覚 地方視察と天皇陵参拝 ・歴史に忠実に従えば、平安時代から江戸時代にかけての天皇の多くは、生前も没後も「~天皇」と呼ばれたわけではなく、没後には「一条院」「御水尾院」という具合に「~院」と呼ばれたが、東宮御学問所で、国史を担当した白鳥倉吉はすべての天皇の表記を「~天皇」で統一した。 百二十四代天皇を実感 ・神武以前の三陵を含むすべての天皇陵が確定するのは一八八九(明治二十二)年になってからであった。 ・その意味では、「万世一系」を象徴する天皇陵もまた、宮中祭祀と同じく「創られた伝統」にほかならない。 ・今日では、天武・持統合葬陵と天智天皇陵を除けば、古代の天皇陵で被葬者が一致するものはほとんどないという見方が有力になっている。 第3章 天皇としての出発 大正天皇死去後の皇太后 ・裕仁は天皇になるや、女官制度の改革を実行に移した。 ・赤坂離宮では皇后宮職がおかれたが、ここに所属するのは女官長、女官、 ・女官は既婚の女性とし、源氏名を廃止するとともに、通勤制も導入した。側室制度は名実ともに廃止されたのである。 第4章 戦争と祭祀 「努力と神力によって」 ・太平洋戦争期の天皇は、宮中祭祀を継続しながら、祭祀権を事実上皇太后に奪われる格好になっていた。 ・皇太后の念頭には神功皇后があったように見えるが、伝説ではなく歴史的に見れば、この時期の皇太后は、むしろ琉球王国における ・琉球には、行政権をつかさどる国王のほかに、祭祀権をつかさどり、国王の姉妹や王妃、王母が任命される聞得大君という女性がいたからである。 ・聞得大君が国王になった例はないが、祭祀権が行政権を超えて効力を発揮した可能性は指摘されている。 「三種の神器」の確保が第一 ・天皇がこだわった「国体」の護持というのは、「万世一系」の皇室を自分の代で終わりにしてはならないということであり、国民の生命を救うのは二の次であった。 ・敗戦直後に天皇は、日光にいた皇太子にあてて手紙を書き、「今度のやうな決心をしなければならない事情」について、「戦争をつゞければ 三種神器を守ることも出来ず 国民をも殺さなければならなくなったので、 涙をのんで 国民の種をのこすべくつとめたのである」と説明している。 ・「三種神器」が一、「国民」が二という順序は変わっていない。 第五章 退位か留位か 天皇とマッカーサー ・当時の米国では、世論はもとより、政府や議会にも天皇を戦争犯罪人として裁くべきだとする声が多かった。 ・しかし、マッカーサーは、占領統治を円滑に進めるためには天皇を利用した方が得策だという政治的判断をしており、天皇制の廃止はもちろん、昭和天皇の戦犯指名も退位も考えていなかった。 ・天皇はやがて退位すべきか留位すべきかで迷うことになるものの、それ以外の点に関しては、マッカーサーの見解と奇妙なまでに一致していた。 ・九月二十七日に開かれた第一回天皇・マッカーサー会見は、日米合作による天皇の免責工作の始まりを意味していた。 ・天皇自身やマッカーサーと同様、ほとんどの日本国民もまた天皇制の存続を望んでおり、昭和天皇の責任を独自に追求することはなかった。 革命を恐れて ・天皇がマッカーサーに擦り寄る背景には、共産党の合法化や東西冷戦という、戦前とは全く違う政治状況があった。 ・四六年五月一日、宮城前広場で開かれた戦後初のメーデーには、五十万人が集まった。「天皇制打倒」「人民政府樹立」を叫ぶ勢力が、宮城のすぐ目の前まで迫ってきたのである。 ・こうした革命前夜のような状況もまた、天皇をして当面の退位を踏みとどまらせる動機につながったのではないか。 ・第三回会見では、天皇がストライキに対する不安を強く訴えたのに対して、マッカーサーは「共産主義者は、教育なき者にいろいろと口約束をし、勢力を獲得して、軍閥がやった様に、日本国民に『レジメンテーション』〔組織化〕を行おうとして居ります。極右、極左何れも危険であります。日本は何れにも片寄らず真中の大道である民主々義を行くべきだと存じます」と述べた。 ・天皇が何よりも恐れていたのは革命であり、マッカーサーも同じ判断をしていた。 内奏と下問 ・天皇は、「日本としては結局アメリカと同調すべきでソ聯との協力は ・首相や閣僚が内奏し、天皇が下問する慣習はその後もずっと続くことになる。 ・それだけではない。天皇は宮内府御用掛の寺崎英成を通して、米国による沖縄の長期占領を望むメッセージを、米国国務省に伝えていた。 ・七九年四月十九日、天皇は入江相政に、「アメリカが〔沖縄を〕占領して守ってくれなければ、沖縄のみならず日本全土もどうなつたかもしれぬ」と述べている。 祭祀にこだわった理由 ・天皇が戦後もなお祭祀にこだわった理由としては、一つには戦中期における自らの誤った祈りを「神」に対して謝罪し、悔い改めて平和を祈り続けようとしたことがあろう。 ・天皇は、「平和の神」であるはずのアマテラスに戦勝祈願をしたことで「御怒り」を買ったという認識をもっていた。 退位の否定 ・東京裁判が結審し、A級戦犯に判決が下されたのは、四八年十一月十二日のことであった。 ・A級戦犯が処刑された同年十二月二十三日とともに、裁判の舞台裏を知り尽くした天皇の精神的危機が最も高まった日だったと思われる。 ・同じ十一月十二日、天皇はマッカーサーにあてて、「いまや私は一層の決意をもって、万難を排し、日本の国家再建を速やかならしめるために、国民と力を合わせ、最善を尽くす所存であります」というメッセージを提出し、退位を否定した。 ・これは天皇自身の積極的な意思というよりは、むしろ退位を認めないマッカーサーの意向に沿ったものであった。 伊勢神宮と靖国神社へ ・退位の道を断たれた天皇は、生涯をかけて平和を祈り続けるという決意を固め、「祖宗」に誓ったのかもしれない。しかし、天皇が発した謝罪の言葉を、「万姓(国民)」が直接耳にすることは永久になかった。 第六章 宮中の闇 靖国神社への参拝 ・天皇は八八年四月二十八日、「私は或る時に A級が合祀され その上 松岡、白取〔鳥〕までもが、・・・だから、私はあれ以来参拝していない それが私の心だ」と話した。 ・靖国神社に参拝しなくなったのは、松岡洋右や白鳥敏夫を含むA級戦犯が合祀されたからであることを、天皇自身が明らかにしたのである。 ・『春秋左氏伝』の「吾以靖国也」を典拠に、東京招魂社を靖国神社と改称させたのは明治天皇であった。 ・天皇は八八年五月二十日、「靖国 明治天皇のお決になって〔た〕お気持ちを逸脱するのは困る」と話している。 ・A級戦犯を合祀すれば、明治天皇が定めた「国をやすらかにする」という靖国神社の根本に反してしまう。それでも参拝すれば、昭和天皇は戦争を遂行した人物を「神」とする神社に平和を祈るという矛盾を冒してしまうことになる。 ・徳川善寛によれば、天皇はA級戦犯の合祀に反対する理由の一つとして、「国のために戦にのぞんで戦死した人々のみ魂を鎮め祭る社であるのに、その性格が変るとお思いになっていること」 最後のこだわり ・八八年に入ると、天皇はますます公務復帰や生物学研究の再開に意欲を見せるようになった。 ・一月二日の一般参賀では、天皇は午前中、宮殿の長和殿にあるバルコニーに、三回にわたって出た。 ・八月十五日に日本武道館で行なわれる、全国戦没者追悼式への出席は、祭祀ができなくなった天皇の最後のこだわりを意味していたはずである。 ・このときはじめて、天皇は「神」に対する御告文よりも、国民に対する「お言葉」の方を優先させたのかもしれない。 ―― 完 ―― |