
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年12月05日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
80 |
18/10 |
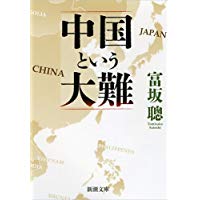 |
中国という大難 |
富坂 聰 |
新潮文庫 |
◎ |
プロローグ ・中国で、服役しているはずの囚人が街中で目撃されたなどという話は珍しくもない。 ・刑務所の近くでは、監獄の内と外とを自由に行き来する囚人の話など、ありふれていちいち驚く価値すらない。 第一章 三峡ダムが中国を滅ぼす 危機的状況の水不足 ・人間の暮らしにとって不可欠な水がそもそも中国には乏しい。 ・ただでさえ乏しい水資源を工業の発展を優先することで容赦なく犠牲にしてきた従来の姿勢をすぐにでも改めなければ、将来、中国社会は本当に深刻な事態に直面する。 ・実は、水不足と洪水こそ中国が有史以来ずっと抱えてきた悩みでもあるのだ。 ・大河を有する中国に水が足りていないことの説明は多岐にわたる。 ・第一に、毛細血管にたとえられるほど細かい河川が中国には決定的に不足していることが挙げられる。 ・乏しい水資源には、さらに水質の問題が重くのしかかる。 ・中国の河川は長い距離をゆっくりと流れる川が多いため、水が汚れやすいという特徴を持つのだ。 環境か経済かで殺し合う人々 ・もし水を汚染から守るために工業廃水に汚染基準を厳格に適用したとすれば、中国の多くの企業が倒産に追いこまれることは避けられない。 ・そうなれば当然、失業者が増え、ひいては社会不安にもつながってくる。治安や安定した雇用に責任のある行政としては難しい判断を迫られることになるのだ。 ・少なくとも、仕事を奪われる者たちは、自分たちの糧道が絶たれるのを唯々諾々と受け入れるはずもない。 ・そこには大きな強制力を働かせなくてはならないのだが、彼らの食を奪う大義が「水を守る」というのではいまの中国の社会ではとても受け入れられないはずである。 ・中国の水汚染は、すでに背水の陣で臨まなければならない段階にまで追いつめられています。 ・現在、工業廃水の処理基準を満たす設備をそなえた企業はわずか二十三万社しかない(全中国の企業数はおよそ三百万社))。 水を奪い合う北京と天津 ・極度の競争社会である中国においては、やはり人々の生存権が水の環境保護より優先されるのである。 第二章 汚職天国 官僚腐敗が国を亡ぼす ・世界が目を見張る経済成長は、中国に大きな富をもたらした。しかし、同時にこの繁栄の代償として、中国は二重の汚染に苦しめられることにもなった。 ・一つは、環境問題、そして、もう一つは、共産党官僚による汚職の蔓延である。 ・国家の研究機関に属する研究員が解説するその深刻な状況 「中国における贈収賄事件は、七九年には、立件はわずかに七百三件でしたが、八九年には六万件、九九年には百一万件、〇〇年から〇四年までの五年間では、一千八百四十五万件にも達しています。 件数の激増だけではなく、高い地位の官僚が事件を起こすようになり、連座する官僚の数も増えています。 そして、賄賂の金額もどんどん跳ね上がっていく傾向にあります。 いまの中国共産党の上層部には、腐敗の蔓延に対する強い警戒感があります。旧ソ連が崩壊に追い込まれた本当の理由が、この官僚や政治家たちの腐敗にあったことを知っているからです」 ・中国共産党の上層部は、九一年のソ連崩壊を反面教師として多くのことを学習してきた。 国外逃亡する腐敗官僚たち ・監察部のある関係者は言う。 「二〇〇四年末までの時点で、不正蓄財の末に海外に逃亡した官僚の数は、六千五百人を上回り、不正に持ち出された金額の合計は四百五十億元を超えています」 「含金量」が高いポストを奪い合う官僚たち ・官僚の占めるポストが、金銭に換算してどれくらいの価値を持かを表す言葉に「含金量」という造語がある。 ・一九九二年当時、同時に「灰色収入」と「黒色収入」という露骨に汚職を想起させるような言葉が聞こえてくるようになった。 ・さらに、「含金量」が高いポストにいち官僚が、その旨味の多い地位にとどまるために出世を拒否したというニュースが話題になっていた。 ・二〇〇六年当時の中国の官僚機構の中で、「灰色」「黒色」の収入が最も見込まれると噂されていたのが、人事を取り仕切る「組織」、そして「税務」、「公安」などの部門だという。 ・これに続いて、「工商管理」といった経済官庁や「建設」、「交通」などといった許認可が絡む部門、そして最近では、「環境保護」関連も「含金量」を伸ばしていたとされるが、現在ではこれに加えて税関職員などが人気を集めているという。 ・公務員の本業は「収賄」だと言っても過言ではない状況すら、一部には生まれてきているのである。 ・賄賂が作り出す格差というのは同じ職場内でのものであり、そのことが引き金になって職場のみならず、地域内に凄まじい軋轢を生み出す。 ・官僚たちは「含金量」の高いポストを手に入れようと、熾烈な猟官運動を繰り広げ、そのプロセスでは当然のように金銭が飛び交うため、人事を司る「組織部」が最も潤うことになる ・問題はこの負の慣習が民間にも連鎖することである。猟官のための資金は、地域内の民間企業が出所となるケースが多いからだ。 ・二〇〇〇年代半ばまでの過去十万件の収賄事件を遡って調べてみると、その六三%が建設事業に絡んでいる。 ・さらに問題なのは、汚職の絡む事業では、巨額の賄賂を捻出しなければならないため、どうしても手抜き工事が横行してしまうことです。 絶望的な不平等 ・忘れてならないことは、人口で九億人とも言われる農民は医療制度からも見放され、年金も当てにできないまま生きているということだ。 ・また、都市部で暮らしていても、出稼ぎのマッサージ師やウェイトレス、新興の中小私営企業、赤字で苦しむ国有企業の労働者たちは実質的には医療保障にも守られていない。もちろん、年金などあてになるはずもない。 ・彼らが直面する厳しい現実と比べれば、官僚の定年後の不安など取るに足らないものだと言えよう。 ・こうした絶望的な不平等が存在する一方で、汚職はこのどうしようもない格差を猛スピードで拡大させる。 ・金が政治との癒着を生み、政治がまた特権的な富をもたらすという腐敗の循環が形作られるからだ。 ・こうして富む者はさらに富み、貧しい者はさらに窮するという、社会の二極分化は、拡大の一途をたどることになる。 ・しかも、汚職という犯罪行為がこのプロセスを加速させている以上、これは資本主義や市場経済とは根本的に異質な、歪んだ社会構造だと言わざるを得ない。 犯罪の陰に女あり ・二〇〇六年から五年間をさかのぼり集計された一つの統計によれば、腐敗事件に絡んで実刑判決を下された官僚のうち、愛人を囲っていた者は全体の六五%、また、九五%の官僚には、囲うまでには至っていなくとも情婦の存在が認められている。 報道の自由がないことの弊害 ・中国が、ソ連の崩壊を反面教師として学び、社会主義一党独裁体制を延命させた。 ・彼らは、そこから官僚腐敗がもたらす結果の深刻さを学習したが、同時にソ連末期におけるグラスノスチ、すなわち「情報公開」の失敗も学び取ったのである。 ・だからこそ、中国は、二十一世紀に入った今日に至っても、依然として、報道や言論の自由を規制し、メディアやインターネットをコントロールし続けているのである。 ・自由な報道活動を許さずメディアの機能を奪ってしまったことで、汚職のような権力の犯罪に対する抑止力を失い、結果的に一部の政府機関による孤軍奮闘を余儀なくされることになった。 ・これはたとえれば、予防という措置を講じないまま、ウイルスの増殖と戦っているような状態である。 ・対症療法だけで腐敗に立ち向かうのは、体制の欠陥と言うほかない。 第三章 十三億人市場という幻想 「スターバックス」と「足ツボマッサージ」 ・北京の足ツボマッサージ店を支えているのは、地方の貧しい町から流れ込んできた出稼ぎ労働者たちである。 ・多くは二十歳前後の女性たちだ。彼女たちは歩合給である上に保障もない。 ・医療保障制度から完全に見放されている彼女たちは、体調を崩しても医者に行くことなどない。ただでさえ収入が低い彼女たちにとって、自費での医療は目玉が飛び出るほど高額だからだ。 ・また、病院の方でも焦げ付きを恐れるあまり診療を拒否するというケースが後を絶たず、社会問題になっている。 ・中国社会においてはいまや低所得者が完全に医療から見放された状態にある。 ・薬に頼らなければならないとき、彼女たちにとっての強い味方とされていたのが、ヤミで売買される「 ・二〇〇六年、「過期葯」が消えてしまった。 ・理由は、「過期葯なんてもう古い。いまは医療保障を受けられない者も知恵をつけた。保険のある者に頼んで医者に行ってもらい、そいつから薬を買うのだ」とのこと。 ・このやり方だと、保険のないやつは薬をより安く手に入れられるし、保険のあるやつは小遣い稼ぎになる。 ・医者だって怪しいと思ったって結局は病院が儲かれば文句はない。誰も損しない。 ・医療保障制度で守られている者は、その恵まれた立場を利用して「持たざる者」から金を稼ぐことができる。これでは恵まれた者はさらに富み、貧しい者はさらに窮するばかりだ。 九億人を超える "虐げられた人々" ・ このしわ寄せは最も弱い農民や出稼ぎ労働者たちを襲い、彼らの生活は、小さな寒暖を繰り返しながらも全体としては年々、確実に追いつめられているのだ。 ・「なぜ、中国の農民たちは団結して立ち上がらないのか? 自分たちの置かれた窮状を訴えようとしないのか」と訊ねたことがある。 ・理由は二つしかない。 一つは中国の農民が極めて我慢強いということ。そしてもう一つは残念ながら無知であるから。 ・彼らはいま自分たちの置かれた苦境が政治のせいだとは考えないのです。それぞれ個人の能力や運命の問題だと考えてしまう。だから、一時的に怒りを爆発させることがあっても、それが政治運動には発展しない。 ・だが、この言葉は、もし彼らの怒りが臨界点に達したとき、その尋常ではないエネルギーが爆発し、ときに取り返しのつかない恐ろしい事態に陥りかねないことを暗示するようでもある。 ・農民は人口にして九億人を上回る中国での最大勢力となっている。 ・そして、ごく一部の富農を除いて、大多数の農民は社会保障から置き去りにされているのだ。 ・だが、中国の "主役" である彼らの置かれている状況が、国外に伝わってくることは滅多にない。 ・日本のメディアが中国農民にスポットを当てることなどなく、それは日本人の興味がそんなところにはないことを知っているからだ。 二十万人に膨らんだ中国人妻たち ・入管幹部が教えてくれた。 「平成十七年の数字で見ると、『日本人の配偶者』の資格で在留する中国人の数は約五万二千人。定住者は約三万二千人。永住者は九万人となっています。三つの数字はそれぞれ『中国人妻』と呼ばれる人々を指し、その合計はざっと十八万人にも上ります。 ・ここ数年、『中国人妻』の新規の入国は毎年四千人から五千人の間で推移していますから、現在、日本で暮らしている『中国人妻』という意味では概算で二十万人はいると考えてよいのではないでしょうか」 ・流入が始まってからわずか十数年という期間を考えれば、著しい急増ぶりだと言えよう。そして二〇一二年にはこの数字も三十万人を超えるまでに膨らんでいる。 在日外国人最大勢力となる中国人 ・中国人の外国人登録者数は、二〇一二年時点で八十万人に達しようとしている。 ・「不法残留の外国人約二十万人のうち半分を中国人と考えれば、すでに中国人の数は在日韓国・朝鮮人と同等。いずれ一、二年のうちには逆転することは間違いない。 ・もしも彼らが、在日韓国・朝鮮人が戦後間もなく設立した民団や総連のような組織を立ち上げれば、日本社会の中で大きな政治力を持つことができる。 ・「ニューカマーの中国人による団体がこの数年で増え続け、いまでは主要なものだけでも四つになりました。何を目的にどんな活動をするのか、注意して見てゆく必要はあるでしょう」(某県警外事担当者) ・五十万人の登録中国人のうち、約四〇%という圧倒的な存在を占めているのが、他ならぬ中国人妻であったのだ。 放り出される中国の労働者たち ・年金と医療保障制度は、手厚い補償を受けられる人とそうでない人々との間に深刻な格差を生み出している。 ・都市の労働者の場合では、本来なら国が責任を持って担うべき制度が、すべて地方政府から各企業単位へとその責任が移ってしまい、その後、企業がそれを持ちこたえられなくなったという事情がある。 ・そのため体力のある企業とそうでない企業の従業員では、将来の備えに対する不安の感じ方に差が生じてしまったのである。 ・時代に取り残された国有大企業の従業員の場合、極端に言えばもはやどちらもあてにはできない状況となっている。 ・労働者を最も多く抱えていた国有セクターは、九六年から二〇〇〇年までの四年間に約三千二百万人をリストラし、これに次ぐ労働者の拠り所だった集団企業も約千五百万人を切り捨てている。 ・一方、国有セクターや集団企業に代わって中国経済の主役となった私営企業は、利益追求に熱心だが、福利厚生など社会的使命には消極的だ。 ・二〇〇九年、中国の年金カバー面積は一五%で、アフリカなどを含めた世界平均である二〇%にも届いていない。 行先の分からない満員列車 ・そもそも、中国の前途に横たわる難問は、見つけたり気付いたりすることが難しいのではない。 ・逆に、誰にでも分かる問題でありながら誰にも解決できない問題がほとんどなのである。 「水は誰がどこから運んできてくれるのか?」 「金持ちが海外に逃げてしまうことを恐れて税金を取り立てられず、相続税もない中国の社会で、どうやって富の再分配をするのか?」 「高齢化社会の財源はどうするのか?」 「官僚の腐敗はどうやって止めるのか?」 「富裕層の海外逃亡をどう防ぐのか?」 「最も深刻な格差をどう解消するのか?」 ・二〇〇六年の春節。やはり中国では故郷に帰る人の大移動が例年のように起きた。 ・金持ちは飛行機を使い、そうでない者は列車に乗る。列車にも一等の寝台から硬座までの四段階があり、その下には座席のない「無座」という切符もある。 ・無座の場合、二十時間でも三十時間でも目的地まで立ち続けていかなければならない。 ・だが、たいてい車両内は満員で足の踏み場もなく身動きが取れないのが常だ。 ・足の踏み場もない車内では混雑のためトイレも使えなくなる。必然的に長距離では大小便がその場で垂れ流されることが多くなる。 ・〇六年は、そんな状況を見越して、大人のオムツがバカ売れした。 第五章 日中外交戦争 「親中派」大臣の登場 ・東シナ海から尖閣諸島を経て与那国島に至る排他的経済水域(EEZ)の帯。常に緊張をはらむこの海を海上警備のプロたちは、 "魔の海" と呼び警戒する。 ・密漁、銃器・薬物の洋上密貿易、密航、反日活動家による不法上陸……。あらゆる犯罪を飲み込む魔の海では、目下、海底資源をめぐる国家間対立が最大の焦点だ。 ・中国でも「もし中国が日本と戦争をするならば、引き金は間違いなく東シナ海」と公然と語られる火種である。 ・そんななか、魔の海を「平和の海、協力の海に」と登場した一人の政治家がいる。二階俊博。 ・大臣就任直後から自民党の党内では、彼が「必ず中国の利益になるような働きをする」と予測されていた。 ・国境を接する二国間に領土・領海問題が存在すること自体決して珍しいことではない。また、それに付随してさまざまな対立が表面化することも、むしろ普遍的なことといえよう。 ・エゴとエゴのぶつかり合いとも形容される国際社会では、こうした場合それぞれの国の代表がきちんと自国の利益に立ち、ギリギリの攻防を演じる。 ・紛争も武力衝突もこの外交の延長線上にあるものだが、それを回避しつつ、あくまで平和的手段での妥結点を模索するために知恵を絞ることこそ健全な国の姿である。 ・だが、一方的に自国の利益を放棄するのであれば、それは交渉とは呼べない。 ・ましてや、武力衝突を回避する手段としては最悪だ。 ・なぜなら、国民が納得しない妥協は歪んだナショナリズムを国内に呼び覚まし、長期的には日本自身、そして中国にとっても利益にはならないからだ。 自らEEZを "放棄" してしまった日本 ・一九九六年の国連海洋法条約の批准を受けて日本は国内法を立法。二百海里を日本の排他的経済水域(EEZ)と定めたのである。 ・その際に問題となったのが、東シナ海には日中の陸地と陸地の間に四百海里の距離がなかったことだった。 ・ここで日本が主張したのは、陸地から二百海里ではなく互いの基線と基線のちょうど真ん中を取る「中間線」だった。 ・それに対して中国は、二百海里そのままの主張どころか、乱暴な解釈をすれば大陸棚を陸続きと見なす「自然延長論」(もしくは大陸棚延伸論)の立場を取ったのだった。 ・中国の考え方に沿えば二百海里を大きく越えて尖閣諸島を含む沖縄トラフまでの膨大な海域がすべて中国のEEZ内に含まれるということになる。 ・日本は、双方の落とし所となるはずのカードを最初から切ってしまうという失態を犯す。それが、「中間線」を持ち出すことであった。 ・日本側のこの提案は、二百海里の内側にあっても中間線より向うにあれば、そこは「決着済み」との中国側の解釈をうみ、結果として中国が一方的に開発を進める口実とされてしまうのだった。 ・中間線ギリギリで中国が資源開発をしても日本は文句をつけられず、逆に日本が中間線より内側で開発すると中国が猛烈な抗議をするといったおかしな関係が成立してしまったのはこうした理由のためだ。 ・日本の焦りをよそに、中国だけがどんどん地下資源を獲得していることの背景には、実力行使も ・だが、それ以上に忘れてならないのは日本自身がその権利を放棄するような行為を繰り返してきたという自らの失敗である。 ・自国の利益のためにあらゆる手段を尽くすのが外交の世界の常識。 ・こと外交に関する議論をするのであれば、大切なことはたとえば政権交代があろうと外交が一つの価値観で継続されるか否かを焦点にすべきであり、どこの党がどうであったのかという評価は二の次であるべきなのだろう。 ・ましてや十二の政党が乱立した一二年末の衆議院選挙のように外交を大きな争点にして戦うなどもってのほかだ。 ・とくに一党独裁で長期的な外交戦略を持ちうる中国のような国と隣り合う日本であればなおさらのことだ。 ・〇六年当時、中国の紙誌には、東シナ海問題での日本の外交に対し、「閣内で意思統一もできず、省庁間でも利害が食い違う国」とか「独自に海洋調査もしない国に交渉の権利はない」といった手厳しい論評が掲載されている。 日本をさらなる苦境に追い込んだ「媚中派」大臣 ・初期の段階なら小さな力で押し戻せたかもしれない中国の行為も、ことここに及べばそうはいかない。 ・今日まで小さな衝突を恐れ、摩擦を避け、妥協を繰り返した交渉や判断ミスが ・「戦後の総決算」を標榜し、終戦記念日に靖國参拝を断行した中曾根総理が、中国からの圧力で翌年からそれを中止した一連の問題は、さまざまな意味でその後の日本外交にとって反面教師とすべきものであったはずだ。 ・重要なことは靖國参拝の中止が日本人にある種の敗北感を残し、中国は形的には外交勝者となったものの日本に対し強い警戒心を持つようになってしまったことだ。 ・隣国に対して配慮することは、外交上必要なことではあるが、それを "させられている" という感情で行えば両国間には歪みが生じるのも当然だ。 ・参拝の中止は、結果的には日本国内での靖國参拝問題をより複雑化させ、二十年を経た二〇〇五年にはこの問題を巡って大規模な反日デモが起きるという事態をまねくのである。 ・国と国が互いの利益を追求し合えば衝突は避けられない。だが、そうした局面にあってもストレスを最小限にとどめて自己の目的を達成する道を徹底して探るのが外交である。 ・その視点で見たとき、中曾根総理はあの参拝の実現のためにどう戦い、何を得て、どこでどう折り合いをつけようとしていたのか。それが何も見えてこないのである。 ・もし内輪の論理や価値観を信じて外の問題も押し切れると発想したのであれば、それこそ過去の戦争にも通じる無策と言わざるを得ないのでないか。 第六章 台湾海峡危機に巻き込まれる日本 中国を内側から揺さぶる台湾スパイ網 ・数々のスパイ事件とともに毎年数十人という単位で関係者が逮捕されるという攻防は、海峡を挟んでいまも火花を散らしている。 ・この現実は本当の国際情報戦とは縁のない日本人には、想像もつかない世界に違いない。 エピローグ 日本の "国内問題" となる中国の大難 ・中国の大難とはどういうことなのだろうか。 ・例えば、中国の漁民が根こそぎ魚を獲るという問題がある。いずれ資源が枯渇することを防ぐために中国は、彼らの生存権や豊かになろうとする欲望を制限できるのだろうか。 ・そういう意味では、這い上がろうとする貧困層の欲望は無限だ。一つの場所でフタをしても、欲望のエネルギーはまた別の問題を引き起こすだろう。過剰な人口による過剰な競争がこの大陸には常に存在するからだ。 ・ルールを守ることのできる社会は、ルールを守っていれば最低限のモノが手に入れられるという裏づけがなくては成立しない。中国にはこの範囲を超えた競争が存在する。 文庫版あとがき ・中国で起きる事象のすべてには、公と私の狭間を行き来する複雑な利害の駆け引きが存在している。 ・共産党政権のガバナンスが緩むということは、すなわち個々の動機が活発になることを意味している。 ・そもそも中国は「上に政策あれば下に対策あり」と表現される国である。為政者は常に人々の欲望にタガをはめることに苦労するという体質を背負っている。 ・日本では「中国政府が対策を」という意見が多く聞かれるが、環境基準を厳格に適応すれば現実には倒産する企業が後を絶たないのである。そうなれば政府は環境問題より喫緊の問題である失業問題と向け合わなければならなくなるのだ。これぞ究極の選択である。 ・日本は中国の大気汚染から逃げることはできない。偏西風は西から日本へと向かい、海流も中国から日本大陸をなめるように流れているからだ。 ・中国が輸出する「大難」は今後も日本を悩ませ続けるだろう。しかし、それは中国を非難することでは解決されない。中国の問題を日本の内政と同じレベルでとらえて解決の道を探る時代がもう近づいてきている。 二〇一三年二月 ―― 完 ―― |