
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年11月27日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
82 |
18/10 |
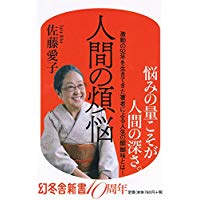 |
人間の煩悩 |
佐藤愛子 |
幻冬舎新書 |
◎ |
第一章 人間とは 🌷人を「救える」と思うのは傲慢である ・人間は自分の力で自分を救うしかない。 🌷災害が教えてくれること ・人間なんて大自然の前では実にちっぽけな存在なのである。 ・昔の人はそれをよくよく知っていた。自然の中に神を感じ、海を見て己の卑小さを知り、山に向かって手を合わせ、自然の恵みに感謝した。 ・それがいつの頃からか、人間は山も海も人を楽しませるレクリエーションの場所にしてしまった。 ・高峰に登るのはいいが、それを「征服」というようになった。 ・科学を産み出した自分たちの知恵能力を過信し、我がもの顔に自然を見下すようになったのだ。 ・「想定外」もヘッタクレもない。自然の力を想定して制するよりも、自分たちの限界を想定するべきだった。 ・人間は人間の「分際」を 🌷観念の弊害 ・今は何かというと思いやり、気くばりだ、念仏みたいに、優しさだ思いやりだといっているうちに、日本人はまことの優しさを失った。優しさがなくなったから、思いやりや気配りをうるさくいうようになったんじゃない。思いやりや気配りをあまり 第二章 人生とは 🌷失敗なくして強さは身につかず ・私は失敗をしては戦い、その戦いによって力を培ってきた。 ・覚悟を決めて生きられるようになったのは、数々の失敗のおかげだといえる。 ・精神の強さというものは一朝一夕で身につくものではない。怒り泣き諦め辛抱しながら、苦しい現実と何とか折合いをつけて生きていく。その経験の中で培われるものなのだ。 ��お金と人生 ・幸福というものは、金があってもなくても、平穏であろうとなかろうと、常に自分自身として平然と生きていけることだと私は考えている。 ・とにもかくにも私は力を抜くことなく、力イッパイ生きた。人生の終幕にさしかかって思うことはその満足である。この満足を与えてくれた、もろもろの苦難をありがたいと思うようになれたことを今、幸福だと思う。 第四章 子供とは 🌷子供のしつけ ・ "自分の思った通りにしつける" ことが優れた子供を作るとは限らないのである。 🌷人間関係が希薄になったワケ ・ ・しかし親友というものは「いいたいことをいい合える」から成立するもので、相手のキモチを忖度してばかりいては友情は深まらない。 ・その一方で「この節は人間関係が希薄になった」と心配している。しかし人間関係が希薄になったのは「人のキモチ」を思いすぎて、なるべくしてなったのではないか。 🌷子供らしい子供が減ったのはなぜか ・この頃はこどもがこどもらしくなくなった。天衣無縫さがなくなった。 ・暴力と子どもの喧嘩は別モノなのである。しかし今は「暴力否定」にひと括りにされて子供を萎縮させている。 ・萎縮は一見「好い子」を造る。だが好い子(と親が思っている)が虐めっ子に雷同して、ウザイ、キモイと叫んでいるかもしれないのだ。 ・子供に子どもの自然さ、子供らしさを取り戻させれば、陰湿な虐めや自殺はなくなる。私はそう思っている。 ・大いに悪態をつき、喧嘩をし、そして仲直りをする――それが子供の自然だ。だが、現状ではそれを認める人はいない。 ・現代文明を生きるために、子供は否応なく子供らしさを捨てさせられている。それを嘆く人は少なくない。 ・しかし、考えてみるとこれは我々おとなが目ざした文明であり、それで我々は幸福になると信じたのだった。嗚呼! ・昔の「子どもの世界」は、おとなの無理解によって成り立っていた部分が少なくなかったような気がする。 ・その頃はおとなと子供の世界は分けられており、子供は子供の世界で、おとなの世界からの圧迫によって鍛えられたのではなかったか。 ・今はおとなも子供も同じひとつの世界で和気あいあいと暮している。おとなは子供をより深く理解しようと努力し、子供はそれに安んじて小型のおとなになった。 ・しかし、刃むかう相手がいない和気あいあいが私には何となく面白くない。 🌷親子の断絶は子供のせいじゃない ・叱り方が、この頃は一律になって来た。 ・「こんな時には叱ってもいいんでしょうか?」と他人に相談して、承認されてからでないと叱れないという母親がいる。皆が叱れば安心して叱る。自分ひとりでは叱れない。そうして、断絶断絶とさわいでいる。 ・断絶は自分が作ったものなのに、子供の力で作っていると思って悲観しているのである。 🌷イジメの効果的な解決法 ・イジメ問題が起きると、なぜそうなったかをおとなはかんがえる。 ・しかしそれがわかったとしても、いじめの解決にはならないのである。 ・「強い奴が弱い者を虐めるなんて、卑怯者のすることだ! 恥を知れ、バカモン!」 力いっぱい罵倒した方が、ああのこうのと分析批評をしているよりもずっと話が早いのではないか。 🌷理屈で子供の良心は育たない ・人には「恐れ ・恐れ畏むものを持たない、目に見えぬ存在を信じる心を失った親に育てられた子供は良心が育たぬまま、怖いものなしに成長していく。 ・良心は今や死語になってしまった。 ・「『なぜ人を殺してはいけないの?』と子供が訊いてきた時、あなたはどう答えますか?」 これは言葉で――理窟で、道徳で教示することじゃない、感性の問題なんだから。 ・あなたは子供の頃、親や先生から「人を殺してはいけません」と教えられましたか? そんなことはいうまでもないことだもの。 ・死を忌む感性は人間だけが持っているものであって、けものにはない。そこが人間とけものの違い、人間の人間たるゆえんでしょう。 ・人の死に対してなにも感じない、いつものように元気でいるということは、人間としての心を持っていない証拠です。 ・だから、「なぜ人を殺してはいけないのですか」という質問に対して答えられないのは当然なのです。 ・人間としての感性のない者に、感性を説いても仕方がない。 「なぜもヘッタクレもない! いけないといったらいけないんだ! バカタレ!」というほかない。 🌷�劣等感は必要な「毒」 ・劣等感のもとを排除することよりも、劣等感と戦ういうち克つことの大事さをなぜ考えないのだろう。なぜそれを教えないのだろう。 ・人間、生きている限り、何らかの形で劣等感はやってくる。劣等感は人が成長する過程に必要な「毒」あるいは「病気」である。 ・子供の幼い身体はハシカや百日咳を乗り越えることによって成長し、強くなっていくのだというが、劣等感は心のハシカや百日咳であろう。 🌷我慢が出来ない子供の将来は…… ・どんな時代が来ても、どんな境遇になっても、嘆かず騒がず順応できる人間に育てておくのが親の責任ではないか。 ・子供が欲しいといっても簡単に与えず、我慢させる。我慢の力があるかないかで、その者の人生は決まるのだ……。 ・今の若者はすぐにキレるという。 ・「わかる、わかる、わかるけれど……」というヘッピリ腰の教育、今ふうにいうと「思いやり教育」がすぐにキレる若者を作ったのだ。 第六章 長寿とは 🌷年寄りの悲劇 ・今の年寄りの悲劇は、若い人の役に立たなくなったことですよ。私たちの若い頃は、にくらしい姑めと思っていても、例えば糠味噌のおいしい漬け方とか、黒豆の煮方とか、子供が熱を出した時とか、いろんなことを教わると、やっぱり一目おくという気になったものです。だから姑はえらそうな顔をしていられた。しかし今は私たちが教えられることって何もないんです。おいしい漬物も煮豆もスーパーで買えばいいんですから。 🌷欲望をなくす ・人間は生まれた時から死に向かって歩いているのだ。 ・老人はいつ死んでもいいように覚悟を決めるべきだ。 🌷老いの時間は死と親しむためにあり ・老人は死と親しむことが必要だと私は思う。老いの時間はそのためにあるのだと私は考える。忍び寄ってくる老いに負けまいと不老強壮にあくせくするよりも、やがて赴くことになる死の世界に想いを近づけて馴染んでおく方がよい。悲惨な死とはこの世に未練を残し、死を拒み恐れて死ぬことであろう。 🌷生きるのも大変だが、死ぬのも大変 ・全く、生きるのも大変だが、死ぬのも大変という事態になってきた。これというのも医学の目ざましい進歩のおかげである。 ・長寿はめでたくはなくなったのである。 ・死んでもいいと思っている者を無理やり検査漬けにして生かそうとするのは僭越じゃないか。老人医療は、苦痛を取り除いて安らかに死へ導くという考えを持ってもらうけにはいかないだろうか。 🌷エネルギーの枯渇 ・「丸くなる」ということは人間が出来て角が取れたのではなく、単にエネルギーが枯渇して来ただけのことであったと、今にしてわかる。なにも感心するほどのことではなかったのだ。 🌷死ぬ時がくれば人は死ぬ ・長命な人は「自然に逆わずに生きた」ための長命なのにちがいない。 ・何をしていても癌になる人はなる。なる時はなる。死ぬ時がくれば人は死ぬのである。 ―― 完 ―― |