
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年01月07日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
84 |
18/11 |
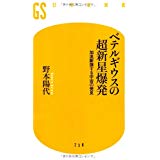 |
ペテルギウスの超新星爆発 |
野本陽代 |
幻冬舎新書 |
◎ |
第一章 ペテルギウスに爆発の兆候?! 晩年を迎えたペテルギウス ・星はその中心で水素原子核四個を核融合させてヘリウム原子核一個に変えることでエネルギーを得、輝いています。 ・しかし、燃料となる中心部の水素が使い尽くされてしまうと、外層が膨らみはじめ、やがて赤く大きな星(赤色巨星)へと変身します。 ・ペテルギウスの場合、星の一生の九割をしめる水素の燃える時代は一〇〇〇万年ほどで、すでにその時期を過ぎ、だいぶ以前に赤色超巨星の時代に入りました。 ・太陽の八倍以上の質量をもって生まれた星の多くは、一生の最後に超新星爆発を起こすことが知られています。 第二章 星の誕生と進化 星への遠い道のり ・星は特別な物質でできているわけではなく、宇宙のそこかしこにあるガスやチリがぎゅっと集まったものなのです。 ペテルギウスはなぜ赤い ・星は水素を核融合させ、ヘリウムに変換することでエネルギーを得ています。 第三章 たそがれを迎えた星たち 客星現わる ・藤原定家といえば鎌倉時代の歌人ですが、『明月記』という日記を残したことでも知られています。 ・この日記には多くの天文現象についての記述があります。その中に、 「一〇五四年五月下旬ころに、おうし座の片方の角の先端近くに、木星と同じくらい明るい星が出現した」 という記述があります。 ・中国や日本では、あるとき出現してしばらく輝いたのち消えてしまう天体を、ふつうの星と区別して、一時的にやってくるお客様の星という意味で「客星」と呼びました ・現在では、かに星雲が実際に一〇五四年の客星の約九六〇年後の姿であることが確認されています。 元素はどこからやってきたのか ・私たち人間の身体は六〇兆個もの細胞で構成されているといいます。 ・そして、それぞれの細胞は何十兆、何百兆という途方もない数の原子でつくられているとか。 ・つまり、人体は六〇兆かける何百兆もの原子が一つになって働くことによって成り立つ、非常に複雑で精密なものだということです。 ・人間を構成する元素のなかで、もっとも重量比が大きいのは酸素で、実に六五パーセントを占めています。次が炭素の一八パーセント、そして水素の一〇パーセント、チッ素の三パーセント、カルシウムの一・五パーセント、リンの一パーセントとつづきます。 ・身体の大半は水でてきていますから、それを構成する酸素と水素が多い。 ・また、タンパク質と脂肪は炭素を中心として形成されていますので、炭素が多い。 ・今から約一三七億年前に忠が誕生したとき、宇宙にあったのは水素とヘリウムだけでした。 一瞬の三重衝突、炭素の誕生 ・老年を迎えたために、ふくらみ始めた星のなかでなにが起きているのか。 ・星の中心には、燃料の水素がすべてヘリウムに変換されてつくられた芯があります。 ・この芯はエネルギーを生成することはできませんが、星の表面からはエネルギーの放出がづいています。 ・それを補うために芯はやむなく縮んで、熱を出します。 ・ヘリウムの芯のなかでは、中心が一億度を超えたところで、ヘリウムの核融合が始まります。 ・ヘリウムは独立独歩の元素で、互いどうしでもペアを組むということがない元素です。 ・そのため、ヘリウムが核融合するためにはある条件を満たさなければなりません。 ・三個のヘリウム原子核がほぼ同時に超高速で衝突することです。 ・一億度という熱い芯のなかでは、ヘリウムが縦横無尽に飛びまわっており、どんなに稀なことでも起こりうる状況となっています。 ・そして、一瞬の三重衝突。炭素の誕生です。 ・難産のすえ生まれた炭素はヘリウムとはちがい、いたって友好的で、炭素の一部はあっというまにヘリウムとくっつき、酸素をつくりだします。 ・これまで宇宙に存在していなかった炭素と酸素が星のなかで生み出されました。 ・このとき、再び大量のエネルギーが放出されるおかげで、芯の収縮は止まります。 ・それと同時にまわりのガスの膨張も止まります。 ・核融合をするといっても、ヘリウムは水素と比べて一〇分の一のエネルギーしか出さないうえ、燃料となる量もずっと少なく、水素よりもはるかに早く燃え尽きてしまう。 ・今度は、ヘリウムの芯のなかに、さらに炭素と水素でできた芯があり、星は三層構造になってしまいました。 ・ヘリウムを燃やすことができなくなると、星の中心部はまた縮みます。 ・まわりのガスは再びふくらみ始め、表面温度が下がって赤くなっていきます。 ・ところが、質量が太陽の八倍以下の星の場合、あるところまで縮むと、質量が足りないため、それ以上縮まなくなってしまいます。 ・一方、まわりのガスはどんどんふくらみ、星は赤色巨星となっていきます。 ・やがて、そのガスが芯から離れ、惑星状星雲となる。 エネルギーをもち逃げするニュートリノ ・水素が核融合してヘリウムになるさい、ニュートリノも一緒につくられます。 ・中央に炭素と酸素の芯、そのまわりにヘリウムの層、外側にふくらみつつある水素の層と三層になった星が、太陽の八倍以上の質量をもっていた場合、それ以下の星とはまったくちがった晩年を迎えることになります。 ・これらの星は十分な質量があるため、電子は縮退という抵抗をせず、炭素と酸素の芯はさらに縮みます。 ・中心温度が三億度を超えると今までになかったことが起きます。 ・あまりの高温に、ニュートリノと反ニュートリノが対になって発生し始めるのです。 ・ニュートリノは生成されるとあっというまに星から飛び出していってしまいますが、そのときエネルギーも一緒にもっていってしまうため、縮みつづけて重力に抵抗するだけのエネルギーをせっせとつくらなければなりません。 ・中心温度はうなぎのぼりに上がっていきます。そして八億度。ここで炭素の核融合が始まり、酸素、ネオン、マグネシウムなどの元素がつくられます。 ・しかし、ニュートリノのエネルギーの持ち出しがつづいていることもあり、ヘリウムの燃える時間の一〇〇分の一以下で炭素は燃え尽きます。 ・あとには酸素、ネオン、マグネシウムの芯が残されます。 ・さらに縮んで温度が上がると、それらの元素もさらに短い時間で燃え尽きます。そして中心にはケイ素、イオウ、カルシウムの芯ができます。 元素製造機と化した星 ・縮んで温度を上げ、核融合を始め、燃え尽きるとまた縮み、温度を上げ、新たな核融合を始めとくり返し、星は自らの重さを利用して次々と新しい元素をつくっていきます。 ・最終的にもっとも安定した元素である鉄がつくられます。 ・私たちの身のまわりにあるさまざまなものを構成している元素の四分の一近くは、こうして星のなかでつくられたものです。 一生の最後を飾る超新星爆発 ・私たちの身のまわりで見られる元素の数々は、星とその最期を飾る大爆発超新星によってつくられたものです。 ・その意味で私たちはスターダスト(星くず)、星の子であるといえるでしょう。 想像を絶する天体、パルサー ・超新星爆発を起こした星は飛び散ってしまいますが、その中心には強い衝撃波をつくりだす原因となった芯が残されています。 ・主に中性子でできていることから、この芯は「中性子星」と呼ばれます。 ・生まれたての中性子星は一〇〇〇億度という超高温であるため、なかでは相変わらずニュートリノと反ニュートリノが次々とつくられています。 ・しかし、一立方センチメートルあたりの密度が四億トンを超える中性子星からは、ニュートリノといえども容易に逃げ出すことはできません。 ・ニュートリノが中性子星から持ち出すエネルギーが、超新星のエネルギーの実に九九パーセントを占めています。 ・ニュートリノがエネルギーをもって去ったあとの中性子星は、一〇キロメートルまで縮み、温度もガクンと下がってしまいます。 ・しかし、その密度は一立方センチメートルあたり一〇億トンという、想像を絶する天体です。 ・パルサーは超新星爆発のときにつくられる中性子星だったのです。 光も出ることのできないブラックホール ・地球から宇宙に向けてロケットを打ち上げようと思ったら、秒速一一・二キロメートル以上の速さにする必要がある。 ・これ以下の速さでは地球の引力に引き戻されてしまうからです。 ・太陽から打ち上げる場合は秒速六一八キロメートル以上、その天体の質量が大きくなれはなるほど、また同じ質量なら、その天体が小さくなればなるほど、その引力は強くなります。 ・平均的な白色矮星から打ち上げるには秒速三〇〇〇キロメートル、太陽と同じ質量の中性子星の場合は秒速約二〇万キロメートルです。 ・ある天体の引力を振り切るのに、光と同じ秒速三〇万キロメートル以上の速度が必要だとしたら、この天体は見えるのでしょうか。 ・見えません。その天体から光が出ることができないからです。 ・私たちは光によってものを見ていますから、光がこなければ何も見ることができません。 ・そこでこの天体は「ブラックホール」と呼ばれます。 ・太陽質量の二倍以上の重さに中性子星がなると、星は重力によって潰れていき、超高密度天体となって、しまいには光さえも出て来られないほど重力が強くなってしまいます。ブラックホールです。 天然の炭素爆弾 ・星が一生の最後に超す大爆発、超新星。 ・質量の大きな星の爆発であるにしろ、連星の進化の果てであるにしろ、ひとつの銀河と同じくらい明るく輝くこともある、大爆発です。 ・そして、大量の元素が新たにつくられ、宇宙空間にばらまかれます。 ・今から五〇億年ほど前、いくつかの超新星爆発によって生成された元素を含む雲から私たちの太陽系が形成されました。 第四章 宇宙の扉を開く 宇宙の過去保見る方法 ・光の速さは音の九〇万倍、秒速三〇万キロメートルもある。 ・光が一年かけて進む距離、約九・五兆キロメートルを一光年といいます。 遠ざかるシリウス ・ドップラー効果 音は波として伝わってきます。一秒あたりの波の数(振動数)が多いほど音は高く、少ないほど低くなります。音源が近づいているときは、音波が次々と押し寄せ圧縮された形になるので振動数が増し、音は高くなります。逆に遠ざかるときには音波が引き延ばされた形になるので振動数が減り、音は低くなります。 ・ある天体が私たちから遠ざかっている場合、赤から紫まで広がったスペクトルに刻まれる線は、より波長の長い赤のほうにずれます(赤方偏移)。 ・逆に近づいている場合には、より波長の短い青や紫のほうへとずれることになります(青方偏移)。 ・スペクトル線がもとの位置からどれだけずれたかを測れば、どれくらいの速さで光源が遠ざかっている(近づいている)かがわかるというわけです。 ・シリウスは私たちから遠ざかりつつあります。 見ることのできない天体を「見る」 ・一度撮影すれば、その写真をいつでも使えるし、天体と天体の位置を正確に測るのも容易です。 ・同じ条件で時間をおいて何枚かの写真を撮ることで、その期間内に起きた変化を知ることもできます。 ・一九世紀末には、プリズムを内蔵した分校写真機を望遠鏡につけることで、スペクトル写真を撮ることもできるようになりました。これでドップラー偏移を測り、星の運動やその速度を知ることができるようになったのです。 ・天文学に写真技術が導入されたことで、より多くの天体が研究対象となり、より正確な記録が残せるようになって、天文学に革命が起きました。 星までの距離を測るには ・腕を伸ばし、人さし指を目の前に立て、右目、左目と片目で指を見ると、後ろの景色に対して指の位置がちがって見えます。 ・右目と左目では、指を見る角度に差があるからです(これを「視差」といいます)。 ・地上で距離を測るのに使われる三角測量はこれと同じ原理を使っています。 ・距離のわかった二点から、距離を測りたいと思うものをそれぞれ測定し、その角度を求めて距離を出すのです。 ・観測をする二点(三角形の基線)の距離が離れていればいるほど、より遠くのものを測ることができます。 ・天文学者はこの視差を使って星までの距離を測ることを考えました。 地道な仕事、人間コンピュータ ・見かけの明るさがちがっても、スペクトルのタイプが同じであれば、二つの星はほぼ同じ明るさと考えてもよいでしょう。 ・そこで、視差によって距離のわかっている星の明るさと、その星と同じ特徴をもつ遠くの星の明るさを比較することで、遠くの星の距離がわかるようになりました(天体の明るさは距離の二乗に反比例して暗くなります)。 宇宙を測るものさしの発見 ・夜空の星はまたたいているように見えます。しかし、このまたたきは揺らいでいる地球の大気のなかを星の光が通り抜けてくるために起こる現象で、星が実際に明るさを変化させているわけではありません。 ・実際に明るさを変化させている星(変光星)もたくさんあります(ただし肉眼でわかるほどではありません)。 膨張する宇宙の発見 ・歴史的にみて、宇宙の謎の解明は、観測と理論がうまくかみ合ったときに大きく進展しています。 第五章 宇宙どこまでわかったか 夜空はなぜ暗いのか ・夜空が暗い理由の一つが明らかになりました。宇宙が膨張していることです。 ・どれほど星や銀河があったとしても、すきまがどんどん広がっているのであれば、夜空が明るくなることはないからです。 銀河中心にひそむブラックホール ・星は原子核が核融合するときに出されるエネルギーで輝いている。 宇宙に蜃気楼現わる ・ブラックホールや銀河、銀河団のように質量の大きな天体の周囲の空間は、星とは比べものにならないほど、その天体の重力によってゆがめられています。はるかかなたにある天体と地球のあいだにそのような重力源があれば、本来なら別の方向に行くはずの光が曲げられて地球に届くということもありえます。この現象は、光がレンズを通したときのように重力によって曲げられるということから「重力レンズ(効果)」と呼ばれています。 第六章 加速膨張する宇宙の発見 多くの星からの贈り物 ・私たちの太陽系のなかにある元素の数を比べてみると、水素を一〇万個としたとき、ヘリウム九七〇〇、酸素八五、炭素三六、ネオン一二、チッ素一一、マグネシウム四、ケイ素四、鉄三、イオウ二……となっています。 ・一九五〇年代初め、天文学者は古い星に含まれる重元素の量が若い星よりも少ないことを発見し、銀河にふくまれる重元素の量は時間とともに増えていると結論づけました。 ・星が生まれて進化し、体内で生み出した重元素を死とともに宇宙空間に戻すことで、銀河にふくまれる重元素の量が増えていったのです。 ・炭素は、太陽の八倍以下の星の中心に炭素と酸素の芯ができたあと、芯の外側のヘリウムが燃えてできた炭素の一部が外層に流れ出し、最終的に宇宙空間にまざると考えられています。 ・鉄を大量につくりだすのはⅠa型超新星です。 ・白色矮星が核爆発を起こしたさいに、それを構成していた物質のほとんどが放射性元素のニッケル56に変換されてしまいます。それが半減期六日で放射性元素コバルト56になり、さらに半減期七七日で鉄56になります。 ・私たちの身体を構成している元素は、宇宙が誕生してから太陽が五〇億年ほど前に誕生するまでのあいだに、何代にもわたっていろいろなタイプの星たちが営々とつくりあげてきたものです。 過去からやってきた光 ・三三〇年前、だれも見ることのなかった超新星爆発の光、それが今になって私たちのもとに届きました。過去からやってきた光によって、爆発当時の超新星のスペクトルを観測することができ、カシオペヤAがⅡ型超新星であることがわかったのです。 アインシュタイン、人生最大の予測 ・現在の宇宙を構成しているのは、約七三パーセントのダークエネルギー、約二三パーセントのダークマター、そして、わずか四パーセントのふつうの物質ということになります。 ・じつに、宇宙の九六パーセントのものがなんだかわからない、ということです。 ―― 完 ―― |