
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年03月06日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
91 |
18/11 |
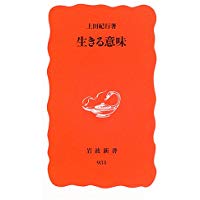 |
生きる意味 |
上田紀行 |
岩波新書 |
☆ |
Ⅱ 数値化と効率化の果てに 第4章 「数字信仰」から「人生の質」へ 1.「意味」は「数字」で測れない 「一〇〇点」は常に正しいのか ・その生徒の将来の夢とか、いま何にワクワクしているのかとか、その生徒が何を喜びとして生きているのかとか、どんな人生のイメージを思い描いているのかを聞くこともなく、生徒と見れば「一〇〇点目指せ!」と言っておけばいいのか。 ・彼らの人生にはひとりひとりの「生きる意味づけ」があって、その中で学校にも通い、テストも受けているのだということが無視され、あたかも生徒はテストで一〇〇点取るために生きているかのように扱ってもいいのか? ・数学ができるからという理由で偏差値の高い大学に入ったものの、何で自分が技術者を目指しているのかが分からず、卒業間近になっても思い悩んでいる若者と、同じ年齢で既に自分に誇りをもって働いている若者のどちらが幸せかは分からない。 ・人間の「生きる意味」は学歴やテストの点で決まるわけではないのだ。 他人の尊厳が見えているか ・中学、高校ともなれば、単に何点を取るということよりも、「人生に何を求めるのか」のレベルこそが重要になってくる。 2.数字信仰からQOL社会へ ・平均寿命が八〇年を超えているにもかかわらず、人生何年生きられるかと言う「数字」を伸ばすことだけ考え続け、一年でも平均寿命が延びればそれだけ幸せになれると考えるのはほとんど滑稽と言っていい。 ・むしろ問題は、それだけ延びた人生の時間をどのように満足して過ごすかということなのではないか。 「QOL社会」とは ・QOLとは「自分の生存状況についての、満足、生きがいなどの意識を含む全般的主観的幸福度」である。 ・私たちがいま求めているのは、私たち自身のQOLの高さであり、それを可能にするような社会のあり方なのである。 ・「数字信仰からQOL社会へ」とは、私たちの発想の前後関係を入れ替えること、発想を逆転させることを意味している。 ・「数字こそがQOL」の時代ではなく、「自分の幸せとは何か」「自分にとってQOLの高い生活とはどのような生活か」ということを最初に考えなければいけない時代になったのである。 Ⅲ 「生きる意味」を創る社会へ 第5章 「苦悩」がきりひらく「内的成長」 1.意味の創造者としての「私」 一点豪華主義 ・人生の満足度の高い人、それは「一点豪華主義」で生きている人である。 ・辛いことがあっても患者さんの笑顔を見れば幸せになるという看護師の人は強い。 「濃淡」から生じる意味 ・「一点豪華主義」の人の満足度が高いのは、自分の「生きる意味」の中心で満たされていて、他のところでちょっと評価が低くなっても「気にならない」からである。 2.「内的成長」の条件 ・私たちの社会はこれまで、年収や成績といった数字に表されるような指標によって、私たちを外側から見る成長観に支えられてきた。 ・それは「経済成長教」が力を持っていた時代には機能してきた成長観だった。 ・しかし、そうした成長観はもはや私たちの生きることを支えてはいけない。 ・私たちの成長を内側から見る目がいま求められている。そして、私はそれを「内的成長」と呼びたいのだ。 ・「内的成長」とは何か。それは「生きる意味」の成長である。 人生の創造性 ・周りからは成功者だと思われていても、本人的にはあまり面白い人生を生きていないと思っていることはよくある。それは人生に「創造性」がないからだ。 ・私たちが「生きる意味」の創造者であり、人生の節目節目で「生きる意味」の再創造を行うことができること、それが人生の創造性なのだ。 ・私たちの社会はもはや物質的には十分豊かだ。いま真に求められているのは、生きることの創造性、「内的成長」の豊かさなのである。 「内的成長」のきっかけ ・それは私たちひとりひとりが、二つのものへの感性を研ぎすますことから始まる。 ・それは、「ワクワクすること」と「苦悩」の二つである。 ・「ワクワクすること」「生きてる! という感覚」は、私たちの「生きる意味」の中核にあるる ・それはまさに「生命の輝き」を実感する一瞬であり、私たちが自分自身の「生きる意味」の創造者となる一瞬である。 ・そしてそれは私たちと世界がどのような「愛」でつながっているのかを実感する瞬間でもある。 「ワクワク」の相乗効果 ・「ワクワクしている人のそばにいなさい」 ・「情熱を持っている人と一緒にいる時間を増やしなさい」 ・「生命の輝き」は必ず伝染してくれる。 ・夢のある人の周りには夢のある人が自然と集まってくる。 ・それはある人の夢を聞いたときに「おおっ、それはすごい!」と、ますますエネルギーをひき出してくれるからだ。 ・そしてそんな場では、ひとりが夢を語ることが他の人の夢を刺激する。 ・それは互いに互いを活性化しあうような相乗的エネルギーの場になっていくのである。 ・「ワクワクすることを大切にすること」、それは私たちの「内的成長」を促す大きなステップなのである。 「苦悩」こそがチャンス ・「内的成長」のもうひとつのきっかけは、それは「苦悩」である。 ・苦悩とは現実の自分と「ワクワクする自分」との間のギャップから起こるものだ。 ・こうすれば「ワクワクする」という「生命の輝き」が現実によって抑え込まれている。そこに苦悩が生じるのだ。 ・だから「苦悩」とは、自分の「ワクワクすること」気づく大きなチャンスなのである。 ・現実に私は「苦悩」している、という場合、その「苦悩」」に立ち向かい、その苦悩の意味を探求していくことで、自分が本当に何を求めているのか、どんなことにワクワクするのかが逆に分かってくるのである。 【 私見 : 話としては理解できるが、今苦悩している人がその苦悩に立ち向かえるのか、又、立ち向かう勇気をどのように持てるのか、そのきっかけは何か。ここを乗り越えられないと次のステップには中々到達できないと思うのだが・・・ 】 ・人生の中で苦悩や違和感があること。それは私たちの「生きる意味の再構築」に必要不可欠である。 ・現在の「癒しブーム」が、常に「癒されたい」と受け身であり、自分で自分の人生を切りひらいていく、創造していくという意識は希薄だ。 ・私は苦悩すべきときに苦悩することがむしろ真の癒しにつながると思っている。 ・「悩み」や「病」は自分の人生に対する警告信号である。 ・私たちは自分自身を「癒す」力を持っている。 ・そしてその「癒す」力とは、病むべきときに「病む」ことができる能力、「病」に気づく能力を含んでいる。 ・「病」への、現実への「違和感」への感受性を持っているからこそ、癒しや征成長が可能になるのである。 苦悩を支え合う ・苦悩するとき、私たちはとても孤独だ。誰も自分の苦悩を分かってくれない、自分は見捨てられている。そんな思いにとらわれることも多い。 ・「苦悩」に向かい合い、それを「内的成長」へとつなげていくには、かなりの時間が必要なのだ。 ・そこを耐え抜き、「生きる意味」へと展開していくには、仲間が、そして仲間とのコミュニケーションが必要なのである。 コミュニケーションがひらく可能性 ・「生きる意味」を求めて、時間をかけながら、意味を探り出していく、意味を熟成させていく、そんなコミュニケーションは効率的ではないが、しかしそこにこそ生きることの豊かさがあるのだ。 ・人がワクワクすることをともに喜び、人が苦悩することをともに受けとめる。私たちの「内的成長」は、他者に支えられることから大きなエネルギーを得る。 ・「内的成長」を支えるのは、まさにそうした「豊かな」コミュニケーションなのである。 ・とすれば、私たちがいまこそ取り組むべきは、豊かなコミュニケーションを可能にする社会作りである。 ・「内的成長」をもたらす新しいコミュニティーの創造、それが私たちの課題となるのである。 第6章 「内的成長」社会へ 3.宗教者たちの挑戦 「苦」「縁起」そして「慈悲」 ・仏教の出発点は、なぜ人々は苦しむのかという「苦」の認識である。 ・そして、その「苦」には原因がある。だからその原因を見つめ、それを克服すれば人間は「苦」から解放されるというのが仏教の教えの原点だ。 ・「人生は苦である」「その苦には原因(集)がある」「その原因がなくなれば苦もなくなり(滅)、涅槃の境地に至る」「涅槃に至る道がある。それが修業の道である」という「苦・集・滅・道」の「四聖諦」と呼ばれる教えこそが仏陀の最初の説法であった。 ・現実の「苦」から出発してその原因を探求し、そこから苦悩を脱した状態に至ろうという教えは、「苦悩を単に除去するのではなく、苦悩に向かい合う」ことから「生きる意味」を再構築し、「内的成長」をもたらす、というこれまで述べてきた道筋に近いものだ。 ・人々の苦しみの原因は認識の誤りによる。その誤りとは「諸行無常」(すべての物は変化する)と「諸法無我」(すべての物は関係性の中にある)という現実を知らないことだ。 ・「私」も他との関係の中で生きている。この関係性の法則を仏教では「縁起」と呼ぶが、私は縁起的な存在である。 ・私たちはすべて互いの支えの中に生きており、それ故他の苦しみは自らの痛みになり、他の喜びは自らの喜びになる。そこに「慈悲」が生じる。 ・慈悲の「悲」は、原始仏典ではウペッカーと言い、「呻き」の意味だ。人の苦しみを見たときに、自分も苦しくなり、うーんと呻く。 ・そして、何とかして代わってあげたいと思い、代われないまでも何とかしてあげたいと考える。それが「慈」(メッター)の心である。 宗教の可能性 ・そもそも宗教とは人間の苦悩に向かい合うものである。だから、これからのコミュニティーの再創造において、宗教も大きな可能性を持っている。 ・しかし、これまでの宗教教団は、人々の多様な「生きる意味」を育むというよりは、教義であったり教組の教えであったりといった、一つの「生きる意味」を信者に与えることによって苦悩から解放されると教えるものが少なくなかった。 ・しかし、そうした「ひとつの意味」によって構成されるコミュニティーは、コミュニケーションの創造性をむしろ封殺することが多い。 ・これからは「生きる意味」のオーダーメイドの時代だ。しかし既製服の「救い」を与えられて、誰でもこの教えで同じように救われるというのでは、救いにおいても私たちは「交換可能」であるということになってしまう。 ・そういった「ひとつの意味」による救いは、既製服の時代には良かった。しかし、もはやそういった救いの賞味期限は既に切れていると言えるだろう。 4.「内的成長」をもたらす社会へ 「抱え込み」から「解放」へ ・学校という場について、生徒ひとりひとりの「生きる意味」を無視して、とにかく良い成績さえ取れればいいといった場からは、人生を生きる意味も感性も育むことはできない。 ・「ワクワクすること」を抑圧する侵襲性の高い教育からの転換が必要だ。 ・生徒ひとりひとりを固有の「生きる意味」を生きている存在として見る、そうした感受性へのシフトが必要である。 ・「内的成長」を含む教育とは、いわゆる「道徳教育」とは全く異なるものだ。 ・人間としての「正しい生き方」をすべての若者に注入すると言った教育が「心の教育」だと思っている人は多い。 ・しかしそういった、ひとりひとりの姿をみない、画一的な教育の対極にこそ、「内的成長」を含む教育はあるのだ。 ・ここでも「苦悩」や「違和感」が受けとめられるような場づくりが必要になる。 ・苦悩や違和感など出したら「クサイ」し嫌われると信じてそれらを抑圧し、しかしその抑圧の結果突然「キレる」という悪循環がいまの学校の世界だ。 ・内的成長のきっかけになりうる現実への違和感をむしろ大切にしていくようなコミュニケーションのあり方が必要なのである。 ・生徒を「内的成長」という視点から見ることができるかは、教師が自分自身も「内的成長」している存在だと感じているかにかかっている。 ・「学校の外の世界をほとんど知らず、たいした人生経験もないのに、自分があたかも出来上がった人物であるかのように振る舞い、創造性を全く欠如させている教師」は、生徒がもっとも軽蔑する種の教師だし、その存在自体が生徒の成長に対するハラスメントでもある。 ・いま述べた文章の「学校」を「会社、宗教集団」などに入れ替え、「教師」を「上司、宗教者」などに入れ替えても全く通じるので、それは教師だけの問題とは言えず、この社会全体に通じる「閉鎖性」の問題だろう。 ・その意味では、教師も生徒もいかに学校以外の世界に開かれているかが大切になるだろう。 ・日本社会は「抱え込み型」の社会である。 ・すべてを学校の中で解決しようというのではなく、これからは学校と外の社会との間のネットワークこそが重要になる。 ともにある「家族」を支えに ・多くの家族はこれまで子どもに「条件付きの愛」を押しつけることで、親の期待に添う「いい子」を育ててきた。 ・さらにその親自体が既に「世間の目」を気にしていて、その目を内面化している人たちであるから、それは私たちの内的成長にとって非常に抑圧的になりがちだった。 ・ひどい場合だと「自分の思い通りにならない」といって子どもを虐待してしまう。身体的虐待をはじめとして、言葉による虐待も少なくない。 ・それはAC(アダルト・チルドレン)的な傾向を持つ、「自尊心のない子ども」たちを大量に生み出してきたのである。 ・しかし、家族とは何よりも私たちが人生で苦難に直面したときに、最後まで自分を助けてくれる存在であろう。 ・何があっても困ったときは家族が助けてくれる、そういった基本的安心の場として家族はあるはずだ。 ・スリランカの父親は、ほんとにすぐ仕事を休んでしまう。理由は「ファミリー・ビジネス」、家の都合。誰かが病気なら、胸を張って休んで当然なのである。 ・日本の父親は子どもの熱くらいでは仕事を休まない。そんなことで会社を休んでいては、会社での評価はがた落ち、昇進もままならないであろう。 ・かくて日本では「ファミリー・ビジネス」は「ビジネス」の前に敗退する。 ・「ビジネス」を追究することこそがファミリーのためだ。昇進できず、給料も増えなければ、困るのは家族だ。 ・子どもだって自分の熱のせいでお父さんの昇進が遅れることは望みはしまい。それよりも、その分増えた収入でゲームのひとつも買ってやったほうが、子どもも喜ぶはずだ……。 ・そうやって日本の多くの父親たちは、自分の優先権を家族よりも仕事に置き、それはあるときまでは成功してきた。 ・右肩上がりの経済の中で、収入も増加し、地位も金も確保されてきた。家にはいなくても昇進する夫のほうが世間体にはいいし、家に早く帰ってくるような夫はうだつが上がらないと見られたものだ。 ・しかし、そんな中で「支え合う家族」の姿は見失われていく。 ・父親の人生の目標は昇進、子どもはいい成績を取ること、母親はその子どもの尻を叩くこと、といった「分かりやすい」目標の中で家族の「内的成長」は停止し、コミュニケーションは形骸化し、家族はバラバラになっていった。 ・そして家族の構造が弱体化したところに、不況が襲い、リストラが襲ってくる。「生きる意味の不況」に「経済的不況」が襲い掛かれば、私たちはひとたまりもない。 ・そのとき、私はスリランカの父親たちを思い出す。自分が熱を出したときいつもそばにいてくれた父親はかけがえのない父親だ。 ・父親が課長であろうと、平社員であろうと、たとえリストラされようが、その価値は変わらない。 ・それはこれまでの日本社会のように、家族でさえも父親の価値をその肩書きで推し量ってしまい、子どもの価値を通っている学校の名前で推し量ってしまうような状況とも、全く異なるものだ。 ・この人の給料がいくらだからすごいとか、どんな学校に通っているから偉いとか、何を買ってくれたから感謝するとか、家族とはそんな次元での関係ではない。 ・困ったとき、傷ついたときに、一緒にいてくれた人。いつも「私とともにある」人。その人の価値は、地位や収入の多寡によってはびくともしないのである。 ・社会の中に「信頼できるもの」、「私をぜったい見捨てることのないもの」をどれだけ持つことができるか、そのことが私たちの「内的成長」を深く支える基盤になる。 ・現在の日本が目ざしている、「何の支えもないところで自由に競争しなさい、それが自由な社会です」ではこの世は地獄だ。 ・支えがあればこそ、私たちは人生にチャレンジすることができる。世界に信頼があるからこそ人生が自由になるのである。 第7章 かけがいのない「私」たち 1.‹我がまま›と‹ワガママ› 創造性と自己中心性 ・「人の目」と「効率性」によってがんじがらめになって、私たち自身の「生きる意味」が見失われているところに私たちの時代の病はある。 ・一見私たちの自立をもたらすように見える、新自由主義的なグローバリズムは私たちをますます効率性と他人からの評価に縛りつけ、私たちの「生きる意味の再構築」をもたらすものではない。 ・いまこそ、経済成長や数字に表される成長といった、私たちや私たちの社会を外から量的に見る見方だけではなく、「生きる意味の成長」といった人生の質に関わる成長を考えるべき時ではないか。 ・そうした「内的成長」をもたらす社会への転換が求められているのである。 ・誰かから、あるいは社会から「生きる意味」を押しつけられるのではなく、私たちひとりひとりが「生きる意味」の創造者となる社会への転換がいまこそ必要だ。 ・押しつけられた「生きる意味」ではなく、自分自身の人生を取り戻すこと、それは抑圧された自分自身から‹我がまま›に生きることへの転換である。 ・しかし、それは自己中心的で周りを意に介さない‹ワガママ›となる可能性を秘めている。 ‹ワガママ›と人の目 ・「人の目」を気にしてきた日本人がいったん「人の目」を気にしなくなったとき、そこには自分自身の行動を律する何ものも存在していないのだろうか。 ・‹ワガママ›な行動は、「人の目」に縛られてきた社会の反動ではないかと思えるのだ。 ・東工大で留学生向けの抗議を受け持ったとき、「日本の大学のどこに一番違和感を感じましたか?」と聞いたことがある。 ・ひとりが「学生が授業中寝ていることです」と答えたところ、皆が「そうだ、そうだ」と大きくうなずいたのである。 ・「どうして大学生が教室で寝ているんですか? それでも大学生ですか!」と言うのだ。 ・それを日本人大学生にぶつけてみると誰もが「だって、誰にも迷惑かけていないんだから、寝ようが勝手じゃないですか」と言う。「寝ていて、授業についていけなくて後で困るのは自分なんですから、別に他人に何か言われる筋合いじゃないでしょう」。 ・しかし、海外からの留学生にとってショックなのは、「大学生にもなって教室で寝ているあなたには、大学生としてのプライドはないのか?」ということなのだ。 ・寝ていたら先生から怒られ、成績が下がるならば寝ない。友達から非難され、最低人間だと思われるなら寝ない。しかしそうした「人の目」がなくなれば、寝てしまう。 ・しかし、「人の目」がなくなっても、「自分の目」から見て教室で寝ることは大学生として恥ずかしいことだと思わないかと留学生たちは問うているのだ。 失われた自尊心 ・ルース・ベネディクトは、「人の目」から非難される「恥」を強く意識する日本文化を「恥の文化」と呼んだ。 ・しかし、彼女はもうひとつの「恥」を見落としていた。 ・それは「私としたことがこんなことをしてしまうとは!」という、「自らを恥じる」という恥である。 ・誰からも見られていなくても、恥じる。あるいは、「こんなことをしてしまって、ご先祖さまに申し訳ない」「亡き恩師の期待を裏切ってしまった」と、既に生きていない人々に対して恥じる。日本人の倫理観は、単に自分の周囲の「人の目」だけではなく、先人たちや恩師たち、そして自分自身に対して恥ずかしいという感覚にも支えられていたのである。 ・しかし、そうした恥の感覚が薄れ、「人の目」のみを気にするように「恥の文化」が縮小してしまい、それ故「人の目」が気にならなくなれば何でもやってしまうというのが現在の日本人の姿なのではないか。 ・そして、そこには決定的に欠けているものがある。それは自分自身に対する「自尊感情」だ。 ・自分自身に対する自尊感情がある人間ならば、「人の目」がないところでも、何でもやり放題ということにはならない。 ・自分自身が尊い存在であるとということを認めている人、尊重されるに足る存在だと感じている人、自己を信頼し、自尊心のある人は、「私としたことが、恥ずかしい」ということはあまりしないし、してしまったにしても反省する。 ・しかし、自尊感情が低く「自分なんかどうせたいしたことないんだよ」と思っている人は、人の目がなくなってしまえばどんなことでもできてしまう。自分という存在が、‹ワガママ›な行動を律する歯止めにならないのだ。 ・‹我がまま›が‹ワガママ›に転ずるかどうか。それは、そこに自尊感情、自己信頼があるかどうかが大きな分かれ目になる。 ・自己信頼に支えられた‹我がまま›の追求は自分を生かし、他者も生かすものとなることが多い。 ・しかし、自己信頼のない‹我がまま›は‹ワガママ›となって他人に多大な迷惑をかけるものになりがちだ。 ・つまり、現在の‹ワガママ›が横行する社会は、私たちひとりひとりの自己信頼、自尊心が低い社会であることの裏返しだと言えるのである。 「敵討ち」としての‹ワガママ› ・自己信頼や自尊感情は私たちが成長していく中で与えられるものだ。 ・私自身が存在しているだけで喜ばしいことだと、親からの「無条件の愛」によって私は愛されるに足る存在だということを知る。 ・あなたは尊重されるに足る存在だと、教師や友達から「私自身への信頼」をプレゼントされる。そうした経験によって私たちは自分自身が尊重され、信頼に足る人間だという感覚を身につけるのである。 ・しかし、現在の日本社会は子どもたちの自尊感情を傷つけ、自己信頼を抑圧するような「生きる意味」のシステムを持っていた。「条件付きの愛」を与え、「いい子」を育てるような社会が続いてきたのだ。 ・多くの人たちは自尊感情や自己信頼の低さの陰で「恨み」を抱いている。 ・あるがままの自分自身を認めてくれなかった親に、社会に恨みを抱く。 ・「人の目」を押しつけて自分自身を抑圧するように仕向けてきた「生きる意味」のシステムに恨みと憎しみを抱いている。 ・そして自由になったら何よりもその恨みを晴らしたいと思っている。 ・だから、いったん「人の目」から解放されてしまうと、私たちの行動は「敵討ち」になる。 ・「人の目」によって抑圧されていた様々な行動がいっぺんに噴出し、とてつもなく ‹ワガママ› になってしまうのだ。 ・恨みを持っている私たちは、「人の目」から解放され、思う存分「敵討ち」をすることが自己実現であり、人生の創造性の発揮であると思いがちだ。しかしそれは違う。 ・恨みを晴らし続けても、自分自身の自尊心や自己信頼が回復されなければ、私たちは永遠に「敵討ち」を続けなければいけない。それは創造性のある人生とはほど遠いものだ。 ・「敵討ち」は最初のうちはひとつの創造的な行為だが、しかしそこに凝り固まってしまえば「内的成長」はそこで止まってしまう。 ・「敵討ち」を続けることは「敵」からの解放ではない。常に「敵」を意識し、そこから逃れられないという意味で、それは「敵」に支配され続ける行為なのだ。 ・そこで自己信頼と自尊心が回復していかなければ、私は結局「敵討ち」という形で、常に「敵」に支配される人生を送ることになるのである。 2.「生きる意味」への第一歩 ・世間に横行する ‹ワガママ› の進行を、私たちが「人の目」を気にしなくなったことが原因だと考え、私たちに、そして特に学校で子どもたちに「人の目」を埋め込もうとすることで乗りきろうとするのは全くの逆効果だ。 ・この社会における「自尊心」「自己信頼」をいかに高めていけるのかこそが問われている。 ・「数字」や「日本人」といった「分かりやすい」もので自分たちを束ねようとしても、そこにひとりひとりが自分の尊厳を取り戻す社会は生まれない。 ・ひとりひとりの「生きる意味」が尊重され、ひとりひとりの人間の生き方に敬意が払われ、お互いに支え合って生きていくような「日本」を愛するのか、それとも、ひとりひとりの「生きる意味」が抑圧され、効率性によって切り捨てられる人を救うこともなく、しかしそうした矛盾をごまかして社会の統合を図るために持ち出される「日本」というブランドを愛するのか、そのどちらの「愛国心」なのかで、結果は全く異なることになる。 ・私はブランドとしての日本ではなく、ひとりひとりのエネルギーと思いが、互いを生かし支え合う、私たちのつながりとしての「日本」を愛したいと思うのだ。 「他者の声」を聞くこと ・現在の仏教が真理を言葉で「説くもの」になってしまっていて、「苦悩」を「聴く」ものとなっていない。 ・私たちの知りたいのは最初から決まりきった正解なのではなく、私の人生の中で起こってきた「苦悩」から私たちの「生きる意味」を紡ぎ出していくことである。 ・説くだけで聴かないコミュニケーションのあり方は、そうした私たちの空しさを倍加させるものであり、私たちが真に求めているものへ届かない。 ・私たちが苦悩しているとき、その苦しみの声を聴いてもらった体験は、確実に自分自身と世界への信頼を深めるものだ。 ・世界は私の声を聴いてくれるという実感を持つ人は、その世界を破壊しようとは思わない。 ・自分の苦しみ、弱さを深く受けとめてもらった経験を持っている人は、人を傷つけたりしたいとは思わない。 ・「いい子」の若者が突然キレて人を傷つけるのは、「いい子」を演じ演じさせられる関係の中で、自分の苦しみの声が聴き逃されてきたからであり、それは決して突然の出来事ではない。 ・表面の体裁を整えることばかりで、私たちの深い苦しみ、呻きが受けとめられない社会は、むしろ暴力が噴出する社会となる。 ・表面上が妙に明るいだけの社会は、裏に大きな闇を抱え込む。 ・一見ネガティブな声を表現してもいい社会、そしてそれが聞き届けられる社会こそが、信頼を醸成する社会なのだ。 ・私の喜びを我がことのようにともに喜んでもらった体験は、私たちにこの世界に生きる大きな幸せを与えてくれる。 ・さらに、私たちは自分自身も他の人の喜びを心からともに喜びたいものと感じる。 ・「自分の幸せのみを喜ぶ者の幸せは有限である。しかし他人の幸せを我がことのように喜べる者の幸せは無限である」という様々な文化に伝えられている教えは、このような社会が私たちに最大の幸せをもたらしてくれる社会のなのかを教えてくれる。 ・「自分を表現すること」、そして「他者の声を聴くこと」、それは私たちが共感しあうコミュニケーションの場をもたらす。そしてそういったコミュニケーションによって、私たちの自己信頼、社会への信頼は回復していくのである。 「オリジナリティー」とは何か ・私たちの出発点は、自分自身が「交換可能」な存在であり、「かけがえのない存在」であると感じることができないという「生きる意味の病」であった。 ・そして私たちの到達点は、自分自身で自らの「生きる意味」を創造していく社会である。それはひとりひとりがオリジナリティーのある生き方を獲得する社会だと言ってもいい。 ・ここで言うオリジナリティーとは、よく使われるように「他の人と違う」という意味ではない。 ・「君の意見にはオリジナリティーがない」といった言い方は「他の人と同じ」という意味で多く使われるが、それは必ずしも正しくない。 ・オリジナリティーとは何よりもまず「自分自身にオリジン(源)がある」ことである。 ・他人の言うことを鵜呑みにしたり、他人に同調したりして同じことしか言わなければそれは「オリジナリティーがない」ということになるが、私が私自身の「生きる意味」を創造する中で結果的に他人と同じ結論に至るのならば、それは私のオリジナリティーなのだ。 ・私が「交換不可能」であり、「かけがえのない」存在であるということは、他の人とことさらに違うところを探すというわけではない。 ・それは自分自身の人生にオリジナリティーがあるかどうか、自分自身が「生きる意味」の創造者となっているかどうかの問題なのである。 ―― 完 ―― |