
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年08月07日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
93 |
18/12 |
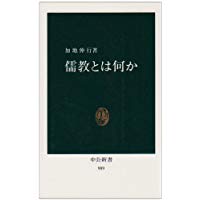 |
儒教とは何か |
加地伸行 |
中公新書 |
◎ |
序章 儒教における死 一 ‹女の姓を返す› 儒教 ・中国・韓国(朝鮮)、そして明治三十一年以前の日本――これらの国々では、結婚後も妻は生家の姓を名乗っていた。 ・その根本理由は、儒教における「同姓不婚」の原則によるものである。 ・「同姓不婚」とは、文字どおり同じ姓の者は結婚しない、ということであり、もとは中国古代の慣習であった。 ・儒教はそれを取り入れ、家族のありかたの重要な原則とし、中国はもちろんのこと、政治上、儒教を重んずる朝鮮、日本へと普及していったのである。 二 仏教における死 ・肉体の死とともに、霊魂は浮遊する。肉体は抜殻であるから、荼毘に付す(火葬する)。仏教ほんらいの立場に立てば、お骨に意味などはなく、山にでも川にでも捨てるべきである。 ・一方、成仏しないかぎり、霊魂は、肉体の死とともに、中陰という時間に入る。その長さは四十九日間である。その間に次に生れ変る場所が定まる。 ・そこで、すこしでも良いところに生れ変ることができるよう、僧を通じて供養する。 ・それは初七日に始まり七日ごとに行なわれ、やがて四十九日目の当日、その人の生前の行為の善し悪し、すなわち因果応報によって生れ変る先が決る。ここで中陰にいる時間が終る。 ・それは「中陰を満たした」ことであるから、「満中陰」となる。 第三章 儒教の成立 一 原儒――そして原始儒家 ・思想の歴史は常にそうであるが、或る思想、或る理論体系が登場するとき、必ずその母胎、あるいは先駆的なものがある。 ・孔子に始まる儒教、理論体系を持った儒教が登場する前、その母胎があった。それを原儒と名づける。 三 孔子の自覚 ・儒教では、死後の日数の数え方は、死亡日の前日から数える。 ・だから三年の喪とは、満二年目の忌日(命日)ということであって、けっして満三年目ではない。 ・仏教はこれを取り入れて三回忌を行なう。三回忌を満三年目ではなくて満二年目に行なうのは、儒教における三年の喪という重要な行事の模倣である。 四 孔子の孝と礼制と ・喪にする期間の意識は、現代日本において今も生きている。 ・それは学校や官庁・会社において認められている忌引という特別の休暇制度である。 ・学校・官庁では、たとえば親の死のときは七日間、兄弟や姉妹のときは三日間、三親等内(伯父叔母など)のときは一日の欠席・欠勤を出席・出勤扱いにしているが、それは儒教の喪制の考えかたに基づくものである。 五 儒教の成立 ・死生の上に孝を置き、孝の上に礼を載せる。この孝が社会の規範(それを延長すると最後は政治理論となる)である。 ・そして、その礼の基準の役割を果しているのが、親の葬儀を中心にしている喪礼である。 七 学校と官僚層の教養と ・シャマニズムを単なる祈祷段階にとどめず、それを思想化して現実の社会に適応する理論を作っていったのは、おそらく、世界で儒教だけであり、原儒から儒教へと、その成立を推進した中心人物が孔子であった。 八 道徳と法と ・孔子の弟子の内、 (一)心の内省や礼の内容・目的を重んじた実践派・哲学者であった、曾子の系統から、後に孟子(前三八五?~前三〇五?)が登場 (二)知識や礼の形式を重んじた文献派・学術派であった子夏の系統から、後に荀子(前三三五~前二五五?)が登場 したと言われる。 ・その結果、孟子は人間の心にある良心を根拠にして、性(人間が生まれつき備えているもの)は善であると主張した。いわゆる性善説という倫理学説である。 ・これに対して、荀子は、人間の心は善とは限っていないとして、良心という自律的なものではなくて、礼に従うという他律的なものによって、しだいに善にしていこうという考えかたをした。いわゆる性悪説という倫理学説である。 ・孔子によって原儒を脱皮して儒教が成立してからは、君子儒(知識儒)は、孝を基礎とする家族理論、その上に立つ政治理論について思考を進めてゆく。 ・同時に、小人儒(祈祷儒)が広く民間にあって活動していた。しかし、祈祷儒たちに、理論の展開はない。 ・儒教と言えば、倫理という概念がほとんど同時に重なるのがふつうであるが、その理由の一つは、孔子以後の知識儒と祈祷儒との分れかたが、かなりはっきりとしている点にある。 ・特に、孟子や荀子によって、現実の政治をどうするのかという政治思想が深められた。 ・そしてついに、倫理的には性善説と性悪説の対立、さらにそれぞれのその倫理的立場に立つ政治思想として、儒家の徳治政治と法家の法治政治という大きな対立へと発展してゆく。 ・この法家とは、荀子の弟子であった韓非子(前二七五?~二三四?)を代表とする学派である。 ・中国哲学史の通俗的教科書は、よくつぎのように書いている。 ・儒家は徳治政治を、法家は法治政治をそれぞれ主張した。徳治とは道徳による政治であり、法治とは法律による政治である。 ・道徳による政治のほうが、法律による政治よりも勝れているのだが、秦の始皇帝は法治政治を行ない、道徳政治を唱えた儒者を弾圧(たとえば焚書坑儒のように)した。 ・そういう苛酷な悪政を行なったので、秦王朝はわずか二十年ほどで滅亡し、漢王朝が登場した。この漢王朝は儒教を重んじたので成功した。 ・以後、王朝は何度も交替してゆくものの、儒教による政治が中国の政治の本流となった。 ・道徳には二種類がある、とする考え方がふつうである。 ・一つは、普遍的なものである。たとえば、人を殺さないとか、人を裏切らないとかいったもので、古今東西を通じて、人々が納得するものである。 ・いま一つは、その時代その社会に適合した慣習である。たとえば、奴隷制の時代では、主人に絶対的に服従するとか、社会主義国では、私利の追求を禁ずるとか、といったものである。 ・この二種類において、前者は普遍であるが、後者は時代や社会の変化に応じて変化する。 ・たとえば現代では、夫が妻以外の女性に子どもを産ませることは不道徳である。のみならず、法的にも誤った行為とされる。 ・しかし前近代の東北アジアにおいては、男系を優先するから、男子を産めなかった妻以外の女性に男子を産ませることは、儒教的には、不道徳どころか、むしろ道徳的だったのである。 ・法治や徳治といわれるものの真相 儒家→道徳第一(共同体的) →慣習法重視→徳治 法家→法律第一(中央集権的)→成文法重視→法治 ・近・現代国家は、成文法(罪刑法定主義)に基づく法治国家である。それは共同体の崩壊度に比例する。 ・いわゆる近・現代国家化とは、共同体をできるかぎりつぶして、個人単位にし、その個人の上に国家を載せようとするものである。 ・現在、中国大陸において、依然として罪刑法定主義が定着していない。 ・つまり成文法による近代的法治国家となっていないのは、共同体が相当程度の規模で依然として生きていることを意味する。 ・そのため、一罰百戒的に、窃盗犯でも、ときには見せしめとして死刑にしたりしている。 ・形式的には社会主義国家と言っているけれども、実質は依然として儒教的共同体の集合であって、およそ近代的法治国家とは縁が遠く、封建時代風であるのが実情である。 九 反儒教の老荘 ・形式主義への堕落を批判したのが、墨子たちや老子・荘子たちである。いわゆる反儒教の人々である。 ・わけても老子は、反儒教の代表格であり、孔子と老子とは、相対立する二つの立場として、このあと、大きな流れを作ってゆく。 ・老子という人物は存在しない、というのが通説である。 ・重要なことは、老子という人物に託されて残っている『老子』という書物の中の思想である。 ・老子の立場とは、一言で言えば、孔子の胸を借りた反儒教である。常に儒教の諸テーマに対して批判するという形である。しかもそれは対照的であった。 ・人間は原始的世界にあるとき、ただひたすら人工的世界を追い求める。その成果が、たとえば儒家の文明賛歌、人工的世界の賛歌である。 ・しかし、老子はそうした文明や人工の世界の賛歌の中にある堕落を批判して、反対に(逆説的に)自然的世界を持ち出してきたのである。 ・原始的な自然的世界から人工的世界となったそれの否定であるから、人工的世界の批判の結果生れてきた、自然的世界の重視である。 ・それは、人工的世界重視を一度経てきた自然的世界重視であり、たんなる原始的自然の世界の賛美ではない。自然の見なおし、自然の再評価とでも言うべきものである。 ・こういう意味で、老子の立場は、儒家の胸を借りた反儒教である。 ・あえて言えば、その儒家批判はなかなか鋭いが、それでは儒家の人工的世界重視を否定して何が残り、どういう具体的世界ができるのかというと、はなはだ心もとない。 ・スケッチとして表されているのは、人々が争わず自給自足の静かな田園生活を送るという空想だけである。家族理論はもとより、政治理論もない。 ・そういう老子からは、具体的な制作や社会規範がないのは当然であり、結局は、中国の実社会や政治において思想として主流となることはなかった。 ・儒教が、個人以外、常に社会を問題とするのに対して、老子は、個人の問題にとどまるものであった。 第四章 経学の時代(上) 二 原始儒家思想から経学へ ・‹聖人と関わり深い古典について解釈を加える学問› を ・『詩』を『詩経』、『書』を『書経』、『易』を『易経』、というふうに、「経」の字をつけ加えてゆくようになったのは、 ‹経学› の登場が原因である。 三 『孝経』 ・『孝経』の内容であるが、孝について述べたものである。 ・周王朝末期に出てきた荀子は、孝の位置づけに手を加えている。 ・すなわち、ただ孝というのは、「小行」であり、父母はもちろん、君主など長上の者に従順であり、目下の者に対して愛情を持つことは「中行」であり、さらには、そうした現実の君や父に従順であることから一歩進み、 ・つまり、道義という普遍的なものが、君父よりも、孝よりも上にあるという考えである。 ・このように、普遍的なものを持ち出してきて、孝という共同体道徳の上に置くことは、荀子が、儒家ながら、当時、共同体を越えて、しだいに中央集権的国家へと向かいつつあった状況を強く意識したからであろう。 ・この荀子の弟子が、韓非子という法家思想家であり、法に基づく中央集権国家の秦王朝の理論的基礎を与えることとなる。 四 春秋学 ・『春秋』というのは、周王朝時代の諸侯の一つであった ・歴史を修養の鑑にしようとする、そういう学問を春秋学と言い、前漢時代に大流行し、五つもの学派がふったという。 ・前漢時代に経学が登場し、諸経典の内、『孝経』と『春秋』とが重視された。 ・武帝の時代になって、建元五年(西暦前一三六年)、五経博士という官職が置かれることとなった。 ・博士とは官職である。いわば国家公務員であり、儒教を国定の学問としたのである。 ・当然、そこで学ぶ学生が増え、この学生が官僚となってゆく。そして、しだいに他の学問を圧倒してゆき、儒教は国の学問、国教(国家公認の教え)となっていった。 ・儒教は、かつての民間在野の学問とまったく異なってしまったのである。 ・この五経博士制定によって、儒学は前漢王朝への乗りこみに完全に成功したのであった。 第五章 経学の時代(下) 一 儒教・仏教・道教――三教 ・儒教自身の宗教性は、各家族における祖先崇拝となり個別化したため、教団といったものができなかった。 ・仏教・道教ともに、後漢時代から魏晋南北朝時代、そして隋唐時代へという、七、八百年の間、中国において盛んであり、その間、はじめは儒・仏・道の三教が争い、やがて融和してゆくという歴史があった。 ・三者に共通する重要な問題はいくつかあるが、最重要点は ‹死について› である。 ・死――その恐怖の解決方法の説明こそ、宗教にとって最大の課題であるからである。 ・仏教は輪廻転生を説き、儒教は招魂再生を言う。道教は死の恐怖の解決として ‹不老長生› を説くのである。 ・ ‹不老長生› は、儒教の ‹招魂再生› と並んで、即物的・現実的な中国人に対する死の不安・恐怖の解決方法として圧倒的に支持されたのである。 ・しかも、儒教が、死自身についてはただその運命を受け容れるだけであり、無抵抗であるのに対して、道教は、死に対して敢然と挑戦し、具体的な延命を教える。 ・たとえば、肉体の運動をして鍛錬する。今日も行われている気功術や太極拳はこの系譜上にある。 ・あるいは薬を飲んで病気を予防したり延命する。 ・サルノコシカケなど、キノコ(道教ではキノコ類を霊芝と言う)類を始め、水銀(水銀は皮膚病によく効いたので、かつてはよく使われた。また、栄養や衛生の状態の悪かった昔は、皮膚病が多かった)に至るまで多くの薬があり、対症療法的に調合も盛んである。 ・また、穀類を食べないという食事療法や、深呼吸法など、精神や身体の安静によってストレスを解消したり、深山幽谷に住んで森林浴をするなど、今日のさまざまな健康法の原型がほとんどすでにあり、実行されていた。 ・そして、その努力の最後は、永遠の生命を持つ仙人となることができるとした。 ・のみならず、信者の場合、道教の神々を拝むことによって、現世利益も得られることとなり、多神教の中国人のことであったから、商売の神・病気平癒の神・縁結びの神……というふうに日常の信仰にもまた広く食いこんでいった。 ・生命を長くし、財物を増やすことができる宗教、それなら盛んになるのは当然であった。 ・あっと言うまに、道教が広がり、中国人の民族宗教となったのである。 ・儒教――家族の祭祀による現世への ‹再生› ――招魂再生 道教――自己の努力による不老 ‹長生› ――――不老長生 仏教――因果や運命に基づく輪廻 ‹転生› ―――輪廻転生 二 選挙――推挙から科挙へ ・徹底的に皇帝の手足となる官僚を持つことが、中央集権国家の貫徹ということになる。 ・皇帝としては、そういう直属的な官僚を持つことが理想であった。 ・それが成功するのは、隋・唐代あたりからの科挙合格者の登場である。 ・科挙とは、「科」目によって人材を「 ・科挙出身の官僚は、皇帝に対して忠誠を誓う直属的な臣下であった。 ・隋代になって試験制の科挙制が布かれ(五八七年)、以後、一九〇五年に至るまでの千三百年間、それが続くことになる。 ・すなわち、人物を「選び挙げる」(選挙)方法が、推薦制(推挙)から試験制(科挙)へと変ったのである。 ・科挙は公平な試験であったから、優秀な人物を得ることができた。そしてこの試験の基準となるものの中心が、儒教であった。 三 朱子学 ①存在論・宇宙論 ・前漢時代、国教の地位を得た儒教は経学として発展したが、後漢時代の後半から強敵を持つこととなる。仏教と道教とである。 ・十一世紀の宋代になって、儒教側から、宇宙論・形而上学に弱かった点を補おうとする。その役目を担ったのが、宋学である。 ・宋学とは、宋代のこの新しい傾向の思想を指し、新儒学とも言われる。 ・その中心人物が朱子(朱熹)であるので、宋学は朱子学とも言われる。 ・だから、朱子学は朱子個人の思想を表わすだけではなくて、宋学の代名詞と言うべきものである。 ②教育 ・人間は唯一最高の神の前にひれふさねばならないとするキリスト教、輪廻転生の長い長い時間の間、懸命の努力をしてやっとあるいは解脱できるとする仏教にくらべて、儒教は遥かに常識的である。 ・日々の人間の努力によって必ず理想像(聖人)に至れるとする。 ・そういう思想や伝統的立場を背景にしていたからこそ、朱子は教育課程を示したのであり、聖人のことばを理解し実行して聖人に成るための方法として教育を重視したのである。 ③道徳論 ・儒教倫理と言うときのイメージに二つのものが重なっている。 ・一つは、徳目そのものである。 ・たとえば五倫(父子の ・いま一つは儒者というイメージである。 ・なにか恐ろしく気まじめな、融通のきかない堅物の人間、篤実とでも表現すべき人間、そういったイメージである。 ・徳目と儒者のイメージとのこの二つが混然としているのが、儒教のイメージである。 四 朱子学以降――そしてキリスト教 ・明代になって王陽明(十五世紀)という人物が登場し、心学は陽明学とも言われる思想に発展することになる。 ・この陽明学は、朱子学理屈の多い主知的な行きかたを批判し、人間にはもっと大切な、溢れ出る生命のような生き生きとしたもの(良知)があり、それをこそ重んずるべきであるとした。 ・つまり、主情的立場によって、主知的な朱子学を批判したのである。この、心の重視とは、強烈な ‹自己› の主張でもあった。 ・典礼問題とは、唯一神を崇めるキリスト教(特にカトリック)の立場からして、天帝(上帝)や孔子や自己の祖先を崇める中国の儀礼との妥協をどこまで認めるのかということである。 ・中心問題は「祖先崇拝および孔子崇拝を宗教的儀礼と見るか否かということと、カトリックの神に対する訳語として ‹天› ‹上帝› のような中国語の使用を許容すべきか否かの三点を骨子とする。 ・今日においても、キリスト教信者が戦死した英霊を祭る靖国神社に政府高官が参拝することに対して批判するのは、一種の典礼問題と見てよいであろう。 ・だれでもカミとなることのできる日本の、八百万の神としての靖国神社の ・「神」という漢字は同じであるが、概念はまったく異なっているのである。 ・これでは多神教の東北アジア人に対して説得力がない。キリスト教徒は、昔も今も依然として東北アジア人の心が分っていない。 ・だから、明治維新以後、キリスト教関係者がどのように努力しても、その信者数はいっこうに増えず、依然として、全宗教信者数の数パーセントにとどまっているのである。 ・日本をはじめとして儒教文化圏では、祖先崇拝や祖霊信仰などを取りいれなければ、宗教として成功することはむつかしいということであろう。 終章 儒教と現代と 一 現代における儒教 ・儒教の宗教性は、現代においてしぶとく生き残っている。 ・すなわち、孝である。祖先崇拝・親への敬愛・子孫の存在という三者を一つにした生命論としての孝、死の恐怖・不安からの解脱に至る宗教的孝である。 ・その孝は、日本では仏教が吸収してしまってはいる。 ・しかし、家庭における仏壇は、実は仏教ほんらいのものではなく、儒教における廟・祠堂あるいは祖先堂(祖先の ・仏壇の最奥上段に座します本尊を拝み、読経すること、これは仏教である。 ・しかし、本尊から一段下った中段に並べられている祖先の位牌は、空中に浮ぶ祖先の霊を ・そこに祖霊を招き(思いを致し)慰霊をする。それは儒教である。 ・仏を崇める経文を読みつつ、一方、香を焚き、まごころ(誠)をこめて祖霊に祈るのは儒教の招魂儀礼である。 ・毎朝、私は仏壇の前で、崇仏(仏教)と慰霊(儒教)とを行なっている。この二つを混合しながら、古来、日本人は仏壇を自分の家の精神的拠りどころとしてきた。 ・儒・仏の二つを混合している中国人・朝鮮人もそうである。 ・私は真言宗信者として仏教を、原感覚として儒教を、論理矛盾を知った上で、とても大切にしている。 ・日本人はお彼岸やお盆には祖先の墓参りをする。仏教においては、墓を建てることはもとより、墓参りなどあり得ないのに、日本人はそれを行なう。 ・すなわち、墓参りは本来儒教であり、その日をお彼岸やお盆の日に選ぶのは日本仏教である。 ・儒教において墓参りし、墓の掃除をするのは、清明節(春分の日からあとの十五日間)のときであって、彼岸や盆とは関係がない。中国人は今もそうしている。 ・儒教文化圏の人々には、キリスト教的な唯一神の恩寵を求めるという他力的な発想はない。 ・仏教的な輪廻転生という発想もまた希薄である。 ・この現在、この現実を家族とともにどう生きてゆくのか、ということを懸命に考え行動する生活者が、儒教文化圏の人々である。 ・それを支えているのが、宗教的孝、生命論としての孝であることは言うまでもない。 ・‹儒教の宗教性›は、一部、家族理論中の礼教性を残しつつ(家族が接点であるから当然であるが)、儒教文化圏、東北アジアの人々の心の中に生きている、心の深層の中に生きている。 二 儒教と脳死・臓器移植と ・脳死について報道で伝えられる議論は、医学・法律・倫理などの方面のそればかりであって、宗教的観点よりする意見が十分でない。 ・人間は、医学的理解・法律的合意・倫理的納得といった生の世界にある一方、死の世界を考える生物である。この死の世界については宗教のみが語りうる。 ・脳死を議論するならば、死の世界を語りうる宗教的立場からの発言に対して、まず耳を傾けるべきであろう。 ・しかし、現在のところ、宗教的立場からの発言も、仏教やキリスト教などからのものがほとんどである。 ・これは偏っている。東北アジア人ならば、まず第一に儒教の立場を聞くべきであろう。 ・問題は、死の把え方である。 ・死後、肉体は土に帰り、魂は肉体から脱けでて存在するという観念は非常に古くからあり、また世界各地に見られることはいうまでもない。 ・さらに、この魂を現世に招いて再生させる招魂儀礼もまた古くから広く行われてきた。いわゆる祖先(祖霊)崇拝はその典型である。 ・儒教は、①一族が亡き祖先を追慕して祭ること、すなわち招魂再生儀礼、②生きてある親につくすこと、③祖先以来の生命を伝えるため子孫を生むこと(人口の適切な増加を求める人口論もここに関わっている)、この三者をあわせて「孝」と称し、儒教理論の根本とした。 ・孝とは、祖先という過去、親という存在、子孫という未来にわたって生命が連続することに基づく思想なのであって、現在の親だけを対象とするものではない。 ・すると、祖霊は招魂儀礼によって、このなつかしい現世に再び帰ってくることができるし、逆に、現在のわれわれをして遠い過去にも生きていたことを知らしめる。 ・現在、われわれが存在すること、すなわち逆に言えば、祖先があるということは、われわれがたとえば百年前、あるいはさらに千年、万年前に確実にどこかで個体として存在し生きていたことを意味する。 ・このように儒教における孝とは、生命の連続を主張する生命論なのである。 ・だからこそ、生きている親が子のために臓器を提供すること、すなわち生体臓器移植などには納得するのである。 ・この結果、死に臨んでは身体の完全さを重んじることになる。 ・そうなると、招魂儀礼によって現世に再生するとき、身体の完全ということを意識せざるをえない。 ・とすると、仮に眼球を提供してしまった場合、再生のとき、物を見ることができにないという恐怖と嫌悪の念とが生じるのである。 ・儒教は、中国・朝鮮、そして日本と、祖先崇拝を核とする儒教文化圏を作ってき、二千年以上にわたって政治や社会を動かしてきた。 ・それを可能にしたのは、儒教理論の根本において孝という生命論があり、祖先崇拝の精神的紐帯とともに儒教文化圏の人々の感情をしっかと捉えてきたからである。 ・その影響は大きく、日本人の心に根深く生きている。流行の新興宗教に共通する呪術的シャマニズム的傾向(とりついている悪霊を取り除くと称する浄霊行為など)は、儒教文化圏の日本人が古くから持ち続けている招魂儀礼・祖先崇拝の心情に巧みに乗ったものである。 ・いや歴史的には、仏教における先祖供養、あるいはさまざまな慰霊祭もまた儒教やその儀礼の影響の下にある。 三 儒教と教育と――そして自然科学的思考の基盤 ・知識教育もさることながら、道徳教育ということが儒教の教育観において大きな位置をしめている。 ・今日、小・中・高校において生徒が義務として掃除をするのは、おそらく儒教文化圏における学校のみではなかろうか。 ・この掃除という習慣は、東北アジア人の労働観にもつながっている。 ・インドのカースト制では、掃除は低い階層のすべきこととなっている。身分の差別と職種とを並行させている。 ・しかし東北アジア人にそのような観念は少ない。だから、必要とあれば、みなが一致協力して掃除(労働)をする。つまりは全員が同一作業(職種)をする。また、掃除は整理整頓という習慣づけの形成に役立つ。 ・現代の工場における共同作業や整理整頓や品質管理の厳密さはおそらく同一線上においてつながっているであろう。 ・日本で「読み書き・そろばん」ということばに表されているように、東北アジアの初等教育では実学を重んじる。 ・なぜなら儒教では身近なことを学ぶことを重視するからである。それは今日においても生きている。 四 儒教と政治意識と ・現代日本の政治において「政治倫理」なるもの(その意味はよくわからないが)が強く求められている。すなわち、政治家的力量や行政官僚的能力よりも清潔な道徳家であることを求めるわけであるが、これは伝統的な儒教的お ・こうしたお上に対して、べったりと甘えてぶらさがるのが、われわれ儒教的民衆である。 ・ふだんはエゴむきだしで、政府は国民のすることに対して干渉するなと言いながら、社会においていったんよろしくない事件が起ると、政府を何をしていたのか、なぜきちんと対策をとらなかったのか、と声高に責める。 ・つまり、本質的には政府の御指導と御加護とを乞い願うという姿勢が抜けきらない。 ・一般的に言って、儒教文化圏の行政官僚は有能であるから(地位も高いから)、エゴ丸出しの民衆に対して、行政指導を行なうという姿勢は今後も絶対に崩さないであろう。 ―― 完 ―― |