
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年02月18日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
94 |
18/12 |
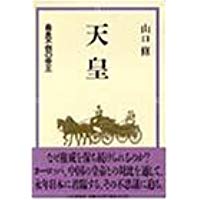 |
天皇 |
山口 修 |
PHP研究所 |
◎ |
一章 世界唯一のエンペラー 唯一のエンペラー ・この国際社会において、いまだに「エンペラー」として処遇されている人物が、ただ一人だけある。その人物は日本国天皇なのです。 ・日本国天皇が、日本国民の思惑とは別に、国際間において、ただ一人「エンペラー」すなわち「皇帝」として処遇されている現実を、はっきり認識している日本国民は、どれほどいるでしょうか。 ・国際社会では、日本国内における解釈(の混乱)にもかかわらず、天皇を日本国の「皇帝」と認めている。 二十世紀・九人の皇帝 ・一九一〇年という時点において、世界には九人の皇帝が君臨していた。 四章 天皇称を採用した時期 オホキミは神にましませば ・従来は "オホキミ" といえば、漢字で「大王」と書き、「天皇」と称する以前における君主の称号と考えられていました。 ・しかし「天皇」称が用いられるようになると、 "オホキミ" と呼ばれる人の範囲が皇子や皇女にまで広げられるに至ったことが示されている、といえましょう。 万世一系の系図 ・今日に伝えられるわが国の古代史の骨格が形成されたのも、七世紀の後半、天武 - 持統 - 文武朝の間と考えられます。 五章 オホキミの政権が成立 オホキミの権威 ・古代の王家および、その直系の子孫と称する天皇一族には、他家と区別するための「氏」がありません。これは各「氏」の名称が定まる以前、きわめて早い時期に、王家が他の氏族から超越する特別の家柄となっていたことを示すものでしょう。 七章 藤原氏の果した役割 絶大化する天皇の権威 ・王家そのものも、天武朝をへて、持統、文武朝となるに及び、他に実権をもった勢力が存在しなくなったことから、絶大の権威をもって君臨するに至っておりました。 ・長く用いられてきた "オホキミ" の称も、新しく「天皇」の称号が採用され、旧来の「王(オホキミ)」の称は、天皇の子女をさすようになりました。 ・そればかりか、天皇や皇子(オホキミ)は "神" であるとさえ、歌の上に示されるに至ったのです。 ・いまや天皇は、かつて天上の高天原に君臨した(という)太陽神、すなわち天照大神の子孫であり、その神勅をうけて、この国土と国民を永遠に統治する、という思想も形成されました。 ・天照大神から始まり、やがて地上には神武(天皇)があらわれて、 ・藤原氏は、天皇が他家を超越した尊貴な身分であることを強調し、その先祖に、建国のはるか以前から従属していたと称することによって、みずからの身分を高めたのでした。 九章 天皇は仏道に帰依した 「仏」と天皇と「神」 ・「神」は、あがめ祀らなければ、祟りをもたらします。「神」はおそろしい存在でした。 ・したがって人びとは、「神」の祟りにふれぬように、心をこめて祈りをささげたのでした。 ・こうして災厄からまぬがれることを期待してのですが、そうかといって「神」が救いを与えてくれる、とは考えられませんでした。 ・それだからこそ、救いを与えてくれる仏教が伝えられますと、上下こぞって帰依するに至ります。 ・やがて天皇(大王)まで信仰するに至り、国家の仏教として発展することになります。 ・お寺にまいりますと、仏(如来)や菩薩の像のまわりを、四天王とか十二天と呼ばれる恐ろしげな神像が取りまいております。 ・これらは元来、インドで古くから崇められていた荒ぶる「神」でした。 ・そうした「神」も仏教に帰依することによって、仏教を守護する「神」となったのです。 ・そこで、わが国における古来の「神」も、このような仏法の守護神と同格に位置づけられるようになりました。 ・天皇は、退位した後には仏門に帰依し、仏弟子となることを誰もふしぎには考えなくなりました。 ・一方で天皇は「神」に対して、位階を授ける例も開かれていたのです。 あまたの「神」の位階 ・日本の「神」は天皇から位階を贈られ、しかも人間と同じように “出世” していったのでした。 ・日本古来の「神」は、天皇から位階を贈られ、その位階の上下によって、人間の官僚と同じように、神格の高さを内外に示してまいりました。 ・すなわち天皇は、その一族を挙げて仏法に帰依する一方において、古来の「神」に対しては、位階を贈っていたのですから、いわば「神」の上に立っていた、と見なすことができましょう。 ・ところが平安時代のなかばをすぎますと、 ・本地垂迹の思想は、「神」と「仏」との習合という形で、早くも奈良時代には芽生えておりました。 ・「神」の本地が「仏」あるいは菩薩であるとすれば、もはや人間と同じような位階も必要ではなくなるでしょう。 ・また神仏が集合し、同じところに合わせて祀られる、という形態が一般となれば、信長のように、寺院を建てて「神」となるという考えも、ふしぎではなくなります。 八幡宮は仏教の霊場 ・九州の宇佐に鎮座した八幡神は、外来の信仰が、土地の神祇信仰と融合して、しだいに神社としての体裁をととのえていった、と考えられます。 ・そして、いつのころからか、天皇の祖先の一人である(と伝えられる) ・八幡神に対する崇敬は、飛鳥時代から高まっており、奈良時代には国家鎮護の神と仰がれました。 ・桓武天皇は、八幡神に "大菩薩" の尊号をささげます。ここに八幡神は「神」から「菩薩」に昇格したわけです。 ・神宮寺とは、神社に付属して営まれた寺院のことですが、古くから宇佐にも弥勒寺が建てられ、僧尼が巫覡(みこ)を兼ねて祭祀を司っていました。 ・形式は神社ですが、当初は神官もおらず、護国寺と一体をなして、寺をとりしきる別当が奉祀していました。 ・八幡神ははじめ大菩薩と称していましたが、本地垂迹説の盛行にともなって、阿弥陀如来を本地とするに至ったのです。 ・本尊の東には観音菩薩、西には勢至菩薩が侍立しています。そして、ご神体は僧形の八幡象でした。 ・八幡宮の社内では、読経の声が絶えることなくつづけられています。神事をつかさどっているのも ・その下に神主がおりましたが、供僧の支配を受けています。まさしく神仏の混淆という形態でした。 ・全国にわたって、多くの主要な神社が、堂塔を建てて仏像を祀り、僧侶が支配権を握っていたのです。 十章 復古という名の御一新 祝祭日の制定 ・四方拝は、天皇が早暁、天地、四方、山陵に拝礼する儀式で、古くから行われ、道教の色彩が強いといわれています。 ・とくに北方の天にむかって唱える呪文の最後「急急如律令」の語は、悪霊が "速やかに退散せよ" の意味に用いられ、もとは漢代の用語でした。 十一章 新しく作られた国体 大元帥とされた天皇 ・平和の時期にも、戦乱の時期にも、天皇が直接に関与した相手は、貴族であるにしても、武家であるにしても、一般の民衆とはかけ離れた権力でした。 ・極言すれば天皇は、政治または軍事の上で民衆と接触することはなかった、ともいえましょう。 ・しかし明治の世になると、すべての国民が、天皇は自分たちを統治する君主であると意識するようになったのです。 ・さらに明治6年1月、徴兵令が発布され、それまで軍事は武士にまかせていた民衆も、天皇の兵卒として軍事に携われねばならないようになりました。 ・ここに天皇と一般の国民とが、直結するに至ったのです。 ・これまで天皇が全国民のなかから徴集された軍人を、直接に統率されたことはありません。 ・もし天皇が軍人の大元帥たることが、わが「国体」の特徴の一つであるというのならば、そのような「国体」は、まさしく新しく創造されたものでありましょう。 ・勅諭は軍人の守るべき忠節・礼儀・武勇・信義・質素の五ヵ条の徳を強調していますが、とくに忠節の項の中で "世論に惑はず政治に拘らず只々一途に己が本分の忠節" を守るよう、さとしていました。まことに適切な指示といえましょう。 ・軍人たる者が脳裏にきざんでいた勅諭の内容は、その後の高級軍人によって守られたのでしょうか。それとも一部の軍人は、明らかに勅諭の精神を無視し、ふみにじったのでしょうか。 十二章 近代の天皇三代の足跡 明治天皇の真意 ・明治天皇が戦争を好まれなかったことについては、これまでにも指摘されています。 ・公式の記録である『明治天皇紀』においても、日清戦争については "今回の戦争は、朕 ・また日露開戦の前にも "今回の戦は朕が志にあらず。然れども ・立憲君主としては、その意に沿わずとも、内閣の決定には従わねばならぬ苦衷が示されている、といえましょう。 日本国の元首は誰か ・現行の憲法によれば、日本国の主権は国民にあり、天皇はその「象徴」であるとされています。 ・しかし国家である以上、国家を代表する元首が存在しなければなりません。 ・憲法の厳密な解釈によって、天皇が主権を行使するものではないとすれば、日本国の元首は誰であるか、という議論が起こってきます。 ・最も有力と認められている憲法学説によれば、日本国の元首は内閣総理大臣ということになっているようです。 ・しかし、この解釈は日本国内の法律学界または政治学界のものであって、国際間では通用していません。 ・しかも内閣総理と最高裁の長官とは、天皇によって「任命」される特別職です。 ・元首を「任命」する天皇とは、国家機構のなかで、どのように位置づければよいのでしょうか。 ・大公使の着任にあたっても、他の国の元首から信任状を奉呈する対象は天皇であって総理ではなく、わが国から派遣される大公使も信任状は天皇から発せられています。 ・さらに天皇は国際上、エンペラー(皇帝)と称せられる唯一の存在であり、その尊称は「陛下His Majesty」である。 ・国内においても天皇・皇后(および皇太后)は陛下、皇族は殿下であって、総理以下の「閣下」とは厳しく区別されています。 ・たしかに憲法においては「君主」という表現は注意ぶかく避けられ、主権も国民にあるところから、わが国は「民主」政体であるとの解釈も成立しますが、真の意味の民主国ならば、国権の長が何ゆえに「任命」されて就任し、その際に任命権者に対して最敬礼をするのでしょうか。 ・憲法学者の解釈は「象徴」という、意味の不明な語句にこだわって、あるいは憲法制定の事情に考慮するあまり、国家形態の実情を強いて曲解しているとしか考えられません。 ・明治の「国体」が変革された以上は、新しい「国体」にのっとり、それこそ古来の伝統にしたがって、元首たるものの地位を、国際間にも通用するよう、実情に即して理解してよいのではないでしょうか。 ―― 完 ―― |