
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年08月14日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク |
12 |
19/03 |
父よ 母よ! 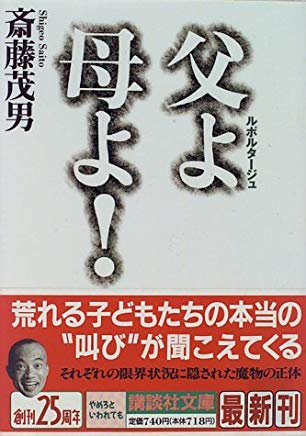 |
斉藤茂男 |
講談社文庫 |
☆ |
視点――「父よ母よ!」まで 「現代の貧しさ」の風景を ・繁栄とされる高度成長期以降の私たちの社会は、大量に生産し、巨大な宣伝をして大量に販売し、その商品を大量に消費するというメカニズムによって成立した。 ・一軒一軒の家庭はそのメカニズムの網の目にガッチリ組みこまれ、逃れることはできない。 ・そういう仕組みのなかで、じつは子どもの人間形成にとってもたいせつな土壌である家庭の「生活」も、その経済の論理に支配されてきたのではないだろうか。 ・たとえば、学校から帰った子どもが母親にオヤツを要求したとする。その場合、母親が原材料から菓子パンでも作り、子どもをその作る労働に参加させ、そのうえで母子ともども食べる喜びを味わおうという面倒な過程をたどるか、それとも、即座に千円札を一枚与え、子どもが商品を買ってすませるか、そんな一見ささいな場面の積みかさなりが、子どもの人間としての成長にとって、大きな差異を生むのではないだろうか。 ・一方には、「待つ」ということ、「モノを創る」おもしろさ、その過程での価値判断、技術といったこと、そして、できあがったモノのなかに、人間のさまざまな思いや工夫がこめられていることを知ること、などたくさんの滋養分がふくまれているはずだ。 ・子どもはそういう滋養分を身につけることによって「人間になる」道筋を歩いていく。 ・かりに母親が働いている場合でも、そのような「生活」の価値について認識があり、日常きめこまかい心遣いを子どもにしてやれない痛みを感じながら生活と闘っている姿を、子どもに見せているかいないか、それは大きな違いを生むのだろう。 Ⅰ 白い森の学校 子どもにからだでわからせる ・遠軽にある社会福祉法人・北海道家庭学校 校長 谷昌恒 氏曰く、 「真実は文字やことばで表わし得ないことを知っていながら、わからせたい一心で、思わず一方通行の説教が多くなってしまうのが私ども教師なのです。しかし、冷たい感じ、暖かい感じ、それは自分で知る以外にないのです」 ・子どもが親の家計を助けるような、切実さに貫かれたこの学校の生産労働。そのママゴトでないきびしさのなかで、少年たちが「生きること」のたいへんさと、自分に打ち勝つがんばりを身につけてほしい。 少年たちの涙 暗い母への思い ・「非行少年」とされて家庭学校に送られてきている少年たちには、父と母の、というより男と女の感情の波間にほんろうされ、愛情の砂漠に放りだされた子どもたちが少なくない。 取材ノート――① 樹下庵の人は語った ・(先代校長の)留岡清男は語った。 「(ぼくは)戦中派という年齢からくるのか、たとえば、安保、ベトナムなど、そういうことで公憤を発することについても、待てよ、という姿勢がある。マスコミが発達しているせいか、いまの世の中、まともに考えると公憤を発せざるをえない問題がいっぱいある。けれども、その人自身が日常、どういう生活をしているのかを切り離して、公憤を発することだけで正義の担い手になっちゃっているようなことがあり過ぎるんじゃないか、もっと自分自身をきびしく問い詰めて、身近なところで何かしなければならない」 「たとえば、日教組の先生なら、君自身、教室でかかわっている子どもはほんとうにどうなのか、そういう具体的な問いをしつこくしていかなくてはね。それがつい、パーッとわかりやすい一般論みたいな問題に食いついてくる。そういうくり返しではほんとうに困ると思う」 「わが寮卒業生の予後記録」から ・卒業生の四三人中二七人の両親が離婚している。 ・そのほに両親死亡三人、父死亡三人、母死亡二人、まがりなりにも両親健在なのはわずか八人。 Ⅱ 飢餓の街 X先生との対話 幻想に魅せられて ・結果として私たちのまえに現われた非行少年たちは、いずれも貧困の影を背負っていた。 Ⅲ 少女漂流 UFO娘の軌道 幼児期から愛の飢餓感に ・普通、緊張や不安があったりして楽しい状態にないと、子どもは指しゃぶりをするといわれる。 ・最近の児童心理の研究では、赤ちゃんのとき、母親と子どものあいだに身体接触や遊びが不足している場合に、がんこな指しゃぶりの癖が残るという。 非行状況をこう考える――番外取材 家庭の内側に過疎状況が モデルがない ・思春期の子どもたちにとってたいせつなことは、自分が将来どのような人間になるかの手がかりになるモデルが、身近に存在していることだ。 ・自己同一化の模範となるべき人間は、本来、父親か母親なのだが、登場する少女たちには、いずれもそれにふさわしい存在が欠けているように思われる。 家庭の非合理性 ・頼りにすべき親が欠けていたり、親自身の生活態度か男女関係の乱れなどで模範にならない場合は、より不幸な結果を生む。 ・母親の生活が乱れているような場合は、どうしても親の生活習慣が子どもの身についてしまい、いわばその家庭内の風土に染まって、批判力を失っていく。 ・親にひけ目があると、子どもをしかるべき場合にもしからないから、より悪い結果になる。 ・非行を生む家庭の親の養育態度を分類すると、ほぼつぎの八つのパターンに分けられる。 ①拒否型 ②厳格型 ③溺愛型 ④期待型 ⑤矛盾型 ⑥不一致型 ⑦放任型 ⑧干渉型 ・これらが混合している場合が多い。 ・だいたい、家庭というところは非合理的なものだ。 ・たとえば、ご飯を何杯食べようがカネをとるわけでなし、深夜まで働いても超過勤務手当を出すわけでもない。 ・その非合理性にこそ、家庭というものの魅力がある。 ・ところが、子どものさまざまな要求に対して、親が合理的か否かの基準だけで頭から拒否したり、あるいはまったく気持ちを理解してやろうとしない「拒否型」態度をとると、子どもにとって家庭は冷たく住みにくい存在でしかなくなっていく。 ・最近、ひじょうに増えているのが期待型だ。親が自分の価値判断で子どもの歩くコースを決めてしまい、子どもの自主性をそっちのけに、計画どおり進ませようとする。 ・この場合、子どもをしかると親の期待する道から脱線しかねないかと心配してつい甘やかすから、きわめて自主性のない子どもができあがる。 過密のなかの過疎 ・日本の家庭の内側に寒ざむとした「過疎状況」が横たわっている。 ・早い話が父親はどれだけ子どもと接しているだろうか。 "生存" はしていても疑似欠損状態にある家庭が多いのではないか。 ・たとえば、夕食の時間、食事のなかにテレビが介入すると、子どもはより強い魅力を持つテレビに引かれてしまい、親と子がその日のできごとを話し合うなどという場面は奪われてしまうだろう。 ・結局、親は単に「勉強しなさい」のくり返しと、断片的な "こごと管理" に終わってしまうのではなかろうか。 ・物理的には過密な居住条件を強いられながら、その内側は家族がバラバラにいるだけの過疎――こういう状態から親たちが本気で脱する手だてを考えるべきときではないだろうか。 父親の役割見なおせ ・作家であり精神医学者でもある加賀乙彦氏(本名は小木貞孝上智大学教授)曰く、 「最近の非行には新しい形態が現われているけれども、基本的には、家庭の問題であるという点で、戦後、少しも変わっていない」 貧しい内面生活 ・彼らの内面生活がたいへん貧しく、かわいそうな状態にあるということだ。 ・創造的なこと、きちんとした人生の目的を持ち、喜びを持って生きるということを知らない “ひまつぶし” これはたいへん哀れで、かわいそうだ。 ・いまの社会はそれに対処することをまったくしないから、彼らは底辺に押しつぶされながらうごめいている。 ・「早熟遅滞現象」 非行少年は一般少年に比べて、からだが早い時期に成長するが、ハイティーンになるとそれが逆転して、成熟が遅滞する傾向があること。 ・この現象は子どもにさまざまなゆがみをもたらす。 ・つまり、ローティーンては身体はおとななのに、精神生活が未熟で押さないままであり、ハイティーンになると身体的な劣等感から暴力的非行に走ったりする。 ・性的には何もかも知っているように見えながら、じつは内面生活は赤ん坊のように未成熟で、早熟でありすぎたために、どこかギクシャクしてうまくいかない。 ウドの大木 ・人間の成長には親との葛藤が必要だ。 ・二―三歳に第一反抗期があり、思春期に第二反抗期があって、とくに重要なのはこの第二期に理想のおとなに対して自分を同一化する、つまり、モラルが出てくるわけだ。 ・ところが、今の子どもはこの人生のいちばんたいせつな十四、五歳ごろに何をやっているかというと、もっぱら受験のための勉強をさせられている。 ・ふつう、男の子だと父親に反抗し、犯行のすえに和解する経路で成熟するのだが、いまは反抗も和解もない。 ・ここがズルズルといってしまうと、幼児性の段階で成熟が止まってしまって、自分でどうして生きていこうという意欲のない人間ができてしまう。 ・しかも、底辺で落ちこぼれた子はいっそう惨めな結果になる。 ・落ちこぼれなかったほうは救われているかというと、これも驚くほど困難に弱い。ウドの大木のようだ。 父親不在の罪 ・こうした成長を阻害しているのは "父親不在" 現象だと思う。 ・父親がモラルを、母親が愛情を、それぞれ受け持つのが文明国共通のパターンだが、そのモラルを担当する父親が、教育を放棄してしまった。 ・とくに一九六〇年代以降の忙しさで家庭にいつかず、父親不在がじつに大きな害をもたらしたと思う。 ・相対的に母親は時間のゆとりができるにつれ、教育に熱中するかたちになった。 ・これは愛情過多、甘えの型であって、いい子なんだがシンがない、迫力がない、そんな感じの子どもを大量に生み出してしまった。 ・しかも、落ちこぼれると、父親がとつぜん権力を行使して殴ったりする。それまで何もしないでおいて、いきなりやるわけだから、強烈な反発を引き起こし、よいことはない。 Ⅳ 砂の上の家族 暴力ベビー すれ違いの愛が悲劇に ・子どもが登校拒否・暴力というプロセスをたどる場合の親に多いのは、子どもをひとりの人格として認めることができずに、自分の思いどおりになる赤ちゃんでいてほしいという願望があることだ。 ・子どもが少しずつ外界とのかかわりを広げていこうとすると、足を引っぱる。そういう親の自己中心的なエゴイズムからの “愛情” は、ほんとうは自己愛に過ぎないけで、子どもの愛情欲求を受けとめたほんとうの愛とは異質のものなのだ。 ・親自身がそれをほんものと錯覚しているとき、悲劇が起きる。 ナイフの裏側 ・少年たちは裸の人間同士として親とぶつかることをバネに、生きなおすエネルギーを獲得するのだ。 裸の王様 ・この人生で何がいちばん高貴なダイヤモンドか、世の中の正義って何なのか、何がいちばん美しいのか、たとえば、そういったことを子どもに伝える人生の師として、父親・母親がいるのだ。 渇きの家 ・夫婦が自分たちにこそ問題があるということを自覚していない。 ・子どもが壁にぶつかった場合、すぐ親がその困難を背負いこんで解決しようとする。 ・カネがあることが子どもの自立に障害になっている。 ・夫婦のあいだで子どもについての話しあいがまったくないケース。 Ⅴ 両親へのメッセージ ・両親の愛のもつれ、たえまない葛藤、離別、蒸発、死亡……。 ・子どもたちの成長発達にかけがえのない人である父親、母親の側に、子ども自身が心とからだでせいいっぱい訴えている叫び声が、どれだけ奥深いところで受けとめられているだろうか。 父母の役割とは 甘えと厳しさのバランスを ・神経精神科の岩井寛・助教授 「よく一般に親の過保護がいけないといわれるんですが、じつは赤ちゃんのときに、たっぷり親の愛情を吸って育っていないと、たいへんなことになるんです」 「子どもの発達には生まれてから二歳児ぐらいまでのあいだに、十分に母親のオッパイを飲み、抱きしめられて育つことが絶対に不可欠」 「十分に甘えるということは、全面的に自分を母親にゆだねるということで、それによって人間を愛し、同時に自分も愛されるという原型を獲得することができ、それが人間として一人立ちする大前提」 「本能のままに、もうかわいくて、かわいくて仕方がない、という調子でやらなくちゃいけません」 「たっぷり甘えの時期を通過してはじめて、子どもは、三、四歳で父親性を自分のなかにとりこんでいく。つまり、それまでの甘えっぱなしから欲しいものをがまんしたり、少しずつ自分を律したりすることを身につけていくわけだ」 「この時期に母親がいつまでも甘えっぱなしにしておくと、一人立ちできない怠惰な子どもになってしまう」 「幼稚園に行くころには仲間と大いに遊ばせないといけない。遊びは社会生活の原型であり、子どもは遊ぶことによって、自分を表現すること(創造性)や自発性を身につけていく」 「こうした土台のうえに学校教育の場で、子どもにとっては神さまのような存在である教師と出会うことで、イヤでもやるべきことはやりとげる勤勉性を体得したりしながら、だんだんと一人歩きをはじめていく」 「こういう積み重ねがあってはじめて、この自分こそが自分なんだという自己同一性が生まれ、同時に社会や異性とかかわっていける人間になる」 自己同一化 ・「たとえば、父親からしかられるとこわいと思うのは、それによって父親を自分のなかにとりこんでいることです。父親が少しぐらいカゼ引いていても、会社に出て責任を果たしているとしたら、そういう父の姿を子どもが見ることによって、父親らしくなろうとする――というように、相手を自分のなかにとりこみ、その相手のようになるということです」 「子どもの自己同一化の対象としての “父親の役割” を十分果たしていない家庭が多いことが問題なのだ」 「父親が健在であっても、いないのも同然の家庭の子どもは、思春期になって母親の手中にとりこまれていて、仲間との交流や社会にかかわっていく力が出てこない。その劣等意識が母親への暴力のかたちで噴出するケースが多いのも、父親不在を物語っている」 おとなになるとは? 快楽原理が支配する ・精神病理学の岩井寛・助教授には小・中学生の息子さんがいる。超多忙人間だから家庭で子どもと遊ぶ時間はほとんどない。 ・それでも、先日、小学校の父母会で先生に聞いたら、お宅の息子さんはお父さんをとても尊敬していると言うんです。なんのことかと思ったら、たとえば、おふろでお父さんともぐりっこしたら、お父さんのほうがすごく長くできたなんてことが理由なんです。 ・忙しければ、ごくわずかな時間でいいから、くっきり鮮明な印象を残すような体験をさせてやること。 ・相撲をとって、ときにはオヤジを負かしたというだけでもいい。要は時間の量ではなく質です。 ・中学生の息子さんは、夜、遅くまで原稿を書いている父親を見て、 「まだ寝ないの?」 と寄ってくる。 「ウーン、あした原稿を取りにくるんでね。たとえ一睡もしなくても、書きあげなくちゃならないんだ。男はつらいよ」 と言うひとことでも、相撲では自分に負けた父親が、社会に対してキチンと責任をとっているということをわからせ、父親の存在を確かなものにさせることはできるのではないか。 検札で露見 ・精神医学の福島章東京医科歯科大助教授 「いまの子どもたちの状況は、幼児期における社会性の訓練、社会生活のためのコントロールが欠けてしまっているところから起きていると思うんです」 ・幼児期の第一反抗期というのは、いわば非論理的にヤンチャを言い、ダダをこねる時期。 ・これに対して、思春期の第二反抗期は、いわば論理的な反抗をする時期で、価値観、世界観、イデオロギーなどをめぐって父親的権威、体制に対決する形をとる。 ・第一反抗期に母親が子どもべったりに甘やかして過ごし、世の中にはいろいろなキマリがあり、規範があって、ときにはガマンしなくてはいけないのだ、ということを教えずに育ててしまうと、幼児のような非論理的なダダをこねる状態が思春期の第二反抗期に現われてくる。赤ちゃんのままおとなになってしまうわけだ。 ・「思春期というのはいわばおとなになるための "検札" の時期ですからね。どこまで行けるキップを持っているか、きびしく調べられるわけですよ。そのとき、第一反抗期を卒業していないと、赤ん坊的なものが出てきてしまう。つまり、おとなになれないわけ。これを私たちは "巣立ちの病い" と呼んでいるんですが、第一反抗期をうまく卒業していないと、思春期になってからの親へ理反抗も、それによって親から独立・自立していくきっかけにならないで、悪あがきになってしまう。そうなると、暴力的にエスカレートしてしまうわけです」 ・この場合、父親が不在だった理、異性関係で不安定だったりすると、母子関係の病理がますます拡大してしまう。 快楽原理 ・母親の話すことばや周辺の人のことば、本を読んで……と、ことばをとおして論理的にものを考えるというパターンにかわって、コマーシャルソングや画像から感覚的に情報がはいってくるようになったために、子どもは「カッコいい」「気持ちいい」を価値の基準にする。 ・子どもがおとなに成長するのは、不快なものに耐える力を身につけることだが、その力がひじょうに弱くなっている。 ・フロイト流に言うと、赤ちゃんはオッパイが欲しければすぐ泣くし、すぐ満足がえられないとすごく不幸に感じる――つまり、快楽原理で生きているわけだが、どうやら快楽原理を引きずって、からだばかり大きくなったどもたちがいっぱいいるのかもしれない――。 愛する技術とは? 闘争を教える ・国学院大学の竹内常一教授(教育学) ・夫と妻、親と子、それぞれが自分の情念のウラミツラミを相手によって埋めあわせてもらおうとするばかりで、相手のために生きるという濃密な愛の関係が感じられない家族に、家庭内暴力が起きているように思える。 ・なんといっても父親の問題がいまの社会でひじょうに大きい。 ・父親は戦後、いち早く会社人間として家庭から退場してしまった。 ・逃亡していながら裏から母親を操作している。 ・学歴にいちばん思い入れが強いのも、実際は父親じゃないですか。母親を締めあげているわけです。 ・逃亡した父親よ、前面に出てこい。父親こそ子どもに闘うことを教えるべきだ。 ・闘うこととは、人生何のために生きるのか、ということです。 ・人生を闘うこと、生きていくこと、それを教えきっていない。 ・それに対して母親は人生を愛すること、人生を味わうこと、もっと端的に、人生を楽しむことと言ってもいいですが、そういうことを子どもに教えるのが役目でしょう。それがいまは子どものシリをたたいている。 ・父親が父親の役割を投げてしまい、母親が自分の夢を子どもに託してベッタリ密着して放さない――そういう家庭構造をどう変えていくかだ。 ・親と子がいっしょに暮らしあう機会をつくる――たとえば、キャンプに行って父親がテキパキと飯ごう炊さんでメシをたいて見せるとか、何でもいいが、困難に親子でいっしょにぶつかってみる体験を味わわせること。 ・それから家庭のなかに月一回儀式をつくること。 子育て三つの決め手は? “よい子” にさせるな ・大妻女子大児童学科 平井信義教授 「子どもがおとなしくて、親の言うことをよく聞いて、しかも、勉強がよくできる、そんな “言うことなしのよい子” だったら、こりゃたいへんだと思ったほうがいい」 ・三つのたいせつな心がけ 「その一つは、三歳未満までは身体接触を多くして徹底的に甘えさせなさいということだ」 「三歳未満まではうんと抱いてやったり、いっしょに寝てやることです」 「母親に甘え慕って、分離しようとすると泣き叫ぶ子どもほど情緒が発達・安定している」 「もう一つは、自主性を尊重させよということだ」 「自主性を身につけさせるためには、幼児期に大いにイタズラをし、親に反抗し、友だちと遊びかつケンカするという体験が、ぜひとも必要だ」 「たとえば、イタズラ、これは “自主性にもとづく探索要求” といわれる行動で、自主性を発達させるためにはぜひ通過しなければならない関門だ」 「イタズラを抑圧しないように注意しながら、徐々に生活秩序に適応する能力を身につけさせるようにするのが親の腕の見せどころだ」 「もし抑圧しすぎると、おとなしい子になる。それが称賛されると、子どもはその評価にしたがって行動するから、おとなには扱いやすいが、ついには自主性の発達がとまってしまう」 「イタズラのあとは何かにつけて『自分でやる』と主張して、おとなの保護・干渉にかんしゃくを起こす状態がくる。これを不可能なことへの挑戦と受け取って、 “悪い子 ” 扱いし、抑圧すると、ここでも自主性の発達は足踏みしてしまう。 ・「思春期になると、この自主性が求められる機会が多くなるわけで、幼児期の過ごし方を間違えていると、子どもはそのころになってどうしたらいいかわからなくなって、辛くなると内へ内へと退却してしまう」 「登校拒否や家庭内暴力の子どものお母さんが共通して言うのは、『小さいときはあんなにいい子だったのに……』ということばですが、私は『それだからこそ、こうなったんですよ』と言うんです」 「それに子どもの失敗を許さないお母さんが多い」 「失敗が発達を援けるのに、すぐ母親が手を貸してしまう。子どもをダメにしていることに気づかない」 「三つ目に、子どもにガマンする力、困難を乗り越える力をつけさせてやることの重要性だ。 「食べものを欲しがるままに与えないで、『待つ』ことを覚えさせたり、家事の手伝いをさせたり、家庭のルールをキチンと守らせたり、幼児期の一見ささいな訓練の積み重ねが、将来を決していく」 「少しでも労働させたり、汗を流させたりする、そういう体験をさせるおとなのチエが、子どもをまっとうな人間にしていくんです」 「子育てはお母さんだけでできることじゃありません」 子どもをしかるとは? 親の捨て身が子を変える ・北アルプスの麓、中等少年院・有明高原寮 院長 倉科茂先生 「怒るというのは親の都合・打算でしてね、感情的になってすぐ怒る。これに対して、しかるというのは自己犠牲ですよ」 「おとなが身を捨てて、自分もまっ裸になって酷寒のきびしさをいっしょに耐える。それでなくてなんで子どもが育ちますか」 「もともと子どもは自分で家庭や親を選ぶことができますか。できんでしょう。子どもの人格にゆがみがでたというのは親に問題があるんです」 「親が変わらんことにはどうしようもない」 「なり振りかまわず、自分が裸になって、子どものまえに自分をさらけ出せ、子どもと対決しろ、そう言いたいね」 「そうやって子どもといっしょにこの事態を真剣に受けとめて格闘しなきゃだめですよ」 「自分たち夫婦にいったい何がたりなかったのか、追いつめてごらんなさいよ。子どものためにオヤジもオフクロも一生懸命、自分を犠牲にして闘ってるんだということが子どもにわかれば、子どもは絶対にこたえてくれるものなんだ」 「打算や見栄で、子どもはついてきやしませんよ」 文庫化にあたって ・子どもは大人社会の鏡だ、時代の心模様を浮かび上がらせる探照灯だ。 ―― 完 ―― |