
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年01月11日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
2 |
19/01 |
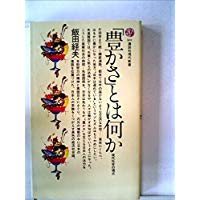 |
「豊かさ」とは何か |
飯田経夫 |
講談社現代文庫 |
◎ |
1―日本人は「ウサギ小屋」に住んでいるか 日本人の “錯覚” ・欧米とはちがって、日本は圧倒的大多数が「中」意識をもつ国である。 ・OECD諸国、つまり西側先進諸国の中で、日本は所得分配がもっとも平等な国だということは、データによってはっきりと確認されている。 ・いろいろな点で、日本は著しく平等主義的な国であり、伝統的にそうであったが、戦後ますますそうである。 3―「ケインズ革命」は何をもたらしたか マルクスかケインズか――脱産業化社会の難問 ・「産業社会」の精巧は、ひとくちでいえば、前例のない豊かさを実現させたし、もう少し具体的にいえば、 (ィ)失業を発生しにくくし、完全雇用を日常茶飯事化させた。、 (ㇿ)かりに失業しても、それがそのまま餓死に直結する悲惨さをなくした。 ・それは驚くべき進歩であり、その功績は主としてケインズに帰せられるだろう。 ケインズは世の中を一変させた ・経済にはつねに労働の移動があり、「摩擦的」な失業があるから、失業率が三・五~四パーセントまで下がれば、ほぼ完全雇用とみなしてもいい。 ・つまり、経済にはつねに、ひとつの仕事を辞めて新しい仕事をさがしている人びとが全体のうち三・五~四パーセントくらいを占めても、別に驚くことはない――というわけである。 選挙民に受ける赤字財政 ・経済全体に占める政府部門のウェイトが高まるとき、その経済は必ず非効率化する。 5―「豊かさ」の維持と「北北問題」 ・経済力だけは巨大だが、食糧すら自給できず、資源・エネルギーも軍備もなく、きわめてアンバランスな日本のばあい、国際社会゛平和で安定していないかぎり、そして、多くの国ぐにから好意と信頼を寄せられないかぎり、すこぶる生きていきにくい。 ・たとえば、国際社会が不安定なときには、ある国との友好・信頼関係は些細なことで傷つきやすく、しかも、いったん開いた傷口は、みるみるうちに広がりやすい。 ・そして、その傷口を修復しようとすると、ただちにそれがよそへとはねかえって、他の国との友好・信頼関係に傷がつきやすい。 ・国民とくに若者たちが、まさに豊かさの結果として、ただ身辺の些事に過大な不平不満を言い立て、より広い世界をみようともしないとき、その豊かさを維持することそれ自体が、おぼつかなくなる危険がある。 ・もちろん、日本のようなアンバランスな国にとって、 ・だが、 6―追いつめられた先進諸国 日本への「南」の高い評価 ・欧米人には中華思想が強く、自分たち以外を “野蛮人” 視する傾向が、いまも残っている。 ・これに対して、日本人は異常なほど中華思想が弱く、自分流のやり方があるいはまちがっていはしないかという弱気(?)を、つねに心の片すみにもっている。 ・非白人国の中では、日本がただひとつ近代化に成功した国だということは、まぎれもない事実である。 ・日露戦争は、非白人国が白人国と戦ってはじめて勝った画期的な戦争で、以後にも旧植民地の独立戦争をのぞいてベトナム戦争しか例がない。 ・これらの事実に対する「南」の国ぐにの評価は、われわれは日本人にとって意外なほど高い。 "例外"としての日本の良さ ・日本は、高品質で低コストの工業製品を大量生産することに、きわめてひいでている。 ・それは、少数の天才だけでできることではなく、上は社長から下はブルーカラーのひとりひとりにいたるまでが、つねに向上意識をもって真面目に仕事することによって、はじめて達成できる成果にほかならない。 ・さらにいえば、それは「ヒラの人たち」を中心とするチームプレーの勝利にほかならないであろう。 ―― 完 ―― |