
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年06月28日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
3 |
19/01 |
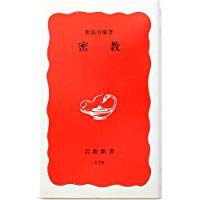 |
密教 |
松長有慶 |
岩波新書 |
◎ |
Ⅰ ヒマラヤを超えて ――密教の歴史的な流れ―― 2 日本密教とチベット密教 日本密教とチベット密教の違い ・密教は現在、生きた宗教としては、日本とチベット周辺地域にだけ残っている。 ・いずれも源はインドに発するが、現在の宗教形態は外形的にはすっかりちがっているようにみえる。 5 中国・西域地方の密教 密教僧の活躍 ・ ・恵果は師の不空の後をつぎ、朝廷に重用せられ、密教の宣布をはかったが、その学徳を慕って中国全土からだけではなく、アジア各地から多くのすぐれた弟子がその門を叩いた。 ・その最晩年の弟子の一人が、日本から留学してきた空海である。 ・恵果の伝記からみると、インドではほとんど別個に展開した『大日経』と『金剛頂経』の両系統の密教を一系列に統合した、新しい密教の思想体系を樹立しようとする意図をもっていたようである。 ・両系統の密教を一元化する思想はそのまま空海に継承され、日本において、真言密教の教学の基本となる。 ・恵果の没後、九世紀初頭、『蘇悉地経』の地位が向上し、『大日経』と『金剛頂経』と並んで三部の大教と称せられるようになった。 ・この三部を尊重する教学の姿勢は、空海ののち入唐した円仁、円珍など天台の学匠が学んで帰り、天台密教の骨格をなす考えかたに展開した。 7 日本の密教 民族宗教の神とともに ・仏教が公式に朝鮮半島から日本に渡来したのは、六世紀の初めのことであった。 ・日本における仏教の受容の決め手となったのは、仏教の仏たちが、在来の民俗信仰の神がみに対して、より呪術的な効力をもつという点が、仏教採否の基準とされたのである。 ・もともと大乗仏教がもっている呪術的な機能が、シャーマニスティックな民族宗教の基盤の中で期待され、歓迎された。 ・密教を受け入れる素地は、早くから日本でもでき上がっていたのである。 ・奈良時代すでに、呪術的な能力を民衆から高く評価されながら、国家からは公認されていない山林修行者が数多くいた。 空海と最澄 ・平安の初期、九世紀の初頭、空海は唐の都であった長安に留学し、インド以来の正系の密教を伝えている恵果につき、『大日経』系と『金剛頂経』系の密教をともに授けられて帰国した。 ・それは前の時代までの呪術的な雰囲気の濃厚な密教に対して、大乗仏教の思想によって裏づけられた理論体系と、それに基とづく実践法をそなえたところに特色が認められる。 ・かれは京都の南に位置する東寺を中心に、律令国家体制に沿いつつ、密教を日本に定着させた。 ・一方、深山の高野山に ・空海は、国家と民衆のために活躍する中国密教の方向と、社会を離れ、大自然の中にみずからを融合しようとするインド密教の目ざすもの、この相反する二つの路線を、一人の人格の中で統合した新しい型の密教を作りあげるべく生涯をかけた。 ・一方、空海とともに中国に渡り、天台山を中心に、天台教学、戒律、禅、密教をあわせ学んで帰った最澄は、比叡山によって天台宗を開創し、日本天台の基礎を築いた。 ・最澄の弟子の円仁と、また後に延暦寺の座主となった円珍らは中国に留学し、とくに密教を学んで帰って、天台教学の中に、密教を重視する姿勢を鮮明に打ち出した。 ・真言宗で学ばれる密教を、空海が本拠地とした東寺の名にちなみ、東密という。 ・それに対して、天台の密教を、天台の台を取って台密と呼びならわすことになっている。 異教の神の仏教化 ・日本における神仏の習合は、奈良時代に始まるといわれるが、仏教と日本の民族宗教との融合が、目にみえる形で進みはじめたのは、真言、天台の両派においてである。 ・仏法を弘めるため、土着神の擁護を期待する姿勢がさらに展開して、在来神は仮の姿で、その本性は仏、菩薩であるとする本地垂迹説が生み出された。 ・鎌倉時代には、真言宗の両部神道とか、天台系の山王神道などの理論体系が構築されるのである。 ・吉野、大峯、熊野など在来の山岳信仰をまた密教の中に習合させて、金峯山を金剛界に、熊のを胎蔵界に配する両部曼荼羅説もでき上がった。 ・また伊勢の内外両宮を金胎両部に当てる信仰は、鎌倉末期に神道の側からおこってきた。 ・明治維新に際して、神仏分離が行われたことは、それまで神道と習合して教線を保ってきた密教関係の教団に、いずれも手痛い打撃を与えた。 ・日本において、密教は空海以後、さしたる思想的な展開が認められないけれども、その総合的、象徴的な性格と、現実を肯定する積極的な姿勢などによって、民衆の精神生活には深いかわりをもち続けて、今日にいたっている。 Ⅱ 人間と宇宙 ――密教の思想―― 2 神、仏、そして人間 即身成仏 ・密教では、われわれが父母から受けたこの現実の身体をもって、目覚めた者になることを目標としている。このことを即身成仏という。 ・即身成仏という言葉をもって、人間存在の中に絶対を見つける原理を説いたのは、日本における空海が最初である。 ・日本では中世以降、霊魂の遊離した身体がミイラとして残ることを即身成仏といいならわしている。 ・この即身成仏の信仰がそのままもちこまれて、即身成仏とは、生きた姿をしたままミイラになることだと誤解されていることも少なくない。 ・即身成仏とは、特定の修業を積んだ行者だけがなるものではなく、われわれ一人ひとりが、それぞれの宗教的な自覚と、正しい実践によって、この現実の身体のままに、真実に目ざめた者となることをいう。 7 二つは一つ 二元の一元化 ・現実世界には、さまざまな対立がある。個人、社会、民族、国家など大小の相違があっても、つねになんらかの対立問題を抱え、ときには紛争に発展することも少なくない。 ・また形を伴った対立だけではなく、哲学とか宗教の場合、概念的に捉えられた対立関係も数多く存在する。 ・デカルト以来、西洋の近代思想の主流となった二元論的な思考方法が、さらにその勢いを加速した。 ・哲学とか宗教の分野からみると、神と人間、聖と俗、マクロとミクロ、理想と現実、主体と客体など数多くの対立した図式が考えられる。 ・キリスト教など一神教では、これらの対立概念の間には明確な一線が引かれる。 ・それに対してインド、中国、チベット、日本などに興り、展開した宗教とか哲学の多くは、これら対立項を一元的に捉えるのが一般的である。 ・大乗仏教では、 ・もちろんこれらの対立は、本質としては一であることを説明するために取り上げられたものである。 ・これらは常識的にみて、別個の概念であり、互いに対立している。 ・ふつうわれわれはこれらを二元的に理解して、日常の生活を支障なく続けている。 ・自分と他人はもともと別の人格であるし、また神や仏の住む悟りの世界は浄らかで、この汚濁に満ちた現実の世界とはまったくかけ離れているように思う。 ・たとえば、苦しみの対は楽しみである。人はだれでも苦を避け、楽を求めようとする。苦と楽とは反対の概念であるかにみえる。ところが過去に苦しんだことが、現在、むしろ楽しみに思えることもある。反対に現在の楽が将来、苦になることもないわけではない。 ・また迷いや悩みが深ければ深いほど、悟りに至ることが早いこともある。迷い悩んだ経験をもたない人が、かえって悟りに近づけないというのも、案外真実であるかもしれない。 ・一見して正反対にみえることも、もともと一つであって、それぞれ片面だけしか視点をもたないために、逆にみえていることも少なくない。 ・相対立する考えかたはもともと同じものの違った面だということに、なんらかの機会に気づくこともある。 ・仏教ではこの二元の一元化の関係を、 ・自我意識に捉われ、自己を中心に世界を見るとき、そこに対立する意識が鮮明となり、ものごとを二元的に把握することになる。 ・仏教はこの自我意識を否定し、無我を説く。 ・自我を中心に展開する世界には、対立する他者が存在するが、自我意識をなくすれば、対立はもはや存在しない。 ・自分も他人も、動物も植物も本来一体のものとして捉えるところに、仏教が説く慈悲の精神の原点が見出される。 ・仏教では自と他の対立関係を、能と所という術語をもってあらわしてきた。主体と客体である。 智と理 ・密教ではその関係を「智」と「理」という独特の言葉であらわす。 ・空海は師の恵果の思想を継承し仏教の主客に対する伝統的な用語である能と所より、智と理の語を用いて、両者の一元的な関係を示す。 ・空海の場合、さらにこの関係をおしすすめて、胎蔵の大日を「理法身」、金剛界の大日を「智法身」にあて、仏身観にまでそれを応用している。 ・後世、日本の真言教学では、宇宙を多元的に捉える多法界を胎蔵に、それを一元的に理解する一法界を金剛界にあてはめる思想も表明されることになった。 ・だが多か一かという対立関係で捉える立場に固定してしまうと、空海の目ざした本来の意義を失ってしまう。 ・智と理、一と多の関係を、空海は説明している。 「一も如であり、多も如である。また理も無数で、智も無辺である」 と、人間の認識作用の規準は、あくまでも相対的で、それだけにたよっては、時間と空間を超越した真実の世界を見透すことができないことを明かす。 ・物と心、主と客など対立概念は、無量、無辺の真実の世界では一つであるという。 ・ここにおいては、理と智、物と心、主と客、一と多といった一切の対立する概念は根底から崩れ去る。 Ⅲ 自己の発見 ――密教の実践―― 3 宇宙を凝縮する 三密の行 ・密教の行の基本的な形は、 ・行者の手に「 ・真言宗のお寺の本堂で護摩をたいたりすることもあろう。このようなとき、行者が両手をもって、さまざまな形をつくる。これが印契である。又それを簡略化して、単に印ともいう。 ・行者が口で唱える呪文は、真言とか陀羅尼といわれ、行者が精神集中することを、三魔地といっている。それはサンスクリット語の音訳であって、 ・この言葉は、読書三昧とか道楽三昧というように、なにか一つのことに熱中して、他のことを一切忘れてしまうことを指す日本語としても日常用いられている。 ・古代インドではもともと人間の行動を大きく分けて、身体的な働き、言語的な働き、精神的な働きの三種とした。 ・これらを ・密教では、この三業を三密という。 6 日本とチベット 密教の観法 日本とチベットの比較 ・現在、密教が生きた宗教として信仰され、伝統を持った観法が伝承されているのは、日本とチベット文化圏とである。 Ⅳ 感覚で捉える ――密教のシンボリズム―― 1 混沌と秩序 宇宙の投影―曼荼羅の登場 ・七世紀ころになると、仏教徒はそれぞれの抱く宇宙観の中に、数多くの神がみと大乗の菩薩たちを含め、それらを一つのパンテオンとして視覚化していくのである。それが曼荼羅である。 ・曼荼羅はそれ自体、仏教徒の抱く世界観を具体的な姿として ・最初に作りあげられた曼荼羅は、七世紀ころにできた胎蔵曼荼羅であるといってよい。 ・それは従来、大乗仏教で信仰されていた仏、菩薩をほとんど包摂するとともに、異教の神がみから変身した忿怒の明王や諸天、さらに星宿や鬼神にいたるまでを十三のセクションに配分したものである。 ・それは仏教コスモスの最初の壮大な具像化と、受け取るべきであろう。 ・曼荼羅は、聖なる世界の視覚化というだけにとどまらない。その中に、鬼神や精霊をも含めた現実の俗なる世界が二重映しに投影されている。 ・この意味で、それは聖俗一体の世界像の縮図ということができる。カオスと共存する仏教的なコスモスの構図が形をとって、胎蔵曼荼羅の中には提示されている。 ・一方、金剛界曼荼羅は、胎蔵曼荼羅の中で包摂され、体系化された仏、菩薩、明王などを三十七尊に整理し、さらにそれらを大日如来わ中心に配置した四仏の系列に統合する。 ・金剛界曼荼羅では、カオス的な要素は周辺部に追われ、中心部は研ぎすまされた整然たるコスモスの世界を現出している。 3 曼荼羅の構造 曼荼羅とは何か ・曼荼羅というのは、サンスクリット語の「マンダラ」の音写である。 ・辞書には円とか輪とか境界線あるいは集合体といった訳語が出てくる。 ・このマンダラとよく似た言葉に「マンダ」というのがある。 ・これはその前に「ボーディ」という言葉を加えて、「ボーディマンダ」、すなわち菩提道場という言葉でよく知られている。 ・マンダという言葉は、もともと本質とか飾りという意味をもつ。本質という意味から、「醍醐」という漢訳もできた。 ・醍醐とは牛乳を煮つめて最後にできる精髄で、とてもおいしいものとされる。日本語の醍醐味もここからきている。 ・曼荼羅とは、檀、集合体、道場、本質を備えたもの、円い形をしたものなどの意味をもつと理解してよいであろう。 曼荼羅の歴史 ・七世紀になると大日如来を中心に、四仏、四菩薩を配し、その周辺にグループ分けされた仏、菩薩、明王、諸天を並べた形のととのった曼荼羅が一挙に完成することになった。 ・日本密教では有名であるが、チベット仏教では、それほどの隆盛をみなかった胎蔵曼荼羅の出現がそれである。 4 胎蔵曼荼羅 両部の曼荼羅 ・日本において古くから知られている曼荼羅といえば、胎蔵と金剛界、この2種類で、これを両部の曼荼羅という。 ・日本の真言宗の寺院では、この両部曼荼羅を一対にして、本堂の両側に掲げてある。 ・空海が両部の曼荼羅とともに、その伝統を中国から持ち帰り、日本ではそれが一般化した。 ・真言宗の伝統的な教学では、胎蔵を理に、金剛界を智に配当する。 ・もともと理と智の考えかたは空海に発したものであるが、理とは客体的なもの、智とは主体的なものをさす。 ・空海の宇宙観としては、本来、主体と客体は同体であって、理と智は不可分であるとみる。 7 対象になりきる 密教芸術の神髄 ・密教の彫刻や絵画、さらには曼荼羅などは作者と一体化した存在であるから、これらを美術作品として鑑賞するということは意味をもたない。 ・美術館でそれらを対象化し、鑑賞しても、それらがわれわれに対してなにも語りかけてこないのも当然のことである。 ・密教の仏像や絵画は、本来あるべき場所において、人間の全身を投げ出して、対象に没入し、真実の世界に入り、宇宙生命に触れることによって、はじめて全体性をもって理解することができる。 ・頭だけで、それらを分かろうとするのが、もともと無理なのである。 Ⅴ 個から全体へ ――密教の社会性―― 1 俗と非俗 非俗の世界に生きる ・仏教に対しては、徹底した非俗の世界での修練とともに、世俗世界での民衆の救済という異なった両面をもつことが社会的に要請されている。 ・在家信者を中心として興った大乗仏教では、このような問題を避けて通ることができなかった。 空海の中の俗と非俗 ・密教はもともと一個の人間が、宇宙を相手に瞑想し、ミクロとマクロの一体化をはかる観法が基本となる。 ・そのためには、人里離れた広野とか山林で修業しなければならない。 ・非俗の世界においてこそ、神秘主義的な宗教としての密教の真価が発揮される。 ・空海に対しては、日本仏教の高僧の中では例をみない ・弘法大師は死せず、生きて高野の山から、民衆の救済にあたるという信仰が、民衆の間に千年を越えて持ち続けられ、現在に至っている。 ・生涯をかけて苦しみ悩む人びとのために社会活動をなした空海が、山に籠り、大宇宙を相手に対話を続けることに人びとは満足しない。 ・民衆とともにあって、いつでも自分たちのために働いてほしいという願いが、弘法大師に対する特異な入定信仰となって、人びとの間に語り伝えられてきたといってよいであろう。 2 欲望の肯定 欲望と人間 ・密教が現実を仮のものとは見ず、現世にこそ心理が宿ると考えて、現実を重視する姿勢をもつ。 ・また同時に、密教は人間の欲望に対して、全面的な否認をもって臨まない。 ・欲望をいちがいに悪ときめつけて除去しようとはせずに、むしろ欲望を積極的に活用しようとする。 ・社会活動の原動力は、大きな意味において、人間的な欲望のもつエネルギーであるといってもよい。 ・ただ欲望をそのまま安易に認めてしまっては、人間の本能をそのまま容認する危険性を多分にもつことになる。 ・密教における欲望肯定論の本当の意味を知っておく必要があろう。 ・動物にも植物にもおのずから備わっている生命力の根源は、大宇宙そのものの生命力だといってよい。 ・この宇宙の生命力がわれわれの日常生活の中ではいろいろな欲望となってあらわれる。 ・病気を治したいとか、長生きしたいとか、金持ちになりたいとか、名誉や地位を得たいとか、欲望を持つという点では、人さまざまである。 ・だが一方、このような欲望がなくなったとき、普通の人であれば、きっと生きていく意欲も失ってしまうことにもなりかねない。 ・欲望というものは、人間が生きていく根底となるエネルギーだといってよいであろう。 ・しかしながら欲望には際限がないことも事実である。 ・太平洋戦争に敗れたのち、われれは衣食住それぞれの面で、きびしい窮乏の生活を経験した。 ・しかし戦後、十年たち、二十年たち、われわれの生活は飛躍的に向上した。 ・欲望がつぎつぎにかなえられていき、四十年余りたったいま、物は街にあふれ、惜しげもなく使い捨てられていく。 ・ところがわれわれは、あの耐乏生活と比べて、はたしてしあわせになったかというと、かならずしもそうとばかりはいえないであろう。 ・また十数年前までは、物を消費すればするほど経済は発展し、みんなが豊かになるといわれていたのに、いまでは物の消費が地球の環境を汚染し、人びとの明日の生活をおびやかそうとしている。 ・欲望のおもむくままに、手あたり次第にかなえていっても、それがかならずしも欲望の充足にはつながらず、かえって人びとを苦しめる原因にもなっていることに、いまわれわれは気づいたのである。 4 衆生救済を戒とする 十善と四恩 ・四恩は般若訳の『 ・空海は中国に留学中に、般若から四恩について教えられ、その考えを日本に持ち帰った。 ・四恩とは、父母、国王、衆生、三宝(仏・法・僧)それぞれの恩をいう。 ・我々が生きているのは、自分の力だけではない。世界中の生きとし生けるものすべての存在と、その働きによって、われわれは生かされている。 ・恩という言葉は、恩にきるとか恩を返すとかいうように、ある種の貸借関係がそこに予想されることが多い。 ・しかしよく考えてみると、それは個が全体とのかかわりの中で生きていることを自覚させるに、最も適切な言葉であるとも理解せられるのである。 5 すべてのものに生命が宿る 水に宿る生命 ・密教は水だけではなく、大地も、太陽も、風も、大空も、いずれもわれわれと同じく生命を持ち、互いに密接な関連を保ちながら地球上の動植物を生かし、またそれらによって生かされている。 ・地球の汚染が急速度で進展する中にあって、このような密教の万物共生の世界観が、現代社会において、改めて見直される日が一日も早く訪れることを期待したい。 あとがき ・密教は無限を相手にする宗教であり、哲学でもある。 ・時間と空間を超越したひろがりと、有限の人間、それらがどのようにかかわり合うのか、それを体験の中で教えてくれるのが密教だといってよい。 ―― 完 ―― |