
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年07月21日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
21 |
19/05 |
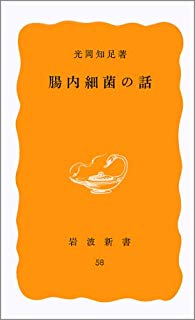 |
腸内細菌の話 |
光岡知足 |
岩波新書 |
◎ |
Ⅱ 腸内細菌を培養する 腸内容の顕微鏡観察 ・細菌は一ミクロン(一〇〇〇分の一ミリメートル)前後の微小な生物です。 ・健康な成人の糞便をとってしらべてみますと、糞便一グラム当り三〇〇〇―五〇〇〇億個の細菌を数えることができます。 ・この数は糞便の三分の一から四分の一くらいが細菌で占められていることになります。つまり糞便の大部分は細菌だということになります。 Ⅲ 腸内細菌を分類する 乳酸菌と腐敗菌 ・タンパク質を分解し、アンモニア、硫化水素、アミン、インドール、フェノール、メルカプタンなど悪臭のある物質をつくる細菌が腐敗菌です。 ・多くの嫌気性菌や、大腸菌、緑膿菌、プロテウス、ブドウ球菌、一部のバチルスや腸球菌、赤痢菌、サルモネラ、コレラ菌、腸炎ビブリオ菌など、下痢・腸炎の原因となる細菌や毒素生成菌はすべてこれに属します。 Ⅳ 腸内細菌の生態 1 消化管のしくみとはたらき 消化管と付属器官 ・消化管は口から肛門までの曲がりくねった長い管で、その長さは成人で約九メートルもあります。 ・小腸は腹腔内をうねりくねって約六メートルもあり、上から順に十二指腸、空腸、回腸に区別されます。 ・膵臓は胃のうしろにあって、消化液である膵液を分泌する外分泌部と、インシュリン、グルカゴンなどのホルモンを分泌する内分泌部とからなっていて、膵液は導管によって十二指腸に開口しています。 ・肝臓は成人で一キログラム以上もある、体の中で一番大きな臓器です。 ・腸で吸収されたブドウ糖はグリコーゲンにつくりかえられて肝臓や筋肉に貯えられ、アミノ酸はヒト固有な形のタンパク質につくりかえられますし、各種のビタミンが貯えられます。 ・また、口からはいってくる食物や薬物の中の有害な物質や、腸内で細菌によってつくられた毒性をもった物質はここで無害な形に処理されます。これが肝臓の解毒作用です。 ・さらに、肝臓では消化液として重要な胆汁がつくられます。 消化と吸収 ・ヒトの一日の胃液の分泌量は二―三リットルで、塩酸、ペプシン、粘液を含んでいます。 2 腸内菌叢の構成 母乳栄養と人工栄養 ・母乳で育てられている乳児(母乳栄養児)は、ミルクで育てられている乳児(人工栄養児)より消化不良症、赤痢、かぜなどにかかりにくく、かかったとしても死亡率がずっと低い。 ・一つは母乳に含まれる感染防御物質であり、もう一つは、母乳栄養児と人工栄養児の腸内菌叢の差によるとされています。 4 腸内菌叢を変動させる要因 宿主の生理 ・私たち人間の生活でも、いろいろなストレスが間接的には腸内菌叢にも影響し、その結果、からだをますます具合の悪い状態にしていることが考えられます。 ・肝硬変、慢性腎炎、ガンなどの患者、便秘症、かぜ、ワクチン接種、放射線治療でも腸内菌叢の異常になることが報告され、そのほとんどが、ビフィズス菌の減少と大腸菌、腸球菌、ブドウ球菌、あるいはウェルシュ菌の増加する傾向で、からだにとってはまことに都合の悪い変わりかたなのです。 抗生物質 ・病気のときに抗生物質を投与すると腸内菌叢の攪乱が起こります。 ・抗生物質投与によって正常腸内菌叢の一部が減少するため、外来菌に対する障壁が除かれ、腸炎菌による腸管感染が容易になる。 ・腸内菌叢の乱れが、感染に対する抵抗性を弱める。 ・抗生物質による治療でしばしば遭遇する菌交代症。通常は病原性の低いと考えられる細菌、とくにブドウ球菌、緑膿菌、プロテウスや酵母、カビが、からだのいろいろなところで増殖し発熱、嘔吐、腹痛、下痢、ビタミン欠乏をひきおこします。 ・これは、抗生物質投与によって腸内常在菌叢の破綻をきたした結果の出来事です。 ・健康なからだでは、潜在的に病原性をもっているだけで、ほとんど力をもっていない細菌が、何らかの原因でいったん腸内菌叢のバランスが崩れ、からだの防御力が弱ってしまったとき病気性を発揮するようになるのです。 Ⅴ 腸内細菌とからだ 一つの仮説 ・一人のヒトが腸内にもっている細菌の種類は一〇〇種近くにもおよび、その数は一〇〇兆以上もあって、毎日食餌成分やからだから腸内に分泌または排泄されたものを栄養として繁殖し、とくに小腸下部から大腸にかけては多種多様の物質がつくられています。 ・腸内細菌には、潜在的に病原性をもったものもいて、からだの抵抗力が減退したとき病原性を発揮し、いろいろな臓器に入りこんで感染症をおこしたり、胃腸炎をおこします。 ・しかしもっと重要なことは、腸内細菌のなかには腐敗産物、毒素、発ガン物質など宿主に有害な物質をつくるものもいて、ただちに宿主をたおすような強い影響は与えないにしても、人間の一生のうちにはガン、肝臓病、動脈硬化、免疫力の減退などいわば老化の原因となっているという考えです。 2 腸内細菌と免疫 免疫のしくみ ・免疫はわたくしたちのからだを細菌やウイルスの感染から護るための重要なはたらきです。 ・このはたらきは、からだのあらゆるところにあるリンパ組織が分担し、リンパ球、プラズマ細胞、マクロアァージという三種類の細胞が主役を演じています。 ・免疫反応は、自己と非自己を識別し、外から入ってくるからだにとって有害な異物を、その化学構造に応じた特異的な抗体をつくりだして応える反応(免疫応答)です。 ・そのしくみは、免疫学的な刺激をうけいれる受容体と、特異的な抗体をつくる反応系に分けられ、抗体をつくる刺激となる物質を抗原と呼んでいます。 腸内細菌による免疫刺激 ・生まれたばかりの動物の腸内に細菌がすみつきますと、からだのいろいろな防御因子を刺激し、粘膜上の局所抗原作用、腸壁の厚化、細網内皮系の刺激、免疫グロブリンの産生、プロパージン‐補体量などが増加し、血液の殺菌力が増します。 ・腸内細菌による抗原刺激によって、からだの中に自分の腸内にいる細菌に対する抗体が検出されるようになります。 ・ヒトや動物では老化に伴ってガンが高率に認められるようになりますが、これは老化するにつれて胸腺でつくられるリンパ球産生能が低下することと関連しているのだという説があります。 外来菌の増殖阻止 ・安定した腸内常在菌が腸粘膜上皮にすみついていることが、各種の病原菌の腸管感染から宿主をまもっています。 3 腸内細菌の代謝と病気 寿命と老化 ・ヒトは生まれてまもなく、腸内に一兆を超す細菌をすまわせることになります。 ・母乳栄養のときにはビフィズス菌最優勢、大腸菌、腸球菌などは劣性の乳酸菌優位の菌叢で、腐敗は全くみられません。 ・しかしながら、牛乳や粉乳をのむ人工栄養や混合栄養では、ビフィズス菌とともに、大腸菌や嫌気性菌など腐敗菌が出現しています。 ・離乳してからは、嫌気性腐敗菌の数が急に増加し、それから一年にわたって腸内では、口から入る食物や薬物、からだからの分泌物が腸内細菌によってたえずいろいろと変換されます。 ・その中には、有害物質もあって、とくに小腸下部から大腸では大量に生成されます。 ・これらの物質の一部は吸収され、長い間には宿主に負担となり、発ガン、老化をはじめいろいろな障害を与えることになります。 ・人間が年をとれば腸内菌叢のパターンはさらに有害菌優勢型に代わり、腸内で産生される有害物質の量はますます増えて、老化を早めることになります。 ・ヒトの病気の原因として環境要因が重要であることを考えると、毎日わたくしたちの腸内でつくられているこの有害物質の意味はひじょうに大きいといわざるをえません。 チクロ ・薬の効果や毒性の発現に、腸内細菌の代謝が重要な役割を果たしている。 日和見感染 ・健康なときは何の病気もおこさない細菌が、ガンの末期や、からだ全体の栄養状態が低下しているような患者の臓器で腫瘍をつくったり創部の感染の原因となることがあのます。これを日和見感染と呼んでいます。 ・そのような原因菌の多くが、腸内で普通にみられる大腸菌、ブドウ球菌、緑膿菌、腸球菌……などで、腸内細菌のなかでも弱い病原性のある細菌です。 ・この感染は、抗生物質の使用によって腸内菌叢のバランスが崩れ、薬剤耐性菌が増殖して菌交代現象をおこしているときとか、ステロイドホルモン、免疫抑制剤、放射線療法などによって、からだの感染防御力が低下したりしたときに起こりやすいのです。 ・また、大きな外科手術、白血病、ガンの末期、重症の糖尿病、動脈硬化などに伴ってもおきます。 5 長寿と腸内細菌 長寿村の食生活 ・いずれの地方の長寿者も、空気のきれいな、気候の温和な土地に住み、早寝早起きをし、適度に働き、ストレスがないということです。 不消化物の効用 ・消化しない食物の大腸ガンや動脈硬化に対する予防効果やその因果関係 ◉その一つは、消化しにくい繊維を食物に加えた場合、これによって腸内で腸内細菌によってつくられた発ガン物質などの有害物質の濃度がうすめられて、腸粘膜に対する作用が弱められ、しかも早く早く排泄されることです。 ◉また、不消化物が大腸に入ってきますと、腸内細菌がこれを利用してかなり分解し、酪酸、乳酸などの有機酸とメタンガス、炭酸ガス、水素ガスを生成し、この有機酸が腸管を刺激して腸蠕動をうながしますから、腸内にたまった有害物質を早く排泄することになります。 ◉さらに繊維には血中コレステロールを下げる効果や、毒物を与えたとき、その作用を緩和するはたらきがあることが確かめられています。 ―― 完 ―― |