
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年07月08日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
23 |
19/06 |
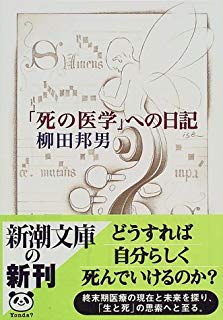 |
「死の医学」への日記 |
柳田邦男 |
新潮文庫 |
◎ |
Ⅲ・医学の再生 痛みからの解放へ ・モルヒネというと、最後の最後になって注射で使うものであり、それを使うと麻薬特有の習慣性の副作用が出るとか、二、三日で命がなくなるといわれてきたが、それは誤った先入観で、少量ずつを飲み薬にして、「時間間隔を一定にした規則正しい、継続的な投与法」にそって飲ませれば、命を縮めることもなく、効果的に痛みをなくすことができる。 サイコオンコロジー事始め ・ガンを自分のものとして共に生きていくイメージを抱くように。 Ⅳ・知性の力 友人の苦悩 ・「人は生きてきたように死ぬ」 知性の力 ・NHK解説委員だった ・この力の源泉は、まさに知性ではなかったろうか。 ・フランクフルが『夜と霧』で指摘していたこと ナチス・ドイツがユダヤ人強制収容所において、精神的に高い生活をしてきた感じやすい人間は、繊細な性質にもかかわらず、精神の自由と内面の豊かさゆえに、しばしば頑丈な身体の人間よりも、よりよく耐え抜いたという事実だ。 Ⅶ・緩和ケアが拓く生 ・「目標に向かって生きること」 他人の痛みは何年でも ・人生は、なんにもしないで、目的がないのはよくない。なにか目的に向かって励み、自分の考えをまとめないと、頭にガタがくる。 Ⅸ・転換期の真只中で 尊厳死の文脈 ・東海大学医学部付属病院で起きた「安楽死」事件(一九九一年)を審理してきた横浜地方裁判所は、いわゆる尊厳死のための「治療行為の中止」と「安楽死(積極的安楽死)」について、それぞれの要件を明確に示した。 ・無駄な延命措置をやめて尊厳ある死を迎えられるようにするための第一段階としての、「治療行為の中止」の要件 (1)患者が治癒不可能な病気に冒され、回復の見込みもなく死が避けられない末期状態にあること。 (2)治療行為の中止を求める患者の事前の意思表示が存在し、治療の中止を行なう時点でもなお存在すること。患者の意思表示が不明確なときは、家族による推定でもよい。ただし、その場合の家族は、 ①患者の性格、価値観、人生観などについて十分に知っていて、その意思を適確に推定しうる立場にあることと、 ②患者の病状、治療内容、予後などについて十分な情報と正確な認識を持っていること、 が必要である。 ・また、中止の対象となる治療行為(延命措置)とは、薬物投与、化学療法、人工透析、人工呼吸器、輸血、栄養・水分補給などのすべてにわたる。 ・積極的安楽死が認められる要件 (1)患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること。精神的苦痛は含まれない。 (2)患者は死が避けられず、その死期が迫っていること。 (3)患者の肉体的苦痛を除去・緩和するための方法を尽くし、他に代替手段がないこと。 (4)生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること(患者本人の明確な意志表示に限定され、家族による推定だけでは認められない。モルヒネ投与などによって結果的に死期がはやまる間接的安楽死の場合は、家族による推定でも認められる)。 ・判決は、たんに治療中止や安楽死の条件を示しただけでなく、そうした決断や行為の前提として、医療界の新しい考え方であり課題でもある「患者の自己決定権」や「リビング・ウィル(生前の意思表示)」、病名告知を含む「インフォームド・コンセント(十分な説明にもとづく納得・同意・選択)」「チーム医療」などの重要性を真正面から論じたという点でも、画期的なものだった。 ・尊厳死・安楽死にかかわる医療態勢はどうあるべきか。病院における医療態勢で重要なのは、「チーム医療」による取り組みを確立することと、「病院倫理委員会」が治療停止などの決定に際して十分に機能することです。 ・ここでいう病院倫理委員会とは、各大学病院などに設けられるようになった倫理委員会とは本質的に違っています。 ・倫理委員会は、議長を看護婦が務め、委員には様々な専門家を網羅しているだけでなく、闘病体験を持つ患者、家族も加えられています。 ・日本においては尊厳死や安楽死の問題を論じるとき、あまりにも最後の追いつめられた段階になってからの「死なせ方」とか「違法にならない方法の線引き」といったニュアンスでの議論や受けとめ方が中心になっているようにみえる。 ・大事なことは、そういう段階に達するまでのプロセス、すなわち医療者と患者・家族間の深い話し合いと理解と納得、さらに医療スタッフのチーム又はグループによる倫理的側面の徹底的な検討を積み重ねるなかから、個別のケースの結論をあぶり出してくる取り組みが求められているのだということです。 ・オランダの安楽死是認の行き方 (1)ホームドクターが患者に対する長年にわたる診療のなかで、その生活と人生と死生観のすべてを理解したうえで、可能な限り生きる道を探し、助言していること。 (2)安楽死の最終判断をするときには、必ず第三の医師による面接・診断・助言・説得が行われていること。 ・横浜地裁判決で述べている点 「(医師は)患者及び家族との接触や意思疎通によって、患者自身の病気や治療方針に関する考え方や態度、患者と家族の関係の程度、密接さなどについて必要な情報を収集し、患者及び家族をよく認識し理解する適確な立場にあることが必要である」 ―― 完 ―― |