
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年07月10日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
25 |
19/06 |
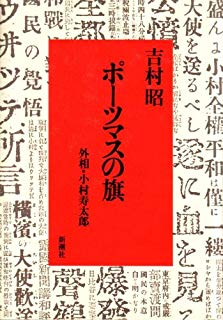 |
ポーツマスの旗 |
吉村 昭 |
新潮文庫 |
◎ |
・日露戦争開始直前、戦争回避のためロシア政府と執拗な交渉がつづけられていたが、日本の暗号表はすでにロシア政府の手に落ちていて、直接ロシア政府との交渉にあたっていた駐露公使栗野慎一郎と小村外相との間にしきりに交されていた機密電が、すべてロシア側に解読されていたのであ。 ・小村は、長い外交生活で、日本の外交の歴史の浅さを身にしみて感じていた。 ・幕末に試練に立たされた日本の外交政策は、鎖国政策を唯一の盾に徹底した受身の姿勢に終始したのであった。 ・それは、欧米列強の植民地拡大政策の激烈さに逆に救われて、各国間に牽制し合う空気を醸成させ、それらの国からの侵蝕をまぬがれる結果を生んだ。 ・受身の外交は維新後もそのまま引きつがれていたが、欧米との交流が増すにつれて攻めの外交も身につけねばならぬという動きが、一種のあせりをともなって顕著になり、実行されるようにもなっていた。 ・小村は、欧米殊にヨーロッパ各国の外交に長い歴史の重みを感じていた。 ・国境を接するそれらの国々では、常に外交は戦争と表裏一体の関係にある。 ・外交が戦争の回避に功を奏したこともあれば、逆に多くの人々に血を流させたことも数知れない。 ・そのようなことをくりかえしている間に、外交は、攻めと守りの術を巧妙に駆使し、自国の利益を守るため他国との間でむすばれた約束事を一方的に破棄することすらある。 ・そうした多様な欧米列強の外交政策に対して、日本の外交姿勢はどのようなものであるべきかを小村は常に考えつづけてきた。 ・結論は、一つしかなかった。歴史の浅い日本の外交は、誠実さを基本方針として貫くことだ、と思っていた。 ・列強の外交関係者からは愚直と蔑笑されても、それを唯一の武器とする以外に対抗できる手段はなさそうだった。 ・人々は、連戦連勝の結果として講和会議に多くの期待を寄せた。 ・講和条件の要求があまりにも小さすぎることに失望し、さらにその条件すらも大譲歩を余儀なくされたことに憤りを爆発させたのだ。 ・人々がそのような感情をいだいたのは、政府が戦争の実情をかたく秘していたことに原因のすべてがあった。 ・海軍は完全に制海権を支配していたが、陸軍は大増強されたロシア軍と戦闘をつづければ勝利の確立が少なく、またそれによる軍費の膨張で日本の財政が崩壊せざるを得ないことを知らせることはしなかった。 ・その理由は、ただ一つであった。もしも、憂うべき実情を公表すれば、ロシアの主戦派は勢いを強め、講和会議に応ずるはずがない。 ・たとえ講和会議が開催されたとしても、ロシア側は日本の要求を拒否し、逆に不当な提案を押しつけてくるにちがいなかった。 ・そうした内情を知らぬ国民は、講和会議を締結した小村全権とそれを支持した元老、閣僚に怒りをいだいたのだ。 ・新聞各紙は、九月一日、日露講和条約の成立を大きく報ずると同時に、一斉にそれに対する激しい非難の論説を掲載した。 ・徳富蘇峰の主宰する「国民新聞」のみが条約の成立を容認する社説をくりかえし掲載していた。 ・蘇峰は、満州、韓国両問題が解決をみたことを喜び、 「此の度の講和条約にて、我が主義は完全に貫徹し、……我れは戦勝の効果を遺憾なく発揮したり」 として、条約締結を屈辱と言い失敗ととなえる説をいましめていた。 ・日露戦争によって、日本は東洋の一大強国となり、世界列強の一員にも加わった。 ・それは、欧米列強の搾取を一方的にうけていた被圧迫民族に影響をあたえた。 ・黄色人種国である日本が白人種国であるロシアをやぶり、しかも欧米各国からの干渉も排して講和を成立させたことに、かれらは驚嘆していた。 ・民族主義者たちは、欧米列強の植民地政策に反抗する自覚を強め、イギリスの植民地であるインドその他で、独立運動が急に勢いを強める結果を生んだ。 ・外相に就任した小村の信念は、軍備の充実と経済振興が日本を守る基礎であるということに尽きていた。 ・かれは、欧米列強と巧みに調和政策をとりながら、清・韓両国に終始強硬な姿勢でのぞんだ。それら両国を勢力下におくことが、日本の安全を守るために絶対に必要だと考えた。 ・外相に就任した小村は、伊藤と韓国問題について協議し、韓国を保護国とすることからさらに進めて日本に併合させることに意見の一致をみた。 ・韓国内の反日運動は激しく、不穏な空気が各地にひろがっていた。 ・明治三十四年十月二十六日、伊藤はハルピンにおもむいて車中でロシア蔵相と会談後、駅頭で各国領事と握手をかわし歓談した。その折、一人の男が走り寄り、突然、短銃を発射した。 ・加害者は、統監をはじめ日韓協約に調印した韓国大臣の暗殺を同志と誓い合っていた韓国人安重根で、伊藤は三十分後に絶命した。六十九歳であった。 ・伊藤の死によって、日本国内に韓国同志会が結成され、韓国の李容九らにひきいれられた一進会とともに、韓国を日本に併合すべきだという運動が起った。 ・明治四十三年春、桂は、併合の機運が熟したと判断し、本格的な準備に入った。小村は、それをうけて危惧されている列国の承認を得る工作にとりかかった。 ・国の名称については、韓国という名称を廃することになり、桂と寺内が朝鮮を強く主張し、これに決定した。 ・八月二十九日、日韓両国は併合条約を公布し、韓国は日本に併合され、朝鮮と名称を変えた。 ・これについて、ロシアをはじめイギリス、ドイツ、アメリカ、フランス、イタリアの諸国も承認する声明を発した。 ・各国は、それぞれ他国を植民地として併合していて、日本の韓国併合を不当としてして責めることができなかったのである。 あとがき ・日露講和条約締結と同時に、戦争と民衆の係り合いの異様さに関心をいだき、また、講和成立が、後の太平洋戦争への起点となっていることにも気づいた。つまり、明治維新と太平洋戦争をむすぶ歴史の分水嶺であることを知ったのである。 解 説 粕谷一希 ・小村寿太郎という外交官に表現された国家意志は、当時の明治藩閥政権、伊藤博文、桂太郎から金子堅太郎にいたる、うるわしくもみごとな共同作業の産物であった。 ・この日露戦争における政治家、軍人、外交官の水も洩らさぬ一致協力振りは、近代日本の若さと健康を象徴している。 ・維新と文明開化、憲法制定と条約改正、四民平等と自由民権といった明治日本人の歩みは、今日から省みて涙ぐましい努力であり、多くの悲劇と矛盾を伴いながらも、「芸術作品としての国家」ともいえる趣きをもっていたのである。 ・日露戦争を終えてからの日本は、もはやそれまでのみごとな国家意志、国家理性を形成することなく、破局への道を歩む。 ・それは過去のことではなく、今後の日本を見つめる貴重な視点となりうるのである。 ―― 完 ―― |