
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年08月07日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
26 |
19/06 |
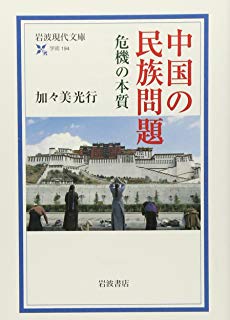 |
中国の民族問題 |
加々美光行 |
岩波現代文庫 |
◎ |
序章 中国の民族問題とは何か ――危機の本質―― 6 「中華民族」の出現とその内的構造 「民族」概念の登場 ・辛亥革命後の中華民国また国共内戦後の中華人民共和国は、いずれも中国史上初めて「中国」の名をもって自国の「国名」とした国家である。 第Ⅰ章 清朝期から民国期までの民族政策 はじめに ・現在、中国政府は民族区域自治と呼ばれる民族政策を採用しており、自国領内の諸民族に対して居住地域における自治を許すのみで、中国国家からの分離権を含むいわゆる自決権については全く認めていない。 ・同様な理由から、中国は諸民族の自決権を前提にして成立する連邦制政体を採用していないだけでなく、連邦制政体の採用を主張する者を分離主義者として厳しく批判し続けている。 第Ⅲ章 文化大革命と新疆辺境 ――中国社会主義と民族の行方―― 4 調整期から継続革命論の出現へ ・一九六四年半ばに登場した、劉春(当時中央民族事務委員会副主任)の論文、この論文こそ文革期を通じて民族政策の基本的綱領文献となったものであった。 (1) 民族は特殊ブルジョア的歴史概念である。 (2) 民族問題は実質的に階級問題である。 (3) 民族主義はブルジョア思想であり、根本的に社会主義とあい容れず、プロレタリア階級の民族観とあい容れない。 (4) 社会主義体制下に階級闘争が存続する以上は、 (5) 社会主義の全過渡期にわたって民族の特殊性と民族間格差は存続する。共産主義の実現と階級の消滅の後、民族は徐々に消滅し民族の融合は実現する。民族間格差はしかし民族矛盾ではない。いわゆる民族矛盾とは階級矛盾であり敵対的矛盾である。 6 文革派の民族論とプロレタリア独裁国家 ・中国は社会主義を選ばなかったら、恐らく欧米列強の植民地的支配ないし新植民地支配のもとで長く呻吟することになったであろう。 ・つまり社会主義以外の道は欧米列強の支配に追随する奴隷的発展の道となるほかなかったのである。 ・文革派の核心思想である毛沢東思想は本来、旧中国社会の半植民地半封建体制との格闘のなかから生まれたものであって、それゆえに中国と欧米列強との関係史を反帝・反植民地の課題の堅持という形で文革期に至るまで意識し続けたのだった。 ・文革派の国家論も欧米中心の近代化論も、世界を一つの均質的な空間に変えることをもって進歩と考える歴史発展観を抜きがたく持っているといえるのである。 ・両者の違いは、均質化への機動力(ないし推進力)として、前者がプロレタリアのインターナショナリズムを考え、後者が資本と金融および資本企業家の世界普遍化力を考える点にある。 ・一九六〇年代末以後、資本・金融および資本企業家は急速に多国籍化し、その普遍力を強めているのに対し、プロレタリアは依然個別国家の枠組みを越えることができずにいる。 ・ある意味で文革の挫折、二千万人もの死者を出したといわれるその悲劇は、文革がこの資本・資本家の普遍力に徹底的な対決を目指したあげく、結局はその多国籍化に示される急速な強大化を前に決定的な敗北を強いられた結果生じたのだといえるのかもしれない。 第Ⅳ章 一九四〇―五〇年代の周辺民族問題と国際政治 ――内蒙古地域と新疆地域を中心として―― 1 内蒙古自治政府の成立 ・中華人民共和国の現在の国内諸民族に対する「民族政策」は、「民族区域自治」政策と呼ばれるものである。 ・この政策のもとで、中国は国内諸民族に対して自治権を認めるのみで、中国国家からの離脱の権利を含む自決権については、全く認めていない。 ・さらに、自決権を前提としてのみ成立する連邦制政体についても、これを全面的に否定している。 4 解放軍のウルムチ進駐 ・米ソ両大国の対立を核とした東西対立の冷戦体制は、アジア地域における米ソ間の勢力拡張競争による戦火を局地的な「地域紛争」にとどめて、その戦火をヨーロッパ地域に飛び火させないものとするためにこそ、作られた体制だったのである。 ・事実、四八年のベルリン封鎖を最後に、ヨーロッパ地域では冷戦体制の全時期を通じて、東西または米ソが直接にあい争う戦争は二度と生起しなかった。 ・その反対に、アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの非ヨーロッパ地域では、戦後一貫して米ソ代理戦争の様相をともなった戦争があい次ぎ、戦火が止むことはなかったのである。 ・だから、冷戦体制は明らかに、非ヨーロッパ地域の戦争の犠牲のもとに、ヨーロッパ地域と北アメリカ大陸、日本列島、オーストラリア大陸が平和と繁栄を維持しようとする体制といえたのである。 ・毛沢東には戦後の国民党との内戦期を通じて、終始中国がアメリカによる侵略の危機はむろんのこと、ソ連による従属化圧力の危機にもさらされているという事実認識があったに違いない。 ・この観点と危機意識からこそ、自治・統一主義的な民族政策(民族区域自治政策)も誕生したといっても過言ではないだろう。 5 ウイグルとチベットの抵抗 ・四九年九月末に開催された第一期中国人民政治協商会議は、その第一回会議において、臨時憲法に当たる「共同綱領」を採択したが、そこで初めて明確に新中国の民族政策として「民族区域自治」を原則とすることがうたわれたのである。 ・その後わずか一年、五〇年十月に、新中国は戦後最大の戦争である朝鮮戦争に参戦を余儀なくされ、文字通り冷戦の熱戦化を体験することになった。 第Ⅴ章 一九九〇年代のチベットとウイグル はじめに ・中国指導部は天安門事件以来、アメリカを中心とした外部の西側勢力が「民主、自由、人権」などの看板を掲げて平和的な手段によって中国の社会主義体制を転覆しようと画策しているという見方を強くしていた。いわゆる外部陰謀による「和平演変論」いわれるものである。 ・今や、この外部陰謀説の中に、周辺少数民族を扇動して中国の統一を破壊する「分裂主義」的策動説が含まれることになった。 ・このため、中国はこの間、とりわけチベット、新疆ウイグル、内モンゴルの周辺三地域に対する警戒心を強めている。 ・中国の民族問題が国際関係の動向に深く関係して現われることを示すものといえる。 1 胡耀邦の中国の民族・宗教政策 ・問題は中国の宗教政策にあった。中国辺境地域のチベット、新疆ウイグル、内モンゴルの三大民族自治区はいずれもチベット仏教とイスラム教の二大宗教が支配的な地域である。それゆえ宗教政策は民族政策に直結すると言えるのである。 2 一九八九年天安門事件までのチベット ・革命的暴力によって成立した国家は、建国後も暴力的な支配メカニズムを不可避的にともなう。 ・民族主義とは、ある民族集団が自分自身の国家権力を保有することを望む感情のみをいうのではなく、むしろ何よりも不当な国家権力によって自分たち民族集団が暴力的に抑圧支配されることを拒絶する感情をいうのである。 ・前者が国家権力の暴力自体を否定せず、かえってみずからが既存の権力に代わって、そのような国家権力の担い手になろうとするポジティブな民族感情であるとすれば、後者はむしろ国家権力による暴力支配自体を拒絶し、その暴力から自由になろうとする抵抗意識に根ざしたネガティブな民族感情である。 ・「台湾独立」を巡っても、台湾人の民族感情には同様の二重性が存在する。 ・中国の保守的指導部は、ダライ・ラマの主張を今日に至るまで「表向きの独立否定、実質的な独立肯定」とし、欺瞞的主張と決めつけてその本来の意義を全く理解しようとしていない。 ・それはかれらが、国家の暴力的支配によって統治されない社会などというものを単なる空想、夢想の産物としか考えず、みずからそうした国家暴力を削減する道を歩むことなど思ってもいないからにほかならない。 ・ダライ・ラマの弟であるテンジン・チョンギャル・リンポチェ氏曰く、 「中国人は暴力の言葉しか理解しない、彼らは権力は銃身から生まれると言っている」 4 一九九〇 ― 二〇〇〇年代の中国の民族政策 ・ダライ・ラマの周辺には、分離独立要求を正面から掲げて暴力をも辞さないとする青年会議派を中心とした「急進派」が存在した。 ・中国政府もダライの「連合体提案」を実質的に「独立要求」を放棄したものではないとして拒否した。 ・このためチベット「急進派」は八八年後半に入ってむしろ反中国キャンペーンを活発化させた。 ・これに追い打ちをかけたのが八九年四月の胡耀邦の急逝をきっかけとした天安門民主化運動の激発と五月二十日の北京市戒厳令施行、趙紫陽の失脚、そして六月四日の天安門の流血だった。 ・「和平演変」とは国内外の勢力があい呼応し「平和的手段によって社会主義の政権を転覆する革命」を意味し、天安門事件に際し鄧小平が用いた語法である。 終章 二〇〇〇年代の辺境民族問題と国際政治 2 中国の「新安保観」と内外新戦略の展開 ・内政面の安全保障が外政面の安全保障と連動するという視点は、既に一九八九年六月の天安門事件の直後、鄧小平が「大気候、小気候」論を語った際に提起されていた。 ・すなわち天安門民主化運動(小気候)の「動乱」化は欧米日本を中心とした外部勢力が平和的手段によって中国社会主義政権を転覆しようと企図(大気候)したことによって内外連動して引き起こされたとしたのである。 ―― 完 ―― |